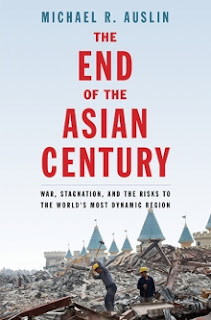"The End of The Asian Century: War, Stagnation, and the Risks to the World's Most Dynamic Region"という本を読んだ。American Enterprise InstituteのMichael Auslinが2017年1月に出版した本です。
アジアは長いこと経済成長が続いてきて、米国なんかでも「これからはアジアの時代だ」なんて言われたりして、オバマ政権も"Pivot to Asia"なんていう戦略を打ち出したりしたわけですけど、このオースリンさんの本は「アジアの未来は明るいばかりじゃないよね」っということを指摘した本です。アジアでの軍事的な緊張は高まっているし、中国経済は維持可能かどうか分らないし、日本はグダグダな状態が長期化しているし、ベトナムにしてもインドネシアにしてもマレーシアにしても政治的に安定しているとは言い難いし、っていうようなことを紹介する内容です。
で、そのうえでオースリンさんはアジアの安定と発展は米国にとっても重要だから、米国はアジアのために積極的に関与していくべきだとしています。だからといって、ものすごいウルトラCでアジアを支えるっていうわけじゃなくて、安全保障でも外交でも文化交流でも現在の取り組みを着実に拡大してくべきだっていう感じですね。南シナ海で中国がアグレッシブになっているから、各国による共同パトロール体制を作ろうとか、ASEANと米国の経済連携を深めようとかそういったことです。
でもまぁ「アジアがグダグダだ」っていうのは大体知っている話ですし、提言の部分もびっくりするような話でもありません。
ただ、最大の短期的なリスクとして「軍事的な衝突」を挙げているところは、それほどにまで警戒すべき事柄とみられているのかという気がしました。もちろんオースリンさんは軍事的な衝突が起こると予想しているわけじゃなくて、「軍事的な衝突が起こりえるリスクがあることは認識せねばならない」と言っているわけですけどね。中期的なリスクとしては「経済の停滞」を挙げています。あと、各国の政治体制のぐらつきとか。
まぁ、最悪のシナリオはいくらでも描けるわけですから、まったくもってアジアがダメになると考えるのもどうかと思いますけど、「これからはアジアの時代だ!」なんていう雰囲気は薄らいできているのかもしれません。
2017年3月21日火曜日
2017年3月18日土曜日
「人類と気候の10万年史~過去に何が起きたのか、これから何が起こるのか」
「人類と気候の10万年史~過去に何が起きたのか、これから何が起こるのか」という本を読んだ。立命館大学の中川毅教授が書いた本で、2017年2月に出た本です。ブルーバックス。懐かしい。
トランプ政権は概して気候変動問題には関心が無いとみられていて、米国の環境保護局(EPA)局長に就任したスコット・プルイット氏も「気候変動に人間の活動が影響していることは理解しているが、それがどの程度の大きさであるかは議論が続いているところである」というのが持論だったりします。
ただ、メディアの方では「プルイットは科学的見地を無視したバカモノだ」といった論調で報じることが多いです。
例えば、3月10日のCNNの朝の番組では、プルイット氏の
"I think that measuring with precision human activity on the climate is something very challenging to do and there's tremendous disagreement about the degree of impact. So, no, I would not agree that it's a primary contributor to the -- to the global warming that we see. OK. Or, we don't know that yet, as far as -- we need -- we need to continue the debate, continue the review and the analysis."
という発言を流したあと、
キャスターが
"That is not what the majority of the scientific community would state as a proposition."
とつないで、
コメンテーターが、
"And in fact, when you said not the majority, I mean, that, Chris, even understates it. The overwhelming -- the overwhelming preponderance of international, you know, scientific bodies have repeatedly reaffirmed that linkage."
応じたりするわけです。
プルイット氏が「人間の活動が気候変動の主要な要因であるかは議論がある」と述べているのに対して、コメンテーターは「人間の活動と気候変動に関連があることは疑いはない」と述べているわけですから、どちらも正しいことを言っている可能性はあるわけですが、キャスターやコメンテーターの発言には「プルイット氏は科学を否定している」と異端視する雰囲気が感じられます。
個人的には、気候変動と人間の活動に関連があることは分かります。
アンデスかどこかの山の上の氷河がどんどん溶けているとかいう話を聞くと「地球が温暖化しているんだな」というのは素直に納得できるますし、二酸化炭素とかに温室効果があることもそうなんだろうなと思いますし、化石燃料を使ったり、森林を伐採したりする人間の活動が地球の大気中に含まれる二酸化炭素の量を増やしているんだろうなというのも分かります。
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書には、こんな記述もあります。
"It is extremely likely that more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010 was caused by the anthropogenic increase in greenhouse gas concentrations and other anthropogenic forcings together."
この60年間の気温上昇の半分超は人間の活動がもたらしたものである可能性が極めて高いということだと思います。
半分超ですから、プルイット氏の"I would not agree that it's a primary contributor to the global warming that we see"という発言は、科学者の見解とは食い違っていることになります。
ただ、プルイット氏の気持ちも分かります。
「半分超」っていうことは、51%かもしれないし100%かもしれないわけで、どこに落ち着くかによってはかなり雰囲気が違います。
あと、昔はマンモスが住んでいたような氷河期があったっていうわけですから、地球上の気温はずっと昔から上昇を続けてきたんでしょう。おそらく人間の活動以外にも地球の気温を上昇させている要因があるはずです。そうした人間以外の要因と、人間という要因のどちらが大きな影響を及ぼしているかなんていうことは、なかなか分からないのではないかとも思うのです。そもそも何十年か前には、科学的な見地をもとに「地球が再び氷河期になる」なんていう騒ぎ方もされていたように思います。
それに本当のことを言うと、IPCCの報告書がなんぼのもんじゃという感覚もあります。だってそもそも「地球の平均気温」という概念がよく分からない。いつの、どこの気温だよ。あと、人間の活動が排出している温室効果ガスの量なんて、そんなに正確に測定できるものなのかよという気もします。いつだったか、中国の排出量に関する報告が大きく訂正されたっていう話もあったように思います。
ということで、何か分かるんじゃないかと思って、この本を読んでみた次第です。非常に面白かったです。
著者の中川教授は古気候学の専門家で、何万年も前から現在に至るまでの過去の地球の気候を研究している人です。
学会の定説とされるミランコビッチ理論によると、地球上の気候は10万年ごとに温暖化のピークがあります。この10万年のサイクルは楕円形である地球の公転軌道が揺らぐことで、地球と太陽の距離が変化することで起こるものです。温暖な時期と寒冷な時期の温度差は10度にも達します。地球の気温が10度変化するというのは、鹿児島が札幌になるぐらいの変化に相当するそうです。なるほど。そりゃ大変だ。
また地球の気候には2万3000年のサイクルもあって、この周期でやはり温暖な時期と寒冷な時期が繰り返されます。これは地球の地軸の傾きが揺らぐことで、地球にそそぐ太陽のエネルギーの分配のパターンが変わることで起こるもので、7度ぐらいの温度差が出るものだそうです。7度といえば東京が那覇になるぐらいのものです。おぉ、大変。
言葉で説明するとよく分りませんが、本のなかにはグラフが出てきます。それをみると地球の気温が2万3000年のサイクルで小さな波を描きながら、全体としては10万年サイクルの大きなトレンドも作っているということが分かります。
現在はこの10万年のサイクルのなかでは、温暖な時期のピークをすぎたあたりだそうです。現在は「例外的に」暖かい時期といえ、本来であれば、これから地球の気温が寒冷になっていく方向に向かうはずです。これは地球の公転とか地軸の傾きとか、宇宙レベルでの物理法則に従ったものですから、トレンドを変えることは難しい。だから昔は「地球が再び氷河期になる」なんていう騒がれ方をしたわけです。
で、この本はどうしてそんなことが分かるのかということと、今とは違う気候だった地球はどんなところだったのかということを分かりやすく説明した本です。率直に言えば「そんなの分かるわけないじゃん」と思ってしまうところですが、それが分かるんだそうです。
カギとなるのは、海や湖のなかに堆積していった「年縞」と呼ばれる地層の中に含まれるプランクトンの化石や化学組成を分析するという手法です。
なかでも中川教授がチームのリーダーとなって福井県の水月湖の湖底から採取した年縞は世界的な価値が認められています。普通なら、水の底に住んでいる生き物や川から流れ込んだ水が薄く積もった地層をかき乱したりして、数万年にもおよぶ地層を保つことはないわけですが、水月湖では1年間で0.7ミリメートルペースでたまっていく薄い地層が奇跡的に保存されているそうです。ここらあたりが、いかに奇跡であるかについても詳しい説明がされていますが、ここでは省略。中川教授は全体として73メートル分(15万年相当)の堆積物を回収し、そのうち45メートル分にはっきりとした年縞を確認することができました。
で、それをどう分析するのかということです。
まず、放射性炭素年代測定という手法があります。自然界に存在する炭素には質量数12、13、14の3種類があります。そして、このうち質量数14の炭素(C14)だけが放射能を持っていて、時間とともに徐々に別の物質に変わっていきます。なので何かに含まれている炭素のなかで、C14がC12やC13に比べてどれだけ減っているかを測定すれば、その何かの年代が推定できるんだそうです。年代不明の麺の化石に含まれた炭素を調べたところ、麺の材料となった植物が刈り取られたのは4000年前だということが分かったケースもあるんだとのこと。
ただ、この放射性炭素年代測定には誤差が大きいという問題点があります。それはスタートラインにおけるC14の比率が正確に分からないからです。
そこで年縞の出番になります。水月湖の年縞には葉っぱの化石が含まれています。しかも年に1層ずつ積もっていく年縞の数を数えれば、その葉っぱが今から何年前に湖底にたまったものかが分かります。さらに、その化石のC14の比率を調べれば、C14がどれだけ残っていれば何年前の炭素に相当するという「換算表」が作ることができるというわけです。水月湖の年縞をもとにした換算表は世界の標準として認められています。
また、水月湖の堆積物のなかには、花粉の化石が含まれています。1立方センチメートルあたり数十万粒の花粉の化石がみつかることもあるそうです。こうした花粉の化石を顕微鏡で調べれば、どういった種類の植物が生えていたかが分かる。例えば、スギの花粉がたくさんみつかったり、ブナの花粉がたくさん見つかったり、スギとブナが半分ずつだったり、そういったことですね。それは水月湖周辺の植生を繁栄しているわけです。
で、その植生を現在の世界の植生と比べます。例えば「今から3万~2万年前の年縞から見つかった花粉は針葉樹とシラカバが混じり合っているから、現在のシベリアのような風景だった」といった推定がなりたつわけです。おぉ。
さらにモダンアナログ法という手法もあって、「2万年前の水月湖の花粉の組成が旭川近くの湖底に現在たまりつつある花粉の組成と似ていた場合、2万年前の福井県南部の気候は現在の旭川に近かった」と判断することができる。で、現在の旭川の平均気温や日照量をひっぱってくれば、2万年前の福井県南部の気温や日照量が推定できるというわけです。おおぉ。
こうした花粉の化石の分析によって、水月湖周辺の気候には10万年のサイクルと、2万3000年のサイクルがあることが分かりました。地球の公転軌道や地軸の傾きをもとにしたミランコビッチ理論と同じ周期です。
具体的には、
・温暖な時期のピークは、12万~11万年前と1万年前にある
・2万年前は氷期のいちばん寒い時期だった
・氷期と温暖な時代の震幅は10度(札幌-鹿児島の差)
ということです。
グラフをみると、12万年ほど前に現在と同じぐらいの暖かい時期があったけど、その後、徐々に気温が下がっていって、2万年前に底を打っています。さらにその後、急激な気温上昇があって1万年前のピークをつけたというイメージです。
また、
・12万年ほど前のピークの後の「徐々に気温が下がって」の部分は、2万3000年のサイクルで気温の上下を繰り返しながら、徐々に気温が下がっている。
・温度の震幅は最大で7度(東京-那覇の差)
ということでもあります。
ただし、こうしたデータの分析結果には、人間の活動が影響しているという指摘もあります。それは「最近の数千年は夏の日射が極小近くまで低下してきているのに対し、温度は反対に上昇しているっように見える」からです。こうしたズレは過去15万年の間ではなかったそうです。つまり1万年ほど前のピークの後に起きるはずの気温の低下が起きていないということですね。
中川教授はこのズレの原因について「まだ議論が続いている」としています。
その一方で、1万年前にピークをつけた温暖な時期が例外的に長く続いているというのは多くの研究者が指摘してきたことで、「ひとつの有力な説が人間活動に原因を求めている」としています。南極の氷に含まれる空気に含まれる温室効果ガスの濃度の研究ではメタンが5000年前、二酸化炭素が8000年前からミランコビッチ理論を外れるペースで増加していることが分っています。この現象について、バージニア大学のウィリアム・ラジマン教授が「アジアにおける水田農耕の普及、およびヨーロッパ人による大規模な森林破壊が原因」と主張していることも紹介されています。
で、ここからがややこしくかつ、奥深いのですが、中川教授は
「ラジマン教授の主張は、人間が気候を左右するようになった歴史は、100年前でなく8000年前にさかのぼるということを意味していた。もし私たちが、温室効果ガスの放出によって『とっくに来ていた』はずの氷期を回避しているのだとしたら、温暖化をめぐる善悪の議論は根底から揺らいでしまう。私たちは自然にやってくる氷期の地球で暮らしたいのか、それとも人為的に暖かく保たれた気候の中で暮らしたいのか。これはもはや、哲学の問題であって科学の問題ではない」
と述べています。
どうして中川教授がこんなことを言い出すかというと、氷期というのは現在の人類にとっては非常に厳しい時代だったからです。
水月湖の年縞の研究からも、氷期における気温の変化は温暖な時期に比べて極めて激しく、予測不能なカオスな動きをみせていたことが分かっています。氷期には「ダンスガード=オシュガー(D-O)イベント」と呼ばれる、原因不明の急激な温暖化が起きていたようです。
気候変動が人類に与える影響は甚大です。
1993年の冷夏は2年前のピナツボ火山の噴火が原因とされ、全国平均のコメの作況を7割にまで落としています。天明の飢饉は、1783年に起きたアイスランドのラキ火山の噴火によって、冷夏が5年以上も続いたことが原因だとされています。このときはヨーロッパでも食料不足が起きて、フランス革命の遠因となったとの分析もあります。また1980年代のアフリカの干ばつは4年間も続いて300万人の命を奪っています。ベネズエラ沿岸のカリアコ海盆の年縞に基づいた研究によると、ユカタン半島では西暦810年ごろ、9年の間に6回もの干ばつがあり、マヤ文明衰退のきっかけを作ったともされているそうです。
中川教授は「ときどき暴れる気候に対しては、現代社会は思っている以上に脆弱な基盤の上に成り立っている。だが少なくとも先進国において、そのような議論を耳にする機会は、意外なほどに少ないように思う」としています。
さらに中川教授は、現在の人類の繁栄の基盤となった農耕の普及にも気候変動が影響していたのではないかと思いを巡らせます。
気候の変化が激しい氷期は一種類の作物を大量に育てる農耕はリスクが大きい。氷期の人類が農耕ではなくて狩猟採取を基盤においていたのは、何も当時の人類が農耕を思いつかなかったわけではなくて、自然のなかで育つ多様な植物や動物を生活の糧とすることで、どんな気候になっても確実に食べ物を確保できる生活のスタイルが最適だったからではないかというわけです。
で、農耕生活と狩猟採取生活という2つのスタイルについて、中川教授は、
「どちらを好ましいと考えるかは、ひょっとすると哲学の問題に帰着するのかもしれない。繁栄と発展をあくまで是とするならば、農耕は欠かせない前提条件である。先進国の科学者である筆者も、基本的にはこの考え方に慣れている。だが、どこか南国の浜辺で野生のフルーツを採ったり、魚を釣ったりして糧を得る暮らしが『気にならない』かと問われたとき、ならないと断言するのは必ずしも正直なことではない」
としています。
もちろん「単純な原始回帰願望はナイーブに過ぎる」とも断っていますけど、10万年単位の気候の歴史を科学的かつ真剣に分析すれば、なかなか深いところに思い至ったりするもんなんでしょう。
中川教授は、宇宙レベルの物理法則に基づいたミランコビッチ理論は崩しがたいものだとみているようです。その理論に基づけば、地球は今後10万年サイクルの寒冷化に向かうわけで、一般的に言われているような地球温暖化への不安については距離をとった記述が目立ちます。
「温暖化の主犯格とされる二酸化炭素にある種の敵意を感じる人の数は、商業的にも無視できない水準に達している」
「現在の温暖化予測も70年代の寒冷化予測と同様に信用できないと主張しているのではない。(ただし、信頼できると主張しているのでもない)」
「私見だが、もっとも恐ろしいのは、現代の『安定で暖かい時代』がいつかは終わるというシナリオではないかと思う」
といった感じです。
あと、とにかく、気候変動は何が起こるか分からない、という言及も多いです。
「気候システムは極めて複雑な系であり、その挙動を理解することはもちろん、正確に記述することすら容易ではない」
「あらゆる未来予測には適用限界がある。このことは、本書に通底する重要なテーマのひとつ」
「本当に劇的な変化の予測は原理的にきわめて困難」
で、そうしたなかでも「だが、もしそれが起こった場合に、人間にとってどの程度の影響があるのか知っておくことは重要である」と指摘しています。
また、われわれが経験的に身につけている「天気予報とのつきあい方」を、現在の「100年後に5度の気温上昇」といった予測にもあてはめるべきだとしています。つまり、普通の天気予報なら、明日の予報だと信用するけれど、1週間後になるとそれほど信用しないし、「来年は冷夏」とか言われれば聞き流す。こうした感覚を100年後の野心的な天気予報を聞くときにも大切にすべきだというわけですね。
ということで、気候変動問題における科学的な予測があることは分るんだけれど、EPAのプルイット長官の気持ちも分らなくもないというのは、地球レベルの気候変動問題を科学的かつ真剣に研究してきた中川教授の感覚の方向性と大きく違うわけではないような気がします。あんまり「俺はなんでも分っているんだ」みたいな顔をして、プルイット長官的な人たちをいじめるのもどうかなと。
ここは完全に私見ですが、気候変動問題っていうか、地球温暖化問題についての危機感の大きさは地域差や個人差があって当然だと思います。海面上昇にさらされている小さな島国に住んでいる人は心配で仕方ないでしょうけど、電力不足が一般的な途上国の人だったら、石炭でもなんでもいいからとにかく安く発電所を作ってくれと思うはずです。あと、石炭産業で働いている人は「俺たちにだって生活がある」って思うでしょう。だから温室効果ガス排出の抑制に消極的な立場をとっている人たちを馬鹿にするのはよくない気がします。
ただ、中川教授は過去の気候の専門家ではあるけれど、未来予測を専門としているわけではないと思います。IPCCの報告書のような将来予測については、スーパーコンピューターの上で地球の気候を丸ごと再現して変化を予測する「気候モデリング」の手法で行われているとの説明がありますが、その内容についての詳しい言及はありませんでした。このあたりについても分りやすく説明してくれる本があれば読んでみたいところです。
もしも本当に人類による温室効果ガス排出が10万年サイクルの気候変動のパターンも打ち破って、ガンガンに地球を温暖化させることが確実に分っているっていうんだったら、プルイット長官に石を投げたくなるかもしれません。
トランプ政権は概して気候変動問題には関心が無いとみられていて、米国の環境保護局(EPA)局長に就任したスコット・プルイット氏も「気候変動に人間の活動が影響していることは理解しているが、それがどの程度の大きさであるかは議論が続いているところである」というのが持論だったりします。
ただ、メディアの方では「プルイットは科学的見地を無視したバカモノだ」といった論調で報じることが多いです。
例えば、3月10日のCNNの朝の番組では、プルイット氏の
"I think that measuring with precision human activity on the climate is something very challenging to do and there's tremendous disagreement about the degree of impact. So, no, I would not agree that it's a primary contributor to the -- to the global warming that we see. OK. Or, we don't know that yet, as far as -- we need -- we need to continue the debate, continue the review and the analysis."
という発言を流したあと、
キャスターが
"That is not what the majority of the scientific community would state as a proposition."
とつないで、
コメンテーターが、
"And in fact, when you said not the majority, I mean, that, Chris, even understates it. The overwhelming -- the overwhelming preponderance of international, you know, scientific bodies have repeatedly reaffirmed that linkage."
応じたりするわけです。
プルイット氏が「人間の活動が気候変動の主要な要因であるかは議論がある」と述べているのに対して、コメンテーターは「人間の活動と気候変動に関連があることは疑いはない」と述べているわけですから、どちらも正しいことを言っている可能性はあるわけですが、キャスターやコメンテーターの発言には「プルイット氏は科学を否定している」と異端視する雰囲気が感じられます。
個人的には、気候変動と人間の活動に関連があることは分かります。
アンデスかどこかの山の上の氷河がどんどん溶けているとかいう話を聞くと「地球が温暖化しているんだな」というのは素直に納得できるますし、二酸化炭素とかに温室効果があることもそうなんだろうなと思いますし、化石燃料を使ったり、森林を伐採したりする人間の活動が地球の大気中に含まれる二酸化炭素の量を増やしているんだろうなというのも分かります。
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書には、こんな記述もあります。
"It is extremely likely that more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010 was caused by the anthropogenic increase in greenhouse gas concentrations and other anthropogenic forcings together."
この60年間の気温上昇の半分超は人間の活動がもたらしたものである可能性が極めて高いということだと思います。
半分超ですから、プルイット氏の"I would not agree that it's a primary contributor to the global warming that we see"という発言は、科学者の見解とは食い違っていることになります。
ただ、プルイット氏の気持ちも分かります。
「半分超」っていうことは、51%かもしれないし100%かもしれないわけで、どこに落ち着くかによってはかなり雰囲気が違います。
あと、昔はマンモスが住んでいたような氷河期があったっていうわけですから、地球上の気温はずっと昔から上昇を続けてきたんでしょう。おそらく人間の活動以外にも地球の気温を上昇させている要因があるはずです。そうした人間以外の要因と、人間という要因のどちらが大きな影響を及ぼしているかなんていうことは、なかなか分からないのではないかとも思うのです。そもそも何十年か前には、科学的な見地をもとに「地球が再び氷河期になる」なんていう騒ぎ方もされていたように思います。
それに本当のことを言うと、IPCCの報告書がなんぼのもんじゃという感覚もあります。だってそもそも「地球の平均気温」という概念がよく分からない。いつの、どこの気温だよ。あと、人間の活動が排出している温室効果ガスの量なんて、そんなに正確に測定できるものなのかよという気もします。いつだったか、中国の排出量に関する報告が大きく訂正されたっていう話もあったように思います。
ということで、何か分かるんじゃないかと思って、この本を読んでみた次第です。非常に面白かったです。
著者の中川教授は古気候学の専門家で、何万年も前から現在に至るまでの過去の地球の気候を研究している人です。
学会の定説とされるミランコビッチ理論によると、地球上の気候は10万年ごとに温暖化のピークがあります。この10万年のサイクルは楕円形である地球の公転軌道が揺らぐことで、地球と太陽の距離が変化することで起こるものです。温暖な時期と寒冷な時期の温度差は10度にも達します。地球の気温が10度変化するというのは、鹿児島が札幌になるぐらいの変化に相当するそうです。なるほど。そりゃ大変だ。
また地球の気候には2万3000年のサイクルもあって、この周期でやはり温暖な時期と寒冷な時期が繰り返されます。これは地球の地軸の傾きが揺らぐことで、地球にそそぐ太陽のエネルギーの分配のパターンが変わることで起こるもので、7度ぐらいの温度差が出るものだそうです。7度といえば東京が那覇になるぐらいのものです。おぉ、大変。
言葉で説明するとよく分りませんが、本のなかにはグラフが出てきます。それをみると地球の気温が2万3000年のサイクルで小さな波を描きながら、全体としては10万年サイクルの大きなトレンドも作っているということが分かります。
現在はこの10万年のサイクルのなかでは、温暖な時期のピークをすぎたあたりだそうです。現在は「例外的に」暖かい時期といえ、本来であれば、これから地球の気温が寒冷になっていく方向に向かうはずです。これは地球の公転とか地軸の傾きとか、宇宙レベルでの物理法則に従ったものですから、トレンドを変えることは難しい。だから昔は「地球が再び氷河期になる」なんていう騒がれ方をしたわけです。
で、この本はどうしてそんなことが分かるのかということと、今とは違う気候だった地球はどんなところだったのかということを分かりやすく説明した本です。率直に言えば「そんなの分かるわけないじゃん」と思ってしまうところですが、それが分かるんだそうです。
カギとなるのは、海や湖のなかに堆積していった「年縞」と呼ばれる地層の中に含まれるプランクトンの化石や化学組成を分析するという手法です。
なかでも中川教授がチームのリーダーとなって福井県の水月湖の湖底から採取した年縞は世界的な価値が認められています。普通なら、水の底に住んでいる生き物や川から流れ込んだ水が薄く積もった地層をかき乱したりして、数万年にもおよぶ地層を保つことはないわけですが、水月湖では1年間で0.7ミリメートルペースでたまっていく薄い地層が奇跡的に保存されているそうです。ここらあたりが、いかに奇跡であるかについても詳しい説明がされていますが、ここでは省略。中川教授は全体として73メートル分(15万年相当)の堆積物を回収し、そのうち45メートル分にはっきりとした年縞を確認することができました。
で、それをどう分析するのかということです。
まず、放射性炭素年代測定という手法があります。自然界に存在する炭素には質量数12、13、14の3種類があります。そして、このうち質量数14の炭素(C14)だけが放射能を持っていて、時間とともに徐々に別の物質に変わっていきます。なので何かに含まれている炭素のなかで、C14がC12やC13に比べてどれだけ減っているかを測定すれば、その何かの年代が推定できるんだそうです。年代不明の麺の化石に含まれた炭素を調べたところ、麺の材料となった植物が刈り取られたのは4000年前だということが分かったケースもあるんだとのこと。
ただ、この放射性炭素年代測定には誤差が大きいという問題点があります。それはスタートラインにおけるC14の比率が正確に分からないからです。
そこで年縞の出番になります。水月湖の年縞には葉っぱの化石が含まれています。しかも年に1層ずつ積もっていく年縞の数を数えれば、その葉っぱが今から何年前に湖底にたまったものかが分かります。さらに、その化石のC14の比率を調べれば、C14がどれだけ残っていれば何年前の炭素に相当するという「換算表」が作ることができるというわけです。水月湖の年縞をもとにした換算表は世界の標準として認められています。
また、水月湖の堆積物のなかには、花粉の化石が含まれています。1立方センチメートルあたり数十万粒の花粉の化石がみつかることもあるそうです。こうした花粉の化石を顕微鏡で調べれば、どういった種類の植物が生えていたかが分かる。例えば、スギの花粉がたくさんみつかったり、ブナの花粉がたくさん見つかったり、スギとブナが半分ずつだったり、そういったことですね。それは水月湖周辺の植生を繁栄しているわけです。
で、その植生を現在の世界の植生と比べます。例えば「今から3万~2万年前の年縞から見つかった花粉は針葉樹とシラカバが混じり合っているから、現在のシベリアのような風景だった」といった推定がなりたつわけです。おぉ。
さらにモダンアナログ法という手法もあって、「2万年前の水月湖の花粉の組成が旭川近くの湖底に現在たまりつつある花粉の組成と似ていた場合、2万年前の福井県南部の気候は現在の旭川に近かった」と判断することができる。で、現在の旭川の平均気温や日照量をひっぱってくれば、2万年前の福井県南部の気温や日照量が推定できるというわけです。おおぉ。
こうした花粉の化石の分析によって、水月湖周辺の気候には10万年のサイクルと、2万3000年のサイクルがあることが分かりました。地球の公転軌道や地軸の傾きをもとにしたミランコビッチ理論と同じ周期です。
具体的には、
・温暖な時期のピークは、12万~11万年前と1万年前にある
・2万年前は氷期のいちばん寒い時期だった
・氷期と温暖な時代の震幅は10度(札幌-鹿児島の差)
ということです。
グラフをみると、12万年ほど前に現在と同じぐらいの暖かい時期があったけど、その後、徐々に気温が下がっていって、2万年前に底を打っています。さらにその後、急激な気温上昇があって1万年前のピークをつけたというイメージです。
また、
・12万年ほど前のピークの後の「徐々に気温が下がって」の部分は、2万3000年のサイクルで気温の上下を繰り返しながら、徐々に気温が下がっている。
・温度の震幅は最大で7度(東京-那覇の差)
ということでもあります。
ただし、こうしたデータの分析結果には、人間の活動が影響しているという指摘もあります。それは「最近の数千年は夏の日射が極小近くまで低下してきているのに対し、温度は反対に上昇しているっように見える」からです。こうしたズレは過去15万年の間ではなかったそうです。つまり1万年ほど前のピークの後に起きるはずの気温の低下が起きていないということですね。
中川教授はこのズレの原因について「まだ議論が続いている」としています。
その一方で、1万年前にピークをつけた温暖な時期が例外的に長く続いているというのは多くの研究者が指摘してきたことで、「ひとつの有力な説が人間活動に原因を求めている」としています。南極の氷に含まれる空気に含まれる温室効果ガスの濃度の研究ではメタンが5000年前、二酸化炭素が8000年前からミランコビッチ理論を外れるペースで増加していることが分っています。この現象について、バージニア大学のウィリアム・ラジマン教授が「アジアにおける水田農耕の普及、およびヨーロッパ人による大規模な森林破壊が原因」と主張していることも紹介されています。
で、ここからがややこしくかつ、奥深いのですが、中川教授は
「ラジマン教授の主張は、人間が気候を左右するようになった歴史は、100年前でなく8000年前にさかのぼるということを意味していた。もし私たちが、温室効果ガスの放出によって『とっくに来ていた』はずの氷期を回避しているのだとしたら、温暖化をめぐる善悪の議論は根底から揺らいでしまう。私たちは自然にやってくる氷期の地球で暮らしたいのか、それとも人為的に暖かく保たれた気候の中で暮らしたいのか。これはもはや、哲学の問題であって科学の問題ではない」
と述べています。
どうして中川教授がこんなことを言い出すかというと、氷期というのは現在の人類にとっては非常に厳しい時代だったからです。
水月湖の年縞の研究からも、氷期における気温の変化は温暖な時期に比べて極めて激しく、予測不能なカオスな動きをみせていたことが分かっています。氷期には「ダンスガード=オシュガー(D-O)イベント」と呼ばれる、原因不明の急激な温暖化が起きていたようです。
気候変動が人類に与える影響は甚大です。
1993年の冷夏は2年前のピナツボ火山の噴火が原因とされ、全国平均のコメの作況を7割にまで落としています。天明の飢饉は、1783年に起きたアイスランドのラキ火山の噴火によって、冷夏が5年以上も続いたことが原因だとされています。このときはヨーロッパでも食料不足が起きて、フランス革命の遠因となったとの分析もあります。また1980年代のアフリカの干ばつは4年間も続いて300万人の命を奪っています。ベネズエラ沿岸のカリアコ海盆の年縞に基づいた研究によると、ユカタン半島では西暦810年ごろ、9年の間に6回もの干ばつがあり、マヤ文明衰退のきっかけを作ったともされているそうです。
中川教授は「ときどき暴れる気候に対しては、現代社会は思っている以上に脆弱な基盤の上に成り立っている。だが少なくとも先進国において、そのような議論を耳にする機会は、意外なほどに少ないように思う」としています。
さらに中川教授は、現在の人類の繁栄の基盤となった農耕の普及にも気候変動が影響していたのではないかと思いを巡らせます。
気候の変化が激しい氷期は一種類の作物を大量に育てる農耕はリスクが大きい。氷期の人類が農耕ではなくて狩猟採取を基盤においていたのは、何も当時の人類が農耕を思いつかなかったわけではなくて、自然のなかで育つ多様な植物や動物を生活の糧とすることで、どんな気候になっても確実に食べ物を確保できる生活のスタイルが最適だったからではないかというわけです。
で、農耕生活と狩猟採取生活という2つのスタイルについて、中川教授は、
「どちらを好ましいと考えるかは、ひょっとすると哲学の問題に帰着するのかもしれない。繁栄と発展をあくまで是とするならば、農耕は欠かせない前提条件である。先進国の科学者である筆者も、基本的にはこの考え方に慣れている。だが、どこか南国の浜辺で野生のフルーツを採ったり、魚を釣ったりして糧を得る暮らしが『気にならない』かと問われたとき、ならないと断言するのは必ずしも正直なことではない」
としています。
もちろん「単純な原始回帰願望はナイーブに過ぎる」とも断っていますけど、10万年単位の気候の歴史を科学的かつ真剣に分析すれば、なかなか深いところに思い至ったりするもんなんでしょう。
中川教授は、宇宙レベルの物理法則に基づいたミランコビッチ理論は崩しがたいものだとみているようです。その理論に基づけば、地球は今後10万年サイクルの寒冷化に向かうわけで、一般的に言われているような地球温暖化への不安については距離をとった記述が目立ちます。
「温暖化の主犯格とされる二酸化炭素にある種の敵意を感じる人の数は、商業的にも無視できない水準に達している」
「現在の温暖化予測も70年代の寒冷化予測と同様に信用できないと主張しているのではない。(ただし、信頼できると主張しているのでもない)」
「私見だが、もっとも恐ろしいのは、現代の『安定で暖かい時代』がいつかは終わるというシナリオではないかと思う」
といった感じです。
あと、とにかく、気候変動は何が起こるか分からない、という言及も多いです。
「気候システムは極めて複雑な系であり、その挙動を理解することはもちろん、正確に記述することすら容易ではない」
「あらゆる未来予測には適用限界がある。このことは、本書に通底する重要なテーマのひとつ」
「本当に劇的な変化の予測は原理的にきわめて困難」
で、そうしたなかでも「だが、もしそれが起こった場合に、人間にとってどの程度の影響があるのか知っておくことは重要である」と指摘しています。
また、われわれが経験的に身につけている「天気予報とのつきあい方」を、現在の「100年後に5度の気温上昇」といった予測にもあてはめるべきだとしています。つまり、普通の天気予報なら、明日の予報だと信用するけれど、1週間後になるとそれほど信用しないし、「来年は冷夏」とか言われれば聞き流す。こうした感覚を100年後の野心的な天気予報を聞くときにも大切にすべきだというわけですね。
ということで、気候変動問題における科学的な予測があることは分るんだけれど、EPAのプルイット長官の気持ちも分らなくもないというのは、地球レベルの気候変動問題を科学的かつ真剣に研究してきた中川教授の感覚の方向性と大きく違うわけではないような気がします。あんまり「俺はなんでも分っているんだ」みたいな顔をして、プルイット長官的な人たちをいじめるのもどうかなと。
ここは完全に私見ですが、気候変動問題っていうか、地球温暖化問題についての危機感の大きさは地域差や個人差があって当然だと思います。海面上昇にさらされている小さな島国に住んでいる人は心配で仕方ないでしょうけど、電力不足が一般的な途上国の人だったら、石炭でもなんでもいいからとにかく安く発電所を作ってくれと思うはずです。あと、石炭産業で働いている人は「俺たちにだって生活がある」って思うでしょう。だから温室効果ガス排出の抑制に消極的な立場をとっている人たちを馬鹿にするのはよくない気がします。
ただ、中川教授は過去の気候の専門家ではあるけれど、未来予測を専門としているわけではないと思います。IPCCの報告書のような将来予測については、スーパーコンピューターの上で地球の気候を丸ごと再現して変化を予測する「気候モデリング」の手法で行われているとの説明がありますが、その内容についての詳しい言及はありませんでした。このあたりについても分りやすく説明してくれる本があれば読んでみたいところです。
もしも本当に人類による温室効果ガス排出が10万年サイクルの気候変動のパターンも打ち破って、ガンガンに地球を温暖化させることが確実に分っているっていうんだったら、プルイット長官に石を投げたくなるかもしれません。
2017年3月2日木曜日
“Death by China: Confronting The Dragon--- A Global Call to Action”
“Death by China: Confronting The Dragon--- A Global Call to Action”を読んだ。トランプ大統領が新設したNational Trade CouncilのDirectorに任命されたPeter Navarroカリフォルニア大学アーバイン校教授が書いた本です。南カリフォルニア大学の非常勤教授だったGreg Autryとの共著です。2011年5月に出版されました。
トランプ大統領は2016年12月21日にナバロ氏をNTCのトップに任命すると発表したときの声明で、こんな風に述べています。
“I read one of Peter’s books on America’s trade problems years ago and was impressed by the clarity of his arguments and thoroughness of his research,"
"He has presciently documented the harms inflicted by globalism on American workers, and laid out a path forward to restore our middle class. He will fulfill an essential role in my administration as a trade advisor."
出版のタイミングからみて、トランプ大統領はこの本を読んで感銘を受けたのだと思います。
この本があることは数年前から知っていたのですが、タイトルが過激なものですから「ちょっとトンデモ系の本なのかな」と思って敬遠していました。でも、ちょっとトンデモな人が大統領になって、しかも著者が重用されているということなので、急いで読んでみた次第です。
いかに中国が悪い国かということを啓蒙するために書いた本のようです。”Death by China”というタイトルは誇張して付けたわけではないようで、実際に中国製品の欠陥でたくさんの人が死んでいるとか、中国国内の人権弾圧でたくさんの人が死んでいるとか、中国の環境汚染はたくさんの人を殺しているとか、そういった話がたくさん出てきます。天安門広場の事件もその一例です。さらに中国の軍事力拡大や宇宙開発の促進が米国にとっての安全保障上の脅威になっているという分析もされています。
で、そういった例のなかに、中国が為替操作や企業に対する補助金で輸出価格を不正に引き下げて、米国の製造業に大きな打撃を与えてきたという批判も含まれています。ナバロ氏は中国の経済政策には外国の製造業を破壊する狙いがあるとして、”Eight Weapons of Job Destruction”と名付けた8つの問題点を挙げています。
・違法な輸出補助金
・為替操作
・知的財産の盗用
・緩い環境規制
・緩い労働規制
・違法な関税、輸入割当などの障壁
・ダンピング
・外国企業の進出を拒む規制
こういった話は別にナバロ氏だけが指摘しているわけじゃなくて、オバマ政権下での対中国外交でも繰り返し問題にされてきました。中国の経済政策について詳しいわけじゃないですが、米国企業からそういった不満が出ていることは間違いないです。
ただ、オバマ政権下では「そういった問題はあるけれども、時間をかけて解決を探っていきましょう。気候変動問題とかでは協力できる余地はあるよね」という立場でしたが、ナバロ氏は「こうした問題は非常に大事なことだから、時間をかけて解決するなんていう生ぬるいことではないけない。即刻解決するべきだ」という立場をとっています。もう中国のことなんて、1ミリも信用していないという感じです。
ナバロ氏はこうした問題点がある中国に対して、米国が自由貿易の精神で関わることは大きな間違いだとしています。
“While free trade is great in theory, it rarely exists in the real world. Such conditions are no more found on Earth than the airless, frictionless realm assumed by high-school physics text. In the case of China v. the United States, this seductive free trade theory is very much like a marriage: It doesn’t work if one country cheats on the other.”
ということです。ナバロ氏の結婚生活も気になるところですが、「自由貿易なんてものは存在しないんだ」という主張は分かります。”The Undoing Project”でも経済学の前提自体が間違っているという話があっただけに、経済学の理論ばかりを重視するのもどうかなと思います。
また、ナバロ氏は製造業というのは国家にとって極めて重要だとして、4つの理由を挙げています。
・製造業はサービス業よりも雇用創出効果が大きい。建設とか金融とか小売りとか運輸とかにも影響が広がっていくから。
・製造業の賃金は平均よりも高い。特に女性やマイノリティへのチャンスとなる。
・製造業が強いと、技術革新も進む。長期的に強い経済を維持できるようになる。
・ボーイング、キャタピラー、GMなどの巨大な製造業企業に依存する中小企業がたくさんある。
こういった主張もよくあります。何もナバロ氏だけが極端な話をしているわけではありません。
あと、これまでに読んだ本のなかでも、米国の製造業で働く人たちが高い誇りを抱いているっていう話もよく出てきました。「製造業が衰退すれば、サービス業で働けばいいじゃないか」っていうのは理屈としてはそうかもしれませんが、製造業で働くのが性に合っている人もいます。「製造業は大事」というのはその通りだと思います。
つまり、製造業はものすごく大事なのに、米国の製造業が中国の不正によって衰退させられているから、これは何としてでも解決せねばならないということですね。うん。分かります。
ナバロ氏はこんなことも言っています。
“When America runs a chronic trade deficit with China, this shaves critical points off our economic growth rate. This slower growth rate, in turn, thereby reduces the number of jobs America creates.”
“If America wants to reduce its overall trade deficit to increase its growth rate and create more jobs, the best place to start is with currency reform with China!”
貿易赤字が成長率を引き下げる要因であることは分かります。これは統計上の定義の話です。ただ、成長率が低ければ雇用増のペースが鈍るとか、中国の為替操作をやめさせれば貿易赤字が減るといった理屈が正しいのかどうかは分かりません。それこそ経済学の理論ではそういうことになるのかもしれませんが、実際の世界ではそんなことにはならないなんていう反論もあるんじゃないでしょうか。
まぁ、とはいえ、トランプ大統領に重用されている人物がこう考えているということは間違いないです。
あと、中国政府が多くの米国債を保有するために、以下のような手法をとっているとも指摘しています。
・中国企業は米国への輸出で多くのドルを受け取っている
・中国政府は中国企業に、ドル建ての中国政府債の購入を強要して、ドルを蓄える
・中国政府がドル建ての米国債を購入する
で、中国が米国債をたくさん保有していることは、いざとなったら「米国債を売って、ドル相場を急落させたり、米国の金利を急上昇させてやるぞ」と脅迫できることを意味します。これも割とよく言われることです。また、中国政府が米国債を購入しなければ、米国にとって国債発行の負担が増すわけですから、そもそも米国の財政は中国に依存しているということにもなります。
ナバロ氏は中国が世界中の企業にとっての生産拠点になったきっかけを、1978年に中国共産党が”opened China’s Worker’s Paradise to the West”したことだとしています。中国が何をしたのかは詳しく書いていないですが、カーター政権下で米中共同宣言が出された年ですね。何かあったんだと思いますが、これをきっかけに、おもちゃとかスニーカーとか自転車とか、そういった業種が中国の安い労働力を目当てに製造拠点を移し始めたそうです。
で、2001年に中国がWTOに加盟すると、さらに製造業の移転が進みます。ナバロ氏はこのときは1978年以降とは違い、米国企業は安い労働力だけでなく、中国の補助金とか環境規制の緩さもメリットとして考えていたと主張します。労働力が安い国なら、バングラディシュやカンボジアやベトナムなんていう国もあったことを理由としてあげています。つまりナバロ氏にすれば、米国企業も最初から中国の不正をあてにしていたという意味で、中国と同罪だということです。
そして中国への製造業の移転は現在も続いています。WTO加盟時は生産拠点としての魅力でしたが、今は中国の市場としての魅力も加わっています。中国政府は、外国企業に”minority ownership”しか認めず、”technology transfer”を強要し、研究開発拠点を中国に移すことを強いています。
ナバロ氏はこういう中国の不正な経済活動に対してどんな対応をとればいいのかという提言もしています。
まず、出てくるのが、
“Congress and the President must tell China in no uncertain terms that the United States will no longer tolerate its anything-but-free trade assault on our manufacturing base”
そのうえで、”American Free and Fair Trade Act”を制定するよう求めています。この法律が定めるところは、
“Any nation wishing to trade freely in manufactured goods with the United States must abandon all illegal export subsidies, maintain a fairly valued currency, offer strict protections for intellectual property, uphold environmental and health and safety standards that meet international norms, provide for an unrestricted global market in energy and raw materials, and offer free and open access to its domestic markets, including media and Internet services”
ということだそうです。
ナバロ氏は中国を名指ししているわけじゃなから、直接的な対決は避けられるとしていますが、これまでのナバロ氏の主張からして、「中国とは自由貿易できません」と宣言するのと同じことだと思います。
あと、ナバロ氏は欧州、ブラジル、日本、インド、その他の中国の不正な経済政策の被害にあっている国々と共に、WTOに対して中国にルールを遵守させるよう訴えるともしています。
さらに為替操作については、中国がそう簡単に止めるわけもないと認めていて、水面下での米中交渉を進めるべきだとしています。で、この際に、中国に伝える内容は、
“The United States will have no other choice than to brand China a currency manipulator at the next biennial Treasury Review and impose appropriate countervailing duties unless China strengthens its currency to fair value on its own”
ということです。つまり中国に対して自ら人民元安を是正しないなら、対抗措置として関税をかけるぞと脅すということですね。
でも、中国が脅しに応じない可能性だってあるわけです。その場合は、
“Of course, if China fails to act in a timely manner, the Department of the Treasury must follow through on branding China a currency manipulator and impose appropriate defensive duties to bring the Chinese yuan to fair value”
だそうです。もう貿易戦争やむなしって感じですね。
こうしたナバロ氏の立場に対しては、「米国の製造業が安価な労働力を求めて海外に流出することは避けられないことだし、中国との貿易赤字を解消したって、どうせベトナムとかインドとかバングラみたいな国の製造業が儲かるだけでしょ」なんていう批判があります。まぁ、そうなんだろうな、とも思います。
しかしナバロ氏は反論します。
“We believe the American companies and workers can compete with any in the world on a level playing field, particularly manufacturing where automation and ingenuity often trump manual labor”
そして例え、中国に不正を改めさせることがベトナムとかインドとかバングラに潤いをもたらすだけだったとしても、それはそれで素晴らしいことじゃないかとも言っています。とにかく不正なことをしている中国が世界経済の真ん中に居座っていることは、極めて不健全で、危険なことだというわけです。
この本では中国のサイバー攻撃とか人権問題とか通商政策以外の点についても解決策を提言しています。それぞれ過激だったり、面白かったりしますが、割愛。
まとめますと、ナバロ氏は中国のことを全く信頼していません。後書きでは1989年の天安門事件以降の中国を、ナチ政権下のドイツやスターリン政権下のソ連と同じ扱いにしています。さらに中国による宇宙開発の章なんかでは、”There’s a Death Star Pointing at Chicago”なんていうタイトルもあったりして、中国は銀河帝国と同じぐらい悪いわけです。だから貿易戦争も辞さないというのも当然といえば当然の話です。ちょっと言い過ぎなんじゃないかという気もします。
ただ、「米国に製造業を取り戻す」というのはまともな主張だと思います。グローバリゼーションの進展していった時期と、先進国経済が元気がなくなっていった時期は重なっているわけで、何かしらの関係があるんじゃないかと主張する気持ちは分かります。そんななかでも米国経済は頑張ってきたわけですけど、ここにきてトランプ大統領という強烈なキャラクターが登場したことで、「中国みたいな国があることを考えれば、グローバリズムが常に正しいわけではない」という考え方が表に出てきたということになるんだと思います。
ただ、中国にとっては現在の状況は居心地のいいものであるわけで、中国は現状の変更は望んでいない。日米欧が結束して、中国をWTOから追い出すとか、逆にWTOから出て行って新しい通商圏を作ってしまうとか、そんな「貿易大戦争」っていうシナリオもあるのかもしれませんが、そうなっちゃうと、どうなっちゃうんだという感じもします。
トランプ大統領が「ソ連を崩壊させたレーガン」のイメージを追って、「中国共産党による経済支配を終わらせたトランプ」みたいな路線を目指したりして。実際にそうするかどうかは別にして、トランプ大統領の脳裏にそんなシナリオがないわけじゃないんだと思います。
トランプ大統領は2016年12月21日にナバロ氏をNTCのトップに任命すると発表したときの声明で、こんな風に述べています。
“I read one of Peter’s books on America’s trade problems years ago and was impressed by the clarity of his arguments and thoroughness of his research,"
"He has presciently documented the harms inflicted by globalism on American workers, and laid out a path forward to restore our middle class. He will fulfill an essential role in my administration as a trade advisor."
出版のタイミングからみて、トランプ大統領はこの本を読んで感銘を受けたのだと思います。
この本があることは数年前から知っていたのですが、タイトルが過激なものですから「ちょっとトンデモ系の本なのかな」と思って敬遠していました。でも、ちょっとトンデモな人が大統領になって、しかも著者が重用されているということなので、急いで読んでみた次第です。
いかに中国が悪い国かということを啓蒙するために書いた本のようです。”Death by China”というタイトルは誇張して付けたわけではないようで、実際に中国製品の欠陥でたくさんの人が死んでいるとか、中国国内の人権弾圧でたくさんの人が死んでいるとか、中国の環境汚染はたくさんの人を殺しているとか、そういった話がたくさん出てきます。天安門広場の事件もその一例です。さらに中国の軍事力拡大や宇宙開発の促進が米国にとっての安全保障上の脅威になっているという分析もされています。
で、そういった例のなかに、中国が為替操作や企業に対する補助金で輸出価格を不正に引き下げて、米国の製造業に大きな打撃を与えてきたという批判も含まれています。ナバロ氏は中国の経済政策には外国の製造業を破壊する狙いがあるとして、”Eight Weapons of Job Destruction”と名付けた8つの問題点を挙げています。
・違法な輸出補助金
・為替操作
・知的財産の盗用
・緩い環境規制
・緩い労働規制
・違法な関税、輸入割当などの障壁
・ダンピング
・外国企業の進出を拒む規制
こういった話は別にナバロ氏だけが指摘しているわけじゃなくて、オバマ政権下での対中国外交でも繰り返し問題にされてきました。中国の経済政策について詳しいわけじゃないですが、米国企業からそういった不満が出ていることは間違いないです。
ただ、オバマ政権下では「そういった問題はあるけれども、時間をかけて解決を探っていきましょう。気候変動問題とかでは協力できる余地はあるよね」という立場でしたが、ナバロ氏は「こうした問題は非常に大事なことだから、時間をかけて解決するなんていう生ぬるいことではないけない。即刻解決するべきだ」という立場をとっています。もう中国のことなんて、1ミリも信用していないという感じです。
ナバロ氏はこうした問題点がある中国に対して、米国が自由貿易の精神で関わることは大きな間違いだとしています。
“While free trade is great in theory, it rarely exists in the real world. Such conditions are no more found on Earth than the airless, frictionless realm assumed by high-school physics text. In the case of China v. the United States, this seductive free trade theory is very much like a marriage: It doesn’t work if one country cheats on the other.”
ということです。ナバロ氏の結婚生活も気になるところですが、「自由貿易なんてものは存在しないんだ」という主張は分かります。”The Undoing Project”でも経済学の前提自体が間違っているという話があっただけに、経済学の理論ばかりを重視するのもどうかなと思います。
また、ナバロ氏は製造業というのは国家にとって極めて重要だとして、4つの理由を挙げています。
・製造業はサービス業よりも雇用創出効果が大きい。建設とか金融とか小売りとか運輸とかにも影響が広がっていくから。
・製造業の賃金は平均よりも高い。特に女性やマイノリティへのチャンスとなる。
・製造業が強いと、技術革新も進む。長期的に強い経済を維持できるようになる。
・ボーイング、キャタピラー、GMなどの巨大な製造業企業に依存する中小企業がたくさんある。
こういった主張もよくあります。何もナバロ氏だけが極端な話をしているわけではありません。
あと、これまでに読んだ本のなかでも、米国の製造業で働く人たちが高い誇りを抱いているっていう話もよく出てきました。「製造業が衰退すれば、サービス業で働けばいいじゃないか」っていうのは理屈としてはそうかもしれませんが、製造業で働くのが性に合っている人もいます。「製造業は大事」というのはその通りだと思います。
つまり、製造業はものすごく大事なのに、米国の製造業が中国の不正によって衰退させられているから、これは何としてでも解決せねばならないということですね。うん。分かります。
ナバロ氏はこんなことも言っています。
“When America runs a chronic trade deficit with China, this shaves critical points off our economic growth rate. This slower growth rate, in turn, thereby reduces the number of jobs America creates.”
“If America wants to reduce its overall trade deficit to increase its growth rate and create more jobs, the best place to start is with currency reform with China!”
貿易赤字が成長率を引き下げる要因であることは分かります。これは統計上の定義の話です。ただ、成長率が低ければ雇用増のペースが鈍るとか、中国の為替操作をやめさせれば貿易赤字が減るといった理屈が正しいのかどうかは分かりません。それこそ経済学の理論ではそういうことになるのかもしれませんが、実際の世界ではそんなことにはならないなんていう反論もあるんじゃないでしょうか。
まぁ、とはいえ、トランプ大統領に重用されている人物がこう考えているということは間違いないです。
あと、中国政府が多くの米国債を保有するために、以下のような手法をとっているとも指摘しています。
・中国企業は米国への輸出で多くのドルを受け取っている
・中国政府は中国企業に、ドル建ての中国政府債の購入を強要して、ドルを蓄える
・中国政府がドル建ての米国債を購入する
で、中国が米国債をたくさん保有していることは、いざとなったら「米国債を売って、ドル相場を急落させたり、米国の金利を急上昇させてやるぞ」と脅迫できることを意味します。これも割とよく言われることです。また、中国政府が米国債を購入しなければ、米国にとって国債発行の負担が増すわけですから、そもそも米国の財政は中国に依存しているということにもなります。
ナバロ氏は中国が世界中の企業にとっての生産拠点になったきっかけを、1978年に中国共産党が”opened China’s Worker’s Paradise to the West”したことだとしています。中国が何をしたのかは詳しく書いていないですが、カーター政権下で米中共同宣言が出された年ですね。何かあったんだと思いますが、これをきっかけに、おもちゃとかスニーカーとか自転車とか、そういった業種が中国の安い労働力を目当てに製造拠点を移し始めたそうです。
で、2001年に中国がWTOに加盟すると、さらに製造業の移転が進みます。ナバロ氏はこのときは1978年以降とは違い、米国企業は安い労働力だけでなく、中国の補助金とか環境規制の緩さもメリットとして考えていたと主張します。労働力が安い国なら、バングラディシュやカンボジアやベトナムなんていう国もあったことを理由としてあげています。つまりナバロ氏にすれば、米国企業も最初から中国の不正をあてにしていたという意味で、中国と同罪だということです。
そして中国への製造業の移転は現在も続いています。WTO加盟時は生産拠点としての魅力でしたが、今は中国の市場としての魅力も加わっています。中国政府は、外国企業に”minority ownership”しか認めず、”technology transfer”を強要し、研究開発拠点を中国に移すことを強いています。
ナバロ氏はこういう中国の不正な経済活動に対してどんな対応をとればいいのかという提言もしています。
まず、出てくるのが、
“Congress and the President must tell China in no uncertain terms that the United States will no longer tolerate its anything-but-free trade assault on our manufacturing base”
そのうえで、”American Free and Fair Trade Act”を制定するよう求めています。この法律が定めるところは、
“Any nation wishing to trade freely in manufactured goods with the United States must abandon all illegal export subsidies, maintain a fairly valued currency, offer strict protections for intellectual property, uphold environmental and health and safety standards that meet international norms, provide for an unrestricted global market in energy and raw materials, and offer free and open access to its domestic markets, including media and Internet services”
ということだそうです。
ナバロ氏は中国を名指ししているわけじゃなから、直接的な対決は避けられるとしていますが、これまでのナバロ氏の主張からして、「中国とは自由貿易できません」と宣言するのと同じことだと思います。
あと、ナバロ氏は欧州、ブラジル、日本、インド、その他の中国の不正な経済政策の被害にあっている国々と共に、WTOに対して中国にルールを遵守させるよう訴えるともしています。
さらに為替操作については、中国がそう簡単に止めるわけもないと認めていて、水面下での米中交渉を進めるべきだとしています。で、この際に、中国に伝える内容は、
“The United States will have no other choice than to brand China a currency manipulator at the next biennial Treasury Review and impose appropriate countervailing duties unless China strengthens its currency to fair value on its own”
ということです。つまり中国に対して自ら人民元安を是正しないなら、対抗措置として関税をかけるぞと脅すということですね。
でも、中国が脅しに応じない可能性だってあるわけです。その場合は、
“Of course, if China fails to act in a timely manner, the Department of the Treasury must follow through on branding China a currency manipulator and impose appropriate defensive duties to bring the Chinese yuan to fair value”
だそうです。もう貿易戦争やむなしって感じですね。
こうしたナバロ氏の立場に対しては、「米国の製造業が安価な労働力を求めて海外に流出することは避けられないことだし、中国との貿易赤字を解消したって、どうせベトナムとかインドとかバングラみたいな国の製造業が儲かるだけでしょ」なんていう批判があります。まぁ、そうなんだろうな、とも思います。
しかしナバロ氏は反論します。
“We believe the American companies and workers can compete with any in the world on a level playing field, particularly manufacturing where automation and ingenuity often trump manual labor”
そして例え、中国に不正を改めさせることがベトナムとかインドとかバングラに潤いをもたらすだけだったとしても、それはそれで素晴らしいことじゃないかとも言っています。とにかく不正なことをしている中国が世界経済の真ん中に居座っていることは、極めて不健全で、危険なことだというわけです。
この本では中国のサイバー攻撃とか人権問題とか通商政策以外の点についても解決策を提言しています。それぞれ過激だったり、面白かったりしますが、割愛。
まとめますと、ナバロ氏は中国のことを全く信頼していません。後書きでは1989年の天安門事件以降の中国を、ナチ政権下のドイツやスターリン政権下のソ連と同じ扱いにしています。さらに中国による宇宙開発の章なんかでは、”There’s a Death Star Pointing at Chicago”なんていうタイトルもあったりして、中国は銀河帝国と同じぐらい悪いわけです。だから貿易戦争も辞さないというのも当然といえば当然の話です。ちょっと言い過ぎなんじゃないかという気もします。
ただ、「米国に製造業を取り戻す」というのはまともな主張だと思います。グローバリゼーションの進展していった時期と、先進国経済が元気がなくなっていった時期は重なっているわけで、何かしらの関係があるんじゃないかと主張する気持ちは分かります。そんななかでも米国経済は頑張ってきたわけですけど、ここにきてトランプ大統領という強烈なキャラクターが登場したことで、「中国みたいな国があることを考えれば、グローバリズムが常に正しいわけではない」という考え方が表に出てきたということになるんだと思います。
ただ、中国にとっては現在の状況は居心地のいいものであるわけで、中国は現状の変更は望んでいない。日米欧が結束して、中国をWTOから追い出すとか、逆にWTOから出て行って新しい通商圏を作ってしまうとか、そんな「貿易大戦争」っていうシナリオもあるのかもしれませんが、そうなっちゃうと、どうなっちゃうんだという感じもします。
トランプ大統領が「ソ連を崩壊させたレーガン」のイメージを追って、「中国共産党による経済支配を終わらせたトランプ」みたいな路線を目指したりして。実際にそうするかどうかは別にして、トランプ大統領の脳裏にそんなシナリオがないわけじゃないんだと思います。
登録:
投稿 (Atom)