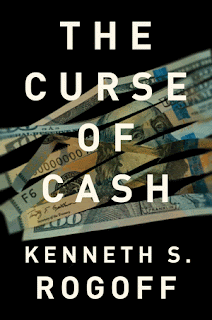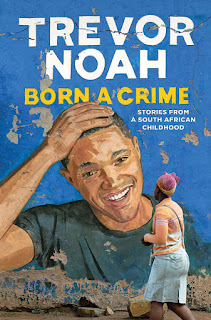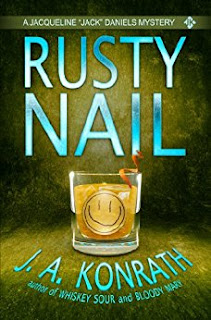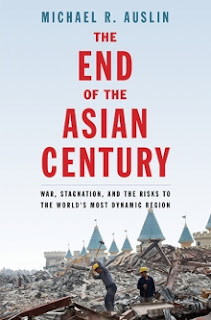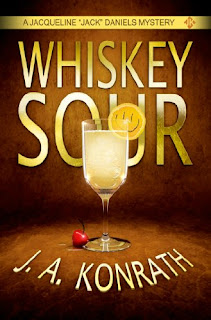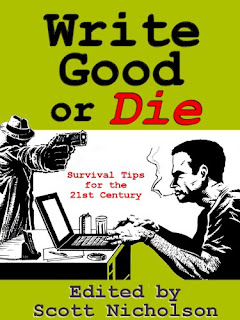TOEFL11回目の結果が出ました。
Reading29, Listening28, Speaking19, Writing24で、100点。一応、目標達成です。
今年6月に受験した前回(10回目)の点数は
Reading29, Listening30, Speaking17, Writing22で、98点でした。
受験時の手応えとしては、Rがダウン、Lがやや減、Sがアップ、Wがダウンで、100点はいかないという予想でした。結果としては、Rで踏みとどまり、Wが予想外にアップした結果、合計で100点を超えたという結果です。
Rは1問目が難しいと感じました。ただし2,3問目を早めに終わらせて、最後の10分ぐらいで1問目も見直しにあてたのがよかったと思います。確か、ひとつ解答を修正しました。
Lは前回が30点ですから、2回連続の満点は難しかった。ただ、リスニングのスキルは昔に比べて格段に上がっている気はします。
課題として取り組んだSは2点アップどまり。1カ月ちょっとのDMM英会話で「話し慣れ」しただけでは大幅な得点アップはならなかったという結果です。20点あれば嬉しかったけど。うちわけとしては、1,2問目がFiar。3,4問目もFair。5,6問目がLimitedです。DMM英会話でも感じていた、複雑な事柄を説明しようとすると、ちょっと自信がなくなるという感じの現れでしょうか。ただし、DMM英会話を続けているうちに、少しずついろんな構文を使って話せるようになってきた実感はありましたから、もうちょっと長い期間やっていれば、5,6問目もFairにできるような気はします。
Wはよく分かりません。2問目で「やっちまった」と思ったわけですが、実際はそうでもなかったのでしょうか。過去最高の24点です。1問目がGoodで、2問目がFairというのは前回と変わりません。ちなみに語数は300語ちょっとです。
2007年1月にアルクのヒアリングマラソンを始めてから(参照)、94点までは2年で到達。そこから100点まで上げるのに、8年以上の年数を要したことになります。ただし94点のときと今の状態を比べると、英語力は格段に上がっている気はしています。まぁ、それでも「英語が少しできます」というぐらいでしょうか。あと10年ぐらいすれば、「英語できます」と自信を持っていえるようになるかもしれません。ならないかもしれないけど。
ちなみに、
2010年6月に受験した9回目は、
Reading26, Listening27, Speaking15, Writing22 で、90点
2007年3月から2008年12月にかけて受験した8回目以前は、
8回目が Reading29, Listening27, Speaking17, Writing21 で、94点
7回目が Reading26, Listening24, Speaking19, Writing20 で、89点
6回目が Reading26, Listening26, Speaking15, Writing21 で、88点
5回目が Reading23, Listening26, Speaking15, Writing20 で、84点
4回目が Reading25, Listening21, Speaking15, Writing18 で、79点
3回目が Reading14, Listening19, Speaking17, Writing15 で、65点
2回目が Reading20, Listening21, Speaking13, Writing17 で、71点
1回目は Reading10, Listening18, Speaking10, Writing14 で、52点
でした。
2017年9月26日火曜日
2017年9月19日火曜日
"Let's Pretend This Never Happened"
"Let's Pretend This Never Happened (A Mostly True Memoir)"という本を読んだ。Jenny Lawsonという女性ブロガーが2012年4月に出した本です。
J.A. Konrathの小説のユーモアが好きでもっと読んでみたいと思うのですが、この人の小説はユーモアかつグロなところがあるので、あんまり沢山読むものでもありません。そこで何かユーモアだけの本はないものかと思って、ファミリーガイで有名なSeth MacFarlanの小説を読んでみたりもしたのですが、なんかイマイチな感じでありました。そんなことを考えているころ、出張で出かけたとある地方空港の本屋さんで「読んだことがある本が置いてあるかなぁ」なんてぶらぶらしていたら、"Humor"をいうコーナーがあるのを見つけました。なるほど、"Humor"でひとつのジャンルになっているのか。
そんなわけでアマゾンで"Humor"と検索してみたら、一番上に出てきたのがこの本でした。4000件近くもレビューがついているので、よく売れた本なのでしょう。で、読んでみました。かなり面白かったです。
内容を説明するのは難しいので、第1章の冒頭部分をそのまま引用します。
Call me Ishmael. I won't answer to it, because it's not my name, but it's much more agreeable than most of the things I've been called. "Call me 'that-weird-chick-who-says-"fuck"-a-lot'" is probably more accurate, but "Ismael" seems classier, and it makes a way more respectable beginning than the sentence I'd originally written, which was about how I'd just run into my gynecologist at Starbucks and she totally looked right past me like she didn't even know me. And so I stood there wondering whether that's something she does on purpose to make her clients feel less uncomfortable, or whether she just genuinely didn't recognize me without my vagina. Either way, it's very disconcerting when people who've been inside your vagina don't acknowledge your existence. Also, I just want to clarify that I don't mean "without my vagina" like I didn't have it with me at the time. I just meant that I wasn't, you know... displaying it while I was at Starbucks. That's probably understood, but I thought I should clarify, since it's the first chapter and you don't know that much about me. it's like my American Express card. (In that I don't leave home without it. Not that I use it to buy stuff with.)
何を言っているんでしょうかね、この人は。
とまぁ、こんな風に、ついついおかしなことばかり考えてしまうローソンさんの妄想日記みたいな趣の本です。
なので、学ぶべきこととか、そういうものはありません。ただ、若い頃にLSDを使ったときのエピソードとかは面白かったです。
A guy I knew had a house on the outskirts of town and offered to host a small LSD party for me and several other people in our group who'd never done acid before either. So we called Travis and asked him to bring over enough acid for six of us that night. Travis arrived and told us the drugs were on their way, and about fifteen minutes later a pizza delivery car pulled up. The delivery guy came to the door with a mushroom pizza and an uncut sheet of acid. The delivery guy was in his late teens, about two feet shorter than me, and very, very white, but he did have a piercing and a pager (which was very impressive, because this was still back in the early nineties, although probably the pager was just used for pizza orders). His name was Jacob. Travis told me later that anyone could by acid from Jacob if they knew the "secret code" to use when you called the pizza place. At the time I thought it was probably something all cloak-and dagger, like "One pepperoni pizza, hold the crust," or "A large cheesy bread and the bird flies at midnight," but in reality it was probably just "And tell Jacob to bring some acid," because honestly neither of them was very imaginative.
Jacob sold Travis the acid for four dollars a hit, and then Travis turned around and sold it to us for five dollars a hit, which was awkward and also a poor profit margin. We each took a hit and Travis said that for another ten bucks he'd stay and babysit us to make sure we didn't cut our hand off. This wasn't something I was actually worried about at all until he mentioned it, but now that the thought was implanted in our heads I became convinced that we would all cut our hands off as soon as he left, so I handed him a ten. Travis cautioned us that if we thought the house cats next door were sending us threatening messages, they probably weren't. And he warned us not to stare at the sun because we'd go blind (which might have been great advice if it hadn't been ten o'clock at night). "Ride the beast... don't let the beast ride you," our wise sage advised us.
このあと、実際にLSDを使ってみて、なんだかんだとバタバタとした展開があります。
ローソンさんのことですから、全部が全部本当というわけじゃないと思いますけど、こんな感じの軽いトーンでドラッグパーティーが開かれるもんなんだなという点が興味深い。知り合いの知り合いみたいな距離感の交友関係から、ドラッグを使うことを目的としたパーティーを開くというお誘いがあって、ちょっと不安だななんて思いながらも、値段もそんなに高くないし、友達もやるっていうし、ちゃんとした「保護者役」もいてくれるというから、ちょっと使ってみようかっていうノリですね。
米国では薬物依存が大きな問題になっているわけですが、今の若者の間でもこんな雰囲気のパーティーが開かれているのだとすれば、好奇心の方が勝ってしまうというのも分からんでもないです。ローソンさんはことのきのLSDでみた幻覚から醒めた後で、幻覚中に自分がとった行動を知って、もうLSDはやらないと思ったそうです。だからまぁ実際の話、一度使えば絶対に後戻りできないというものでもないんじゃないかとも思います。もちろん「ダメ、絶対」ですけどね。最初のLSDの経験が良い記憶として残ってしまえば、常習化していくでしょうし、常習化すれば依存にもつながるのでしょう。でも、「ダメ、絶対」にも関わらず、「ダメ、絶対」になっていない事情の裏には、こんな雰囲気があるんだなということです。
いや「ダメ、絶対」ですからね。ダメですよ、本当に。
J.A. Konrathの小説のユーモアが好きでもっと読んでみたいと思うのですが、この人の小説はユーモアかつグロなところがあるので、あんまり沢山読むものでもありません。そこで何かユーモアだけの本はないものかと思って、ファミリーガイで有名なSeth MacFarlanの小説を読んでみたりもしたのですが、なんかイマイチな感じでありました。そんなことを考えているころ、出張で出かけたとある地方空港の本屋さんで「読んだことがある本が置いてあるかなぁ」なんてぶらぶらしていたら、"Humor"をいうコーナーがあるのを見つけました。なるほど、"Humor"でひとつのジャンルになっているのか。
そんなわけでアマゾンで"Humor"と検索してみたら、一番上に出てきたのがこの本でした。4000件近くもレビューがついているので、よく売れた本なのでしょう。で、読んでみました。かなり面白かったです。
内容を説明するのは難しいので、第1章の冒頭部分をそのまま引用します。
Call me Ishmael. I won't answer to it, because it's not my name, but it's much more agreeable than most of the things I've been called. "Call me 'that-weird-chick-who-says-"fuck"-a-lot'" is probably more accurate, but "Ismael" seems classier, and it makes a way more respectable beginning than the sentence I'd originally written, which was about how I'd just run into my gynecologist at Starbucks and she totally looked right past me like she didn't even know me. And so I stood there wondering whether that's something she does on purpose to make her clients feel less uncomfortable, or whether she just genuinely didn't recognize me without my vagina. Either way, it's very disconcerting when people who've been inside your vagina don't acknowledge your existence. Also, I just want to clarify that I don't mean "without my vagina" like I didn't have it with me at the time. I just meant that I wasn't, you know... displaying it while I was at Starbucks. That's probably understood, but I thought I should clarify, since it's the first chapter and you don't know that much about me. it's like my American Express card. (In that I don't leave home without it. Not that I use it to buy stuff with.)
何を言っているんでしょうかね、この人は。
とまぁ、こんな風に、ついついおかしなことばかり考えてしまうローソンさんの妄想日記みたいな趣の本です。
なので、学ぶべきこととか、そういうものはありません。ただ、若い頃にLSDを使ったときのエピソードとかは面白かったです。
A guy I knew had a house on the outskirts of town and offered to host a small LSD party for me and several other people in our group who'd never done acid before either. So we called Travis and asked him to bring over enough acid for six of us that night. Travis arrived and told us the drugs were on their way, and about fifteen minutes later a pizza delivery car pulled up. The delivery guy came to the door with a mushroom pizza and an uncut sheet of acid. The delivery guy was in his late teens, about two feet shorter than me, and very, very white, but he did have a piercing and a pager (which was very impressive, because this was still back in the early nineties, although probably the pager was just used for pizza orders). His name was Jacob. Travis told me later that anyone could by acid from Jacob if they knew the "secret code" to use when you called the pizza place. At the time I thought it was probably something all cloak-and dagger, like "One pepperoni pizza, hold the crust," or "A large cheesy bread and the bird flies at midnight," but in reality it was probably just "And tell Jacob to bring some acid," because honestly neither of them was very imaginative.
Jacob sold Travis the acid for four dollars a hit, and then Travis turned around and sold it to us for five dollars a hit, which was awkward and also a poor profit margin. We each took a hit and Travis said that for another ten bucks he'd stay and babysit us to make sure we didn't cut our hand off. This wasn't something I was actually worried about at all until he mentioned it, but now that the thought was implanted in our heads I became convinced that we would all cut our hands off as soon as he left, so I handed him a ten. Travis cautioned us that if we thought the house cats next door were sending us threatening messages, they probably weren't. And he warned us not to stare at the sun because we'd go blind (which might have been great advice if it hadn't been ten o'clock at night). "Ride the beast... don't let the beast ride you," our wise sage advised us.
このあと、実際にLSDを使ってみて、なんだかんだとバタバタとした展開があります。
ローソンさんのことですから、全部が全部本当というわけじゃないと思いますけど、こんな感じの軽いトーンでドラッグパーティーが開かれるもんなんだなという点が興味深い。知り合いの知り合いみたいな距離感の交友関係から、ドラッグを使うことを目的としたパーティーを開くというお誘いがあって、ちょっと不安だななんて思いながらも、値段もそんなに高くないし、友達もやるっていうし、ちゃんとした「保護者役」もいてくれるというから、ちょっと使ってみようかっていうノリですね。
米国では薬物依存が大きな問題になっているわけですが、今の若者の間でもこんな雰囲気のパーティーが開かれているのだとすれば、好奇心の方が勝ってしまうというのも分からんでもないです。ローソンさんはことのきのLSDでみた幻覚から醒めた後で、幻覚中に自分がとった行動を知って、もうLSDはやらないと思ったそうです。だからまぁ実際の話、一度使えば絶対に後戻りできないというものでもないんじゃないかとも思います。もちろん「ダメ、絶対」ですけどね。最初のLSDの経験が良い記憶として残ってしまえば、常習化していくでしょうし、常習化すれば依存にもつながるのでしょう。でも、「ダメ、絶対」にも関わらず、「ダメ、絶対」になっていない事情の裏には、こんな雰囲気があるんだなということです。
いや「ダメ、絶対」ですからね。ダメですよ、本当に。
2017年9月17日日曜日
TOEFL(11回目)受験
TOEFL11回目を受験してきました。
今年6月に受験した前回(10回目)の点数は
Reading29, Listening30, Speaking17, Writing22で、98点でした。
今回の手応えとしては「やっちまったなぁ」という感じです。
とりあえずReadingの1問目が難しいと感じた。得意種目でつまづいた形で、前回より1、2点は下がっているかも。
Listeningは前回とさほど変わらない手応え。でもまぁ前回が満点ですから、1点マイナスぐらいは覚悟せねば。
問題のSpeakingですが、6問中2問は回答の時間配分をミスして「タイムアップギリギリで回答を詰め込む」形になってしまいました。一応、この1カ月ちょっとDMM英会話に取り組んで「話し慣れ」はしたつもりなんですが、どこまで点が上がるかは分からない。前回のスコアを見直してみたところ、1,2問目がFair。3,4問目がLimited。5、6問目がLimitedでした。これがすべてのセクションでFiarになってくれていると嬉しいんですがね。
で、Writingなんですが、2問目の設問が「それとそれを比較するの?」っていうようなテーマで、回答の内容に自信が持てない。ここが一番「やっちまった」と感じているところなんですが、これは自分のスキルというよりは出題に振り回された感じがする。1問目はまぁ、できたと思います。前回は、1問目がGoodで、2問目がFair。今回も同じようなものじゃないでしょうか。でも点数的には下がっている予感がプンプンします。
トータルで考えると、Speaking以外で3,4点は下がっていると覚悟しています。それでも100点に到達しようと思えば、Speakingで5,6点上げなければならないわけですが、せいぜい3点アップぐらいが関の山じゃないかと。ということは最終的な点数は98点とか97点あたりで、残念ながらミッション達成ならずってことになります。
これほど結果が出るのが楽しみじゃないTOEFLも珍しい。
ちなみに、
2010年6月に受験した9回目は、
Reading26, Listening27, Speaking15, Writing22 で、90点
2007年3月から2008年12月にかけて受験した8回目以前は、
8回目が Reading29, Listening27, Speaking17, Writing21 で、94点
7回目が Reading26, Listening24, Speaking19, Writing20 で、89点
6回目が Reading26, Listening26, Speaking15, Writing21 で、88点
5回目が Reading23, Listening26, Speaking15, Writing20 で、84点
4回目が Reading25, Listening21, Speaking15, Writing18 で、79点
3回目が Reading14, Listening19, Speaking17, Writing15 で、65点
2回目が Reading20, Listening21, Speaking13, Writing17 で、71点
1回目は Reading10, Listening18, Speaking10, Writing14 で、52点
となっております。
今年6月に受験した前回(10回目)の点数は
Reading29, Listening30, Speaking17, Writing22で、98点でした。
今回の手応えとしては「やっちまったなぁ」という感じです。
とりあえずReadingの1問目が難しいと感じた。得意種目でつまづいた形で、前回より1、2点は下がっているかも。
Listeningは前回とさほど変わらない手応え。でもまぁ前回が満点ですから、1点マイナスぐらいは覚悟せねば。
問題のSpeakingですが、6問中2問は回答の時間配分をミスして「タイムアップギリギリで回答を詰め込む」形になってしまいました。一応、この1カ月ちょっとDMM英会話に取り組んで「話し慣れ」はしたつもりなんですが、どこまで点が上がるかは分からない。前回のスコアを見直してみたところ、1,2問目がFair。3,4問目がLimited。5、6問目がLimitedでした。これがすべてのセクションでFiarになってくれていると嬉しいんですがね。
で、Writingなんですが、2問目の設問が「それとそれを比較するの?」っていうようなテーマで、回答の内容に自信が持てない。ここが一番「やっちまった」と感じているところなんですが、これは自分のスキルというよりは出題に振り回された感じがする。1問目はまぁ、できたと思います。前回は、1問目がGoodで、2問目がFair。今回も同じようなものじゃないでしょうか。でも点数的には下がっている予感がプンプンします。
トータルで考えると、Speaking以外で3,4点は下がっていると覚悟しています。それでも100点に到達しようと思えば、Speakingで5,6点上げなければならないわけですが、せいぜい3点アップぐらいが関の山じゃないかと。ということは最終的な点数は98点とか97点あたりで、残念ながらミッション達成ならずってことになります。
これほど結果が出るのが楽しみじゃないTOEFLも珍しい。
ちなみに、
2010年6月に受験した9回目は、
Reading26, Listening27, Speaking15, Writing22 で、90点
2007年3月から2008年12月にかけて受験した8回目以前は、
8回目が Reading29, Listening27, Speaking17, Writing21 で、94点
7回目が Reading26, Listening24, Speaking19, Writing20 で、89点
6回目が Reading26, Listening26, Speaking15, Writing21 で、88点
5回目が Reading23, Listening26, Speaking15, Writing20 で、84点
4回目が Reading25, Listening21, Speaking15, Writing18 で、79点
3回目が Reading14, Listening19, Speaking17, Writing15 で、65点
2回目が Reading20, Listening21, Speaking13, Writing17 で、71点
1回目は Reading10, Listening18, Speaking10, Writing14 で、52点
となっております。
2017年8月30日水曜日
"The Curse of Cash"
"The Curse of Cash: How Large-Denomination Bills Aid Crime and Tax Evasion and Constrain Monetary Policy"という本を読んだ。2016年にハーバード大学のケネス・ロゴフ教授が出した、100ドルとか1万円みたいな高額紙幣がいかに犯罪や脱税に使われていて、金融政策の足かせにもなっているかということを解説した本です。タイトルそのまんまですね。
ロゴフ教授といえば、"This Time is Different"という国家の財政破綻の歴史について書いた本で有名になった人です。留学中にとった授業で教科書に指定されていたことと、その授業でBをとってしまったことが懐かしい。バーマン教授には心から御礼申し上げます。
で、この本でいわんとすることはさきほど書いた通りです。実際には高額紙幣がどのぐらい使われていて、それがどのぐらい犯罪や脱税に関わっているかなんていうことはオフィシャルな統計で示せるわけではないのですが、ロゴフ教授は入手可能なデータを駆使して、さらにそこに色んな仮定を重ねて、自説を補強していきます。現金がいかに闇経済で使われているかというのは、以前に読んだExorbitant Privilegeでも触れられていました。まぁ、具体的な規模は分かりませんが、そりゃそうだろうなという気はします。
あと、金融政策については、マイナス金利政策の効果が高額紙幣によって損なわれると主張します。中央銀行は景気を刺激するために金利を引き下げるわけですが、政策金利がゼロにまで到達してしまうと、そこから先は金利を引き下げることはできない。そこで量的緩和政策なんていうのが発案されたわけですが、それがどのぐらい景気を刺激する効果があったかどうかはよく分からないわけです。そこで、日本や欧州はマイナス金利を採用するようになりました。ところが中央銀行がマイナス金利をかけて景気を刺激しようとしても、預金者が銀行口座のお金を現金化してしまえば、そこにはマイナス金利の影響は及ばないわけです。だから、大きなお金の金額の現金化のツールである高額紙幣が金融政策のあしかせになっているといえるという主張です。
ロゴフ教授はここから、だから高額紙幣は廃止するべきだ。各種カードによる電子決済が普及している先進国だったら十分に可能だし、それで犯罪を抑え込み、金融政策の効果も大きくなるんだったら、いいことじゃないかと話を進めます。
こういう主張をすると、中央銀行の通貨発行益(シニョレッジ)が失われるからだめだとか、低所得者はカードなんて持っていないんだから困るだろうとか、犯罪者は高額紙幣が廃止されたって別の抜け道を見つけるだろうとか、マイナス金利みたいな銀行から強制的にお金を巻き上げるようなことをしていいのかとか、いろんな反論が出るそうです。で、ロゴフ教授は、そうした反論の有効性をひとつひとつ検証して、やっぱり高額紙幣廃止によるメリットの方が大きいですよね、と結論づけます。
まぁ、それだけの本です。ハーバードの教授が高額紙幣を廃止したらいいんじゃないのと思いついて、自説の正しさを証明するために反論を丁寧につぶしていく。ただ、個人的には高額紙幣廃止で犯罪が抑制できるんだからそれでいいじゃないかと思うんですが、別にそこまで説明してくれなくてもいいよっていう感じもします。「電子決済が普及しているんで、高額紙幣はなくてもいいですよね」って一言だけ言ってくれれば、みんなそれで納得するんじゃないか。
ただしシヨレッジについて丁寧に説明してくれるのはありがたかったです。中央銀行は通貨を発行することで利益を得られるっていうのはいろんなところで見聞きするんですが、具体的にはどういうことが行われているのかよく分からなかったからです。「何か物が欲しいときに印刷機を動かして好きなだけ紙幣を作っているの?」なんていう風にも思えるわけですが、実際には以下のような手順を踏んでいるそうです。
1.政府が収入以上にお金を使って、それを賄うために債券(debt)を発行する
2.中央銀行が市中からdebtを買い取る。この際、electric bank reserve (which are the electric equivalent of cash)を発行する
3.bank reserveに対して中央銀行が払う利息よりも、debtから得られる利息の方が大きいので中央銀行には長期的に利益が出る
2のところがミソなんでしょうけど、中央銀行は市中からdebtを買い取るときに売り手である銀行に現金を渡すわけじゃなくて、銀行の当座預金の残高の数字を変更するだけなわけですね。これが現代における通貨の発行だというわけです。で、いつでも引き出し可能な当座預金につく利息は、政府が発行した債券につく利息よりも小さい。だから3のところで中央銀行に利益が出る。これがいわゆるシニョレッジ(通貨発行益)というわけです。
だから、高額紙幣が廃止されて、印刷機を動かせなくなっても、中央銀行は利益を出すことができます。ロゴフ教授は"even if paper money revenue disappeared completely, the central bank would still earn money from electronic reserves"と明言しています。
ちなみにこの通貨発行益は中央銀行から政府に納められます。結局、政府は一切損をしていないようにも思ってしまいそうですが、実際には当座預金についた利息分は政府の負担が生じているのだと思います。ここは私の勝手な理解です。
また、ロゴフ氏は高額紙幣を廃止する際には、政府・中央銀行は債券を発行して高額紙幣を買い取らねばならない(it will have to issue ordinary interest-bearing debt to buy back the currency it is retiring)と書いています。
ここのところは直感的によく分からなかったのですが、多分、こういうことです。
1.「高額紙幣を廃止するぞ」とのお達しに従って、銀行が金庫に入っている大量の1万円札を中央銀行に持ち込む
2.中央銀行は銀行から受け取った金額を銀行の当座預金に電子的に記入する
3.でも、この受け取った大量の1万円札は無効になったただの紙切れだから、現金としてはもう使えない
4.だから、中央銀行の損失を埋めるために、政府は債券を発行して資金を調達せねばならない
どうでしょう。これで正しいんでしょうか?
とまぁ、こんなことをつらつらと説明している本です。
This time is differentのときは「そうか。やっぱり政府が負債を積み上げすぎるのは問題だな」という気がしましたが、今回は「知らんがな」という感は否めません。
ロゴフ教授といえば、"This Time is Different"という国家の財政破綻の歴史について書いた本で有名になった人です。留学中にとった授業で教科書に指定されていたことと、その授業でBをとってしまったことが懐かしい。バーマン教授には心から御礼申し上げます。
で、この本でいわんとすることはさきほど書いた通りです。実際には高額紙幣がどのぐらい使われていて、それがどのぐらい犯罪や脱税に関わっているかなんていうことはオフィシャルな統計で示せるわけではないのですが、ロゴフ教授は入手可能なデータを駆使して、さらにそこに色んな仮定を重ねて、自説を補強していきます。現金がいかに闇経済で使われているかというのは、以前に読んだExorbitant Privilegeでも触れられていました。まぁ、具体的な規模は分かりませんが、そりゃそうだろうなという気はします。
あと、金融政策については、マイナス金利政策の効果が高額紙幣によって損なわれると主張します。中央銀行は景気を刺激するために金利を引き下げるわけですが、政策金利がゼロにまで到達してしまうと、そこから先は金利を引き下げることはできない。そこで量的緩和政策なんていうのが発案されたわけですが、それがどのぐらい景気を刺激する効果があったかどうかはよく分からないわけです。そこで、日本や欧州はマイナス金利を採用するようになりました。ところが中央銀行がマイナス金利をかけて景気を刺激しようとしても、預金者が銀行口座のお金を現金化してしまえば、そこにはマイナス金利の影響は及ばないわけです。だから、大きなお金の金額の現金化のツールである高額紙幣が金融政策のあしかせになっているといえるという主張です。
ロゴフ教授はここから、だから高額紙幣は廃止するべきだ。各種カードによる電子決済が普及している先進国だったら十分に可能だし、それで犯罪を抑え込み、金融政策の効果も大きくなるんだったら、いいことじゃないかと話を進めます。
こういう主張をすると、中央銀行の通貨発行益(シニョレッジ)が失われるからだめだとか、低所得者はカードなんて持っていないんだから困るだろうとか、犯罪者は高額紙幣が廃止されたって別の抜け道を見つけるだろうとか、マイナス金利みたいな銀行から強制的にお金を巻き上げるようなことをしていいのかとか、いろんな反論が出るそうです。で、ロゴフ教授は、そうした反論の有効性をひとつひとつ検証して、やっぱり高額紙幣廃止によるメリットの方が大きいですよね、と結論づけます。
まぁ、それだけの本です。ハーバードの教授が高額紙幣を廃止したらいいんじゃないのと思いついて、自説の正しさを証明するために反論を丁寧につぶしていく。ただ、個人的には高額紙幣廃止で犯罪が抑制できるんだからそれでいいじゃないかと思うんですが、別にそこまで説明してくれなくてもいいよっていう感じもします。「電子決済が普及しているんで、高額紙幣はなくてもいいですよね」って一言だけ言ってくれれば、みんなそれで納得するんじゃないか。
ただしシヨレッジについて丁寧に説明してくれるのはありがたかったです。中央銀行は通貨を発行することで利益を得られるっていうのはいろんなところで見聞きするんですが、具体的にはどういうことが行われているのかよく分からなかったからです。「何か物が欲しいときに印刷機を動かして好きなだけ紙幣を作っているの?」なんていう風にも思えるわけですが、実際には以下のような手順を踏んでいるそうです。
1.政府が収入以上にお金を使って、それを賄うために債券(debt)を発行する
2.中央銀行が市中からdebtを買い取る。この際、electric bank reserve (which are the electric equivalent of cash)を発行する
3.bank reserveに対して中央銀行が払う利息よりも、debtから得られる利息の方が大きいので中央銀行には長期的に利益が出る
2のところがミソなんでしょうけど、中央銀行は市中からdebtを買い取るときに売り手である銀行に現金を渡すわけじゃなくて、銀行の当座預金の残高の数字を変更するだけなわけですね。これが現代における通貨の発行だというわけです。で、いつでも引き出し可能な当座預金につく利息は、政府が発行した債券につく利息よりも小さい。だから3のところで中央銀行に利益が出る。これがいわゆるシニョレッジ(通貨発行益)というわけです。
だから、高額紙幣が廃止されて、印刷機を動かせなくなっても、中央銀行は利益を出すことができます。ロゴフ教授は"even if paper money revenue disappeared completely, the central bank would still earn money from electronic reserves"と明言しています。
ちなみにこの通貨発行益は中央銀行から政府に納められます。結局、政府は一切損をしていないようにも思ってしまいそうですが、実際には当座預金についた利息分は政府の負担が生じているのだと思います。ここは私の勝手な理解です。
また、ロゴフ氏は高額紙幣を廃止する際には、政府・中央銀行は債券を発行して高額紙幣を買い取らねばならない(it will have to issue ordinary interest-bearing debt to buy back the currency it is retiring)と書いています。
ここのところは直感的によく分からなかったのですが、多分、こういうことです。
1.「高額紙幣を廃止するぞ」とのお達しに従って、銀行が金庫に入っている大量の1万円札を中央銀行に持ち込む
2.中央銀行は銀行から受け取った金額を銀行の当座預金に電子的に記入する
3.でも、この受け取った大量の1万円札は無効になったただの紙切れだから、現金としてはもう使えない
4.だから、中央銀行の損失を埋めるために、政府は債券を発行して資金を調達せねばならない
どうでしょう。これで正しいんでしょうか?
とまぁ、こんなことをつらつらと説明している本です。
This time is differentのときは「そうか。やっぱり政府が負債を積み上げすぎるのは問題だな」という気がしましたが、今回は「知らんがな」という感は否めません。
2017年8月17日木曜日
"The Healing of America"
"The Healing of America: A Global Quest for Better, Cheaper, and Fairer Health Care"という本を読んだ。T. R. Reidという、慢性的な肩の痛みを抱えるジャーナリストが世界各国の医者にかかりながら、各国の医療制度について探求し、米国の医療保険制度の問題点をあぶり出すという内容です。2010年8月出版。オバマケア関連法案成立して間もないころですね。
とても面白かった。American Sicknessよりも格段に読みやすい。米国医療がいかにしてダメになっていったかということはAmerican Sicknessでこれでもかと言わんばかりに書かれていたわけですが、こちらのThe Healing of Americaでは、他の国はどうしてダメになっていないのかということが書かれています。さらに、かつてはダメな制度だったのに改革に成功した、台湾とスイスのケースも紹介しています。なのでAmerican Sicknessよりも救いがあります。
書かれていることは単純。米国の医療制度をまともなものにするには、国民が「全員が医療保険に加入できるべきだ」という考え方で一致できるかどうかがキモだということです。世界の医療保険制度はいろんな仕組みがありますが、米国以外の先進国はすべてこの考え方に基づいています。
ところが米国ではこういう主張をすると、必ず「社会主義化された医療制度だ! ムダだらけで、革新も生まれない。国民の医療への選択肢も狭められる。自由を尊ぶ米国の理念に反する」という反発が出ます。そういった主張に、現在の医療保険制度で恩恵を受けている医療保険会社や医療機関、製薬会社が乗っかってロビー活動を展開するので、議会は動きがとれなくなります。オバマ大統領に上院60議席、下院過半数の議席を与えたって、問題は解決できなかったわけですからなかなか根深い問題です。
そこでリードさんは、こうした「社会主義化された医療制度だ!」という批判は的外れだと繰り返し説明します。
まず、他の先進国の医療制度は別に社会主義化されているわけではないという点です。
リードさんは先進国の医療制度を以下のように分類します。
ビスマルク型(ドイツ、日本など)=医療保険提供者が民間、医療サービス提供者も民間
ベバリッジ型(英国、北欧など)=医療保険提供者が国、医療サービス提供者も国
国民健康保険型(カナダ、韓国など)=医療保険提供者は国、医療サービス提供者は民間
まぁ、ベバレッジ型は国が全面的に関与していますから、バリバリの自由経済主義者からみれば「社会主義的」といえるかもしれません。でも英国を社会主義国だと思う人は多くはないです。あとビスマルク型や国民健康保険型は民間が関与していますから、社会主義ってわけじゃないですよね。
ただし、こうした民間が関与する仕組みでも規制はきついです。例えばビスマルク型として取り上げられている日本は、医療保険は主に企業別の医療保険組合が提供していて、医療サービスも民間がやっているわけですが、医薬品の価格なんかは政府がコントロールしているわけです。それは「すべての国民が医療保険に加入できるべきだ」との考え方から正当化されます。こうした厳しい規制のおかげで日本の医療費は国際的にみて安いですし、しかも患者は自由に医療機関を選べる。
ベバレッジ型は医療保険も医療サービスも国が主体です。そのおかげで患者は病院に行っても請求書を受け取ることはありません。それだったら患者が好きなだけ病院に行くことになって医療費が高騰しそうなものですが、「国はすべての人を保険でカバーするけれど、すべての医療行為をカバーするわけじゃない」という立場をとっているため、たいしたことのない病気であったりすれば病院にかかる前に行くことになる"general practitioner"のオフィスの段階で「病院に行かなくていいですよ。様子をみましょう」ということになる。また、すべての医療費は国民の税金で負担することになりますから、有権者や政治家も医療費の無駄遣いには敏感です。「94歳の女性への人工関節手術を認めるべきか」「50歳以上の男性すべてに前立腺がんの検査を認めるべきか」といった問題が、医学的なエビデンスの基づいて議論されたりします。
国民健康保険型も医療保険を国が提供するわけですから、どんな治療に対しても費用を払うというわけではないです。医療サービスは民間ですから、民間同士の競争がありますし、国がいくらでも医療費を払ってくれるわけじゃないので、コスト意識が働きます。
もちろん、それぞれの制度には問題点があります。日本なんかは「医療従事者の報酬が低い」なんていう問題点も指摘されます。ベバレッジ型の英国や北欧は米国に比べて税金が高いです。国民健康保険型のカナダなんかは、緊急性がない治療の場合は、受診までに数カ月~1年以上も待たねばならないという問題があります。
ただ、それだって米国の医療制度よりは格段にいいわけです。一人あたり医療費は安いし、健康を維持できる年齢も高い。どこの国だって「米国みたいにはなりたくない」と思っています。それなのに、どうして米国が現在の米国の医療制度にこだわる必要があるのかというわけです。
リードさんはさらに、米国内の「他の国の医療制度は自由を尊ぶ米国の理念に反する」という意見も的外れだとします。それは米国の医療制度のなかには、すでにこれらの仕組みが根を張っているからです。
例えば、高齢者向け公的医療保険のメディケアは国が医療費を負担して民間が医療サービスを提供していますから国民健康保険型です。退役軍人向けには専門の病院もありますから、これは医療保険も医療サービスも国が提供するベバリッジ型です。そのほかの企業が提供する医療保険に加入している米国人にとっては、ビスマルク型の医療保険制度が存在しているわけです。
ただ、米国には「全員が医療保険に加入できるべきだ」という理念がないために、どの制度からもこぼれてしまっている人たちがいます。メディケアに入れるほど年寄りではないし、低所得者向けのメディケイドに入れるほど所得が低いわけでもないし、医療保険を提供してくれる会社に勤めているわけでもないし、退役軍人でもないという人たちですね。この人たちは行き所がないです。利益目的の保険会社に高い保険料や高い自己負担額を強いられ、病院からも高い医療費を請求されて、生活を維持できなくなってしまうような人たちです。さらに医療保険を提供してくれる会社に勤めていたけど、病気で仕事を続けられなくなって退職したら、医療保険がなくなったなんていう事態も起きるわけです。
また、こうした医療保険制度のパッチワーク状態が余計なコストを生みます。オバマケアはこのパッチワークに拍車をかけました。
リードさんはこう書いています。
Facing an entrenched army of well-financed and powerful interests determined to preserve the status quo, Obama declared from the start that he would not seek to replace the existing health care system with a simpler, cheaper model. "We have to build on what we've got already," Obama said. The result was an enormously expensive and complicated piece of legislation ---the "Obamacare" bill runs to 2,400 pages of legalese ---that retains most of the structure of the U.S. system ....
もちろんリードさんはオバマケアが結果的に無保険者を大幅に減らすであろうことや、保険会社が病歴のある人の加入を断ることを禁じる制度を作ったことは高く評価しているわけですが、根本的な問題解決にはほど遠いということなんでしょう。
あと、リードさんは医療保険制度の抜本的な改革に成功した台湾やスイスの取り組みも詳しく取り上げています。どちらも、まず最初にリベラル側が「全員が医療保険に加入できるべきだ」と声を上げ、それを国民が熱狂的に支持し、保守側が人気とりのためにそれを受け入れたという展開だったようです。あと、どちらも経済が好調だったという背景もあるそうです。
米国では2016年に民主党の大統領候補指名争いで健闘したバーニー・サンダース上院議員が"single-payer"のシステムを目指しています。これは医療保険を国が提供するという意味です。オバマケアの失敗を踏まえたうえで、より抜本的な改革を実現させるということなのでしょう。
じゃあ、2020年の大統領選で79歳になったサンダース氏が当選。そのときには2018年の中間選挙と大統領選と同時に行われる議会選挙で、上下両院ともに民主党が過半数を握っていて、サンダース氏が訴える抜本的な医療保険制度改革をトランプ政権にこりた共和党も受け入れる。そんなシナリオはどうでしょうか。
どうでしょうか。米国人のみなさん。
とても面白かった。American Sicknessよりも格段に読みやすい。米国医療がいかにしてダメになっていったかということはAmerican Sicknessでこれでもかと言わんばかりに書かれていたわけですが、こちらのThe Healing of Americaでは、他の国はどうしてダメになっていないのかということが書かれています。さらに、かつてはダメな制度だったのに改革に成功した、台湾とスイスのケースも紹介しています。なのでAmerican Sicknessよりも救いがあります。
書かれていることは単純。米国の医療制度をまともなものにするには、国民が「全員が医療保険に加入できるべきだ」という考え方で一致できるかどうかがキモだということです。世界の医療保険制度はいろんな仕組みがありますが、米国以外の先進国はすべてこの考え方に基づいています。
ところが米国ではこういう主張をすると、必ず「社会主義化された医療制度だ! ムダだらけで、革新も生まれない。国民の医療への選択肢も狭められる。自由を尊ぶ米国の理念に反する」という反発が出ます。そういった主張に、現在の医療保険制度で恩恵を受けている医療保険会社や医療機関、製薬会社が乗っかってロビー活動を展開するので、議会は動きがとれなくなります。オバマ大統領に上院60議席、下院過半数の議席を与えたって、問題は解決できなかったわけですからなかなか根深い問題です。
そこでリードさんは、こうした「社会主義化された医療制度だ!」という批判は的外れだと繰り返し説明します。
まず、他の先進国の医療制度は別に社会主義化されているわけではないという点です。
リードさんは先進国の医療制度を以下のように分類します。
ビスマルク型(ドイツ、日本など)=医療保険提供者が民間、医療サービス提供者も民間
ベバリッジ型(英国、北欧など)=医療保険提供者が国、医療サービス提供者も国
国民健康保険型(カナダ、韓国など)=医療保険提供者は国、医療サービス提供者は民間
まぁ、ベバレッジ型は国が全面的に関与していますから、バリバリの自由経済主義者からみれば「社会主義的」といえるかもしれません。でも英国を社会主義国だと思う人は多くはないです。あとビスマルク型や国民健康保険型は民間が関与していますから、社会主義ってわけじゃないですよね。
ただし、こうした民間が関与する仕組みでも規制はきついです。例えばビスマルク型として取り上げられている日本は、医療保険は主に企業別の医療保険組合が提供していて、医療サービスも民間がやっているわけですが、医薬品の価格なんかは政府がコントロールしているわけです。それは「すべての国民が医療保険に加入できるべきだ」との考え方から正当化されます。こうした厳しい規制のおかげで日本の医療費は国際的にみて安いですし、しかも患者は自由に医療機関を選べる。
ベバレッジ型は医療保険も医療サービスも国が主体です。そのおかげで患者は病院に行っても請求書を受け取ることはありません。それだったら患者が好きなだけ病院に行くことになって医療費が高騰しそうなものですが、「国はすべての人を保険でカバーするけれど、すべての医療行為をカバーするわけじゃない」という立場をとっているため、たいしたことのない病気であったりすれば病院にかかる前に行くことになる"general practitioner"のオフィスの段階で「病院に行かなくていいですよ。様子をみましょう」ということになる。また、すべての医療費は国民の税金で負担することになりますから、有権者や政治家も医療費の無駄遣いには敏感です。「94歳の女性への人工関節手術を認めるべきか」「50歳以上の男性すべてに前立腺がんの検査を認めるべきか」といった問題が、医学的なエビデンスの基づいて議論されたりします。
国民健康保険型も医療保険を国が提供するわけですから、どんな治療に対しても費用を払うというわけではないです。医療サービスは民間ですから、民間同士の競争がありますし、国がいくらでも医療費を払ってくれるわけじゃないので、コスト意識が働きます。
もちろん、それぞれの制度には問題点があります。日本なんかは「医療従事者の報酬が低い」なんていう問題点も指摘されます。ベバレッジ型の英国や北欧は米国に比べて税金が高いです。国民健康保険型のカナダなんかは、緊急性がない治療の場合は、受診までに数カ月~1年以上も待たねばならないという問題があります。
ただ、それだって米国の医療制度よりは格段にいいわけです。一人あたり医療費は安いし、健康を維持できる年齢も高い。どこの国だって「米国みたいにはなりたくない」と思っています。それなのに、どうして米国が現在の米国の医療制度にこだわる必要があるのかというわけです。
リードさんはさらに、米国内の「他の国の医療制度は自由を尊ぶ米国の理念に反する」という意見も的外れだとします。それは米国の医療制度のなかには、すでにこれらの仕組みが根を張っているからです。
例えば、高齢者向け公的医療保険のメディケアは国が医療費を負担して民間が医療サービスを提供していますから国民健康保険型です。退役軍人向けには専門の病院もありますから、これは医療保険も医療サービスも国が提供するベバリッジ型です。そのほかの企業が提供する医療保険に加入している米国人にとっては、ビスマルク型の医療保険制度が存在しているわけです。
ただ、米国には「全員が医療保険に加入できるべきだ」という理念がないために、どの制度からもこぼれてしまっている人たちがいます。メディケアに入れるほど年寄りではないし、低所得者向けのメディケイドに入れるほど所得が低いわけでもないし、医療保険を提供してくれる会社に勤めているわけでもないし、退役軍人でもないという人たちですね。この人たちは行き所がないです。利益目的の保険会社に高い保険料や高い自己負担額を強いられ、病院からも高い医療費を請求されて、生活を維持できなくなってしまうような人たちです。さらに医療保険を提供してくれる会社に勤めていたけど、病気で仕事を続けられなくなって退職したら、医療保険がなくなったなんていう事態も起きるわけです。
また、こうした医療保険制度のパッチワーク状態が余計なコストを生みます。オバマケアはこのパッチワークに拍車をかけました。
リードさんはこう書いています。
Facing an entrenched army of well-financed and powerful interests determined to preserve the status quo, Obama declared from the start that he would not seek to replace the existing health care system with a simpler, cheaper model. "We have to build on what we've got already," Obama said. The result was an enormously expensive and complicated piece of legislation ---the "Obamacare" bill runs to 2,400 pages of legalese ---that retains most of the structure of the U.S. system ....
もちろんリードさんはオバマケアが結果的に無保険者を大幅に減らすであろうことや、保険会社が病歴のある人の加入を断ることを禁じる制度を作ったことは高く評価しているわけですが、根本的な問題解決にはほど遠いということなんでしょう。
あと、リードさんは医療保険制度の抜本的な改革に成功した台湾やスイスの取り組みも詳しく取り上げています。どちらも、まず最初にリベラル側が「全員が医療保険に加入できるべきだ」と声を上げ、それを国民が熱狂的に支持し、保守側が人気とりのためにそれを受け入れたという展開だったようです。あと、どちらも経済が好調だったという背景もあるそうです。
米国では2016年に民主党の大統領候補指名争いで健闘したバーニー・サンダース上院議員が"single-payer"のシステムを目指しています。これは医療保険を国が提供するという意味です。オバマケアの失敗を踏まえたうえで、より抜本的な改革を実現させるということなのでしょう。
じゃあ、2020年の大統領選で79歳になったサンダース氏が当選。そのときには2018年の中間選挙と大統領選と同時に行われる議会選挙で、上下両院ともに民主党が過半数を握っていて、サンダース氏が訴える抜本的な医療保険制度改革をトランプ政権にこりた共和党も受け入れる。そんなシナリオはどうでしょうか。
どうでしょうか。米国人のみなさん。
2017年7月21日金曜日
"An American Sickness"
"An American Sickness: How Healthcare Became Big Business and How You Can Take It Back"という本を読んだ。医師として働いたこともあるニューヨーク・タイムズの元記者、Elisabeth Rosenthalが米国の医療制度が抱える問題について書いた本です。2017年4月発売。
5月にニューヨーク・タイムズの書評で米国の医療制度を理解するための本として紹介されてたので、ちょっと読んでみた。聞き慣れない医療用語の多さとか、医療制度に関する基本的な知識の欠如もあって、なかなかスムーズには読めませんでした。でも考えさせられるところが多くて、面白かった。
米国の医療制度は悪名高いです。OECDのデータによると、2015年の米国の1人あたり医療費(実質、購買力平価ベース)は8748ドルで世界1位。2位のスイス(6493ドル)に大差をつけています。日本は4036ドルですから、米国は日本の2倍以上の医療費がかかっていることになります。
OECDのページ
医療費が高いと、医療保険の保険料は高くなります。そうなると医療保険に入れなかったり、入りたくなくなったりする人が出てきます。
そういう状況に対応しようとしたのが2010年に成立したオバマケアだったわけです。でもオバマケア後も米国の医療費は上がり続けています。オバマケアが2014年に個人に保険加入を義務づけるなどしてから無保険者は1900万人減っていますが、それは保険料を連邦政府として負担したからであって、米国の医療費が世界的にみて例外的に高いという根本的な問題を解決できたわけではありません。
で、この本はどうしてこんなことになっているのかを説明しようとした本です。ただ、話が話だけに事は単純ではありません。
エピローグの言葉を引用すると、
No one player created the mess that is the $3 trillion American medical system in 2017. People in every sector of medicine are feeding trough: insurers, hospitals, doctors, manufacturers, politicians, regulators, charities, and more.
とのことです。この本は医療費や保険料の高騰の背景を象徴するいろんなエピソードを紹介しながら進みます。だからまとまりはないです。ただし、ローゼンタールさんは冒頭で、米国の医療制度がまともに機能していないことを象徴する、米国の医療がこだわる10の原則なるものを示しています。
1.常に治療せよ。最初の選択肢は最も高価な治療法。
2.一生治療を続けることは、治癒することよりも好ましい。
3.治療そのものよりも、快適さやマーケティングが大切。
4.技術革新の時代において、医療価格は上がり続ける。
5.患者は常に言いなり。常に米国の医療を購入する。
6.医療では競合があっても価格はさがらず、むしろ上がる。
7.医療機関は規模が大きくなっても価格は下げない。ただ稼ぎを増やすだけ。
8.適正価格などない。無保険者が最も高い医療費を払う。
9.請求書に基準はない。あらゆるものにお金がかかる。
10.患者が負担するギリギリまで価格は上がる。
まぁ、なんとなく分かるような内容です。
そもそも医療というのは病気の人を相手にしているわけです。で、病気の人は働けないわけですから、お金なんかもっていない。だから本来、医者なんていう仕事は儲かるハズがない。ローゼンタールさんによると、100年ほど前には、そもそも医療というのは簡素なもので、安くて、多くの場合は宗教関係者によって運営されていました。病院というのは人々が死ぬための場所でもあったのです。
一方で、19世紀後半には、企業が従業員の医療費を負担する仕組みが生まれます。従業員が働けなくなることは、会社にとって損失だからです。1890年代、ワシントン州の木材会社は従業員が医師にかかる際に1カ月あたり50セントを負担したそうで、こうした仕組みが今の米国における企業負担型の医療保険のはしりだそうです。
現在の医療保険の元祖は1920年代までにテキサス州ダラスで生まれました。教職員組合の加入者を対象に、年間6ドルを払えば、21日分の入院治療が受けられるというものです。ただし保険の支払いは、最初に1日あたり5ドルの自己負担を1週間続けた後で発動されるという仕組みでした。21日という期間は、当時の医療水準では21日もあれば患者の多くは治るか、死ぬかのどちらになるという判断で決められました。
第二次世界大戦が終わると、企業は人手不足に陥ります。そこで企業は従業員に医療保険を提供することで人を集めようとします。連邦政府もこれを後押しして、従業員の医療費は非課税とすることにしました。すると1940年から1955年にかけて、米国の保険加入者は人口の10%から60%まで急増しました。保険を提供していたのはBlueCrossのようは非営利組織で、年齢や健康状態に関わらず、すべての加入者は同じ額の保険料を払っていました。
こんな風にして医療保険への需要が高まってくると、営利目的の保険会社が医療保険に参入してきます。こうした保険会社は年齢によって保険料を変えたり、カバーの範囲を変えたりして、より安い保険料を提示するようになります。1951年までにはAetnaやCignaがシェアを伸ばし、BlueCrossのようなすべての保険加入者を平等に扱う非営利組織は不利になっていきます。そして1994年、BlueCrossは営利組織になることを容認。社会的な使命を意識する保険会社が駆逐されてしまった形になりました。
1993年、保険会社は保険料の95%を医療費に使っていましたが、現在では80%近くまで下がっています。なかには64.4%なんていう保険会社もあるそうです。オバマケアは保険会社に対して、この比率(medical loss ratio)を80~85%にするよう求めました。ただ、高齢者向け公的医療保険のメディケアのmedical loss ratioは98%ですから、オバマケアは十分甘いともいえます。
つまり保険会社は公的な使命を忘れてしまっていて、オバマケアもそれを容認してしまったということです。
医療機関にも問題があります。そもそもほとんどの医療機関は非営利組織として運営されているため、利益を上げることができません。すると医療費として集めたお金が実際にかかったコストよりも大きくなると、余ったお金を無駄遣いする構造になっています。つまり節約するという意識がない。1960年代にメディケアが登場すると、65歳以下の世代でも保険加入が進みます。すると患者の方でも自分がいくら負担するかを気にしなくなってきて、医療機関は好き勝手な医療費を請求するようになります。1967年から1983年にかけて、メディケアの支払い額は30億ドルから370億ドルまで増えました。
メディケアも対応に乗り出します。1980年代の半ばにはdiagnosis related group (DRG)という仕組みを導入し、治療の種類に応じて支払い額を固定するよう決めました。一方、民間の保険会社はDRGでは医療費が高止まりする可能性があるとして、ケアマネジャーを雇って適正な医療費の価格をはじき出して、医療機関と交渉する仕組みを採用します。
すると、医療機関はメディケアや交渉力のある保険会社が手強くなってきたと判断し、小さな保険会社や無保険の患者に高い医療費を請求するようになります。さらに医療機関は収入を増やすためにコンサルタントを雇い、戦略的な医療費設定(strategic pricing)を始めます。コンサルタントは保険会社が支払いに応じないような品目での請求を止め、酸素吸入や処方薬のような保険会社が支払いに応じることが多い品目での請求を増やし、その結果、こうした品目として請求される医療費が実際の費用からかけ離れた高額になるといった事態が生じます。大手の医療コンサルタント企業は年間342億ドルもの売上を稼いでいるんだそうです。
さらに医療機関のなかには医師に対して固定給ではなく、行った治療の収益性に応じて報酬を払うケースもあります。治療や検査の複雑さを示すレベル1~5までの分類に応じて、医師が受け取る報酬が決まっているわけです。普通にひざの関節への注射をすれば1200ドルの収入になるけれど、その際に超音波で針を刺す場所を特定すればさらに300ドルの収入になる。ひざへの注射は特段難しいわけじゃないので、超音波による検査は必要ないんだけれど、医師は報酬を増やすために超音波を使うようになるといった具合で医療費が上がっていきます。
メディケアにまわされた請求を分析したところ、緊急治療室で治療を受けた患者のうちレベル4と5の治療を受けた患者の割合は2001年には4分の1ですたが、2008年には半分にまで増えていた。一方、レベル2の請求は15%まで半減。医療機関2400カ所のうち500カ所では、患者の60%に対してレベル4と5の治療が行われていました。
つまり医療機関は保険会社やメディケアなんかの監視の目をかいくぐるようにして、患者から医療費をむしりとっているという構図です。病院の経営者の収入は2011年から2012年にかけて24.2%増えました。オバマケア成立後のことです。医師の報酬も2009年以降、増え続けています。医師以外の職業ではみられない現象だそうです。ローゼンタールさんが医療現場で働いていた1990年台、医師たちは「時給で考えたら、配管工より給料が安い」なんて文句を言っていたそうです。でも、今はNBAのレブロン・ジェームズやゴールドマン・サックスの会長が比較の対象になっているようだと、ローゼンタールさんは書いています。
メディケアの方にも間抜けなところがあります。メディケアは地域ごとに支払い額を決めているのですが、その支払い額はその地域の医療機関による過去の請求額などを基準に決められています。しかし、ある地域で特定の治療を行う医療機関が少数であれば、それらの医療機関はお互いに競争するのではなく、そろって請求額を上げていこうという動機が生まれます。その結果、2014年段階で、ニューヨークのクイーンズでの胆嚢手術のコストは2000ドルであるにも関わらず、20マイル離れたロングアイランドのナッソー郡での胆嚢手術は2万5000ドルと計上される。そんなおかしな事態が起きています。
メディケアは1980年代に医療行為の時間や管理コスト、医師育成にかかるコスト、過誤によるコストをもとにしてrelative value units(RVUs)を算出。これをもとに医療機関への支払い額を決めるアルゴリズムを作ります。こうしたアルゴリズムは常にアップデートする必要があるわけですが、メディケアはこの任務をAmerican Medical Associationに委ねてしまします。医療行為の適正価格を医療機関自身に決めさせてしまうようなものです。AMAは3年に一度、Relative Value Scale Update Committeeを開いて見直しを進めるのですが、この委員会は各医療関連団体のロビーイング競争の場になっています。
もちろん製薬会社も無茶苦茶です。最近でも、安い値段で売られている薬の販売に関わる権利を買い集めて、一気に大幅に値上げするといった悪行がニュースになります。
かつて医薬品を開発した研究者は特許をとろうとはしませんでした。ポリオワクチンの開発に力を尽くしたJonas Salkeは「誰がポリオワクチンの特許を持っているのか」と問われて、"Well, the people, I would say. There is no patent. Could you patent the sun?"と答えたそうです。実際、当時の法制度では、多くの研究者が関わったポリオワクチンは特許をとることができないと判断されていたそうです。
しかし1980年のBayh-Dole Actで政府の資金援助を受けた研究から得られた成果でも特許を取ることが認められるようになりました。今ではひとつの医薬品に対して3.5件の特許がかかっています。1984年の別の法律改正(Hatch-Waxman)ではジェネリック医薬品の導入促進のための規制緩和が実現しましたが、同時に大手製薬会社を納得させるために、一部のケースで特許期間の延長を認めました。こうしたジェネリック企業と大手製薬会社の軋轢が法廷闘争に発展すると、その間はジェネリック医薬品の導入が遅れるケースも出ることになります。米国は欧州に比べて特許の力が強く、医薬品の価格にも規制がかかっていないため、多くの製薬企業が米国に投資するようになっています。
大手製薬会社は自社の医薬品が特許切れに寸前になると、わずかに仕様や成分を変えた医薬品を開発して新たに特許を取り直すという戦略も採ります。例えばワーナーチルコットは経口避妊薬Loestrin24 Feが特許切れになる前に、「噛めるタイプ」のMinastrin24 Feを販売。Loestrin24 Feの販売を取りやめます。新薬の方は旧薬よりも3割ほど高い価格設定ですが、まだジェネリックは出ていないので、利用者は新薬に乗り換えざるを得ません。
1994年に特許を得たスプレータイプの処方薬Flonaseの場合、2006年にジェネリック版が登場。Flonaseを販売していたグラクソスミソクラインは訴訟を起こすなどして抵抗しましたが、2010年にはジェネリック版が市販薬として20ドルの価格でドラッグストアの店頭に並ぶようになりました。処方薬であるFlonaseは医療保険の対象となる分、価格は高く設定されていますから、ジェネリック版に市場を奪われることは必至です。しかしそこでグラクソスミソクラインはFlonaseを市販薬に変更し、市場に投入。すると米国法では、同じ医薬品がひとつの市場で同時に売られることを禁じているため、ジェネリック版のメーカーは在庫を売り切って工場を閉鎖するよう要求されることになりました。さらに米国では、処方薬を市販薬に変更した場合には、3年間の市場独占期間が保障されていて、新規の参入もブロックすることができます。グラクソスミソクラインはこの市販薬版のFlonaseを40ドルで売ったとのことです。
とまぁですね、こんなややこしいエピソードが山ほど書かれている本です。ややこしいので、ここまでに書いた文章にも誤解があるかもしれません。このほか患者の側のかわいそうな話も満載です。
本の後半では、医療の消費者である患者の側はどのように対応すればいいかといった話も出てくるのですが、正直、これだけ根深い問題を見せられた後ではなかなか明るい希望は抱けません。多分、政策上とか理論上ではできることはいくらでもあるのでしょう。でも、政治の状況を考えれば、なんか絶望的です。
オバマケア(Affordable Care Act)についてこんな記述があります。
The ACA did little directly, however, to control run-away spending. President Obama had initially included several ideas in the bill that would have done so ---like national negotiation for pharmaceutical prices. To get a healthcare bill passed and to win support from powerful groups like PhRMA, the AMA, the American Hospital Association, and America's Health Insurance Plans, the administration had to cave on anything that would directly limit the industry's ability to profit.
医療業界によるロビイングは共和党だけでなく、もちろん民主党にも浸透しています。ハリー・リードとかチャック・シューマーのようないかにも悪そうな人たちだけならまだしも、エリザベス・ウォレンやエイミー・クローブシャーのような、いかにも「庶民の味方」といったイメージの議員まで医療業界の世話になっているようです。そんなことになっていたら、オバマ大統領だって法律を通そうと思えば、妥協せざるをえなかったということなのかもしれません。
トランプ大統領だったら、医療業界ごとぶっとばしてくれる。そんな期待もあるかもしれません。でもトランプ大統領だって法律を通すには議会の協力を得ねばなりません。予算編成で強い影響力を持つ上院財政委員会の委員長は医薬品業界とのつながりで有名なオリン・ハッチです。他の共和党議員だって、医療業界にお世話になっているだろうことは想像に難くありません。
まぁ、病気にならないように気をつけるしかないですかね。100年前と同じですね。
5月にニューヨーク・タイムズの書評で米国の医療制度を理解するための本として紹介されてたので、ちょっと読んでみた。聞き慣れない医療用語の多さとか、医療制度に関する基本的な知識の欠如もあって、なかなかスムーズには読めませんでした。でも考えさせられるところが多くて、面白かった。
米国の医療制度は悪名高いです。OECDのデータによると、2015年の米国の1人あたり医療費(実質、購買力平価ベース)は8748ドルで世界1位。2位のスイス(6493ドル)に大差をつけています。日本は4036ドルですから、米国は日本の2倍以上の医療費がかかっていることになります。
OECDのページ
医療費が高いと、医療保険の保険料は高くなります。そうなると医療保険に入れなかったり、入りたくなくなったりする人が出てきます。
そういう状況に対応しようとしたのが2010年に成立したオバマケアだったわけです。でもオバマケア後も米国の医療費は上がり続けています。オバマケアが2014年に個人に保険加入を義務づけるなどしてから無保険者は1900万人減っていますが、それは保険料を連邦政府として負担したからであって、米国の医療費が世界的にみて例外的に高いという根本的な問題を解決できたわけではありません。
で、この本はどうしてこんなことになっているのかを説明しようとした本です。ただ、話が話だけに事は単純ではありません。
エピローグの言葉を引用すると、
No one player created the mess that is the $3 trillion American medical system in 2017. People in every sector of medicine are feeding trough: insurers, hospitals, doctors, manufacturers, politicians, regulators, charities, and more.
とのことです。この本は医療費や保険料の高騰の背景を象徴するいろんなエピソードを紹介しながら進みます。だからまとまりはないです。ただし、ローゼンタールさんは冒頭で、米国の医療制度がまともに機能していないことを象徴する、米国の医療がこだわる10の原則なるものを示しています。
1.常に治療せよ。最初の選択肢は最も高価な治療法。
2.一生治療を続けることは、治癒することよりも好ましい。
3.治療そのものよりも、快適さやマーケティングが大切。
4.技術革新の時代において、医療価格は上がり続ける。
5.患者は常に言いなり。常に米国の医療を購入する。
6.医療では競合があっても価格はさがらず、むしろ上がる。
7.医療機関は規模が大きくなっても価格は下げない。ただ稼ぎを増やすだけ。
8.適正価格などない。無保険者が最も高い医療費を払う。
9.請求書に基準はない。あらゆるものにお金がかかる。
10.患者が負担するギリギリまで価格は上がる。
まぁ、なんとなく分かるような内容です。
そもそも医療というのは病気の人を相手にしているわけです。で、病気の人は働けないわけですから、お金なんかもっていない。だから本来、医者なんていう仕事は儲かるハズがない。ローゼンタールさんによると、100年ほど前には、そもそも医療というのは簡素なもので、安くて、多くの場合は宗教関係者によって運営されていました。病院というのは人々が死ぬための場所でもあったのです。
一方で、19世紀後半には、企業が従業員の医療費を負担する仕組みが生まれます。従業員が働けなくなることは、会社にとって損失だからです。1890年代、ワシントン州の木材会社は従業員が医師にかかる際に1カ月あたり50セントを負担したそうで、こうした仕組みが今の米国における企業負担型の医療保険のはしりだそうです。
現在の医療保険の元祖は1920年代までにテキサス州ダラスで生まれました。教職員組合の加入者を対象に、年間6ドルを払えば、21日分の入院治療が受けられるというものです。ただし保険の支払いは、最初に1日あたり5ドルの自己負担を1週間続けた後で発動されるという仕組みでした。21日という期間は、当時の医療水準では21日もあれば患者の多くは治るか、死ぬかのどちらになるという判断で決められました。
第二次世界大戦が終わると、企業は人手不足に陥ります。そこで企業は従業員に医療保険を提供することで人を集めようとします。連邦政府もこれを後押しして、従業員の医療費は非課税とすることにしました。すると1940年から1955年にかけて、米国の保険加入者は人口の10%から60%まで急増しました。保険を提供していたのはBlueCrossのようは非営利組織で、年齢や健康状態に関わらず、すべての加入者は同じ額の保険料を払っていました。
こんな風にして医療保険への需要が高まってくると、営利目的の保険会社が医療保険に参入してきます。こうした保険会社は年齢によって保険料を変えたり、カバーの範囲を変えたりして、より安い保険料を提示するようになります。1951年までにはAetnaやCignaがシェアを伸ばし、BlueCrossのようなすべての保険加入者を平等に扱う非営利組織は不利になっていきます。そして1994年、BlueCrossは営利組織になることを容認。社会的な使命を意識する保険会社が駆逐されてしまった形になりました。
1993年、保険会社は保険料の95%を医療費に使っていましたが、現在では80%近くまで下がっています。なかには64.4%なんていう保険会社もあるそうです。オバマケアは保険会社に対して、この比率(medical loss ratio)を80~85%にするよう求めました。ただ、高齢者向け公的医療保険のメディケアのmedical loss ratioは98%ですから、オバマケアは十分甘いともいえます。
つまり保険会社は公的な使命を忘れてしまっていて、オバマケアもそれを容認してしまったということです。
医療機関にも問題があります。そもそもほとんどの医療機関は非営利組織として運営されているため、利益を上げることができません。すると医療費として集めたお金が実際にかかったコストよりも大きくなると、余ったお金を無駄遣いする構造になっています。つまり節約するという意識がない。1960年代にメディケアが登場すると、65歳以下の世代でも保険加入が進みます。すると患者の方でも自分がいくら負担するかを気にしなくなってきて、医療機関は好き勝手な医療費を請求するようになります。1967年から1983年にかけて、メディケアの支払い額は30億ドルから370億ドルまで増えました。
メディケアも対応に乗り出します。1980年代の半ばにはdiagnosis related group (DRG)という仕組みを導入し、治療の種類に応じて支払い額を固定するよう決めました。一方、民間の保険会社はDRGでは医療費が高止まりする可能性があるとして、ケアマネジャーを雇って適正な医療費の価格をはじき出して、医療機関と交渉する仕組みを採用します。
すると、医療機関はメディケアや交渉力のある保険会社が手強くなってきたと判断し、小さな保険会社や無保険の患者に高い医療費を請求するようになります。さらに医療機関は収入を増やすためにコンサルタントを雇い、戦略的な医療費設定(strategic pricing)を始めます。コンサルタントは保険会社が支払いに応じないような品目での請求を止め、酸素吸入や処方薬のような保険会社が支払いに応じることが多い品目での請求を増やし、その結果、こうした品目として請求される医療費が実際の費用からかけ離れた高額になるといった事態が生じます。大手の医療コンサルタント企業は年間342億ドルもの売上を稼いでいるんだそうです。
さらに医療機関のなかには医師に対して固定給ではなく、行った治療の収益性に応じて報酬を払うケースもあります。治療や検査の複雑さを示すレベル1~5までの分類に応じて、医師が受け取る報酬が決まっているわけです。普通にひざの関節への注射をすれば1200ドルの収入になるけれど、その際に超音波で針を刺す場所を特定すればさらに300ドルの収入になる。ひざへの注射は特段難しいわけじゃないので、超音波による検査は必要ないんだけれど、医師は報酬を増やすために超音波を使うようになるといった具合で医療費が上がっていきます。
メディケアにまわされた請求を分析したところ、緊急治療室で治療を受けた患者のうちレベル4と5の治療を受けた患者の割合は2001年には4分の1ですたが、2008年には半分にまで増えていた。一方、レベル2の請求は15%まで半減。医療機関2400カ所のうち500カ所では、患者の60%に対してレベル4と5の治療が行われていました。
つまり医療機関は保険会社やメディケアなんかの監視の目をかいくぐるようにして、患者から医療費をむしりとっているという構図です。病院の経営者の収入は2011年から2012年にかけて24.2%増えました。オバマケア成立後のことです。医師の報酬も2009年以降、増え続けています。医師以外の職業ではみられない現象だそうです。ローゼンタールさんが医療現場で働いていた1990年台、医師たちは「時給で考えたら、配管工より給料が安い」なんて文句を言っていたそうです。でも、今はNBAのレブロン・ジェームズやゴールドマン・サックスの会長が比較の対象になっているようだと、ローゼンタールさんは書いています。
メディケアの方にも間抜けなところがあります。メディケアは地域ごとに支払い額を決めているのですが、その支払い額はその地域の医療機関による過去の請求額などを基準に決められています。しかし、ある地域で特定の治療を行う医療機関が少数であれば、それらの医療機関はお互いに競争するのではなく、そろって請求額を上げていこうという動機が生まれます。その結果、2014年段階で、ニューヨークのクイーンズでの胆嚢手術のコストは2000ドルであるにも関わらず、20マイル離れたロングアイランドのナッソー郡での胆嚢手術は2万5000ドルと計上される。そんなおかしな事態が起きています。
メディケアは1980年代に医療行為の時間や管理コスト、医師育成にかかるコスト、過誤によるコストをもとにしてrelative value units(RVUs)を算出。これをもとに医療機関への支払い額を決めるアルゴリズムを作ります。こうしたアルゴリズムは常にアップデートする必要があるわけですが、メディケアはこの任務をAmerican Medical Associationに委ねてしまします。医療行為の適正価格を医療機関自身に決めさせてしまうようなものです。AMAは3年に一度、Relative Value Scale Update Committeeを開いて見直しを進めるのですが、この委員会は各医療関連団体のロビーイング競争の場になっています。
もちろん製薬会社も無茶苦茶です。最近でも、安い値段で売られている薬の販売に関わる権利を買い集めて、一気に大幅に値上げするといった悪行がニュースになります。
かつて医薬品を開発した研究者は特許をとろうとはしませんでした。ポリオワクチンの開発に力を尽くしたJonas Salkeは「誰がポリオワクチンの特許を持っているのか」と問われて、"Well, the people, I would say. There is no patent. Could you patent the sun?"と答えたそうです。実際、当時の法制度では、多くの研究者が関わったポリオワクチンは特許をとることができないと判断されていたそうです。
しかし1980年のBayh-Dole Actで政府の資金援助を受けた研究から得られた成果でも特許を取ることが認められるようになりました。今ではひとつの医薬品に対して3.5件の特許がかかっています。1984年の別の法律改正(Hatch-Waxman)ではジェネリック医薬品の導入促進のための規制緩和が実現しましたが、同時に大手製薬会社を納得させるために、一部のケースで特許期間の延長を認めました。こうしたジェネリック企業と大手製薬会社の軋轢が法廷闘争に発展すると、その間はジェネリック医薬品の導入が遅れるケースも出ることになります。米国は欧州に比べて特許の力が強く、医薬品の価格にも規制がかかっていないため、多くの製薬企業が米国に投資するようになっています。
大手製薬会社は自社の医薬品が特許切れに寸前になると、わずかに仕様や成分を変えた医薬品を開発して新たに特許を取り直すという戦略も採ります。例えばワーナーチルコットは経口避妊薬Loestrin24 Feが特許切れになる前に、「噛めるタイプ」のMinastrin24 Feを販売。Loestrin24 Feの販売を取りやめます。新薬の方は旧薬よりも3割ほど高い価格設定ですが、まだジェネリックは出ていないので、利用者は新薬に乗り換えざるを得ません。
1994年に特許を得たスプレータイプの処方薬Flonaseの場合、2006年にジェネリック版が登場。Flonaseを販売していたグラクソスミソクラインは訴訟を起こすなどして抵抗しましたが、2010年にはジェネリック版が市販薬として20ドルの価格でドラッグストアの店頭に並ぶようになりました。処方薬であるFlonaseは医療保険の対象となる分、価格は高く設定されていますから、ジェネリック版に市場を奪われることは必至です。しかしそこでグラクソスミソクラインはFlonaseを市販薬に変更し、市場に投入。すると米国法では、同じ医薬品がひとつの市場で同時に売られることを禁じているため、ジェネリック版のメーカーは在庫を売り切って工場を閉鎖するよう要求されることになりました。さらに米国では、処方薬を市販薬に変更した場合には、3年間の市場独占期間が保障されていて、新規の参入もブロックすることができます。グラクソスミソクラインはこの市販薬版のFlonaseを40ドルで売ったとのことです。
とまぁですね、こんなややこしいエピソードが山ほど書かれている本です。ややこしいので、ここまでに書いた文章にも誤解があるかもしれません。このほか患者の側のかわいそうな話も満載です。
本の後半では、医療の消費者である患者の側はどのように対応すればいいかといった話も出てくるのですが、正直、これだけ根深い問題を見せられた後ではなかなか明るい希望は抱けません。多分、政策上とか理論上ではできることはいくらでもあるのでしょう。でも、政治の状況を考えれば、なんか絶望的です。
オバマケア(Affordable Care Act)についてこんな記述があります。
The ACA did little directly, however, to control run-away spending. President Obama had initially included several ideas in the bill that would have done so ---like national negotiation for pharmaceutical prices. To get a healthcare bill passed and to win support from powerful groups like PhRMA, the AMA, the American Hospital Association, and America's Health Insurance Plans, the administration had to cave on anything that would directly limit the industry's ability to profit.
医療業界によるロビイングは共和党だけでなく、もちろん民主党にも浸透しています。ハリー・リードとかチャック・シューマーのようないかにも悪そうな人たちだけならまだしも、エリザベス・ウォレンやエイミー・クローブシャーのような、いかにも「庶民の味方」といったイメージの議員まで医療業界の世話になっているようです。そんなことになっていたら、オバマ大統領だって法律を通そうと思えば、妥協せざるをえなかったということなのかもしれません。
トランプ大統領だったら、医療業界ごとぶっとばしてくれる。そんな期待もあるかもしれません。でもトランプ大統領だって法律を通すには議会の協力を得ねばなりません。予算編成で強い影響力を持つ上院財政委員会の委員長は医薬品業界とのつながりで有名なオリン・ハッチです。他の共和党議員だって、医療業界にお世話になっているだろうことは想像に難くありません。
まぁ、病気にならないように気をつけるしかないですかね。100年前と同じですね。
2017年6月16日金曜日
"The Ax"
"The Ax"という小説を読んだ。Donald Westlakeが1997年に書いた作品です。ウエストレイクはエドガー賞を3度獲ったほどの著名作家です。私は全然知りませんでしたが。
私はもともとミステリーが好きで、これまでJ.A. Konrathの本を読んでいたのですが、どうもこの人の本はジョーク満載で面白いんだけど、描写がグロいところがあって、なんか食傷気味になってきたところでした。
そこで、以前読んだ本のなかで、Konrath自身が好きだと書いていた作家をピックアップして、そのなかから、私が気に入るような作家を捜してみようと思ったのです。
Konrathが好きだと書いていた作家は6人。
Janet Evanovich
Rovert Parker
Lawrence Block
Robert Crais
Donald Westlake
Ridley Pearson
一人も読んだことがないので「このミステリーがすごい!」の過去のランキングを調べてみたところ、このうち、ローレンス・ブロックと、ウエストレイクは過去に何度もトップ10に入っています。
2013年10位のローレンス・ブロック「償いの報酬」A Drop of the Hard Stuff (Matthew Scudder 17)
2004年5位のドナルド・ウエストレイク「鉤」The Hook(2000, シリーズなし)
2002年4位のドナルド・ウエストレイク「斧」The Ax(1997, シリーズなし)
1998年9位のドナルド・ウエストレイク「天から降ってきた泥棒」Good Behavior (1985, Dortmunder)
1995年3位のドナルド・ウエストレイク「踊る黄金像」Dancing Aztecs(1976, シリーズなし)
1994年6位のローレンス・ブロック「倒錯の舞踏」A Dance at the Slaughterhouse (Matthew Scudder 9)
1993年2位のローレンス・ブロック「墓場への切符」A Ticket to the Boneyard (Matthew Scudder 8)
じゃぁ、このなかからどれを読むかということですが、シリーズものじゃない、比較的新しいという基準で"The Ax"を選んだ。"The Hook"を選ばなかった理由は忘れた。
で、肝心の読んでみた感想ですが、Konrathの作品とは正反対で「ジョークは一切無く、グロさもほとんどない」といった作風です。1990年台半ばのコネチカット、ニューヨーク、マサチューセッツを舞台にして、製紙メーカーをリストラされた男が殺人を繰り返すという話。一貫して犯人の視点で書かれているので、ミステリーではありません。本当に淡々と話が進んでいきます。
じゃぁ、面白くないかというと、そうではなくて、なかなか読ませます。リストラされた男が殺人を始めるまでの屈折した心理とか、家族との関係とか、ターゲットに対する心情とか、だんだんと犯罪慣れしていく様子とかが詳細に描かれていきます。描写がグロいわけじゃないですが、犯人の身勝手な理屈はなかなかにグロテスクです。また、この男をリストラした会社はコネチカットの工場を閉めて、カナダに製造拠点を移したという設定になっています。NAFTA(1994年発効)なんかも言及されていて、今日的な話題である「米国における製造業の衰退」なんていうテーマも重ね合わせてしまいますね。
淡々と話は進みますが、ラストにどうなるかは最後まで分かりません。そういった意味でも面白い。
ウエストレイクは多作な人みたいなので、しばらく楽しめそう。
私はもともとミステリーが好きで、これまでJ.A. Konrathの本を読んでいたのですが、どうもこの人の本はジョーク満載で面白いんだけど、描写がグロいところがあって、なんか食傷気味になってきたところでした。
そこで、以前読んだ本のなかで、Konrath自身が好きだと書いていた作家をピックアップして、そのなかから、私が気に入るような作家を捜してみようと思ったのです。
Konrathが好きだと書いていた作家は6人。
Janet Evanovich
Rovert Parker
Lawrence Block
Robert Crais
Donald Westlake
Ridley Pearson
一人も読んだことがないので「このミステリーがすごい!」の過去のランキングを調べてみたところ、このうち、ローレンス・ブロックと、ウエストレイクは過去に何度もトップ10に入っています。
2013年10位のローレンス・ブロック「償いの報酬」A Drop of the Hard Stuff (Matthew Scudder 17)
2004年5位のドナルド・ウエストレイク「鉤」The Hook(2000, シリーズなし)
2002年4位のドナルド・ウエストレイク「斧」The Ax(1997, シリーズなし)
1998年9位のドナルド・ウエストレイク「天から降ってきた泥棒」Good Behavior (1985, Dortmunder)
1995年3位のドナルド・ウエストレイク「踊る黄金像」Dancing Aztecs(1976, シリーズなし)
1994年6位のローレンス・ブロック「倒錯の舞踏」A Dance at the Slaughterhouse (Matthew Scudder 9)
1993年2位のローレンス・ブロック「墓場への切符」A Ticket to the Boneyard (Matthew Scudder 8)
じゃぁ、このなかからどれを読むかということですが、シリーズものじゃない、比較的新しいという基準で"The Ax"を選んだ。"The Hook"を選ばなかった理由は忘れた。
で、肝心の読んでみた感想ですが、Konrathの作品とは正反対で「ジョークは一切無く、グロさもほとんどない」といった作風です。1990年台半ばのコネチカット、ニューヨーク、マサチューセッツを舞台にして、製紙メーカーをリストラされた男が殺人を繰り返すという話。一貫して犯人の視点で書かれているので、ミステリーではありません。本当に淡々と話が進んでいきます。
じゃぁ、面白くないかというと、そうではなくて、なかなか読ませます。リストラされた男が殺人を始めるまでの屈折した心理とか、家族との関係とか、ターゲットに対する心情とか、だんだんと犯罪慣れしていく様子とかが詳細に描かれていきます。描写がグロいわけじゃないですが、犯人の身勝手な理屈はなかなかにグロテスクです。また、この男をリストラした会社はコネチカットの工場を閉めて、カナダに製造拠点を移したという設定になっています。NAFTA(1994年発効)なんかも言及されていて、今日的な話題である「米国における製造業の衰退」なんていうテーマも重ね合わせてしまいますね。
淡々と話は進みますが、ラストにどうなるかは最後まで分かりません。そういった意味でも面白い。
ウエストレイクは多作な人みたいなので、しばらく楽しめそう。
2017年6月13日火曜日
TOEFL(10回目)結果
TOEFL10回目の結果が出ました。
Reading29, Listening30, Speaking17, Writing22で、98点
9回目が Reading26, Listening27, Speaking15, Writing22 で、90点
8回目が Reading29, Listening27, Speaking17, Writing21 で、94点
7回目が Reading26, Listening24, Speaking19, Writing20 で、89点
6回目が Reading26, Listening26, Speaking15, Writing21 で、88点
5回目が Reading23, Listening26, Speaking15, Writing20 で、84点
4回目が Reading25, Listening21, Speaking15, Writing18 で、79点
3回目が Reading14, Listening19, Speaking17, Writing15 で、65点
2回目が Reading20, Listening21, Speaking13, Writing17 で、71点
1回目は Reading10, Listening18, Speaking10, Writing14 で、52点
わはは。これはつまり、SpeakingとWritingが全然上がっていない、というやつです。
Speakingで過去最高点(19)が出ていれば、100点に届いたのに。
まぁ、最高点が19点っていうのは、なかなかに情けない話ですけど。
受験時の予想が100点前後だったので、予想通りの結果といえます。(本当は100点超期待していたけど)
インプット系のReadingとListeningに自信があったのは間違いじゃないかった。
アウトプット系(特にSpeaking)に不安があったのも間違いじゃなかった。
そしてインプットの向上がアウトプットの点を後押ししてくれるというのは幻想だった。
ということで、TOEFLで100点超をとろうと思ったら、アウトプットの向上が不可欠ということです。
そのためにはアウトプットを意識的に練習することが必要だということです。
7年ぶり10回目の受験にして、当たり前の知見を得ることになりました。
ただ、ちょっと言い訳させてもらうと、2015年11月に英検1級には合格しているんですよ。
このときの2次試験(面接形式)は100点中82点。
内訳は、short speech 27/30、 interaction 27/30、grammar and vocabulary 16/20、pronunciation 12/20。
ネイティブスピーカーとコミュニケーションを取れるだけの能力がないわけじゃないんだと思うんですよね。っていうか、そう信じたい。
英検の2次は面接形式だから、こちらの発言の趣旨がうまく伝わらなくても、面接者が追加質問してくれるので、それに答えることで考えを伝えられます。
あと、周りに人もいないし、制限時間もシビアではないので、ゆっくりとハキハキと話すことができます。
でもTOEFLの場合は、制限時間1分の枠内で、マイクに向かって話すという形式ですから、より高度なスピーキングのスキルが求められる。
周りに他の受験者がいるので、なんかこっぱずかしい感じもある。他の受験者がリスニングしているのに、下手な発音で話すのって何かアレじゃないですか。
くっそぉ。悔しいなぁ。でも「取りこぼし」があったわけじゃないから、すぐに再チャレンジしても成果は期待できない。
100点超めざすなら、TOEFLのスピーキング対策をとる必要があるんだと思います。
それと、やっぱり発音をもうちょっと向上させないとダメなんだろうな。練習してないからな。
このあたりが向上した自信がつけば、再受験するかも。でも、どうやったら自信をつけられるかは分からない。
Reading29, Listening30, Speaking17, Writing22で、98点
9回目が Reading26, Listening27, Speaking15, Writing22 で、90点
8回目が Reading29, Listening27, Speaking17, Writing21 で、94点
7回目が Reading26, Listening24, Speaking19, Writing20 で、89点
6回目が Reading26, Listening26, Speaking15, Writing21 で、88点
5回目が Reading23, Listening26, Speaking15, Writing20 で、84点
4回目が Reading25, Listening21, Speaking15, Writing18 で、79点
3回目が Reading14, Listening19, Speaking17, Writing15 で、65点
2回目が Reading20, Listening21, Speaking13, Writing17 で、71点
1回目は Reading10, Listening18, Speaking10, Writing14 で、52点
わはは。これはつまり、SpeakingとWritingが全然上がっていない、というやつです。
Speakingで過去最高点(19)が出ていれば、100点に届いたのに。
まぁ、最高点が19点っていうのは、なかなかに情けない話ですけど。
受験時の予想が100点前後だったので、予想通りの結果といえます。(本当は100点超期待していたけど)
インプット系のReadingとListeningに自信があったのは間違いじゃないかった。
アウトプット系(特にSpeaking)に不安があったのも間違いじゃなかった。
そしてインプットの向上がアウトプットの点を後押ししてくれるというのは幻想だった。
ということで、TOEFLで100点超をとろうと思ったら、アウトプットの向上が不可欠ということです。
そのためにはアウトプットを意識的に練習することが必要だということです。
7年ぶり10回目の受験にして、当たり前の知見を得ることになりました。
ただ、ちょっと言い訳させてもらうと、2015年11月に英検1級には合格しているんですよ。
このときの2次試験(面接形式)は100点中82点。
内訳は、short speech 27/30、 interaction 27/30、grammar and vocabulary 16/20、pronunciation 12/20。
ネイティブスピーカーとコミュニケーションを取れるだけの能力がないわけじゃないんだと思うんですよね。っていうか、そう信じたい。
英検の2次は面接形式だから、こちらの発言の趣旨がうまく伝わらなくても、面接者が追加質問してくれるので、それに答えることで考えを伝えられます。
あと、周りに人もいないし、制限時間もシビアではないので、ゆっくりとハキハキと話すことができます。
でもTOEFLの場合は、制限時間1分の枠内で、マイクに向かって話すという形式ですから、より高度なスピーキングのスキルが求められる。
周りに他の受験者がいるので、なんかこっぱずかしい感じもある。他の受験者がリスニングしているのに、下手な発音で話すのって何かアレじゃないですか。
くっそぉ。悔しいなぁ。でも「取りこぼし」があったわけじゃないから、すぐに再チャレンジしても成果は期待できない。
100点超めざすなら、TOEFLのスピーキング対策をとる必要があるんだと思います。
それと、やっぱり発音をもうちょっと向上させないとダメなんだろうな。練習してないからな。
このあたりが向上した自信がつけば、再受験するかも。でも、どうやったら自信をつけられるかは分からない。
2017年6月4日日曜日
TOEFL(10回目)受験
TOEFLを受けてみた。前回は2010年6月。7年ぶり10回目。
これまでの結果は以下の通り。
9回目が Reading26, Listening27, Speaking15, Writing22 で、90点
8回目が Reading29, Listening27, Speaking17, Writing21 で、94点
7回目が Reading26, Listening24, Speaking19, Writing20 で、89点
6回目が Reading26, Listening26, Speaking15, Writing21 で、88点
5回目が Reading23, Listening26, Speaking15, Writing20 で、84点
4回目が Reading25, Listening21, Speaking15, Writing18 で、79点
3回目が Reading14, Listening19,Speaking17,Writing15 で、65点
2回目が Reading20, Listening21, Speaking13, Writing17 で、71点
1回目は Reading10, Listening18, Speaking10, Writing14 で、52点
8回目が留学前の最後。9回目は留学の最終盤に受けたものです。
留学の最終盤の方が留学前より点が下がっています。スピーキングが悪くなってんのね。
9回目の受験時のブログ
9回目の結果のブログ
受験の感想としては、リスニングの精度はこれまで以上に上がっていると思うんですね。
全部分かる。「うんうん、分かった、分かった。もういいよ。で、何が聞きたいの?」って思うぐらい分かる。
もっと言えば、「どうせ、こういうことを聞くんでしょ」っていうぐらいまで思う。
リスニングパート自体の点はもう27点とかになっているから、それほど上積みは期待できません。
でも、スピーキングとライティングのパートでも、出題には会話や講義の音声が含まれるわけだから、
このリスニングの精度の高さは大きな前進だと思います。
ただ、問題はアウトプットですよね。
そりゃ、最高点だった8回目(留学前)と比べても、さらに合計5年の米国生活が積み重なっていますから、
アウトプットの点でもレベルは上がっているんだとは思う。そう思いたい。
でもスピーキングとかね。やっぱね。ダメだね。
一応、答えるべきことは分かっているけど、スムーズにペラペラと話せるわけじゃない。
とりあえず言葉は口から出てくる。でも、それを文章として完成させようとすると、
ちょっと考える時間が必要だったり、文法的にねじれが生じてしまったりといった感じです。
制限時間があるので、このあたりはなかなか難しい。
会話の要約する部分で時間を使いすぎて、自分の意見を述べる部分が早口になってしまうこともあった
まぁ、実生活では制限時間付で英語を話す機会はあまりないですどね。
発音は普通です。特に練習したことないですし、ネイティブみたいに話すつもりもない。
ライティングも、出題が終われば、書くべきことが頭に浮かんで、すぐに書き出すことができた。
単語数も、意識しなくても、出題時に示される適切な語数をちょっと超えるぐらいになった。
ざっと書いて、読み直したら、ちょうど時間が終わるぐらいの感覚です。
ということで、そんなにひどい点ではないと思う。
それぞれのセクションで自己新がでれば、Reading29、Listening27、Speaking19、Writing22で、97点。
ここから、SpeakingとWritingがどのぐらい上乗せされていて、
ReadingとListeningでどれぐらい取りこぼしているかっていう感じでしょうか。
プラスマイナスが同じぐらいであれば97点ですが、
受験してみた感覚としては、100点前後っていう予想。
スピーキングやライティングのアウトップットのスキルが上がっているわけじゃないですけど、
出題時のインプットの精度があがっていることが点数を後押ししてくれていると信じたい。
まぁ、赤っ恥をかくことは覚悟のうえです。
受験前は、これで100点超えてなければ、もう一度チャレンジしようかと思いましたが、
まぁ、今回以上のパフォーマンスが出ることもないでしょうから、100点未満でも受け入れます。
受験時間は3時間半ぐらい。長い。疲れる。受験料は195ドル。昔より高くなっていないか?
これまでの結果は以下の通り。
9回目が Reading26, Listening27, Speaking15, Writing22 で、90点
8回目が Reading29, Listening27, Speaking17, Writing21 で、94点
7回目が Reading26, Listening24, Speaking19, Writing20 で、89点
6回目が Reading26, Listening26, Speaking15, Writing21 で、88点
5回目が Reading23, Listening26, Speaking15, Writing20 で、84点
4回目が Reading25, Listening21, Speaking15, Writing18 で、79点
3回目が Reading14, Listening19,Speaking17,Writing15 で、65点
2回目が Reading20, Listening21, Speaking13, Writing17 で、71点
1回目は Reading10, Listening18, Speaking10, Writing14 で、52点
8回目が留学前の最後。9回目は留学の最終盤に受けたものです。
留学の最終盤の方が留学前より点が下がっています。スピーキングが悪くなってんのね。
9回目の受験時のブログ
9回目の結果のブログ
受験の感想としては、リスニングの精度はこれまで以上に上がっていると思うんですね。
全部分かる。「うんうん、分かった、分かった。もういいよ。で、何が聞きたいの?」って思うぐらい分かる。
もっと言えば、「どうせ、こういうことを聞くんでしょ」っていうぐらいまで思う。
リスニングパート自体の点はもう27点とかになっているから、それほど上積みは期待できません。
でも、スピーキングとライティングのパートでも、出題には会話や講義の音声が含まれるわけだから、
このリスニングの精度の高さは大きな前進だと思います。
ただ、問題はアウトプットですよね。
そりゃ、最高点だった8回目(留学前)と比べても、さらに合計5年の米国生活が積み重なっていますから、
アウトプットの点でもレベルは上がっているんだとは思う。そう思いたい。
でもスピーキングとかね。やっぱね。ダメだね。
一応、答えるべきことは分かっているけど、スムーズにペラペラと話せるわけじゃない。
とりあえず言葉は口から出てくる。でも、それを文章として完成させようとすると、
ちょっと考える時間が必要だったり、文法的にねじれが生じてしまったりといった感じです。
制限時間があるので、このあたりはなかなか難しい。
会話の要約する部分で時間を使いすぎて、自分の意見を述べる部分が早口になってしまうこともあった
まぁ、実生活では制限時間付で英語を話す機会はあまりないですどね。
発音は普通です。特に練習したことないですし、ネイティブみたいに話すつもりもない。
ライティングも、出題が終われば、書くべきことが頭に浮かんで、すぐに書き出すことができた。
単語数も、意識しなくても、出題時に示される適切な語数をちょっと超えるぐらいになった。
ざっと書いて、読み直したら、ちょうど時間が終わるぐらいの感覚です。
ということで、そんなにひどい点ではないと思う。
それぞれのセクションで自己新がでれば、Reading29、Listening27、Speaking19、Writing22で、97点。
ここから、SpeakingとWritingがどのぐらい上乗せされていて、
ReadingとListeningでどれぐらい取りこぼしているかっていう感じでしょうか。
プラスマイナスが同じぐらいであれば97点ですが、
受験してみた感覚としては、100点前後っていう予想。
スピーキングやライティングのアウトップットのスキルが上がっているわけじゃないですけど、
出題時のインプットの精度があがっていることが点数を後押ししてくれていると信じたい。
まぁ、赤っ恥をかくことは覚悟のうえです。
受験前は、これで100点超えてなければ、もう一度チャレンジしようかと思いましたが、
まぁ、今回以上のパフォーマンスが出ることもないでしょうから、100点未満でも受け入れます。
受験時間は3時間半ぐらい。長い。疲れる。受験料は195ドル。昔より高くなっていないか?
2017年5月31日水曜日
"A Million Ways To Die In The West"
"A Million Ways To Die In The West"という本を読んだ。"Family Guy"で有名なSeth MacFarlaneの同名の映画の小説版です。
ちょっと前にシンプソンズの脚本に参加したことがあるというライターのエッセイを読んだのですが、これが面白くかつ読みやすかった。
https://www.wsj.com/articles/the-prom-a-survival-guide-for-parents-1494593931?tesla=y
で、このライターが何か本を出していないかと思って探してみたけど見つからなかったもので、それならファミリー・ガイのセス・マクファーレンの本だったら面白いんじゃないかと思って読んでみた次第です。
まぁ、面白かったことは間違いないですが、「お勧め!」っていうほどのものでもないです。
1882年のアリゾナを舞台に繰り広げられるコメディです。主人公はアルバートという男で、ヒツジ牧場を経営する気の優しい男。このアルバートと、美人の彼女ルイーズ、親友のエドワードとその恋人のルス、金持ちのフォイ、お尋ね者のクリンチ、その妻のアナたちが主要な登場人物で、まぁ、なんだかんだとドタバタするという話です。
ストーリーは単純です。まぁ、ちょっと凝った昔話みたいなもんです。だから話の筋道というよりは、主人公たちのキャラとか会話とかを楽しむタイプの本です。
例えば、エドワードとルスは実に仲の良いカップルなのですが、ルスは売春婦でエドワードもそのことを知っています。しかもルスとエドワードはそういった関係には至っていない。エドワードはなんとかそういう関係に持ち込みたいと思わないでもないのですが、ルスから「私たちはクリスチャンだから、婚前交渉は持つべきじゃない」と言われると、「そんなもんかなぁ」と思ってしまう。まぁ、そんなおかしなシチュエーションが面白いっていう本です。
だから面白いんです。でも、2時間ほどの映画と本にまとめたわけだから、映画で見た方が面白いんだと思います。
本を読むときに期待するほどの面白さではないと思います。
すぐに読める点はよかったです。
ちょっと前にシンプソンズの脚本に参加したことがあるというライターのエッセイを読んだのですが、これが面白くかつ読みやすかった。
https://www.wsj.com/articles/the-prom-a-survival-guide-for-parents-1494593931?tesla=y
で、このライターが何か本を出していないかと思って探してみたけど見つからなかったもので、それならファミリー・ガイのセス・マクファーレンの本だったら面白いんじゃないかと思って読んでみた次第です。
まぁ、面白かったことは間違いないですが、「お勧め!」っていうほどのものでもないです。
1882年のアリゾナを舞台に繰り広げられるコメディです。主人公はアルバートという男で、ヒツジ牧場を経営する気の優しい男。このアルバートと、美人の彼女ルイーズ、親友のエドワードとその恋人のルス、金持ちのフォイ、お尋ね者のクリンチ、その妻のアナたちが主要な登場人物で、まぁ、なんだかんだとドタバタするという話です。
ストーリーは単純です。まぁ、ちょっと凝った昔話みたいなもんです。だから話の筋道というよりは、主人公たちのキャラとか会話とかを楽しむタイプの本です。
例えば、エドワードとルスは実に仲の良いカップルなのですが、ルスは売春婦でエドワードもそのことを知っています。しかもルスとエドワードはそういった関係には至っていない。エドワードはなんとかそういう関係に持ち込みたいと思わないでもないのですが、ルスから「私たちはクリスチャンだから、婚前交渉は持つべきじゃない」と言われると、「そんなもんかなぁ」と思ってしまう。まぁ、そんなおかしなシチュエーションが面白いっていう本です。
だから面白いんです。でも、2時間ほどの映画と本にまとめたわけだから、映画で見た方が面白いんだと思います。
本を読むときに期待するほどの面白さではないと思います。
すぐに読める点はよかったです。
2017年5月20日土曜日
"Courage to Soar: A Body in Motion, A Life in Balance"
"Courage to Soar: A body in Motion, A Life in Balance"という本を読んだ。リオ五輪の女子体操で団体と個人総合、跳馬、床で金メダル。平均台で銅メダルをとったシモン・バイルズの回想録です。まだ20歳。痛快なお話でした。
前のトレバー・ノアの本が大変な子供時代を過ごした話でした。シモン・バイルスも母親がドラッグ中毒で、子供のころに祖父母に引き取られたという話を聞いたことがあったもので、どんなサクセスストーリーなのかと思って読んでみた。
ただ、あまり子供時代に家族のことで苦労したというわけではなさそうです。というのも、シモンは実の母親との生活をよく覚えていないんだそうです。
実の母親のシャノンさんは祖父の前妻との間の子供。シャノンさんは前妻のもとで育ち、シモンの姉(7歳上)、兄(3歳上)、シモン、妹(2歳下)を生みました。しかしドラッグなどへの依存症で、行政から育児放棄と認定されてしまいます。で、シモンが3歳のとき4人の子供たちは保護施設を通じて、ボランティアの里親のもとに引き取られる。しばらくして、テキサス州に住む祖父母が4人のきょうだいを引き取ることになります。
その後、4人は一度、オハイオ州に住むシャノンさんのもとに戻りますが、シャノンさんはドラッグをやめられなかった。それでも姉と兄は実の母親であるシャノンさんと暮らしたがったので、結局、2人はオハイオ州に住む祖父の姉のもとに、シモンと妹は祖父母のもとに戻ることになります。2002年12月24日、シモンが5歳のときのことです。そして2003年11月に、祖父母は2人と正式に養子縁組みし、シモンと妹の両親となります。この日からシモンは祖父母のことを、"Dad"、"Mom"と呼ぶようになります。
オハイオ州の話ですから、ヒルビリー・エレジーを思い出してしまいますが、シモンはどうもこのシャノンさんという女性にシンパシーを感じられないみたいです。
こんな一文があります。
Shanon still calls Adria and me on birthdays and holidays, but we don't have much contact beyond that. Some days, I feel a little bit sad for her. It's not that I ever wanted to go back to live in Ohio, but I do wish she'd been able to make better decisions when she was younger.
笑っちゃうぐらい、あっさりしています。シャノンさんにもいろいろ事情があったんだろうと思いますけどね。まぁ、だからといってシモンに何ができるっていうわけじゃないでしょうけど。
祖母は一番最初に4人のきょうだいを引き受けるとき、かなり不安だったそうです。4人は自分とは血のつながりがない子供たちだし、上の2人は物心がついていてシャノンさんに懐いている。しかも自分自身の2人の息子がどちらも高校生になって、子育てが一段落ついたばかり。そんなところに、また複雑な事情を抱えた幼い子供たちの面倒をみなければならないわけで、尻込みする気持ちも分かります。
ただ、そのとき、祖母の相談に乗っていた養子を育てた経験がある女性が、祖母にこんなことを言ったそうです。
"the Lord doesn't make any mistakes. And he never gives you more than you can handle."
この言葉に勇気づけられて、祖母は4人の面倒を見ることを決意したんだとのこと。ベリーズ出身の祖母はなかなか信仰に篤い人みたいです。
そんなシモンが体操を始めるきっかけは、祖父母の家にトランポリンがあったからだそうです。最初の里親の家にもトランポリンがあったんですが、そのときはシモンがケガをすることを心配する里親がトランポリンで遊ぶことを許してくれなかった。でも、祖父母の家だと、高校生の兄2人が見守るなかで遊ばしてもらえた。そのトランポリンが大好きで、ピョンピョンピョンピョン跳んでいたそうです。
で、6歳のときの保育園の遠足の行き先が、雨のため、牧場から体操クラブがある体育館に変更になった。その体育館でシモンがピョンピョンピョンピョン飛び跳ねているのをみて、体操クラブのコーチがクラブにスカウトしたんだそうです。このとき、遠足の行き先を体操クラブに変更したのは、保育園でバイトをしていた兄たちだった。まぁ、なんかマンガみたいな展開があるもんです。
あとは怒濤のサクセスストーリーになります。もちろんジュニアの米国代表に僅差で入れなかったとか、プレッシャーがきつかったとか、高校に通うかホームスクーリングにするかで悩んだとか、段違い平行棒が苦手でトカチェフをマスターするのに7カ月かかったとか、ケガしたとか、トップアスリートならではの苦労はあります。それぞれがほんの数年前の出来事だったりするわけで、10台の女の子としての実感がこもっています。大変だったでしょう。
ただ、やっぱり超恵まれた展開もあります。
特に最初の世界選手権制覇の後の2014年2月、体操を始めてからずっとコーチをしてくれた女性が突然、体操クラブを辞めることになったときのエピソードはすごい。シモンはこの女性コーチのもとでずっと練習したいと思うわけですが、女性コーチの移籍先が決まっているわけじゃないし、移籍先が決まったところでシモンが通える場所になるかどうかは分からない。今の体操クラブに残留するのが一番の安全策ですが、やっぱりシモンのことを一番理解してくれいるのはこの女性コーチだというジレンマがあります。
子供のころから夢見てきたオリンピックまで2年あまりというなかでのこのピンチ。これを切り抜けた方法は、
「祖母(養母)が女性コーチのために新しい体育館と体操クラブを作る」
というもの。
祖母は看護師としてキャリアを積んできた人で、14カ所の老人ホームを共同経営するほどにまで成功した人だそうです。で、その持ち分を売却して資金を作り、体育館を建て、新しい体操クラブを作ってしまった。その名もワールド・チャンピオン・センターです。もちろん、すぐに体育館ができるわけじゃないですから、シモンは最初の半年は元の体操クラブの体育館に間借りして、その後は倉庫を改装した仮の体育館を使って練習を続けたんだそうです。マンガ的ですが、本当の話です。
ということで、期待していた苦労話ではなかったですが、小柄でも体操が大好きな天才少女がいろんな苦労をしながらも、優しい祖父母や兄や妹に支えられながらマンガ的な展開で連戦連勝を重ね、最後にはオリンピックでの勝利をつかみ取るという痛快なストーリーではあります。
これはこれで面白かった。
前のトレバー・ノアの本が大変な子供時代を過ごした話でした。シモン・バイルスも母親がドラッグ中毒で、子供のころに祖父母に引き取られたという話を聞いたことがあったもので、どんなサクセスストーリーなのかと思って読んでみた。
ただ、あまり子供時代に家族のことで苦労したというわけではなさそうです。というのも、シモンは実の母親との生活をよく覚えていないんだそうです。
実の母親のシャノンさんは祖父の前妻との間の子供。シャノンさんは前妻のもとで育ち、シモンの姉(7歳上)、兄(3歳上)、シモン、妹(2歳下)を生みました。しかしドラッグなどへの依存症で、行政から育児放棄と認定されてしまいます。で、シモンが3歳のとき4人の子供たちは保護施設を通じて、ボランティアの里親のもとに引き取られる。しばらくして、テキサス州に住む祖父母が4人のきょうだいを引き取ることになります。
その後、4人は一度、オハイオ州に住むシャノンさんのもとに戻りますが、シャノンさんはドラッグをやめられなかった。それでも姉と兄は実の母親であるシャノンさんと暮らしたがったので、結局、2人はオハイオ州に住む祖父の姉のもとに、シモンと妹は祖父母のもとに戻ることになります。2002年12月24日、シモンが5歳のときのことです。そして2003年11月に、祖父母は2人と正式に養子縁組みし、シモンと妹の両親となります。この日からシモンは祖父母のことを、"Dad"、"Mom"と呼ぶようになります。
オハイオ州の話ですから、ヒルビリー・エレジーを思い出してしまいますが、シモンはどうもこのシャノンさんという女性にシンパシーを感じられないみたいです。
こんな一文があります。
Shanon still calls Adria and me on birthdays and holidays, but we don't have much contact beyond that. Some days, I feel a little bit sad for her. It's not that I ever wanted to go back to live in Ohio, but I do wish she'd been able to make better decisions when she was younger.
笑っちゃうぐらい、あっさりしています。シャノンさんにもいろいろ事情があったんだろうと思いますけどね。まぁ、だからといってシモンに何ができるっていうわけじゃないでしょうけど。
祖母は一番最初に4人のきょうだいを引き受けるとき、かなり不安だったそうです。4人は自分とは血のつながりがない子供たちだし、上の2人は物心がついていてシャノンさんに懐いている。しかも自分自身の2人の息子がどちらも高校生になって、子育てが一段落ついたばかり。そんなところに、また複雑な事情を抱えた幼い子供たちの面倒をみなければならないわけで、尻込みする気持ちも分かります。
ただ、そのとき、祖母の相談に乗っていた養子を育てた経験がある女性が、祖母にこんなことを言ったそうです。
"the Lord doesn't make any mistakes. And he never gives you more than you can handle."
この言葉に勇気づけられて、祖母は4人の面倒を見ることを決意したんだとのこと。ベリーズ出身の祖母はなかなか信仰に篤い人みたいです。
そんなシモンが体操を始めるきっかけは、祖父母の家にトランポリンがあったからだそうです。最初の里親の家にもトランポリンがあったんですが、そのときはシモンがケガをすることを心配する里親がトランポリンで遊ぶことを許してくれなかった。でも、祖父母の家だと、高校生の兄2人が見守るなかで遊ばしてもらえた。そのトランポリンが大好きで、ピョンピョンピョンピョン跳んでいたそうです。
で、6歳のときの保育園の遠足の行き先が、雨のため、牧場から体操クラブがある体育館に変更になった。その体育館でシモンがピョンピョンピョンピョン飛び跳ねているのをみて、体操クラブのコーチがクラブにスカウトしたんだそうです。このとき、遠足の行き先を体操クラブに変更したのは、保育園でバイトをしていた兄たちだった。まぁ、なんかマンガみたいな展開があるもんです。
あとは怒濤のサクセスストーリーになります。もちろんジュニアの米国代表に僅差で入れなかったとか、プレッシャーがきつかったとか、高校に通うかホームスクーリングにするかで悩んだとか、段違い平行棒が苦手でトカチェフをマスターするのに7カ月かかったとか、ケガしたとか、トップアスリートならではの苦労はあります。それぞれがほんの数年前の出来事だったりするわけで、10台の女の子としての実感がこもっています。大変だったでしょう。
ただ、やっぱり超恵まれた展開もあります。
特に最初の世界選手権制覇の後の2014年2月、体操を始めてからずっとコーチをしてくれた女性が突然、体操クラブを辞めることになったときのエピソードはすごい。シモンはこの女性コーチのもとでずっと練習したいと思うわけですが、女性コーチの移籍先が決まっているわけじゃないし、移籍先が決まったところでシモンが通える場所になるかどうかは分からない。今の体操クラブに残留するのが一番の安全策ですが、やっぱりシモンのことを一番理解してくれいるのはこの女性コーチだというジレンマがあります。
子供のころから夢見てきたオリンピックまで2年あまりというなかでのこのピンチ。これを切り抜けた方法は、
「祖母(養母)が女性コーチのために新しい体育館と体操クラブを作る」
というもの。
祖母は看護師としてキャリアを積んできた人で、14カ所の老人ホームを共同経営するほどにまで成功した人だそうです。で、その持ち分を売却して資金を作り、体育館を建て、新しい体操クラブを作ってしまった。その名もワールド・チャンピオン・センターです。もちろん、すぐに体育館ができるわけじゃないですから、シモンは最初の半年は元の体操クラブの体育館に間借りして、その後は倉庫を改装した仮の体育館を使って練習を続けたんだそうです。マンガ的ですが、本当の話です。
ということで、期待していた苦労話ではなかったですが、小柄でも体操が大好きな天才少女がいろんな苦労をしながらも、優しい祖父母や兄や妹に支えられながらマンガ的な展開で連戦連勝を重ね、最後にはオリンピックでの勝利をつかみ取るという痛快なストーリーではあります。
これはこれで面白かった。
2017年5月6日土曜日
"Born A Crime: Stories from a south African childhood"
"Born A Crime: Stories from a south African childhood"という本を読んだ。南アフリカ出身のコメディアン、Trevor Noahが南アフリカでの少年時代を振り返った本です。2016年11月発刊です。
ノアさんは2015年9月から、アメリカのコメディセントラルというケーブルテレビ局で"The Daily Show"の司会をしています。政治風刺を売り物にしたコメディ番組です。前任のJon Stewartはとても人気があったのですが、引退することになって、その後任として米国では無名の南アフリカ出身のコメディアンが抜擢されたと話題になった人です。
番組はyoutubeで見ることができます。どれも面白いです。
https://www.youtube.com/channel/UCwWhs_6x42TyRM4Wstoq8HA/featured
で、そんな面白いノアさんの本ですから、面白いんじゃないかと思って読んでみました。そしたら、想像以上に面白かった。生涯最高の本に認定します。
まず、ノアさんの出自なんですが、1984年2月20日、南アフリカのヨハネスブルグで生まれています。つまり1990年のネルソン・マンデラ釈放前で、アパルトヘイトが続いていたころです。で、ノアさんの母親はXhosa(コサ)族の黒人女性ですが、父親は当時南アに駐在していたドイツ系スイス人。当時はアパルトヘイトのもとで、異人種間の性交渉は犯罪でしたから、ノアさんは存在自体が犯罪の証拠だったということになります。
もう設定からして、私が想像したことがなかった世界。もちろんアパルトヘイトがあったことは知っていたわけですが、そこでの生活がどんなものであったかということは考えたことがなかったし、そのアパルトヘイトの枠からはみ出た人たちがいることも想像したことなかった。
で、そんな話なので、実にしめっぽい話になるのかと思うところですが、そんなことはないです。どこを読んでも笑えてしまう。
ノアさんは両親が白人と黒人ですから、南アの人種的な分類では"ミックス"ということになります。ただ、異人種間の混血というのは何世代も前から起きていることですから、一口に黒人といっても肌の色の濃さは様々です。だから、真っ黒な肌でない人はノアさん以外にもいるわけで、そういう人たちはひとまとめにして「カラード」と分類されます。カラードでいることは犯罪ではありませんでした。また、このほか、アパルトヘイト下での南アにはインディアンという分類もあって、白人と黒人とカラードとインディアンは、それぞれ別の地区に住まねばなりませんでした。就くことができる仕事にも制限がありました。
で、どこまで肌が黒ければ黒人で、黒さが薄ければカラードになるかとか、どこまで肌が白っぽかったら白人になるのかというのは、人種登録を担当する役人のフィーリングで決まるそうです。両親がともに白人と分類されていても、肌の色が濃いめの子供が生まれてくることもあります。「鉛筆テスト」なんていうものもあったそうで、髪の毛に鉛筆をさして下に落ちたら白人、巻き毛のせいで下に落ちなかったらカラードと分類される。まぁ、そのぐらいのいい加減な基準です。
さらに馬鹿げた話ですが、アパルトヘイト下での南アでは日本人は白人に分類されていました。自動車や電子機器を南アに輸出するために駐在する日本人に不都合があれば、南ア経済に不利益が生じるからです。でも、中国人は黒人だったそうです。まだ経済力が強くなかったせいでしょう。
つまりアパルトヘイトなんていうものは、まったく何の根拠もないルールだったわけです。そしてノアさんの母親のパトリシアさんは意味のないルールに従うことが大嫌いで、なおかつおそろしく頑固な人でした。
パトリシアさんはコサ族の家庭に育ちましたが、一緒に住んでいた母親よりも、別居中だった父親に懐いて、9歳のときに母親に対して「お父さんと一緒に住めみたい」と申し出ます。で、父親が迎えにきたのですが、この父親が困った人で、何の説明もなしにパトリシアさんを妹の家に預けてしまいます。パトリシアさんは、父親と一緒に暮らすつもりが、おばさんと暮らすことになったわけです。
で、このおばさんはいろんなところから子供を預かって、畑仕事とかをさせて生活の糧をえている人でした。家には14人の子供がいたそうです。子供たちは十分な食事を与えられず、パトリシアさんは犬や豚のえさを食べて空腹を満たしたこともあった。なんかグリム童話みたいな話ですが、そんな現実もあるということです。
ただ、パトリシアさんにとって幸運だったのは、このおばさんの住む村には白人の牧師が運営するミッションスクールがあったのです。当時、黒人に白人と同等の教育を与えることは禁止されていましたが、使命感にかられた牧師たちがこうした学校を開くことがあったらしい。そこでパトリシアさんは英語を学びます。読み書きができるようになると、そのうち畑仕事ではなく衣料品の工場で働くことができるようになり、工場で食事にもありつけるようになります。そして21歳のとき、おばさんが病気になったことをきっかけに母親のもとに戻り、タイピングを学び、秘書の仕事でお金を稼げるようになります。パトリシアさんは一家の稼ぎ手として働き続けます。しかしいくら稼いでも家族のためにお金がなくなっていく生活に耐えられなくなって、母親の家から逃げ出します。22歳のときです。
パトリシアさんが逃げ出した先は、ヨハネスブルグのダウンタウンです。でも当時、黒人がヨハネスブルグに住むことは違法です。パトリシアさんは隠れるようにして暮らすしかありません。
そんなパトリシアさんを助けてくれたのがヨハネスブルグで暮らす同じコサ族の売春婦たちです。彼女たちの顧客は南アに駐在する外国人たちです。南アの法律を気にする必要もない立場ですし、彼らにとっては売春婦が身近で暮らしている方が都合がよかったようで、黒人の売春婦たちに住む場所を提供していました。パトリシアさんは秘書として稼いだお金で家賃を払い、住む場所を確保します。なんかグリム童話の世界から、なんかの近未来アニメみたいな雰囲気に移っていますが、やっぱりそんな現実もあるんでしょう。
そんな生活をするなかで知り合ったのが、ドイツ系スイス人のロバートさんです。パトリシアさん24歳、ロバートさん46歳。そこにどんな恋愛感情があったのか、なかったのかは分かりませんが、パトリシアさんは「子供を生むのを手伝って欲しい。生まれた子供に責任を持つ必要はないし、お金を払う必要もない。ただ精子が欲しいだけ」と切り出します。
そんな形で生まれたのがノアさんです。
"on February 20, 1984, my mother checked into Hillbrow Hospital for a scheduled C-section delivery. Estranged from her family, pregnant by a man she could no be seen in public, she was alone. The doctors took her up to the delivery room, cut open her belly, and reached in and pulled out a half-white, half-black child who violated any number of laws, statutes, and regulations--- I was born a crime. "
こんな話、面白いに決まっているでしょう。ただ、この本の面白さはこんなものじゃないです。とにかくめちゃくちゃ面白いのです。
まぁ、とにかくいろんなエピソードが出てきます。いちいち紹介するのはやめておきますが、
どんな苦難に見舞われても教会通いをやめないパトリシアさんに振り回されるノアさんの抵抗とか、
家のなかにトイレがない生活の悲しみとか、
いろいろあって出会う機会がなくなった父親との再会と喜びとか、
チョコレートの万引きでの退学を肌の色で免れた話とか、
生涯最高の美少女とのデートと意外な真実とか、
高校時代から音楽の違法ダウンロードでお金を稼いでいた話とか、
存在自体が違法なミックスとして黒人とも白人ともカラードともしっくりいかない感覚とか、
そうしたなかでもどのグループとも「面白いアウトサイダー」としてつきあえる術を身につけた話とか、
言葉ができることの大切さとか、
「ヒトラー」という名前のダンサーと巻き起こした騒動とか、
南アの闇市のなかで暮らす人々とお金を稼ぐ方法とか、
無登録車の運転で逮捕された話とか、
もうとにかく色々です。
面白いなかにも、シリアスなトーンは残ります。何しろアパルトヘイトの下で十分な教育を与えられなかった黒人たちの生活は、アパルトヘイトがなくなった後でも苦しい生活を続けざるをえないのです。パトシリアさんがお金を稼げるようになったのは幸運にも英語教育を受ける機会があったからですし、ノアさんの生活が違法ダウンロードでお金を稼げるようになったのは、たまたま白人の知り合いがCDライターをくれたからです。ノアさんはアパルトヘイト後の黒人の生活について、「魚の釣り方は教えてもらったけど、釣り竿が手に入らない状態だ」と説明します。貧困から這い上がれないでいる黒人たちの実態も実感をもって説明されています。
あと、最後の章はシャレになりません。パトリシアさんが後に結婚した男の家庭内暴力でノアさんたちの生活が危機にさらされたというエピソードで、結局、この男はパトリシアさんとの離婚後、パトリシアさんの頭を拳銃で撃つことになります。とんでもない話です。でも最後のシーンは笑えるのです。どう説明したって、この感覚は伝わりそうにないですけど、人間と神様と母親と子供と愛情とユーモアに関わるイメージが同時にぶわっと頭の中に広がるような感じです。
いろんな学びが得られる本です。それでいて説教くさくない、エンターテインメントとして読める本でもあります。
ノアさんは2015年9月から、アメリカのコメディセントラルというケーブルテレビ局で"The Daily Show"の司会をしています。政治風刺を売り物にしたコメディ番組です。前任のJon Stewartはとても人気があったのですが、引退することになって、その後任として米国では無名の南アフリカ出身のコメディアンが抜擢されたと話題になった人です。
番組はyoutubeで見ることができます。どれも面白いです。
https://www.youtube.com/channel/UCwWhs_6x42TyRM4Wstoq8HA/featured
で、そんな面白いノアさんの本ですから、面白いんじゃないかと思って読んでみました。そしたら、想像以上に面白かった。生涯最高の本に認定します。
まず、ノアさんの出自なんですが、1984年2月20日、南アフリカのヨハネスブルグで生まれています。つまり1990年のネルソン・マンデラ釈放前で、アパルトヘイトが続いていたころです。で、ノアさんの母親はXhosa(コサ)族の黒人女性ですが、父親は当時南アに駐在していたドイツ系スイス人。当時はアパルトヘイトのもとで、異人種間の性交渉は犯罪でしたから、ノアさんは存在自体が犯罪の証拠だったということになります。
もう設定からして、私が想像したことがなかった世界。もちろんアパルトヘイトがあったことは知っていたわけですが、そこでの生活がどんなものであったかということは考えたことがなかったし、そのアパルトヘイトの枠からはみ出た人たちがいることも想像したことなかった。
で、そんな話なので、実にしめっぽい話になるのかと思うところですが、そんなことはないです。どこを読んでも笑えてしまう。
ノアさんは両親が白人と黒人ですから、南アの人種的な分類では"ミックス"ということになります。ただ、異人種間の混血というのは何世代も前から起きていることですから、一口に黒人といっても肌の色の濃さは様々です。だから、真っ黒な肌でない人はノアさん以外にもいるわけで、そういう人たちはひとまとめにして「カラード」と分類されます。カラードでいることは犯罪ではありませんでした。また、このほか、アパルトヘイト下での南アにはインディアンという分類もあって、白人と黒人とカラードとインディアンは、それぞれ別の地区に住まねばなりませんでした。就くことができる仕事にも制限がありました。
で、どこまで肌が黒ければ黒人で、黒さが薄ければカラードになるかとか、どこまで肌が白っぽかったら白人になるのかというのは、人種登録を担当する役人のフィーリングで決まるそうです。両親がともに白人と分類されていても、肌の色が濃いめの子供が生まれてくることもあります。「鉛筆テスト」なんていうものもあったそうで、髪の毛に鉛筆をさして下に落ちたら白人、巻き毛のせいで下に落ちなかったらカラードと分類される。まぁ、そのぐらいのいい加減な基準です。
さらに馬鹿げた話ですが、アパルトヘイト下での南アでは日本人は白人に分類されていました。自動車や電子機器を南アに輸出するために駐在する日本人に不都合があれば、南ア経済に不利益が生じるからです。でも、中国人は黒人だったそうです。まだ経済力が強くなかったせいでしょう。
つまりアパルトヘイトなんていうものは、まったく何の根拠もないルールだったわけです。そしてノアさんの母親のパトリシアさんは意味のないルールに従うことが大嫌いで、なおかつおそろしく頑固な人でした。
パトリシアさんはコサ族の家庭に育ちましたが、一緒に住んでいた母親よりも、別居中だった父親に懐いて、9歳のときに母親に対して「お父さんと一緒に住めみたい」と申し出ます。で、父親が迎えにきたのですが、この父親が困った人で、何の説明もなしにパトリシアさんを妹の家に預けてしまいます。パトリシアさんは、父親と一緒に暮らすつもりが、おばさんと暮らすことになったわけです。
で、このおばさんはいろんなところから子供を預かって、畑仕事とかをさせて生活の糧をえている人でした。家には14人の子供がいたそうです。子供たちは十分な食事を与えられず、パトリシアさんは犬や豚のえさを食べて空腹を満たしたこともあった。なんかグリム童話みたいな話ですが、そんな現実もあるということです。
ただ、パトリシアさんにとって幸運だったのは、このおばさんの住む村には白人の牧師が運営するミッションスクールがあったのです。当時、黒人に白人と同等の教育を与えることは禁止されていましたが、使命感にかられた牧師たちがこうした学校を開くことがあったらしい。そこでパトリシアさんは英語を学びます。読み書きができるようになると、そのうち畑仕事ではなく衣料品の工場で働くことができるようになり、工場で食事にもありつけるようになります。そして21歳のとき、おばさんが病気になったことをきっかけに母親のもとに戻り、タイピングを学び、秘書の仕事でお金を稼げるようになります。パトリシアさんは一家の稼ぎ手として働き続けます。しかしいくら稼いでも家族のためにお金がなくなっていく生活に耐えられなくなって、母親の家から逃げ出します。22歳のときです。
パトリシアさんが逃げ出した先は、ヨハネスブルグのダウンタウンです。でも当時、黒人がヨハネスブルグに住むことは違法です。パトリシアさんは隠れるようにして暮らすしかありません。
そんなパトリシアさんを助けてくれたのがヨハネスブルグで暮らす同じコサ族の売春婦たちです。彼女たちの顧客は南アに駐在する外国人たちです。南アの法律を気にする必要もない立場ですし、彼らにとっては売春婦が身近で暮らしている方が都合がよかったようで、黒人の売春婦たちに住む場所を提供していました。パトリシアさんは秘書として稼いだお金で家賃を払い、住む場所を確保します。なんかグリム童話の世界から、なんかの近未来アニメみたいな雰囲気に移っていますが、やっぱりそんな現実もあるんでしょう。
そんな生活をするなかで知り合ったのが、ドイツ系スイス人のロバートさんです。パトリシアさん24歳、ロバートさん46歳。そこにどんな恋愛感情があったのか、なかったのかは分かりませんが、パトリシアさんは「子供を生むのを手伝って欲しい。生まれた子供に責任を持つ必要はないし、お金を払う必要もない。ただ精子が欲しいだけ」と切り出します。
そんな形で生まれたのがノアさんです。
"on February 20, 1984, my mother checked into Hillbrow Hospital for a scheduled C-section delivery. Estranged from her family, pregnant by a man she could no be seen in public, she was alone. The doctors took her up to the delivery room, cut open her belly, and reached in and pulled out a half-white, half-black child who violated any number of laws, statutes, and regulations--- I was born a crime. "
こんな話、面白いに決まっているでしょう。ただ、この本の面白さはこんなものじゃないです。とにかくめちゃくちゃ面白いのです。
まぁ、とにかくいろんなエピソードが出てきます。いちいち紹介するのはやめておきますが、
どんな苦難に見舞われても教会通いをやめないパトリシアさんに振り回されるノアさんの抵抗とか、
家のなかにトイレがない生活の悲しみとか、
いろいろあって出会う機会がなくなった父親との再会と喜びとか、
チョコレートの万引きでの退学を肌の色で免れた話とか、
生涯最高の美少女とのデートと意外な真実とか、
高校時代から音楽の違法ダウンロードでお金を稼いでいた話とか、
存在自体が違法なミックスとして黒人とも白人ともカラードともしっくりいかない感覚とか、
そうしたなかでもどのグループとも「面白いアウトサイダー」としてつきあえる術を身につけた話とか、
言葉ができることの大切さとか、
「ヒトラー」という名前のダンサーと巻き起こした騒動とか、
南アの闇市のなかで暮らす人々とお金を稼ぐ方法とか、
無登録車の運転で逮捕された話とか、
もうとにかく色々です。
面白いなかにも、シリアスなトーンは残ります。何しろアパルトヘイトの下で十分な教育を与えられなかった黒人たちの生活は、アパルトヘイトがなくなった後でも苦しい生活を続けざるをえないのです。パトシリアさんがお金を稼げるようになったのは幸運にも英語教育を受ける機会があったからですし、ノアさんの生活が違法ダウンロードでお金を稼げるようになったのは、たまたま白人の知り合いがCDライターをくれたからです。ノアさんはアパルトヘイト後の黒人の生活について、「魚の釣り方は教えてもらったけど、釣り竿が手に入らない状態だ」と説明します。貧困から這い上がれないでいる黒人たちの実態も実感をもって説明されています。
あと、最後の章はシャレになりません。パトリシアさんが後に結婚した男の家庭内暴力でノアさんたちの生活が危機にさらされたというエピソードで、結局、この男はパトリシアさんとの離婚後、パトリシアさんの頭を拳銃で撃つことになります。とんでもない話です。でも最後のシーンは笑えるのです。どう説明したって、この感覚は伝わりそうにないですけど、人間と神様と母親と子供と愛情とユーモアに関わるイメージが同時にぶわっと頭の中に広がるような感じです。
いろんな学びが得られる本です。それでいて説教くさくない、エンターテインメントとして読める本でもあります。
2017年4月14日金曜日
"Rusty Nail"
ちょっと仮説を立ててみました。テンポ良く読める本を読んでいる時期の方が、音声で英語を聞いたときの理解度が上がるというものです。
頭のなかに単語ごとに入ってくる英語を文章としてとらえて、意味をとらえるスピードが上がるといってもいいかもしれません。
込み入った内容の本を読んでいるときは、やっぱり「ん?」と引っかかってしまいます。じっくりと読めば理解できるんですけどね。
こういう本ばかりを読んでいると反射神経が衰えてしまって、音声で英語を聞いたときの理解のスピードが落ちるような気がします。
逆に、テンポ良く読める本を読んでいるときは、文章の意味がスラスラ分りますから、頭がそのスピードになれる。
そうすると、音声で聞いた英語を処理するスピードも上がるということです。
込み入った内容の英語を音声できいたときは、なかなか理解することは難しいです。ただ、これは英語でも日本語でも同じな気もします。
ということで、スラスラ読める本として、これまでに2作読んだ、J.A. KonrathのJack Danielsシリーズの第3作目"Rusty Nail"を読んでみました。
Konrathさんは「読者にストレスなく理解させることが重要だ」と考えている人で、しかもユーモアーを交えた文章なので楽しめます。
Konrathさんのサイトで掲載された紹介文を引用すると、内容はこんな感じです。
Lt. Jacqueline "Jack" Daniels of the Chicago Police Department is back, and once again she's up to her Armani in murder.
Someone is sending Jack snuff videos. The victims are people she knows, and they share a common trait—each was involved in one of Jack's previous cases. With her stalwart partner hospitalized and unable to help, Jack follows a trail of death throughout the Midwest, on a collision course with the smartest and deadliest adversary she's ever known.
During the chase, Jack jeopardizes her career, her love life, and her closest friends. She also comes to a startling realization—serial killers have families, and blood runs thick.
Rusty Nail features more of the laugh-out-loud humor and crazy characters that saturated Whiskey Sour and Bloody Mary, without sacrificing the nail-biting thrills. This is Jack Daniels's third, and most exciting, adventure yet.
確かにその通りの内容です。面白かったです。英語理解のスピードへの影響も仮説通りな感じもします。
ただ、ちょっと犠牲者についてのグロい描写の頻度が高くて、ちょっとしんどい部分もある本です。
印象に残ったフレーズがあったので引用しておきます。Alexという登場人物と精神科医の会話です。
"That's an interesting question, Doctor. Can you ever truly know if love is being returned? You wear a wedding ring, so I assume you're married, and I assume you love your wife. But even if she says she loves you, you can't crawl around in her head and feel it for yourself. You can't ever truly know."
"I feel loved, and that's reassurance enough."
なんか、かっこいいよね。
あと、シリーズにレギュラーとして登場しているHarry McGladeという人物がいるのですが、エキセントリックさが京極夏彦の小説に出てくる榎木津礼二郎に似ていることに気づきました。まぁ、榎木津の方がメチャクチャですけど、このHarryもなかなかのものです。
頭のなかに単語ごとに入ってくる英語を文章としてとらえて、意味をとらえるスピードが上がるといってもいいかもしれません。
込み入った内容の本を読んでいるときは、やっぱり「ん?」と引っかかってしまいます。じっくりと読めば理解できるんですけどね。
こういう本ばかりを読んでいると反射神経が衰えてしまって、音声で英語を聞いたときの理解のスピードが落ちるような気がします。
逆に、テンポ良く読める本を読んでいるときは、文章の意味がスラスラ分りますから、頭がそのスピードになれる。
そうすると、音声で聞いた英語を処理するスピードも上がるということです。
込み入った内容の英語を音声できいたときは、なかなか理解することは難しいです。ただ、これは英語でも日本語でも同じな気もします。
ということで、スラスラ読める本として、これまでに2作読んだ、J.A. KonrathのJack Danielsシリーズの第3作目"Rusty Nail"を読んでみました。
Konrathさんは「読者にストレスなく理解させることが重要だ」と考えている人で、しかもユーモアーを交えた文章なので楽しめます。
Konrathさんのサイトで掲載された紹介文を引用すると、内容はこんな感じです。
Lt. Jacqueline "Jack" Daniels of the Chicago Police Department is back, and once again she's up to her Armani in murder.
Someone is sending Jack snuff videos. The victims are people she knows, and they share a common trait—each was involved in one of Jack's previous cases. With her stalwart partner hospitalized and unable to help, Jack follows a trail of death throughout the Midwest, on a collision course with the smartest and deadliest adversary she's ever known.
During the chase, Jack jeopardizes her career, her love life, and her closest friends. She also comes to a startling realization—serial killers have families, and blood runs thick.
Rusty Nail features more of the laugh-out-loud humor and crazy characters that saturated Whiskey Sour and Bloody Mary, without sacrificing the nail-biting thrills. This is Jack Daniels's third, and most exciting, adventure yet.
確かにその通りの内容です。面白かったです。英語理解のスピードへの影響も仮説通りな感じもします。
ただ、ちょっと犠牲者についてのグロい描写の頻度が高くて、ちょっとしんどい部分もある本です。
印象に残ったフレーズがあったので引用しておきます。Alexという登場人物と精神科医の会話です。
"That's an interesting question, Doctor. Can you ever truly know if love is being returned? You wear a wedding ring, so I assume you're married, and I assume you love your wife. But even if she says she loves you, you can't crawl around in her head and feel it for yourself. You can't ever truly know."
"I feel loved, and that's reassurance enough."
なんか、かっこいいよね。
あと、シリーズにレギュラーとして登場しているHarry McGladeという人物がいるのですが、エキセントリックさが京極夏彦の小説に出てくる榎木津礼二郎に似ていることに気づきました。まぁ、榎木津の方がメチャクチャですけど、このHarryもなかなかのものです。
2017年3月21日火曜日
"The End of The Asian Century: War, Stagnation, and the Risks to the World's Most Dynamic Region"
"The End of The Asian Century: War, Stagnation, and the Risks to the World's Most Dynamic Region"という本を読んだ。American Enterprise InstituteのMichael Auslinが2017年1月に出版した本です。
アジアは長いこと経済成長が続いてきて、米国なんかでも「これからはアジアの時代だ」なんて言われたりして、オバマ政権も"Pivot to Asia"なんていう戦略を打ち出したりしたわけですけど、このオースリンさんの本は「アジアの未来は明るいばかりじゃないよね」っということを指摘した本です。アジアでの軍事的な緊張は高まっているし、中国経済は維持可能かどうか分らないし、日本はグダグダな状態が長期化しているし、ベトナムにしてもインドネシアにしてもマレーシアにしても政治的に安定しているとは言い難いし、っていうようなことを紹介する内容です。
で、そのうえでオースリンさんはアジアの安定と発展は米国にとっても重要だから、米国はアジアのために積極的に関与していくべきだとしています。だからといって、ものすごいウルトラCでアジアを支えるっていうわけじゃなくて、安全保障でも外交でも文化交流でも現在の取り組みを着実に拡大してくべきだっていう感じですね。南シナ海で中国がアグレッシブになっているから、各国による共同パトロール体制を作ろうとか、ASEANと米国の経済連携を深めようとかそういったことです。
でもまぁ「アジアがグダグダだ」っていうのは大体知っている話ですし、提言の部分もびっくりするような話でもありません。
ただ、最大の短期的なリスクとして「軍事的な衝突」を挙げているところは、それほどにまで警戒すべき事柄とみられているのかという気がしました。もちろんオースリンさんは軍事的な衝突が起こると予想しているわけじゃなくて、「軍事的な衝突が起こりえるリスクがあることは認識せねばならない」と言っているわけですけどね。中期的なリスクとしては「経済の停滞」を挙げています。あと、各国の政治体制のぐらつきとか。
まぁ、最悪のシナリオはいくらでも描けるわけですから、まったくもってアジアがダメになると考えるのもどうかと思いますけど、「これからはアジアの時代だ!」なんていう雰囲気は薄らいできているのかもしれません。
アジアは長いこと経済成長が続いてきて、米国なんかでも「これからはアジアの時代だ」なんて言われたりして、オバマ政権も"Pivot to Asia"なんていう戦略を打ち出したりしたわけですけど、このオースリンさんの本は「アジアの未来は明るいばかりじゃないよね」っということを指摘した本です。アジアでの軍事的な緊張は高まっているし、中国経済は維持可能かどうか分らないし、日本はグダグダな状態が長期化しているし、ベトナムにしてもインドネシアにしてもマレーシアにしても政治的に安定しているとは言い難いし、っていうようなことを紹介する内容です。
で、そのうえでオースリンさんはアジアの安定と発展は米国にとっても重要だから、米国はアジアのために積極的に関与していくべきだとしています。だからといって、ものすごいウルトラCでアジアを支えるっていうわけじゃなくて、安全保障でも外交でも文化交流でも現在の取り組みを着実に拡大してくべきだっていう感じですね。南シナ海で中国がアグレッシブになっているから、各国による共同パトロール体制を作ろうとか、ASEANと米国の経済連携を深めようとかそういったことです。
でもまぁ「アジアがグダグダだ」っていうのは大体知っている話ですし、提言の部分もびっくりするような話でもありません。
ただ、最大の短期的なリスクとして「軍事的な衝突」を挙げているところは、それほどにまで警戒すべき事柄とみられているのかという気がしました。もちろんオースリンさんは軍事的な衝突が起こると予想しているわけじゃなくて、「軍事的な衝突が起こりえるリスクがあることは認識せねばならない」と言っているわけですけどね。中期的なリスクとしては「経済の停滞」を挙げています。あと、各国の政治体制のぐらつきとか。
まぁ、最悪のシナリオはいくらでも描けるわけですから、まったくもってアジアがダメになると考えるのもどうかと思いますけど、「これからはアジアの時代だ!」なんていう雰囲気は薄らいできているのかもしれません。
2017年3月18日土曜日
「人類と気候の10万年史~過去に何が起きたのか、これから何が起こるのか」
「人類と気候の10万年史~過去に何が起きたのか、これから何が起こるのか」という本を読んだ。立命館大学の中川毅教授が書いた本で、2017年2月に出た本です。ブルーバックス。懐かしい。
トランプ政権は概して気候変動問題には関心が無いとみられていて、米国の環境保護局(EPA)局長に就任したスコット・プルイット氏も「気候変動に人間の活動が影響していることは理解しているが、それがどの程度の大きさであるかは議論が続いているところである」というのが持論だったりします。
ただ、メディアの方では「プルイットは科学的見地を無視したバカモノだ」といった論調で報じることが多いです。
例えば、3月10日のCNNの朝の番組では、プルイット氏の
"I think that measuring with precision human activity on the climate is something very challenging to do and there's tremendous disagreement about the degree of impact. So, no, I would not agree that it's a primary contributor to the -- to the global warming that we see. OK. Or, we don't know that yet, as far as -- we need -- we need to continue the debate, continue the review and the analysis."
という発言を流したあと、
キャスターが
"That is not what the majority of the scientific community would state as a proposition."
とつないで、
コメンテーターが、
"And in fact, when you said not the majority, I mean, that, Chris, even understates it. The overwhelming -- the overwhelming preponderance of international, you know, scientific bodies have repeatedly reaffirmed that linkage."
応じたりするわけです。
プルイット氏が「人間の活動が気候変動の主要な要因であるかは議論がある」と述べているのに対して、コメンテーターは「人間の活動と気候変動に関連があることは疑いはない」と述べているわけですから、どちらも正しいことを言っている可能性はあるわけですが、キャスターやコメンテーターの発言には「プルイット氏は科学を否定している」と異端視する雰囲気が感じられます。
個人的には、気候変動と人間の活動に関連があることは分かります。
アンデスかどこかの山の上の氷河がどんどん溶けているとかいう話を聞くと「地球が温暖化しているんだな」というのは素直に納得できるますし、二酸化炭素とかに温室効果があることもそうなんだろうなと思いますし、化石燃料を使ったり、森林を伐採したりする人間の活動が地球の大気中に含まれる二酸化炭素の量を増やしているんだろうなというのも分かります。
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書には、こんな記述もあります。
"It is extremely likely that more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010 was caused by the anthropogenic increase in greenhouse gas concentrations and other anthropogenic forcings together."
この60年間の気温上昇の半分超は人間の活動がもたらしたものである可能性が極めて高いということだと思います。
半分超ですから、プルイット氏の"I would not agree that it's a primary contributor to the global warming that we see"という発言は、科学者の見解とは食い違っていることになります。
ただ、プルイット氏の気持ちも分かります。
「半分超」っていうことは、51%かもしれないし100%かもしれないわけで、どこに落ち着くかによってはかなり雰囲気が違います。
あと、昔はマンモスが住んでいたような氷河期があったっていうわけですから、地球上の気温はずっと昔から上昇を続けてきたんでしょう。おそらく人間の活動以外にも地球の気温を上昇させている要因があるはずです。そうした人間以外の要因と、人間という要因のどちらが大きな影響を及ぼしているかなんていうことは、なかなか分からないのではないかとも思うのです。そもそも何十年か前には、科学的な見地をもとに「地球が再び氷河期になる」なんていう騒ぎ方もされていたように思います。
それに本当のことを言うと、IPCCの報告書がなんぼのもんじゃという感覚もあります。だってそもそも「地球の平均気温」という概念がよく分からない。いつの、どこの気温だよ。あと、人間の活動が排出している温室効果ガスの量なんて、そんなに正確に測定できるものなのかよという気もします。いつだったか、中国の排出量に関する報告が大きく訂正されたっていう話もあったように思います。
ということで、何か分かるんじゃないかと思って、この本を読んでみた次第です。非常に面白かったです。
著者の中川教授は古気候学の専門家で、何万年も前から現在に至るまでの過去の地球の気候を研究している人です。
学会の定説とされるミランコビッチ理論によると、地球上の気候は10万年ごとに温暖化のピークがあります。この10万年のサイクルは楕円形である地球の公転軌道が揺らぐことで、地球と太陽の距離が変化することで起こるものです。温暖な時期と寒冷な時期の温度差は10度にも達します。地球の気温が10度変化するというのは、鹿児島が札幌になるぐらいの変化に相当するそうです。なるほど。そりゃ大変だ。
また地球の気候には2万3000年のサイクルもあって、この周期でやはり温暖な時期と寒冷な時期が繰り返されます。これは地球の地軸の傾きが揺らぐことで、地球にそそぐ太陽のエネルギーの分配のパターンが変わることで起こるもので、7度ぐらいの温度差が出るものだそうです。7度といえば東京が那覇になるぐらいのものです。おぉ、大変。
言葉で説明するとよく分りませんが、本のなかにはグラフが出てきます。それをみると地球の気温が2万3000年のサイクルで小さな波を描きながら、全体としては10万年サイクルの大きなトレンドも作っているということが分かります。
現在はこの10万年のサイクルのなかでは、温暖な時期のピークをすぎたあたりだそうです。現在は「例外的に」暖かい時期といえ、本来であれば、これから地球の気温が寒冷になっていく方向に向かうはずです。これは地球の公転とか地軸の傾きとか、宇宙レベルでの物理法則に従ったものですから、トレンドを変えることは難しい。だから昔は「地球が再び氷河期になる」なんていう騒がれ方をしたわけです。
で、この本はどうしてそんなことが分かるのかということと、今とは違う気候だった地球はどんなところだったのかということを分かりやすく説明した本です。率直に言えば「そんなの分かるわけないじゃん」と思ってしまうところですが、それが分かるんだそうです。
カギとなるのは、海や湖のなかに堆積していった「年縞」と呼ばれる地層の中に含まれるプランクトンの化石や化学組成を分析するという手法です。
なかでも中川教授がチームのリーダーとなって福井県の水月湖の湖底から採取した年縞は世界的な価値が認められています。普通なら、水の底に住んでいる生き物や川から流れ込んだ水が薄く積もった地層をかき乱したりして、数万年にもおよぶ地層を保つことはないわけですが、水月湖では1年間で0.7ミリメートルペースでたまっていく薄い地層が奇跡的に保存されているそうです。ここらあたりが、いかに奇跡であるかについても詳しい説明がされていますが、ここでは省略。中川教授は全体として73メートル分(15万年相当)の堆積物を回収し、そのうち45メートル分にはっきりとした年縞を確認することができました。
で、それをどう分析するのかということです。
まず、放射性炭素年代測定という手法があります。自然界に存在する炭素には質量数12、13、14の3種類があります。そして、このうち質量数14の炭素(C14)だけが放射能を持っていて、時間とともに徐々に別の物質に変わっていきます。なので何かに含まれている炭素のなかで、C14がC12やC13に比べてどれだけ減っているかを測定すれば、その何かの年代が推定できるんだそうです。年代不明の麺の化石に含まれた炭素を調べたところ、麺の材料となった植物が刈り取られたのは4000年前だということが分かったケースもあるんだとのこと。
ただ、この放射性炭素年代測定には誤差が大きいという問題点があります。それはスタートラインにおけるC14の比率が正確に分からないからです。
そこで年縞の出番になります。水月湖の年縞には葉っぱの化石が含まれています。しかも年に1層ずつ積もっていく年縞の数を数えれば、その葉っぱが今から何年前に湖底にたまったものかが分かります。さらに、その化石のC14の比率を調べれば、C14がどれだけ残っていれば何年前の炭素に相当するという「換算表」が作ることができるというわけです。水月湖の年縞をもとにした換算表は世界の標準として認められています。
また、水月湖の堆積物のなかには、花粉の化石が含まれています。1立方センチメートルあたり数十万粒の花粉の化石がみつかることもあるそうです。こうした花粉の化石を顕微鏡で調べれば、どういった種類の植物が生えていたかが分かる。例えば、スギの花粉がたくさんみつかったり、ブナの花粉がたくさん見つかったり、スギとブナが半分ずつだったり、そういったことですね。それは水月湖周辺の植生を繁栄しているわけです。
で、その植生を現在の世界の植生と比べます。例えば「今から3万~2万年前の年縞から見つかった花粉は針葉樹とシラカバが混じり合っているから、現在のシベリアのような風景だった」といった推定がなりたつわけです。おぉ。
さらにモダンアナログ法という手法もあって、「2万年前の水月湖の花粉の組成が旭川近くの湖底に現在たまりつつある花粉の組成と似ていた場合、2万年前の福井県南部の気候は現在の旭川に近かった」と判断することができる。で、現在の旭川の平均気温や日照量をひっぱってくれば、2万年前の福井県南部の気温や日照量が推定できるというわけです。おおぉ。
こうした花粉の化石の分析によって、水月湖周辺の気候には10万年のサイクルと、2万3000年のサイクルがあることが分かりました。地球の公転軌道や地軸の傾きをもとにしたミランコビッチ理論と同じ周期です。
具体的には、
・温暖な時期のピークは、12万~11万年前と1万年前にある
・2万年前は氷期のいちばん寒い時期だった
・氷期と温暖な時代の震幅は10度(札幌-鹿児島の差)
ということです。
グラフをみると、12万年ほど前に現在と同じぐらいの暖かい時期があったけど、その後、徐々に気温が下がっていって、2万年前に底を打っています。さらにその後、急激な気温上昇があって1万年前のピークをつけたというイメージです。
また、
・12万年ほど前のピークの後の「徐々に気温が下がって」の部分は、2万3000年のサイクルで気温の上下を繰り返しながら、徐々に気温が下がっている。
・温度の震幅は最大で7度(東京-那覇の差)
ということでもあります。
ただし、こうしたデータの分析結果には、人間の活動が影響しているという指摘もあります。それは「最近の数千年は夏の日射が極小近くまで低下してきているのに対し、温度は反対に上昇しているっように見える」からです。こうしたズレは過去15万年の間ではなかったそうです。つまり1万年ほど前のピークの後に起きるはずの気温の低下が起きていないということですね。
中川教授はこのズレの原因について「まだ議論が続いている」としています。
その一方で、1万年前にピークをつけた温暖な時期が例外的に長く続いているというのは多くの研究者が指摘してきたことで、「ひとつの有力な説が人間活動に原因を求めている」としています。南極の氷に含まれる空気に含まれる温室効果ガスの濃度の研究ではメタンが5000年前、二酸化炭素が8000年前からミランコビッチ理論を外れるペースで増加していることが分っています。この現象について、バージニア大学のウィリアム・ラジマン教授が「アジアにおける水田農耕の普及、およびヨーロッパ人による大規模な森林破壊が原因」と主張していることも紹介されています。
で、ここからがややこしくかつ、奥深いのですが、中川教授は
「ラジマン教授の主張は、人間が気候を左右するようになった歴史は、100年前でなく8000年前にさかのぼるということを意味していた。もし私たちが、温室効果ガスの放出によって『とっくに来ていた』はずの氷期を回避しているのだとしたら、温暖化をめぐる善悪の議論は根底から揺らいでしまう。私たちは自然にやってくる氷期の地球で暮らしたいのか、それとも人為的に暖かく保たれた気候の中で暮らしたいのか。これはもはや、哲学の問題であって科学の問題ではない」
と述べています。
どうして中川教授がこんなことを言い出すかというと、氷期というのは現在の人類にとっては非常に厳しい時代だったからです。
水月湖の年縞の研究からも、氷期における気温の変化は温暖な時期に比べて極めて激しく、予測不能なカオスな動きをみせていたことが分かっています。氷期には「ダンスガード=オシュガー(D-O)イベント」と呼ばれる、原因不明の急激な温暖化が起きていたようです。
気候変動が人類に与える影響は甚大です。
1993年の冷夏は2年前のピナツボ火山の噴火が原因とされ、全国平均のコメの作況を7割にまで落としています。天明の飢饉は、1783年に起きたアイスランドのラキ火山の噴火によって、冷夏が5年以上も続いたことが原因だとされています。このときはヨーロッパでも食料不足が起きて、フランス革命の遠因となったとの分析もあります。また1980年代のアフリカの干ばつは4年間も続いて300万人の命を奪っています。ベネズエラ沿岸のカリアコ海盆の年縞に基づいた研究によると、ユカタン半島では西暦810年ごろ、9年の間に6回もの干ばつがあり、マヤ文明衰退のきっかけを作ったともされているそうです。
中川教授は「ときどき暴れる気候に対しては、現代社会は思っている以上に脆弱な基盤の上に成り立っている。だが少なくとも先進国において、そのような議論を耳にする機会は、意外なほどに少ないように思う」としています。
さらに中川教授は、現在の人類の繁栄の基盤となった農耕の普及にも気候変動が影響していたのではないかと思いを巡らせます。
気候の変化が激しい氷期は一種類の作物を大量に育てる農耕はリスクが大きい。氷期の人類が農耕ではなくて狩猟採取を基盤においていたのは、何も当時の人類が農耕を思いつかなかったわけではなくて、自然のなかで育つ多様な植物や動物を生活の糧とすることで、どんな気候になっても確実に食べ物を確保できる生活のスタイルが最適だったからではないかというわけです。
で、農耕生活と狩猟採取生活という2つのスタイルについて、中川教授は、
「どちらを好ましいと考えるかは、ひょっとすると哲学の問題に帰着するのかもしれない。繁栄と発展をあくまで是とするならば、農耕は欠かせない前提条件である。先進国の科学者である筆者も、基本的にはこの考え方に慣れている。だが、どこか南国の浜辺で野生のフルーツを採ったり、魚を釣ったりして糧を得る暮らしが『気にならない』かと問われたとき、ならないと断言するのは必ずしも正直なことではない」
としています。
もちろん「単純な原始回帰願望はナイーブに過ぎる」とも断っていますけど、10万年単位の気候の歴史を科学的かつ真剣に分析すれば、なかなか深いところに思い至ったりするもんなんでしょう。
中川教授は、宇宙レベルの物理法則に基づいたミランコビッチ理論は崩しがたいものだとみているようです。その理論に基づけば、地球は今後10万年サイクルの寒冷化に向かうわけで、一般的に言われているような地球温暖化への不安については距離をとった記述が目立ちます。
「温暖化の主犯格とされる二酸化炭素にある種の敵意を感じる人の数は、商業的にも無視できない水準に達している」
「現在の温暖化予測も70年代の寒冷化予測と同様に信用できないと主張しているのではない。(ただし、信頼できると主張しているのでもない)」
「私見だが、もっとも恐ろしいのは、現代の『安定で暖かい時代』がいつかは終わるというシナリオではないかと思う」
といった感じです。
あと、とにかく、気候変動は何が起こるか分からない、という言及も多いです。
「気候システムは極めて複雑な系であり、その挙動を理解することはもちろん、正確に記述することすら容易ではない」
「あらゆる未来予測には適用限界がある。このことは、本書に通底する重要なテーマのひとつ」
「本当に劇的な変化の予測は原理的にきわめて困難」
で、そうしたなかでも「だが、もしそれが起こった場合に、人間にとってどの程度の影響があるのか知っておくことは重要である」と指摘しています。
また、われわれが経験的に身につけている「天気予報とのつきあい方」を、現在の「100年後に5度の気温上昇」といった予測にもあてはめるべきだとしています。つまり、普通の天気予報なら、明日の予報だと信用するけれど、1週間後になるとそれほど信用しないし、「来年は冷夏」とか言われれば聞き流す。こうした感覚を100年後の野心的な天気予報を聞くときにも大切にすべきだというわけですね。
ということで、気候変動問題における科学的な予測があることは分るんだけれど、EPAのプルイット長官の気持ちも分らなくもないというのは、地球レベルの気候変動問題を科学的かつ真剣に研究してきた中川教授の感覚の方向性と大きく違うわけではないような気がします。あんまり「俺はなんでも分っているんだ」みたいな顔をして、プルイット長官的な人たちをいじめるのもどうかなと。
ここは完全に私見ですが、気候変動問題っていうか、地球温暖化問題についての危機感の大きさは地域差や個人差があって当然だと思います。海面上昇にさらされている小さな島国に住んでいる人は心配で仕方ないでしょうけど、電力不足が一般的な途上国の人だったら、石炭でもなんでもいいからとにかく安く発電所を作ってくれと思うはずです。あと、石炭産業で働いている人は「俺たちにだって生活がある」って思うでしょう。だから温室効果ガス排出の抑制に消極的な立場をとっている人たちを馬鹿にするのはよくない気がします。
ただ、中川教授は過去の気候の専門家ではあるけれど、未来予測を専門としているわけではないと思います。IPCCの報告書のような将来予測については、スーパーコンピューターの上で地球の気候を丸ごと再現して変化を予測する「気候モデリング」の手法で行われているとの説明がありますが、その内容についての詳しい言及はありませんでした。このあたりについても分りやすく説明してくれる本があれば読んでみたいところです。
もしも本当に人類による温室効果ガス排出が10万年サイクルの気候変動のパターンも打ち破って、ガンガンに地球を温暖化させることが確実に分っているっていうんだったら、プルイット長官に石を投げたくなるかもしれません。
トランプ政権は概して気候変動問題には関心が無いとみられていて、米国の環境保護局(EPA)局長に就任したスコット・プルイット氏も「気候変動に人間の活動が影響していることは理解しているが、それがどの程度の大きさであるかは議論が続いているところである」というのが持論だったりします。
ただ、メディアの方では「プルイットは科学的見地を無視したバカモノだ」といった論調で報じることが多いです。
例えば、3月10日のCNNの朝の番組では、プルイット氏の
"I think that measuring with precision human activity on the climate is something very challenging to do and there's tremendous disagreement about the degree of impact. So, no, I would not agree that it's a primary contributor to the -- to the global warming that we see. OK. Or, we don't know that yet, as far as -- we need -- we need to continue the debate, continue the review and the analysis."
という発言を流したあと、
キャスターが
"That is not what the majority of the scientific community would state as a proposition."
とつないで、
コメンテーターが、
"And in fact, when you said not the majority, I mean, that, Chris, even understates it. The overwhelming -- the overwhelming preponderance of international, you know, scientific bodies have repeatedly reaffirmed that linkage."
応じたりするわけです。
プルイット氏が「人間の活動が気候変動の主要な要因であるかは議論がある」と述べているのに対して、コメンテーターは「人間の活動と気候変動に関連があることは疑いはない」と述べているわけですから、どちらも正しいことを言っている可能性はあるわけですが、キャスターやコメンテーターの発言には「プルイット氏は科学を否定している」と異端視する雰囲気が感じられます。
個人的には、気候変動と人間の活動に関連があることは分かります。
アンデスかどこかの山の上の氷河がどんどん溶けているとかいう話を聞くと「地球が温暖化しているんだな」というのは素直に納得できるますし、二酸化炭素とかに温室効果があることもそうなんだろうなと思いますし、化石燃料を使ったり、森林を伐採したりする人間の活動が地球の大気中に含まれる二酸化炭素の量を増やしているんだろうなというのも分かります。
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書には、こんな記述もあります。
"It is extremely likely that more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010 was caused by the anthropogenic increase in greenhouse gas concentrations and other anthropogenic forcings together."
この60年間の気温上昇の半分超は人間の活動がもたらしたものである可能性が極めて高いということだと思います。
半分超ですから、プルイット氏の"I would not agree that it's a primary contributor to the global warming that we see"という発言は、科学者の見解とは食い違っていることになります。
ただ、プルイット氏の気持ちも分かります。
「半分超」っていうことは、51%かもしれないし100%かもしれないわけで、どこに落ち着くかによってはかなり雰囲気が違います。
あと、昔はマンモスが住んでいたような氷河期があったっていうわけですから、地球上の気温はずっと昔から上昇を続けてきたんでしょう。おそらく人間の活動以外にも地球の気温を上昇させている要因があるはずです。そうした人間以外の要因と、人間という要因のどちらが大きな影響を及ぼしているかなんていうことは、なかなか分からないのではないかとも思うのです。そもそも何十年か前には、科学的な見地をもとに「地球が再び氷河期になる」なんていう騒ぎ方もされていたように思います。
それに本当のことを言うと、IPCCの報告書がなんぼのもんじゃという感覚もあります。だってそもそも「地球の平均気温」という概念がよく分からない。いつの、どこの気温だよ。あと、人間の活動が排出している温室効果ガスの量なんて、そんなに正確に測定できるものなのかよという気もします。いつだったか、中国の排出量に関する報告が大きく訂正されたっていう話もあったように思います。
ということで、何か分かるんじゃないかと思って、この本を読んでみた次第です。非常に面白かったです。
著者の中川教授は古気候学の専門家で、何万年も前から現在に至るまでの過去の地球の気候を研究している人です。
学会の定説とされるミランコビッチ理論によると、地球上の気候は10万年ごとに温暖化のピークがあります。この10万年のサイクルは楕円形である地球の公転軌道が揺らぐことで、地球と太陽の距離が変化することで起こるものです。温暖な時期と寒冷な時期の温度差は10度にも達します。地球の気温が10度変化するというのは、鹿児島が札幌になるぐらいの変化に相当するそうです。なるほど。そりゃ大変だ。
また地球の気候には2万3000年のサイクルもあって、この周期でやはり温暖な時期と寒冷な時期が繰り返されます。これは地球の地軸の傾きが揺らぐことで、地球にそそぐ太陽のエネルギーの分配のパターンが変わることで起こるもので、7度ぐらいの温度差が出るものだそうです。7度といえば東京が那覇になるぐらいのものです。おぉ、大変。
言葉で説明するとよく分りませんが、本のなかにはグラフが出てきます。それをみると地球の気温が2万3000年のサイクルで小さな波を描きながら、全体としては10万年サイクルの大きなトレンドも作っているということが分かります。
現在はこの10万年のサイクルのなかでは、温暖な時期のピークをすぎたあたりだそうです。現在は「例外的に」暖かい時期といえ、本来であれば、これから地球の気温が寒冷になっていく方向に向かうはずです。これは地球の公転とか地軸の傾きとか、宇宙レベルでの物理法則に従ったものですから、トレンドを変えることは難しい。だから昔は「地球が再び氷河期になる」なんていう騒がれ方をしたわけです。
で、この本はどうしてそんなことが分かるのかということと、今とは違う気候だった地球はどんなところだったのかということを分かりやすく説明した本です。率直に言えば「そんなの分かるわけないじゃん」と思ってしまうところですが、それが分かるんだそうです。
カギとなるのは、海や湖のなかに堆積していった「年縞」と呼ばれる地層の中に含まれるプランクトンの化石や化学組成を分析するという手法です。
なかでも中川教授がチームのリーダーとなって福井県の水月湖の湖底から採取した年縞は世界的な価値が認められています。普通なら、水の底に住んでいる生き物や川から流れ込んだ水が薄く積もった地層をかき乱したりして、数万年にもおよぶ地層を保つことはないわけですが、水月湖では1年間で0.7ミリメートルペースでたまっていく薄い地層が奇跡的に保存されているそうです。ここらあたりが、いかに奇跡であるかについても詳しい説明がされていますが、ここでは省略。中川教授は全体として73メートル分(15万年相当)の堆積物を回収し、そのうち45メートル分にはっきりとした年縞を確認することができました。
で、それをどう分析するのかということです。
まず、放射性炭素年代測定という手法があります。自然界に存在する炭素には質量数12、13、14の3種類があります。そして、このうち質量数14の炭素(C14)だけが放射能を持っていて、時間とともに徐々に別の物質に変わっていきます。なので何かに含まれている炭素のなかで、C14がC12やC13に比べてどれだけ減っているかを測定すれば、その何かの年代が推定できるんだそうです。年代不明の麺の化石に含まれた炭素を調べたところ、麺の材料となった植物が刈り取られたのは4000年前だということが分かったケースもあるんだとのこと。
ただ、この放射性炭素年代測定には誤差が大きいという問題点があります。それはスタートラインにおけるC14の比率が正確に分からないからです。
そこで年縞の出番になります。水月湖の年縞には葉っぱの化石が含まれています。しかも年に1層ずつ積もっていく年縞の数を数えれば、その葉っぱが今から何年前に湖底にたまったものかが分かります。さらに、その化石のC14の比率を調べれば、C14がどれだけ残っていれば何年前の炭素に相当するという「換算表」が作ることができるというわけです。水月湖の年縞をもとにした換算表は世界の標準として認められています。
また、水月湖の堆積物のなかには、花粉の化石が含まれています。1立方センチメートルあたり数十万粒の花粉の化石がみつかることもあるそうです。こうした花粉の化石を顕微鏡で調べれば、どういった種類の植物が生えていたかが分かる。例えば、スギの花粉がたくさんみつかったり、ブナの花粉がたくさん見つかったり、スギとブナが半分ずつだったり、そういったことですね。それは水月湖周辺の植生を繁栄しているわけです。
で、その植生を現在の世界の植生と比べます。例えば「今から3万~2万年前の年縞から見つかった花粉は針葉樹とシラカバが混じり合っているから、現在のシベリアのような風景だった」といった推定がなりたつわけです。おぉ。
さらにモダンアナログ法という手法もあって、「2万年前の水月湖の花粉の組成が旭川近くの湖底に現在たまりつつある花粉の組成と似ていた場合、2万年前の福井県南部の気候は現在の旭川に近かった」と判断することができる。で、現在の旭川の平均気温や日照量をひっぱってくれば、2万年前の福井県南部の気温や日照量が推定できるというわけです。おおぉ。
こうした花粉の化石の分析によって、水月湖周辺の気候には10万年のサイクルと、2万3000年のサイクルがあることが分かりました。地球の公転軌道や地軸の傾きをもとにしたミランコビッチ理論と同じ周期です。
具体的には、
・温暖な時期のピークは、12万~11万年前と1万年前にある
・2万年前は氷期のいちばん寒い時期だった
・氷期と温暖な時代の震幅は10度(札幌-鹿児島の差)
ということです。
グラフをみると、12万年ほど前に現在と同じぐらいの暖かい時期があったけど、その後、徐々に気温が下がっていって、2万年前に底を打っています。さらにその後、急激な気温上昇があって1万年前のピークをつけたというイメージです。
また、
・12万年ほど前のピークの後の「徐々に気温が下がって」の部分は、2万3000年のサイクルで気温の上下を繰り返しながら、徐々に気温が下がっている。
・温度の震幅は最大で7度(東京-那覇の差)
ということでもあります。
ただし、こうしたデータの分析結果には、人間の活動が影響しているという指摘もあります。それは「最近の数千年は夏の日射が極小近くまで低下してきているのに対し、温度は反対に上昇しているっように見える」からです。こうしたズレは過去15万年の間ではなかったそうです。つまり1万年ほど前のピークの後に起きるはずの気温の低下が起きていないということですね。
中川教授はこのズレの原因について「まだ議論が続いている」としています。
その一方で、1万年前にピークをつけた温暖な時期が例外的に長く続いているというのは多くの研究者が指摘してきたことで、「ひとつの有力な説が人間活動に原因を求めている」としています。南極の氷に含まれる空気に含まれる温室効果ガスの濃度の研究ではメタンが5000年前、二酸化炭素が8000年前からミランコビッチ理論を外れるペースで増加していることが分っています。この現象について、バージニア大学のウィリアム・ラジマン教授が「アジアにおける水田農耕の普及、およびヨーロッパ人による大規模な森林破壊が原因」と主張していることも紹介されています。
で、ここからがややこしくかつ、奥深いのですが、中川教授は
「ラジマン教授の主張は、人間が気候を左右するようになった歴史は、100年前でなく8000年前にさかのぼるということを意味していた。もし私たちが、温室効果ガスの放出によって『とっくに来ていた』はずの氷期を回避しているのだとしたら、温暖化をめぐる善悪の議論は根底から揺らいでしまう。私たちは自然にやってくる氷期の地球で暮らしたいのか、それとも人為的に暖かく保たれた気候の中で暮らしたいのか。これはもはや、哲学の問題であって科学の問題ではない」
と述べています。
どうして中川教授がこんなことを言い出すかというと、氷期というのは現在の人類にとっては非常に厳しい時代だったからです。
水月湖の年縞の研究からも、氷期における気温の変化は温暖な時期に比べて極めて激しく、予測不能なカオスな動きをみせていたことが分かっています。氷期には「ダンスガード=オシュガー(D-O)イベント」と呼ばれる、原因不明の急激な温暖化が起きていたようです。
気候変動が人類に与える影響は甚大です。
1993年の冷夏は2年前のピナツボ火山の噴火が原因とされ、全国平均のコメの作況を7割にまで落としています。天明の飢饉は、1783年に起きたアイスランドのラキ火山の噴火によって、冷夏が5年以上も続いたことが原因だとされています。このときはヨーロッパでも食料不足が起きて、フランス革命の遠因となったとの分析もあります。また1980年代のアフリカの干ばつは4年間も続いて300万人の命を奪っています。ベネズエラ沿岸のカリアコ海盆の年縞に基づいた研究によると、ユカタン半島では西暦810年ごろ、9年の間に6回もの干ばつがあり、マヤ文明衰退のきっかけを作ったともされているそうです。
中川教授は「ときどき暴れる気候に対しては、現代社会は思っている以上に脆弱な基盤の上に成り立っている。だが少なくとも先進国において、そのような議論を耳にする機会は、意外なほどに少ないように思う」としています。
さらに中川教授は、現在の人類の繁栄の基盤となった農耕の普及にも気候変動が影響していたのではないかと思いを巡らせます。
気候の変化が激しい氷期は一種類の作物を大量に育てる農耕はリスクが大きい。氷期の人類が農耕ではなくて狩猟採取を基盤においていたのは、何も当時の人類が農耕を思いつかなかったわけではなくて、自然のなかで育つ多様な植物や動物を生活の糧とすることで、どんな気候になっても確実に食べ物を確保できる生活のスタイルが最適だったからではないかというわけです。
で、農耕生活と狩猟採取生活という2つのスタイルについて、中川教授は、
「どちらを好ましいと考えるかは、ひょっとすると哲学の問題に帰着するのかもしれない。繁栄と発展をあくまで是とするならば、農耕は欠かせない前提条件である。先進国の科学者である筆者も、基本的にはこの考え方に慣れている。だが、どこか南国の浜辺で野生のフルーツを採ったり、魚を釣ったりして糧を得る暮らしが『気にならない』かと問われたとき、ならないと断言するのは必ずしも正直なことではない」
としています。
もちろん「単純な原始回帰願望はナイーブに過ぎる」とも断っていますけど、10万年単位の気候の歴史を科学的かつ真剣に分析すれば、なかなか深いところに思い至ったりするもんなんでしょう。
中川教授は、宇宙レベルの物理法則に基づいたミランコビッチ理論は崩しがたいものだとみているようです。その理論に基づけば、地球は今後10万年サイクルの寒冷化に向かうわけで、一般的に言われているような地球温暖化への不安については距離をとった記述が目立ちます。
「温暖化の主犯格とされる二酸化炭素にある種の敵意を感じる人の数は、商業的にも無視できない水準に達している」
「現在の温暖化予測も70年代の寒冷化予測と同様に信用できないと主張しているのではない。(ただし、信頼できると主張しているのでもない)」
「私見だが、もっとも恐ろしいのは、現代の『安定で暖かい時代』がいつかは終わるというシナリオではないかと思う」
といった感じです。
あと、とにかく、気候変動は何が起こるか分からない、という言及も多いです。
「気候システムは極めて複雑な系であり、その挙動を理解することはもちろん、正確に記述することすら容易ではない」
「あらゆる未来予測には適用限界がある。このことは、本書に通底する重要なテーマのひとつ」
「本当に劇的な変化の予測は原理的にきわめて困難」
で、そうしたなかでも「だが、もしそれが起こった場合に、人間にとってどの程度の影響があるのか知っておくことは重要である」と指摘しています。
また、われわれが経験的に身につけている「天気予報とのつきあい方」を、現在の「100年後に5度の気温上昇」といった予測にもあてはめるべきだとしています。つまり、普通の天気予報なら、明日の予報だと信用するけれど、1週間後になるとそれほど信用しないし、「来年は冷夏」とか言われれば聞き流す。こうした感覚を100年後の野心的な天気予報を聞くときにも大切にすべきだというわけですね。
ということで、気候変動問題における科学的な予測があることは分るんだけれど、EPAのプルイット長官の気持ちも分らなくもないというのは、地球レベルの気候変動問題を科学的かつ真剣に研究してきた中川教授の感覚の方向性と大きく違うわけではないような気がします。あんまり「俺はなんでも分っているんだ」みたいな顔をして、プルイット長官的な人たちをいじめるのもどうかなと。
ここは完全に私見ですが、気候変動問題っていうか、地球温暖化問題についての危機感の大きさは地域差や個人差があって当然だと思います。海面上昇にさらされている小さな島国に住んでいる人は心配で仕方ないでしょうけど、電力不足が一般的な途上国の人だったら、石炭でもなんでもいいからとにかく安く発電所を作ってくれと思うはずです。あと、石炭産業で働いている人は「俺たちにだって生活がある」って思うでしょう。だから温室効果ガス排出の抑制に消極的な立場をとっている人たちを馬鹿にするのはよくない気がします。
ただ、中川教授は過去の気候の専門家ではあるけれど、未来予測を専門としているわけではないと思います。IPCCの報告書のような将来予測については、スーパーコンピューターの上で地球の気候を丸ごと再現して変化を予測する「気候モデリング」の手法で行われているとの説明がありますが、その内容についての詳しい言及はありませんでした。このあたりについても分りやすく説明してくれる本があれば読んでみたいところです。
もしも本当に人類による温室効果ガス排出が10万年サイクルの気候変動のパターンも打ち破って、ガンガンに地球を温暖化させることが確実に分っているっていうんだったら、プルイット長官に石を投げたくなるかもしれません。
2017年3月2日木曜日
“Death by China: Confronting The Dragon--- A Global Call to Action”
“Death by China: Confronting The Dragon--- A Global Call to Action”を読んだ。トランプ大統領が新設したNational Trade CouncilのDirectorに任命されたPeter Navarroカリフォルニア大学アーバイン校教授が書いた本です。南カリフォルニア大学の非常勤教授だったGreg Autryとの共著です。2011年5月に出版されました。
トランプ大統領は2016年12月21日にナバロ氏をNTCのトップに任命すると発表したときの声明で、こんな風に述べています。
“I read one of Peter’s books on America’s trade problems years ago and was impressed by the clarity of his arguments and thoroughness of his research,"
"He has presciently documented the harms inflicted by globalism on American workers, and laid out a path forward to restore our middle class. He will fulfill an essential role in my administration as a trade advisor."
出版のタイミングからみて、トランプ大統領はこの本を読んで感銘を受けたのだと思います。
この本があることは数年前から知っていたのですが、タイトルが過激なものですから「ちょっとトンデモ系の本なのかな」と思って敬遠していました。でも、ちょっとトンデモな人が大統領になって、しかも著者が重用されているということなので、急いで読んでみた次第です。
いかに中国が悪い国かということを啓蒙するために書いた本のようです。”Death by China”というタイトルは誇張して付けたわけではないようで、実際に中国製品の欠陥でたくさんの人が死んでいるとか、中国国内の人権弾圧でたくさんの人が死んでいるとか、中国の環境汚染はたくさんの人を殺しているとか、そういった話がたくさん出てきます。天安門広場の事件もその一例です。さらに中国の軍事力拡大や宇宙開発の促進が米国にとっての安全保障上の脅威になっているという分析もされています。
で、そういった例のなかに、中国が為替操作や企業に対する補助金で輸出価格を不正に引き下げて、米国の製造業に大きな打撃を与えてきたという批判も含まれています。ナバロ氏は中国の経済政策には外国の製造業を破壊する狙いがあるとして、”Eight Weapons of Job Destruction”と名付けた8つの問題点を挙げています。
・違法な輸出補助金
・為替操作
・知的財産の盗用
・緩い環境規制
・緩い労働規制
・違法な関税、輸入割当などの障壁
・ダンピング
・外国企業の進出を拒む規制
こういった話は別にナバロ氏だけが指摘しているわけじゃなくて、オバマ政権下での対中国外交でも繰り返し問題にされてきました。中国の経済政策について詳しいわけじゃないですが、米国企業からそういった不満が出ていることは間違いないです。
ただ、オバマ政権下では「そういった問題はあるけれども、時間をかけて解決を探っていきましょう。気候変動問題とかでは協力できる余地はあるよね」という立場でしたが、ナバロ氏は「こうした問題は非常に大事なことだから、時間をかけて解決するなんていう生ぬるいことではないけない。即刻解決するべきだ」という立場をとっています。もう中国のことなんて、1ミリも信用していないという感じです。
ナバロ氏はこうした問題点がある中国に対して、米国が自由貿易の精神で関わることは大きな間違いだとしています。
“While free trade is great in theory, it rarely exists in the real world. Such conditions are no more found on Earth than the airless, frictionless realm assumed by high-school physics text. In the case of China v. the United States, this seductive free trade theory is very much like a marriage: It doesn’t work if one country cheats on the other.”
ということです。ナバロ氏の結婚生活も気になるところですが、「自由貿易なんてものは存在しないんだ」という主張は分かります。”The Undoing Project”でも経済学の前提自体が間違っているという話があっただけに、経済学の理論ばかりを重視するのもどうかなと思います。
また、ナバロ氏は製造業というのは国家にとって極めて重要だとして、4つの理由を挙げています。
・製造業はサービス業よりも雇用創出効果が大きい。建設とか金融とか小売りとか運輸とかにも影響が広がっていくから。
・製造業の賃金は平均よりも高い。特に女性やマイノリティへのチャンスとなる。
・製造業が強いと、技術革新も進む。長期的に強い経済を維持できるようになる。
・ボーイング、キャタピラー、GMなどの巨大な製造業企業に依存する中小企業がたくさんある。
こういった主張もよくあります。何もナバロ氏だけが極端な話をしているわけではありません。
あと、これまでに読んだ本のなかでも、米国の製造業で働く人たちが高い誇りを抱いているっていう話もよく出てきました。「製造業が衰退すれば、サービス業で働けばいいじゃないか」っていうのは理屈としてはそうかもしれませんが、製造業で働くのが性に合っている人もいます。「製造業は大事」というのはその通りだと思います。
つまり、製造業はものすごく大事なのに、米国の製造業が中国の不正によって衰退させられているから、これは何としてでも解決せねばならないということですね。うん。分かります。
ナバロ氏はこんなことも言っています。
“When America runs a chronic trade deficit with China, this shaves critical points off our economic growth rate. This slower growth rate, in turn, thereby reduces the number of jobs America creates.”
“If America wants to reduce its overall trade deficit to increase its growth rate and create more jobs, the best place to start is with currency reform with China!”
貿易赤字が成長率を引き下げる要因であることは分かります。これは統計上の定義の話です。ただ、成長率が低ければ雇用増のペースが鈍るとか、中国の為替操作をやめさせれば貿易赤字が減るといった理屈が正しいのかどうかは分かりません。それこそ経済学の理論ではそういうことになるのかもしれませんが、実際の世界ではそんなことにはならないなんていう反論もあるんじゃないでしょうか。
まぁ、とはいえ、トランプ大統領に重用されている人物がこう考えているということは間違いないです。
あと、中国政府が多くの米国債を保有するために、以下のような手法をとっているとも指摘しています。
・中国企業は米国への輸出で多くのドルを受け取っている
・中国政府は中国企業に、ドル建ての中国政府債の購入を強要して、ドルを蓄える
・中国政府がドル建ての米国債を購入する
で、中国が米国債をたくさん保有していることは、いざとなったら「米国債を売って、ドル相場を急落させたり、米国の金利を急上昇させてやるぞ」と脅迫できることを意味します。これも割とよく言われることです。また、中国政府が米国債を購入しなければ、米国にとって国債発行の負担が増すわけですから、そもそも米国の財政は中国に依存しているということにもなります。
ナバロ氏は中国が世界中の企業にとっての生産拠点になったきっかけを、1978年に中国共産党が”opened China’s Worker’s Paradise to the West”したことだとしています。中国が何をしたのかは詳しく書いていないですが、カーター政権下で米中共同宣言が出された年ですね。何かあったんだと思いますが、これをきっかけに、おもちゃとかスニーカーとか自転車とか、そういった業種が中国の安い労働力を目当てに製造拠点を移し始めたそうです。
で、2001年に中国がWTOに加盟すると、さらに製造業の移転が進みます。ナバロ氏はこのときは1978年以降とは違い、米国企業は安い労働力だけでなく、中国の補助金とか環境規制の緩さもメリットとして考えていたと主張します。労働力が安い国なら、バングラディシュやカンボジアやベトナムなんていう国もあったことを理由としてあげています。つまりナバロ氏にすれば、米国企業も最初から中国の不正をあてにしていたという意味で、中国と同罪だということです。
そして中国への製造業の移転は現在も続いています。WTO加盟時は生産拠点としての魅力でしたが、今は中国の市場としての魅力も加わっています。中国政府は、外国企業に”minority ownership”しか認めず、”technology transfer”を強要し、研究開発拠点を中国に移すことを強いています。
ナバロ氏はこういう中国の不正な経済活動に対してどんな対応をとればいいのかという提言もしています。
まず、出てくるのが、
“Congress and the President must tell China in no uncertain terms that the United States will no longer tolerate its anything-but-free trade assault on our manufacturing base”
そのうえで、”American Free and Fair Trade Act”を制定するよう求めています。この法律が定めるところは、
“Any nation wishing to trade freely in manufactured goods with the United States must abandon all illegal export subsidies, maintain a fairly valued currency, offer strict protections for intellectual property, uphold environmental and health and safety standards that meet international norms, provide for an unrestricted global market in energy and raw materials, and offer free and open access to its domestic markets, including media and Internet services”
ということだそうです。
ナバロ氏は中国を名指ししているわけじゃなから、直接的な対決は避けられるとしていますが、これまでのナバロ氏の主張からして、「中国とは自由貿易できません」と宣言するのと同じことだと思います。
あと、ナバロ氏は欧州、ブラジル、日本、インド、その他の中国の不正な経済政策の被害にあっている国々と共に、WTOに対して中国にルールを遵守させるよう訴えるともしています。
さらに為替操作については、中国がそう簡単に止めるわけもないと認めていて、水面下での米中交渉を進めるべきだとしています。で、この際に、中国に伝える内容は、
“The United States will have no other choice than to brand China a currency manipulator at the next biennial Treasury Review and impose appropriate countervailing duties unless China strengthens its currency to fair value on its own”
ということです。つまり中国に対して自ら人民元安を是正しないなら、対抗措置として関税をかけるぞと脅すということですね。
でも、中国が脅しに応じない可能性だってあるわけです。その場合は、
“Of course, if China fails to act in a timely manner, the Department of the Treasury must follow through on branding China a currency manipulator and impose appropriate defensive duties to bring the Chinese yuan to fair value”
だそうです。もう貿易戦争やむなしって感じですね。
こうしたナバロ氏の立場に対しては、「米国の製造業が安価な労働力を求めて海外に流出することは避けられないことだし、中国との貿易赤字を解消したって、どうせベトナムとかインドとかバングラみたいな国の製造業が儲かるだけでしょ」なんていう批判があります。まぁ、そうなんだろうな、とも思います。
しかしナバロ氏は反論します。
“We believe the American companies and workers can compete with any in the world on a level playing field, particularly manufacturing where automation and ingenuity often trump manual labor”
そして例え、中国に不正を改めさせることがベトナムとかインドとかバングラに潤いをもたらすだけだったとしても、それはそれで素晴らしいことじゃないかとも言っています。とにかく不正なことをしている中国が世界経済の真ん中に居座っていることは、極めて不健全で、危険なことだというわけです。
この本では中国のサイバー攻撃とか人権問題とか通商政策以外の点についても解決策を提言しています。それぞれ過激だったり、面白かったりしますが、割愛。
まとめますと、ナバロ氏は中国のことを全く信頼していません。後書きでは1989年の天安門事件以降の中国を、ナチ政権下のドイツやスターリン政権下のソ連と同じ扱いにしています。さらに中国による宇宙開発の章なんかでは、”There’s a Death Star Pointing at Chicago”なんていうタイトルもあったりして、中国は銀河帝国と同じぐらい悪いわけです。だから貿易戦争も辞さないというのも当然といえば当然の話です。ちょっと言い過ぎなんじゃないかという気もします。
ただ、「米国に製造業を取り戻す」というのはまともな主張だと思います。グローバリゼーションの進展していった時期と、先進国経済が元気がなくなっていった時期は重なっているわけで、何かしらの関係があるんじゃないかと主張する気持ちは分かります。そんななかでも米国経済は頑張ってきたわけですけど、ここにきてトランプ大統領という強烈なキャラクターが登場したことで、「中国みたいな国があることを考えれば、グローバリズムが常に正しいわけではない」という考え方が表に出てきたということになるんだと思います。
ただ、中国にとっては現在の状況は居心地のいいものであるわけで、中国は現状の変更は望んでいない。日米欧が結束して、中国をWTOから追い出すとか、逆にWTOから出て行って新しい通商圏を作ってしまうとか、そんな「貿易大戦争」っていうシナリオもあるのかもしれませんが、そうなっちゃうと、どうなっちゃうんだという感じもします。
トランプ大統領が「ソ連を崩壊させたレーガン」のイメージを追って、「中国共産党による経済支配を終わらせたトランプ」みたいな路線を目指したりして。実際にそうするかどうかは別にして、トランプ大統領の脳裏にそんなシナリオがないわけじゃないんだと思います。
トランプ大統領は2016年12月21日にナバロ氏をNTCのトップに任命すると発表したときの声明で、こんな風に述べています。
“I read one of Peter’s books on America’s trade problems years ago and was impressed by the clarity of his arguments and thoroughness of his research,"
"He has presciently documented the harms inflicted by globalism on American workers, and laid out a path forward to restore our middle class. He will fulfill an essential role in my administration as a trade advisor."
出版のタイミングからみて、トランプ大統領はこの本を読んで感銘を受けたのだと思います。
この本があることは数年前から知っていたのですが、タイトルが過激なものですから「ちょっとトンデモ系の本なのかな」と思って敬遠していました。でも、ちょっとトンデモな人が大統領になって、しかも著者が重用されているということなので、急いで読んでみた次第です。
いかに中国が悪い国かということを啓蒙するために書いた本のようです。”Death by China”というタイトルは誇張して付けたわけではないようで、実際に中国製品の欠陥でたくさんの人が死んでいるとか、中国国内の人権弾圧でたくさんの人が死んでいるとか、中国の環境汚染はたくさんの人を殺しているとか、そういった話がたくさん出てきます。天安門広場の事件もその一例です。さらに中国の軍事力拡大や宇宙開発の促進が米国にとっての安全保障上の脅威になっているという分析もされています。
で、そういった例のなかに、中国が為替操作や企業に対する補助金で輸出価格を不正に引き下げて、米国の製造業に大きな打撃を与えてきたという批判も含まれています。ナバロ氏は中国の経済政策には外国の製造業を破壊する狙いがあるとして、”Eight Weapons of Job Destruction”と名付けた8つの問題点を挙げています。
・違法な輸出補助金
・為替操作
・知的財産の盗用
・緩い環境規制
・緩い労働規制
・違法な関税、輸入割当などの障壁
・ダンピング
・外国企業の進出を拒む規制
こういった話は別にナバロ氏だけが指摘しているわけじゃなくて、オバマ政権下での対中国外交でも繰り返し問題にされてきました。中国の経済政策について詳しいわけじゃないですが、米国企業からそういった不満が出ていることは間違いないです。
ただ、オバマ政権下では「そういった問題はあるけれども、時間をかけて解決を探っていきましょう。気候変動問題とかでは協力できる余地はあるよね」という立場でしたが、ナバロ氏は「こうした問題は非常に大事なことだから、時間をかけて解決するなんていう生ぬるいことではないけない。即刻解決するべきだ」という立場をとっています。もう中国のことなんて、1ミリも信用していないという感じです。
ナバロ氏はこうした問題点がある中国に対して、米国が自由貿易の精神で関わることは大きな間違いだとしています。
“While free trade is great in theory, it rarely exists in the real world. Such conditions are no more found on Earth than the airless, frictionless realm assumed by high-school physics text. In the case of China v. the United States, this seductive free trade theory is very much like a marriage: It doesn’t work if one country cheats on the other.”
ということです。ナバロ氏の結婚生活も気になるところですが、「自由貿易なんてものは存在しないんだ」という主張は分かります。”The Undoing Project”でも経済学の前提自体が間違っているという話があっただけに、経済学の理論ばかりを重視するのもどうかなと思います。
また、ナバロ氏は製造業というのは国家にとって極めて重要だとして、4つの理由を挙げています。
・製造業はサービス業よりも雇用創出効果が大きい。建設とか金融とか小売りとか運輸とかにも影響が広がっていくから。
・製造業の賃金は平均よりも高い。特に女性やマイノリティへのチャンスとなる。
・製造業が強いと、技術革新も進む。長期的に強い経済を維持できるようになる。
・ボーイング、キャタピラー、GMなどの巨大な製造業企業に依存する中小企業がたくさんある。
こういった主張もよくあります。何もナバロ氏だけが極端な話をしているわけではありません。
あと、これまでに読んだ本のなかでも、米国の製造業で働く人たちが高い誇りを抱いているっていう話もよく出てきました。「製造業が衰退すれば、サービス業で働けばいいじゃないか」っていうのは理屈としてはそうかもしれませんが、製造業で働くのが性に合っている人もいます。「製造業は大事」というのはその通りだと思います。
つまり、製造業はものすごく大事なのに、米国の製造業が中国の不正によって衰退させられているから、これは何としてでも解決せねばならないということですね。うん。分かります。
ナバロ氏はこんなことも言っています。
“When America runs a chronic trade deficit with China, this shaves critical points off our economic growth rate. This slower growth rate, in turn, thereby reduces the number of jobs America creates.”
“If America wants to reduce its overall trade deficit to increase its growth rate and create more jobs, the best place to start is with currency reform with China!”
貿易赤字が成長率を引き下げる要因であることは分かります。これは統計上の定義の話です。ただ、成長率が低ければ雇用増のペースが鈍るとか、中国の為替操作をやめさせれば貿易赤字が減るといった理屈が正しいのかどうかは分かりません。それこそ経済学の理論ではそういうことになるのかもしれませんが、実際の世界ではそんなことにはならないなんていう反論もあるんじゃないでしょうか。
まぁ、とはいえ、トランプ大統領に重用されている人物がこう考えているということは間違いないです。
あと、中国政府が多くの米国債を保有するために、以下のような手法をとっているとも指摘しています。
・中国企業は米国への輸出で多くのドルを受け取っている
・中国政府は中国企業に、ドル建ての中国政府債の購入を強要して、ドルを蓄える
・中国政府がドル建ての米国債を購入する
で、中国が米国債をたくさん保有していることは、いざとなったら「米国債を売って、ドル相場を急落させたり、米国の金利を急上昇させてやるぞ」と脅迫できることを意味します。これも割とよく言われることです。また、中国政府が米国債を購入しなければ、米国にとって国債発行の負担が増すわけですから、そもそも米国の財政は中国に依存しているということにもなります。
ナバロ氏は中国が世界中の企業にとっての生産拠点になったきっかけを、1978年に中国共産党が”opened China’s Worker’s Paradise to the West”したことだとしています。中国が何をしたのかは詳しく書いていないですが、カーター政権下で米中共同宣言が出された年ですね。何かあったんだと思いますが、これをきっかけに、おもちゃとかスニーカーとか自転車とか、そういった業種が中国の安い労働力を目当てに製造拠点を移し始めたそうです。
で、2001年に中国がWTOに加盟すると、さらに製造業の移転が進みます。ナバロ氏はこのときは1978年以降とは違い、米国企業は安い労働力だけでなく、中国の補助金とか環境規制の緩さもメリットとして考えていたと主張します。労働力が安い国なら、バングラディシュやカンボジアやベトナムなんていう国もあったことを理由としてあげています。つまりナバロ氏にすれば、米国企業も最初から中国の不正をあてにしていたという意味で、中国と同罪だということです。
そして中国への製造業の移転は現在も続いています。WTO加盟時は生産拠点としての魅力でしたが、今は中国の市場としての魅力も加わっています。中国政府は、外国企業に”minority ownership”しか認めず、”technology transfer”を強要し、研究開発拠点を中国に移すことを強いています。
ナバロ氏はこういう中国の不正な経済活動に対してどんな対応をとればいいのかという提言もしています。
まず、出てくるのが、
“Congress and the President must tell China in no uncertain terms that the United States will no longer tolerate its anything-but-free trade assault on our manufacturing base”
そのうえで、”American Free and Fair Trade Act”を制定するよう求めています。この法律が定めるところは、
“Any nation wishing to trade freely in manufactured goods with the United States must abandon all illegal export subsidies, maintain a fairly valued currency, offer strict protections for intellectual property, uphold environmental and health and safety standards that meet international norms, provide for an unrestricted global market in energy and raw materials, and offer free and open access to its domestic markets, including media and Internet services”
ということだそうです。
ナバロ氏は中国を名指ししているわけじゃなから、直接的な対決は避けられるとしていますが、これまでのナバロ氏の主張からして、「中国とは自由貿易できません」と宣言するのと同じことだと思います。
あと、ナバロ氏は欧州、ブラジル、日本、インド、その他の中国の不正な経済政策の被害にあっている国々と共に、WTOに対して中国にルールを遵守させるよう訴えるともしています。
さらに為替操作については、中国がそう簡単に止めるわけもないと認めていて、水面下での米中交渉を進めるべきだとしています。で、この際に、中国に伝える内容は、
“The United States will have no other choice than to brand China a currency manipulator at the next biennial Treasury Review and impose appropriate countervailing duties unless China strengthens its currency to fair value on its own”
ということです。つまり中国に対して自ら人民元安を是正しないなら、対抗措置として関税をかけるぞと脅すということですね。
でも、中国が脅しに応じない可能性だってあるわけです。その場合は、
“Of course, if China fails to act in a timely manner, the Department of the Treasury must follow through on branding China a currency manipulator and impose appropriate defensive duties to bring the Chinese yuan to fair value”
だそうです。もう貿易戦争やむなしって感じですね。
こうしたナバロ氏の立場に対しては、「米国の製造業が安価な労働力を求めて海外に流出することは避けられないことだし、中国との貿易赤字を解消したって、どうせベトナムとかインドとかバングラみたいな国の製造業が儲かるだけでしょ」なんていう批判があります。まぁ、そうなんだろうな、とも思います。
しかしナバロ氏は反論します。
“We believe the American companies and workers can compete with any in the world on a level playing field, particularly manufacturing where automation and ingenuity often trump manual labor”
そして例え、中国に不正を改めさせることがベトナムとかインドとかバングラに潤いをもたらすだけだったとしても、それはそれで素晴らしいことじゃないかとも言っています。とにかく不正なことをしている中国が世界経済の真ん中に居座っていることは、極めて不健全で、危険なことだというわけです。
この本では中国のサイバー攻撃とか人権問題とか通商政策以外の点についても解決策を提言しています。それぞれ過激だったり、面白かったりしますが、割愛。
まとめますと、ナバロ氏は中国のことを全く信頼していません。後書きでは1989年の天安門事件以降の中国を、ナチ政権下のドイツやスターリン政権下のソ連と同じ扱いにしています。さらに中国による宇宙開発の章なんかでは、”There’s a Death Star Pointing at Chicago”なんていうタイトルもあったりして、中国は銀河帝国と同じぐらい悪いわけです。だから貿易戦争も辞さないというのも当然といえば当然の話です。ちょっと言い過ぎなんじゃないかという気もします。
ただ、「米国に製造業を取り戻す」というのはまともな主張だと思います。グローバリゼーションの進展していった時期と、先進国経済が元気がなくなっていった時期は重なっているわけで、何かしらの関係があるんじゃないかと主張する気持ちは分かります。そんななかでも米国経済は頑張ってきたわけですけど、ここにきてトランプ大統領という強烈なキャラクターが登場したことで、「中国みたいな国があることを考えれば、グローバリズムが常に正しいわけではない」という考え方が表に出てきたということになるんだと思います。
ただ、中国にとっては現在の状況は居心地のいいものであるわけで、中国は現状の変更は望んでいない。日米欧が結束して、中国をWTOから追い出すとか、逆にWTOから出て行って新しい通商圏を作ってしまうとか、そんな「貿易大戦争」っていうシナリオもあるのかもしれませんが、そうなっちゃうと、どうなっちゃうんだという感じもします。
トランプ大統領が「ソ連を崩壊させたレーガン」のイメージを追って、「中国共産党による経済支配を終わらせたトランプ」みたいな路線を目指したりして。実際にそうするかどうかは別にして、トランプ大統領の脳裏にそんなシナリオがないわけじゃないんだと思います。
2017年2月25日土曜日
眼鏡をクイっとする
眼鏡のブリッジのところをクイっと押し上げるのには理由がある。
高校時代から眼鏡をかけていている。もう30年近いキャリアだ。これまでに眼鏡をクイっと押し上げてきた回数は、文字通り数えられないぐらいということだろう。眼鏡はかけているうちに、すこしずつ下にズレ落ちていく。その程度があまりに大きくなると、なんか鼻のあたりが気持ち悪いので、クイっと押し上げるのだ。
あと、眼鏡が少しだけズレ落ちた状態からでも、クイっと押し上げることがある。少しズレ落ちただけでも目とレンズの距離が変わってくるので、ピントがしっかりと合わなくなることがあるからだ。特に遠くの物を見ようとして「なんかよく見えないなぁ」と思ったときは眼鏡をクイっと押し上げると、きちんとピントが合って見やすくなったりする。
最近、気づいたのだが、道を歩いていて反対方向から美人らしき人が歩いてきたとき、眼鏡をクイっとすることが多い。
女性の皆さんは、遠くから歩いてきた男性が眼鏡をクイっとしたら、にっこりと微笑みかけてあげて欲しいと思う。
高校時代から眼鏡をかけていている。もう30年近いキャリアだ。これまでに眼鏡をクイっと押し上げてきた回数は、文字通り数えられないぐらいということだろう。眼鏡はかけているうちに、すこしずつ下にズレ落ちていく。その程度があまりに大きくなると、なんか鼻のあたりが気持ち悪いので、クイっと押し上げるのだ。
あと、眼鏡が少しだけズレ落ちた状態からでも、クイっと押し上げることがある。少しズレ落ちただけでも目とレンズの距離が変わってくるので、ピントがしっかりと合わなくなることがあるからだ。特に遠くの物を見ようとして「なんかよく見えないなぁ」と思ったときは眼鏡をクイっと押し上げると、きちんとピントが合って見やすくなったりする。
最近、気づいたのだが、道を歩いていて反対方向から美人らしき人が歩いてきたとき、眼鏡をクイっとすることが多い。
女性の皆さんは、遠くから歩いてきた男性が眼鏡をクイっとしたら、にっこりと微笑みかけてあげて欲しいと思う。
2017年2月18日土曜日
タバコデビュー
そろそろタバコデビューしてもいいんじゃないか。
なんだかんだで44歳になった。長男は来春から中学2年生で、次男も小学2年生になる。長男はもちろん、次男も週末に「とぉちゃん遊ぼ」と言うことも少なくなった。これからは週末に自由な時間を使えるようになったのだ。ただ44歳ともなると、老後の心配もせねばならない。すでに平均寿命の半分ぐらいだと思う。あんまり長生きしすぎると、貯金が尽きてしまうのではないかなんてことを考えたりもする。
そこで考えたのだが、今からタバコを吸い始めるというのはどうだろうか。ちょっと調べたところによると、1日に吸うタバコの本数×年数で得られる数字が600を超えると飛躍的に肺がんになる可能性が高まるらしい。つまりこれから1日15本ペースで吸い始めれば、40年で肺がんになる。84歳。ちょうどいいんじゃないか。
44歳でタバコデビューした新人だということを隠しておけば、以前流行ったチョイ悪な雰囲気にもなるのではないか。もう近所の公園で子供と遊ぶこともないのだから、渋いチョイ悪を目指したっておかしくない。それにきっと、タバコは美味しいものなのだろう。これだけ健康に良くないと言われていても、未だに結構な数の人が吸い続けていることが証拠だ。
ただし問題がないわけではない。1日にタバコを15本も吸うだけの体力がない気がするのだ。2、3本吸ったら、「もうダメ。気分悪い」ってことになりやしないか。
心配しなくても、そのうち死んじゃうじゃないかと思う。
なんだかんだで44歳になった。長男は来春から中学2年生で、次男も小学2年生になる。長男はもちろん、次男も週末に「とぉちゃん遊ぼ」と言うことも少なくなった。これからは週末に自由な時間を使えるようになったのだ。ただ44歳ともなると、老後の心配もせねばならない。すでに平均寿命の半分ぐらいだと思う。あんまり長生きしすぎると、貯金が尽きてしまうのではないかなんてことを考えたりもする。
そこで考えたのだが、今からタバコを吸い始めるというのはどうだろうか。ちょっと調べたところによると、1日に吸うタバコの本数×年数で得られる数字が600を超えると飛躍的に肺がんになる可能性が高まるらしい。つまりこれから1日15本ペースで吸い始めれば、40年で肺がんになる。84歳。ちょうどいいんじゃないか。
44歳でタバコデビューした新人だということを隠しておけば、以前流行ったチョイ悪な雰囲気にもなるのではないか。もう近所の公園で子供と遊ぶこともないのだから、渋いチョイ悪を目指したっておかしくない。それにきっと、タバコは美味しいものなのだろう。これだけ健康に良くないと言われていても、未だに結構な数の人が吸い続けていることが証拠だ。
ただし問題がないわけではない。1日にタバコを15本も吸うだけの体力がない気がするのだ。2、3本吸ったら、「もうダメ。気分悪い」ってことになりやしないか。
心配しなくても、そのうち死んじゃうじゃないかと思う。
2017年2月8日水曜日
"The Undoing Project: A Friendship that Changed Our Mind"
"The Undoing Project: A Friendship that Changed Our Mind"という本を読んだ。今日、読み終わりました。
「マネー・ボール」で有名なマイケル・ルイスが2016年12月6日に出した本です。
マネー・ボールはメジャーリーグのオークランド・アスレチックスがこれまで注目されてこなかった、プレイヤーに関する統計上の数値を重視して、独自のチームを作り上げて強豪チームを育て上げるという話です。随分と前に日本語で読んだことがあります。とても面白い本でした。
マイケル・ルイスはその後もたくさんの本を出しているのですが、いずれも未読でした。でも、また新しいしい本を出したということで、買ってみた次第です。
マネー・ボールみたいな話を期待して読むとハズレの本だと思います。ただ、これはこれで面白いです。
この本も第1章こそは、NBAのヒューストン・ロケッツのGMになったDaryl Moreyがマネー・ボール的なチーム作りを目指すところから始まります。実際、いろんなデータを駆使して、そこそこの強豪チームを作り上げるわけですが、この本はそこで終わるわけではなくて、「それでもやっぱり、完璧なチーム作りは難しい」という結論に落ち着きます。というのも人間の心理というものは、「理論的に正しい選択肢が分かっているときでも、間違った判断をしてしまうような仕組みになっているから」だということです。
ニューヨーク・ニックスで2012年にブレークした、ジェレミー・リンがそうした例の一人です。リンはほとんどのNBAプレイヤーよりも素早くプレーできる選手でしたが、長らくスカウトやコーチたちの目にとまることはありませんでした。選手の素質を見極めるプロである彼らがリンのスピードに気づかないわけがないのですが、それでもやっぱり「リンを使ってみよう」という判断が出なかったのです。それは中国系アメリカ人であるリンの姿が、彼らの頭にある「良いプレイヤー」のイメージからかけ離れていたから。目の前に素晴らしいスピードの選手がいるのに、それを見落としてしまっていたというわけです。
で、こうした話が第2章以降も続くのかなと思ったら、いきなり話はイスラエルの心理学者、ダニー・カーネマン(Danny Kahneman)の話になります。で、第3章は同じくイスラエルの心理学者、エイモス・トベルスキー(Amos Tversky)の話になります。なぜかというと、この2人が「分かっていても間違えてしまう人間の心理」について研究した第一人者だからです。まぁ、言ってみれば、錯視の問題みたいなもんです。同じ長さの線でも、<ーーー>となっているのと、>ーーー<となっているのでは長さが違って見えます。「同じ長さだ」と分かっていても、やっぱり違う長さにみえる。こういった問題は、視覚以外の分野でも起きているんじゃないかということです。
ダニーとエイモスはいろんな実験をします。例えば、高校生を2つのグループに分けて、
グループAには、8×7×6×5×4×3×2×1=? という問題、
グループBには、1×2×3×4×5×6×7×8=? という問題を出して、
5秒以内に答えを出すようにお願いします。5秒ですから、カンで答えるしかありません。
するとグループAの答えの平均は2250で、グループBの答えの平均は512でした。冷静に考えれば2つは全く同じ問題ですから、カンで出した答えの平均は同じになってもよさそうなものです。でも前者の方が圧倒的に大きな数字になってしまうのです。(本当の答えは40320ですが)
これはグループAの問題は最初に大きい数字が出てくるために高校生たちが「大きな数字」のイメージに引っ張られてしまい、グループBではそれとは逆の効果が出たということです。
また、別の実験では、
あるグループに「100人の人がいて、このうち70人がエンジニアで、30人が弁護士です。ここから1人を選んだとき、その人が弁護士である確率は何%でしょう」と尋ねると、尋ねられた方は「30%」と正しい答えを出します。
しかし同じ状況を提示したあとで、「選ばれた1人はディックという30歳の男性です。ディックは結婚はしていますが、子供はいません。能力が高くて意欲も高いです。きっと仕事で成功するだろうと期待されて、みんなから好かれています。さて、ディックが弁護士である確率は何%でしょう」と尋ねると、回答者の反応にばらつきが出ます。ディックに関する説明の部分には、彼が弁護士かエンジニアかを示す情報は一切含まれていないにも関わらずです。
つまり、人間は全く関係のない情報が加わることで、当たり前の確率の計算ができなくなってしまうということです。
こうした研究は、こんな奇妙な質問を投げかける実験にもつながります。
選択肢A:50%の確率で1000ドルがあたるくじ引き
選択肢B:確実に500ドルがもらえる
あなたはどちらを選びますか?
この場合、多くの人が選択肢Bを選ぶそうです。どちらの選択肢でも期待値は同じなわけですが、人間の心理には不確実な大きな喜びよりも、確実な中程度の喜びを選ぶ傾向があるということです。つまり、失敗するリスクを避けるわけです。
では、次の場合はどうか。
選択肢A:50%の確率で1000ドルを失うくじ引き
選択肢B:確実に500ドルを失う
あなたはどちらを選びますか?
この場合、多くの人が選択肢Aを選びました。どちらの選択肢でも期待値は同じなわけですが、この場合、人々は「リスクテイカー」となるわけです。
こうした人間の心理の不合理性を示す出来事は「面白いなぁ」だけの話じゃなくて、現実の世界にも大きな変化をもたらしています。例えば、
病気の患者に手術のリスクを説明するとき「90%の確率で生存できます」と説明すると、82%の患者が手術を受けることを決断するが、「10%の確率で死にます」と説明すると、54%の患者しか手術を決断しないそうです。同じデータを説明しているのに、患者の反応は全然違うということです。
あと、結腸ガンの検診の際、肛門から内視鏡を入れて腸内を診察するわけですが、これがなかなか不愉快なもので、一度検査を受けた患者が次の検査を受けたがらないという問題があるそうです。で、ある病院で実験が行われます。一つのグループには一定時間の診察が終わったら、すぐに内視鏡を引き抜く。もう一方のグループには、同じ時間の診察が終わった後、内視鏡を直腸のあたりまで引き抜いたところで3分間ストップさせます。この3分間は、検診をしている間よりは不快感が少ないけれど、やっぱり不快であることには変わりがないということです。で、術後に患者に尋ねたところ、次回の検査を受けてもよいとの回答は2番目のグループの方が多かった。2番目のグループは、トータルでの検査時間は1番目のグループよりも3分間長いのですが、それでも「最後の3分間の不快感が1番目のグループよりも少なかった」ので、次回の検査への抵抗感が薄れたのだということです。"Last impressions can be lasting impression"なんだそうです。
とまぁ、こんな風なわけで、2人が切り開いた新しい心理学の分野は、心理学以外の分野にも影響を与えていったわけです。
ところが、そのうち、2人の間に亀裂が入ります。2人の共同研究は高く評価されたのですが、どういうわけかエイモスの方の名声ばかりが高まっていったからです。
エイモスという人は、話をした人なら誰でもすぐに「この人、めちゃくちゃ頭いいなぁ」と気づかせてしまうような天才肌で、数学や統計についても詳しかった。自分の専門外の分野の学者と話をしていても、30分もすれば相手の学者のほうがびっくりしてしまうような深い洞察を披露したり、的確な疑問点を提示してみせたりできた人だったそうです。そんなエイモスにとって、ダニーはかけがえのない、一緒にいて最も心が安らぐ友人でした。2人の研究室には2人以外の誰も入れず、周囲の人間たちは外で2人の笑い声を聞くしかなかったそうです。
しかしダニーの方は、エイモスのそばにいると、自分がエイモスの陰に隠されてしまったような気分になるのです。そんなわけで、ダニーは次第にエイモスとの共同研究を敬遠するようになります。
そうしたなかダニーは独自の発想で、さまざまな人間の心理が引き起こす不合理な行動とその法則を見つけ出していきます。そのなかのひとつが、"rules of undoing"というものです。
例えば、
AさんとBさんは同じ時間に出発する2つの飛行機に乗る予定でした。2人は同じリムジンに乗って空港に向かいましたが、渋滞につかまってしまって、結局、飛行機の出発時間よりも30分遅れて空港に到着しました。
Aさんは空港でこう言われました。「あなたの飛行機は定刻通りに出発しました。あなたは30分、間に合いませんでした」
Bさんは空港でこう言われました。「あなたの飛行機は遅延が出たんです。でも5分前に出発しちゃいました」
こういう状況の下では、Bさんの方がAさんよりも不満に思う度合いが大きい。AさんとBさんは同じ行動をとって、どちらも飛行機に乗り遅れたにも関わらずです。
ダニーは、こうした不満の大きさは、「実現しなかった現実の望ましさ」と「実現しなかった現実の可能性」の関数として定義できると考えました。さっきの飛行機のケースでは、「実現しなかった現実の可能性」をみてみると、Bさんの方がAさんよりも大きかった。あと5分だけでも渋滞を早く抜けられていたら、Bさんは飛行機に乗れていた可能性があったからです。
さらにダニーは、「後悔」と「不満」と「嫉妬」についての違いも定義します。
「後悔」は実現しなかった現実への道筋が「ありえる場合」、「自分が別の行動をとればよかった」と思う感情。
「不満」は実現しなかった現実への道筋が「ありえる場合」、「周りの環境が異なっていれば良かったのに」と思う感情。
「嫉妬」は実現しなかった現実への道筋が「ありえなくても」、実現しなかった現実のイメージがありありと描ける状況で起きる感情。
という具合です。
そして、
「人は元に戻さねばならない現実が多ければ多いほど、現実を元の戻そうとは思わなくなる。地震で知人を失った人は、落雷で知人を失った人よりも、あの人が生きていれば良かったのにと思う度合いは少ない。地震がもたらす被害は広範囲なので、『もしも地震がなければ』と思うことが難しくなる」
「出来事が起きてから時間がたてばたつほど、別の現実もあったのではないかと思う度合いは小さくなる」
といったルールを導き出します。
さらに「日常から非日常への心理的な距離は、非日常から日常への心理的な距離よりも遠い」というルールも発見します。
例えば、
ある銀行員がある日、いつもと「同じ」道を通って通勤したら、赤信号を無視して突っ込んできたドラッグ中毒の若者が運転する車にはねられて死んだ場合と、
ある銀行員がある日、いつもと「違う」道を通って通勤したら、赤信号を無視して突っ込んできたドラッグ中毒の若者が運転する車にはねられて死んだ場合では、
前者の方では「いつもと違う道を通っていれば良かったのに!」とは思いにくい。いつもと同じ状況から、いつもと違う状況に発想を移すことは難しい。
後者の方では「いつもと同じ道を通っていれば良かったのに!」と思いやすい。いつもと違う状況から、いつもと同じ状況に発想を移すことは簡単。
ということです。
ダニーはこうした独自の発想についてエイモスとの共同研究は避けていましたが、アイデアについてはダニーに話していました。そしてあるとき、エイモスと一緒に出席した発表会の場で、ダニーはこうしたルールについて講演して、聴衆から大いに関心を集めました。すると、ある参加者がダニーとエイモスに向かって、「こんな発想は、お二人のどちらから生まれるんですか?」と尋ねました。ダニーとエイモスは2人の間の亀裂については公にしていなかったので、この参加者は2人の共同研究の成果なのだと思い込んだわけです。
するとエイモスが答えました。「私とダニーは、そういったことについては話さないことにしているのです」
この一言がダニーにとってはエイモスと決別する決定的なきっかけになったそうです。この発表内容はダニーのものです。そしてエイモスは、この参加者から、ダニーを称える発言をするチャンスを与えられたようなものです。ところがエイモスはこのチャンスを無視した。それがダニーには許せなかった。そしてダニーは別の研究者との共同研究として、論文"The Undoing Project"を発表します。
とまぁ、だいたいこんなことが書かれている本です。この他にも様々な研究結果に関する実例が出てきて面白いです。
2人の研究に関しては、経済学者から強い反発を受けたことにもページが割かれています。ダニーとエイモスに言わせれば、「人間の心理は合理的ではない誤った選択肢をとらせる。しかもその誤り方には法則性がある」というわけです。となると、「人間はシステマチックに間違う。だから市場だってシステマチックに間違っている」という結論になります。経済学は「人間は合理的に行動する」ということを前提にして発展してきたわけですから、そりゃ経済学者にすれば面白くない話です。
しかし2人の研究を受け入れるべきだと考える経済学者も出てきて、「行動経済学」という分野を開拓していきます。2人の研究成果のうち"Prospect Theory"は、今では経済学の分野で2番目に引用されることが多い論文だそうです。
こうした経済学への貢献が評価されて、ダニーは2002年にノーベル経済学賞を受賞します。しかし共同研究者だったエイモスは受賞できませんでした。1996年にガンのために亡くなっていたからです。エイモスは亡くなる前、毎日のようにダニーと話していたそうです。
多分、心理学のパートの部分だけの話を知りたいのなら、ダニー・カーネマン自身の著作を読んだ方がいいのかもしれません。それはそれで面白いことは間違いなさそうです。そこにダニーとエイモスの人間ドラマを付け加えたところが、この本のキモなのだと思います。ただ、時系列が結構ぐちゃぐちゃなので、ドラマを追いにくいところがあります。時系列でたどっていくと、いろいろと筋書き的に矛盾が生じるのかなと推察します。
このほか、2人の研究とイスラエル軍の関わりとか、イスラエルにおける中東での立場とか国民が共有している危機感の話とかがあって、これはこれで興味深いです。イスラエルの歴史っていうのも勉強してみたいですね。
この本は大統領選後に出版された本です。だから人間が非合理的な判断をシステマチックにしてしまうということと、ドナルド・トランプが当選したことを重ね合わせて読んでしまうところもあります。行動政治学なんていう分野があったりするんでしょうか?
「マネー・ボール」で有名なマイケル・ルイスが2016年12月6日に出した本です。
マネー・ボールはメジャーリーグのオークランド・アスレチックスがこれまで注目されてこなかった、プレイヤーに関する統計上の数値を重視して、独自のチームを作り上げて強豪チームを育て上げるという話です。随分と前に日本語で読んだことがあります。とても面白い本でした。
マイケル・ルイスはその後もたくさんの本を出しているのですが、いずれも未読でした。でも、また新しいしい本を出したということで、買ってみた次第です。
マネー・ボールみたいな話を期待して読むとハズレの本だと思います。ただ、これはこれで面白いです。
この本も第1章こそは、NBAのヒューストン・ロケッツのGMになったDaryl Moreyがマネー・ボール的なチーム作りを目指すところから始まります。実際、いろんなデータを駆使して、そこそこの強豪チームを作り上げるわけですが、この本はそこで終わるわけではなくて、「それでもやっぱり、完璧なチーム作りは難しい」という結論に落ち着きます。というのも人間の心理というものは、「理論的に正しい選択肢が分かっているときでも、間違った判断をしてしまうような仕組みになっているから」だということです。
ニューヨーク・ニックスで2012年にブレークした、ジェレミー・リンがそうした例の一人です。リンはほとんどのNBAプレイヤーよりも素早くプレーできる選手でしたが、長らくスカウトやコーチたちの目にとまることはありませんでした。選手の素質を見極めるプロである彼らがリンのスピードに気づかないわけがないのですが、それでもやっぱり「リンを使ってみよう」という判断が出なかったのです。それは中国系アメリカ人であるリンの姿が、彼らの頭にある「良いプレイヤー」のイメージからかけ離れていたから。目の前に素晴らしいスピードの選手がいるのに、それを見落としてしまっていたというわけです。
で、こうした話が第2章以降も続くのかなと思ったら、いきなり話はイスラエルの心理学者、ダニー・カーネマン(Danny Kahneman)の話になります。で、第3章は同じくイスラエルの心理学者、エイモス・トベルスキー(Amos Tversky)の話になります。なぜかというと、この2人が「分かっていても間違えてしまう人間の心理」について研究した第一人者だからです。まぁ、言ってみれば、錯視の問題みたいなもんです。同じ長さの線でも、<ーーー>となっているのと、>ーーー<となっているのでは長さが違って見えます。「同じ長さだ」と分かっていても、やっぱり違う長さにみえる。こういった問題は、視覚以外の分野でも起きているんじゃないかということです。
ダニーとエイモスはいろんな実験をします。例えば、高校生を2つのグループに分けて、
グループAには、8×7×6×5×4×3×2×1=? という問題、
グループBには、1×2×3×4×5×6×7×8=? という問題を出して、
5秒以内に答えを出すようにお願いします。5秒ですから、カンで答えるしかありません。
するとグループAの答えの平均は2250で、グループBの答えの平均は512でした。冷静に考えれば2つは全く同じ問題ですから、カンで出した答えの平均は同じになってもよさそうなものです。でも前者の方が圧倒的に大きな数字になってしまうのです。(本当の答えは40320ですが)
これはグループAの問題は最初に大きい数字が出てくるために高校生たちが「大きな数字」のイメージに引っ張られてしまい、グループBではそれとは逆の効果が出たということです。
また、別の実験では、
あるグループに「100人の人がいて、このうち70人がエンジニアで、30人が弁護士です。ここから1人を選んだとき、その人が弁護士である確率は何%でしょう」と尋ねると、尋ねられた方は「30%」と正しい答えを出します。
しかし同じ状況を提示したあとで、「選ばれた1人はディックという30歳の男性です。ディックは結婚はしていますが、子供はいません。能力が高くて意欲も高いです。きっと仕事で成功するだろうと期待されて、みんなから好かれています。さて、ディックが弁護士である確率は何%でしょう」と尋ねると、回答者の反応にばらつきが出ます。ディックに関する説明の部分には、彼が弁護士かエンジニアかを示す情報は一切含まれていないにも関わらずです。
つまり、人間は全く関係のない情報が加わることで、当たり前の確率の計算ができなくなってしまうということです。
こうした研究は、こんな奇妙な質問を投げかける実験にもつながります。
選択肢A:50%の確率で1000ドルがあたるくじ引き
選択肢B:確実に500ドルがもらえる
あなたはどちらを選びますか?
この場合、多くの人が選択肢Bを選ぶそうです。どちらの選択肢でも期待値は同じなわけですが、人間の心理には不確実な大きな喜びよりも、確実な中程度の喜びを選ぶ傾向があるということです。つまり、失敗するリスクを避けるわけです。
では、次の場合はどうか。
選択肢A:50%の確率で1000ドルを失うくじ引き
選択肢B:確実に500ドルを失う
あなたはどちらを選びますか?
この場合、多くの人が選択肢Aを選びました。どちらの選択肢でも期待値は同じなわけですが、この場合、人々は「リスクテイカー」となるわけです。
こうした人間の心理の不合理性を示す出来事は「面白いなぁ」だけの話じゃなくて、現実の世界にも大きな変化をもたらしています。例えば、
病気の患者に手術のリスクを説明するとき「90%の確率で生存できます」と説明すると、82%の患者が手術を受けることを決断するが、「10%の確率で死にます」と説明すると、54%の患者しか手術を決断しないそうです。同じデータを説明しているのに、患者の反応は全然違うということです。
あと、結腸ガンの検診の際、肛門から内視鏡を入れて腸内を診察するわけですが、これがなかなか不愉快なもので、一度検査を受けた患者が次の検査を受けたがらないという問題があるそうです。で、ある病院で実験が行われます。一つのグループには一定時間の診察が終わったら、すぐに内視鏡を引き抜く。もう一方のグループには、同じ時間の診察が終わった後、内視鏡を直腸のあたりまで引き抜いたところで3分間ストップさせます。この3分間は、検診をしている間よりは不快感が少ないけれど、やっぱり不快であることには変わりがないということです。で、術後に患者に尋ねたところ、次回の検査を受けてもよいとの回答は2番目のグループの方が多かった。2番目のグループは、トータルでの検査時間は1番目のグループよりも3分間長いのですが、それでも「最後の3分間の不快感が1番目のグループよりも少なかった」ので、次回の検査への抵抗感が薄れたのだということです。"Last impressions can be lasting impression"なんだそうです。
とまぁ、こんな風なわけで、2人が切り開いた新しい心理学の分野は、心理学以外の分野にも影響を与えていったわけです。
ところが、そのうち、2人の間に亀裂が入ります。2人の共同研究は高く評価されたのですが、どういうわけかエイモスの方の名声ばかりが高まっていったからです。
エイモスという人は、話をした人なら誰でもすぐに「この人、めちゃくちゃ頭いいなぁ」と気づかせてしまうような天才肌で、数学や統計についても詳しかった。自分の専門外の分野の学者と話をしていても、30分もすれば相手の学者のほうがびっくりしてしまうような深い洞察を披露したり、的確な疑問点を提示してみせたりできた人だったそうです。そんなエイモスにとって、ダニーはかけがえのない、一緒にいて最も心が安らぐ友人でした。2人の研究室には2人以外の誰も入れず、周囲の人間たちは外で2人の笑い声を聞くしかなかったそうです。
しかしダニーの方は、エイモスのそばにいると、自分がエイモスの陰に隠されてしまったような気分になるのです。そんなわけで、ダニーは次第にエイモスとの共同研究を敬遠するようになります。
そうしたなかダニーは独自の発想で、さまざまな人間の心理が引き起こす不合理な行動とその法則を見つけ出していきます。そのなかのひとつが、"rules of undoing"というものです。
例えば、
AさんとBさんは同じ時間に出発する2つの飛行機に乗る予定でした。2人は同じリムジンに乗って空港に向かいましたが、渋滞につかまってしまって、結局、飛行機の出発時間よりも30分遅れて空港に到着しました。
Aさんは空港でこう言われました。「あなたの飛行機は定刻通りに出発しました。あなたは30分、間に合いませんでした」
Bさんは空港でこう言われました。「あなたの飛行機は遅延が出たんです。でも5分前に出発しちゃいました」
こういう状況の下では、Bさんの方がAさんよりも不満に思う度合いが大きい。AさんとBさんは同じ行動をとって、どちらも飛行機に乗り遅れたにも関わらずです。
ダニーは、こうした不満の大きさは、「実現しなかった現実の望ましさ」と「実現しなかった現実の可能性」の関数として定義できると考えました。さっきの飛行機のケースでは、「実現しなかった現実の可能性」をみてみると、Bさんの方がAさんよりも大きかった。あと5分だけでも渋滞を早く抜けられていたら、Bさんは飛行機に乗れていた可能性があったからです。
さらにダニーは、「後悔」と「不満」と「嫉妬」についての違いも定義します。
「後悔」は実現しなかった現実への道筋が「ありえる場合」、「自分が別の行動をとればよかった」と思う感情。
「不満」は実現しなかった現実への道筋が「ありえる場合」、「周りの環境が異なっていれば良かったのに」と思う感情。
「嫉妬」は実現しなかった現実への道筋が「ありえなくても」、実現しなかった現実のイメージがありありと描ける状況で起きる感情。
という具合です。
そして、
「人は元に戻さねばならない現実が多ければ多いほど、現実を元の戻そうとは思わなくなる。地震で知人を失った人は、落雷で知人を失った人よりも、あの人が生きていれば良かったのにと思う度合いは少ない。地震がもたらす被害は広範囲なので、『もしも地震がなければ』と思うことが難しくなる」
「出来事が起きてから時間がたてばたつほど、別の現実もあったのではないかと思う度合いは小さくなる」
といったルールを導き出します。
さらに「日常から非日常への心理的な距離は、非日常から日常への心理的な距離よりも遠い」というルールも発見します。
例えば、
ある銀行員がある日、いつもと「同じ」道を通って通勤したら、赤信号を無視して突っ込んできたドラッグ中毒の若者が運転する車にはねられて死んだ場合と、
ある銀行員がある日、いつもと「違う」道を通って通勤したら、赤信号を無視して突っ込んできたドラッグ中毒の若者が運転する車にはねられて死んだ場合では、
前者の方では「いつもと違う道を通っていれば良かったのに!」とは思いにくい。いつもと同じ状況から、いつもと違う状況に発想を移すことは難しい。
後者の方では「いつもと同じ道を通っていれば良かったのに!」と思いやすい。いつもと違う状況から、いつもと同じ状況に発想を移すことは簡単。
ということです。
ダニーはこうした独自の発想についてエイモスとの共同研究は避けていましたが、アイデアについてはダニーに話していました。そしてあるとき、エイモスと一緒に出席した発表会の場で、ダニーはこうしたルールについて講演して、聴衆から大いに関心を集めました。すると、ある参加者がダニーとエイモスに向かって、「こんな発想は、お二人のどちらから生まれるんですか?」と尋ねました。ダニーとエイモスは2人の間の亀裂については公にしていなかったので、この参加者は2人の共同研究の成果なのだと思い込んだわけです。
するとエイモスが答えました。「私とダニーは、そういったことについては話さないことにしているのです」
この一言がダニーにとってはエイモスと決別する決定的なきっかけになったそうです。この発表内容はダニーのものです。そしてエイモスは、この参加者から、ダニーを称える発言をするチャンスを与えられたようなものです。ところがエイモスはこのチャンスを無視した。それがダニーには許せなかった。そしてダニーは別の研究者との共同研究として、論文"The Undoing Project"を発表します。
とまぁ、だいたいこんなことが書かれている本です。この他にも様々な研究結果に関する実例が出てきて面白いです。
2人の研究に関しては、経済学者から強い反発を受けたことにもページが割かれています。ダニーとエイモスに言わせれば、「人間の心理は合理的ではない誤った選択肢をとらせる。しかもその誤り方には法則性がある」というわけです。となると、「人間はシステマチックに間違う。だから市場だってシステマチックに間違っている」という結論になります。経済学は「人間は合理的に行動する」ということを前提にして発展してきたわけですから、そりゃ経済学者にすれば面白くない話です。
しかし2人の研究を受け入れるべきだと考える経済学者も出てきて、「行動経済学」という分野を開拓していきます。2人の研究成果のうち"Prospect Theory"は、今では経済学の分野で2番目に引用されることが多い論文だそうです。
こうした経済学への貢献が評価されて、ダニーは2002年にノーベル経済学賞を受賞します。しかし共同研究者だったエイモスは受賞できませんでした。1996年にガンのために亡くなっていたからです。エイモスは亡くなる前、毎日のようにダニーと話していたそうです。
多分、心理学のパートの部分だけの話を知りたいのなら、ダニー・カーネマン自身の著作を読んだ方がいいのかもしれません。それはそれで面白いことは間違いなさそうです。そこにダニーとエイモスの人間ドラマを付け加えたところが、この本のキモなのだと思います。ただ、時系列が結構ぐちゃぐちゃなので、ドラマを追いにくいところがあります。時系列でたどっていくと、いろいろと筋書き的に矛盾が生じるのかなと推察します。
このほか、2人の研究とイスラエル軍の関わりとか、イスラエルにおける中東での立場とか国民が共有している危機感の話とかがあって、これはこれで興味深いです。イスラエルの歴史っていうのも勉強してみたいですね。
この本は大統領選後に出版された本です。だから人間が非合理的な判断をシステマチックにしてしまうということと、ドナルド・トランプが当選したことを重ね合わせて読んでしまうところもあります。行動政治学なんていう分野があったりするんでしょうか?
"Bloody Mary"
"Bloody Mary"を読んだ。直前に読んだシカゴ市警を舞台にした小説"Whiskey Sour"の続編です。
期待にたがわず楽しめました。12月下旬に読了しています。
内容を本人の公式サイトから引用すると、
Start with a tough but vulnerable Chicago cop. Stir in a psychopath with an unique mental condition that programs him to kill. Add a hyperactive cat, an ailing mother, a jealous boyfriend, a high-maintenance ex-husband, and a partner in the throes of a mid-life crisis. Mix with equal parts humor and suspense, and enjoy Bloody Mary—the second novel in the funny, frightening world of Lieutenant Jacqueline "Jack" Daniels.
When Jack receives a report of an excess of body parts appearing at the Cook County Morgue, she hopes it's only a miscount. It's not. Even worse, these extra limbs seem to be accessorized with Jack's handcuffs.
Someone has plans for Jack. Very bad plans. Plans that involve everything and everyone that she cares about.
Jack must put her train wreck of a personal life on hold to catch an elusive, brilliant maniac—a maniac for whom getting caught is only the beginning...
この本の前書きに書いてあるのですが、大きな謎の判明が中盤で出てきます。「途中で謎が分かっちゃうわけだから、そこから先の展開は読めないでしょ?」という狙いだそうです。確かにほとんどのミステリは大きな謎を解くまでに至る経緯を楽しむわけですから、途中で謎が解けたら、そこから先の展開は読者には想像できません。あと、残酷な描写は控えめにしたそうです。
まぁ、この狙いがうまくいったかどうかは別にして、面白いストーリーでした。次作も読みます。
期待にたがわず楽しめました。12月下旬に読了しています。
内容を本人の公式サイトから引用すると、
Start with a tough but vulnerable Chicago cop. Stir in a psychopath with an unique mental condition that programs him to kill. Add a hyperactive cat, an ailing mother, a jealous boyfriend, a high-maintenance ex-husband, and a partner in the throes of a mid-life crisis. Mix with equal parts humor and suspense, and enjoy Bloody Mary—the second novel in the funny, frightening world of Lieutenant Jacqueline "Jack" Daniels.
When Jack receives a report of an excess of body parts appearing at the Cook County Morgue, she hopes it's only a miscount. It's not. Even worse, these extra limbs seem to be accessorized with Jack's handcuffs.
Someone has plans for Jack. Very bad plans. Plans that involve everything and everyone that she cares about.
Jack must put her train wreck of a personal life on hold to catch an elusive, brilliant maniac—a maniac for whom getting caught is only the beginning...
この本の前書きに書いてあるのですが、大きな謎の判明が中盤で出てきます。「途中で謎が分かっちゃうわけだから、そこから先の展開は読めないでしょ?」という狙いだそうです。確かにほとんどのミステリは大きな謎を解くまでに至る経緯を楽しむわけですから、途中で謎が解けたら、そこから先の展開は読者には想像できません。あと、残酷な描写は控えめにしたそうです。
まぁ、この狙いがうまくいったかどうかは別にして、面白いストーリーでした。次作も読みます。
2017年1月5日木曜日
"Whiskey Sour"
"Whiskey Sour"という本を読んだ。12月あたまぐらいのことです。
前回の"Write Good or Die"で面白い文章を書いていた、J.A. Konrahという作家が2004年に発表した処女作です。
シカゴ市警の女性警部補、ジャクリーン(ジャック)・ダニエルが猟奇殺人事件を解決する話です。
だめですね、こんな紹介では「面白そうだな」と思わせることができません。
だもんで、作者の公式サイトから紹介文を引用しますと、
Lieutenant Jacqueline "Jack" Daniels is having a bad week. Her live-in boyfriend has left her for his personal trainer, chronic insomnia has caused her to max out her credit cards with late-night home shopping purchases, and a frightening killer who calls himself 'The Gingerbread Man' is dumping mutilated bodies in her district.
While avoiding the FBI and its moronic profiling computer, joining a dating service, mixing it up with street thugs, and parrying the advances of an uncouth PI, Jack and her binge-eating partner, Herb, must catch the maniac before he kills again... and Jack is next on his murder list.
Whiskey Sour is the first book in the bestselling Jack Daniels series, full of laugh-out-loud humor and edge-of-your-seat suspense.
ってことです。面白そうでしょ?
実際、面白かったです。
一応、警察が事件を解決するストーリーですが、推理小説のような謎解きよりは「次の展開はどうなるのか?」とハラハラドキドキさせるエンターテインメント小説です。登場人物が交わすジョークに加え、登場人物たちのキャラクターづけもマンガっぽかったりするので、その立ち居振る舞いだけでも笑わせられます。
また読みます。
前回の"Write Good or Die"で面白い文章を書いていた、J.A. Konrahという作家が2004年に発表した処女作です。
シカゴ市警の女性警部補、ジャクリーン(ジャック)・ダニエルが猟奇殺人事件を解決する話です。
だめですね、こんな紹介では「面白そうだな」と思わせることができません。
だもんで、作者の公式サイトから紹介文を引用しますと、
Lieutenant Jacqueline "Jack" Daniels is having a bad week. Her live-in boyfriend has left her for his personal trainer, chronic insomnia has caused her to max out her credit cards with late-night home shopping purchases, and a frightening killer who calls himself 'The Gingerbread Man' is dumping mutilated bodies in her district.
While avoiding the FBI and its moronic profiling computer, joining a dating service, mixing it up with street thugs, and parrying the advances of an uncouth PI, Jack and her binge-eating partner, Herb, must catch the maniac before he kills again... and Jack is next on his murder list.
Whiskey Sour is the first book in the bestselling Jack Daniels series, full of laugh-out-loud humor and edge-of-your-seat suspense.
ってことです。面白そうでしょ?
実際、面白かったです。
一応、警察が事件を解決するストーリーですが、推理小説のような謎解きよりは「次の展開はどうなるのか?」とハラハラドキドキさせるエンターテインメント小説です。登場人物が交わすジョークに加え、登場人物たちのキャラクターづけもマンガっぽかったりするので、その立ち居振る舞いだけでも笑わせられます。
また読みます。
"Write Good or Die"
"Write Good of Die"という本を読んだ。11月の初めぐらいの読了です。
英語を読んだり、聞いたりすることは多いけど、英語で文章を書く機会は少ないもので、ひとつ英語による文章作法でも勉強してみようかと思って購入。米国の作家やライターなど文章に関わるさまざまな職種の人たちが書いた「ライター心得」をまとめたものです。
ただし実際には文章作法についての本というよりは、「作家になりたければ、こういうところに気をつけろ!」といったアドバイス集のような内容でした。それはそれで面白かったです。
印象に残ったアドバイスは、
「誰でも文章は書けるから、その気になれば誰でもライターになれると思われがちだが、なめるな。ライターになるには、オリンピックに出場するのと同じぐらい厳しい訓練が必要だ」
「アイデアはいくらでもある。問題はどうやって書くかだ」
「ライターとして成功するには、自分が面白いと思うものを書き続けるしかない」
「スティーブン・キングは処女作『キャリー』を執筆しているとき、行き詰まってしまって原稿をゴミ箱に捨てたことがある。でも妻がその原稿をゴミ箱から拾い上げて読んでくれて、書き終えるように励ましてくれた。あきらめるな」
「JKローリングはハリーポッターの第1作の発表する前、12の出版社に断られた。編集者はあてにならない」
「あなたたちはキングやローリングのような天才じゃないのだから、何百回と断られて当然」
「編集者の言うことはちゃんと聞け。ひとりよがりになるな。編集者に好かれろ」
といった感じですかね。ほかにもいろいろありますけど。まぁ、ある意味、なかなか実践的です。
あと、小説を書くなら1文で「面白そうだな」と思わせるだけの内容でなければならない、というのがライターにとっては鉄則のようです。
例えば、
"When a great white shark starts attacking beachgoers in a coastal town during high tourist season, a water-phobic Sheriff must assemble a team to hunt it down before it kills again."
"A young female FBI trainee must barter personal information with an imprisoned psychopathic genius in order to catch a serial killer who is capturing and killing young women for their skins."
"A treasure-hunting archeologist caces over the globe to find the legendary Lost Ark of the Covenant before Hitler's minions can acquire and use it to supernaturally power the Nazi army."
っていう感じです。
確かに面白そう。読んでみたいと思わされます。
あと、この本を読んだ思いがけない収穫は、いろんな米国のライターの文章が読めるので、気に入った文章があれば「この人が書いた本を読んでみようかな」というとっかかりになることです。
なかでも、J.A. Konrathという作家が書いた、自らが処女作を出版するまでのストーリーはとてもユーモアーにあふれていて面白かった。処女作出版までに12年かけて、10本の作品を書き、460回も出版を断られたそうです。
ライター稼業も大変ですね。
英語を読んだり、聞いたりすることは多いけど、英語で文章を書く機会は少ないもので、ひとつ英語による文章作法でも勉強してみようかと思って購入。米国の作家やライターなど文章に関わるさまざまな職種の人たちが書いた「ライター心得」をまとめたものです。
ただし実際には文章作法についての本というよりは、「作家になりたければ、こういうところに気をつけろ!」といったアドバイス集のような内容でした。それはそれで面白かったです。
印象に残ったアドバイスは、
「誰でも文章は書けるから、その気になれば誰でもライターになれると思われがちだが、なめるな。ライターになるには、オリンピックに出場するのと同じぐらい厳しい訓練が必要だ」
「アイデアはいくらでもある。問題はどうやって書くかだ」
「ライターとして成功するには、自分が面白いと思うものを書き続けるしかない」
「スティーブン・キングは処女作『キャリー』を執筆しているとき、行き詰まってしまって原稿をゴミ箱に捨てたことがある。でも妻がその原稿をゴミ箱から拾い上げて読んでくれて、書き終えるように励ましてくれた。あきらめるな」
「JKローリングはハリーポッターの第1作の発表する前、12の出版社に断られた。編集者はあてにならない」
「あなたたちはキングやローリングのような天才じゃないのだから、何百回と断られて当然」
「編集者の言うことはちゃんと聞け。ひとりよがりになるな。編集者に好かれろ」
といった感じですかね。ほかにもいろいろありますけど。まぁ、ある意味、なかなか実践的です。
あと、小説を書くなら1文で「面白そうだな」と思わせるだけの内容でなければならない、というのがライターにとっては鉄則のようです。
例えば、
"When a great white shark starts attacking beachgoers in a coastal town during high tourist season, a water-phobic Sheriff must assemble a team to hunt it down before it kills again."
"A young female FBI trainee must barter personal information with an imprisoned psychopathic genius in order to catch a serial killer who is capturing and killing young women for their skins."
"A treasure-hunting archeologist caces over the globe to find the legendary Lost Ark of the Covenant before Hitler's minions can acquire and use it to supernaturally power the Nazi army."
っていう感じです。
確かに面白そう。読んでみたいと思わされます。
あと、この本を読んだ思いがけない収穫は、いろんな米国のライターの文章が読めるので、気に入った文章があれば「この人が書いた本を読んでみようかな」というとっかかりになることです。
なかでも、J.A. Konrathという作家が書いた、自らが処女作を出版するまでのストーリーはとてもユーモアーにあふれていて面白かった。処女作出版までに12年かけて、10本の作品を書き、460回も出版を断られたそうです。
ライター稼業も大変ですね。
登録:
投稿 (Atom)