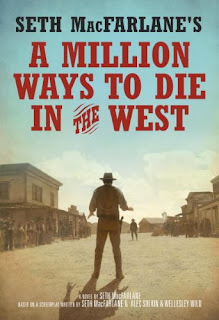"Let's Pretend This Never Happened (A Mostly True Memoir)"という本を読んだ。Jenny Lawsonという女性ブロガーが2012年4月に出した本です。
J.A. Konrathの小説のユーモアが好きでもっと読んでみたいと思うのですが、この人の小説はユーモアかつグロなところがあるので、あんまり沢山読むものでもありません。そこで何かユーモアだけの本はないものかと思って、ファミリーガイで有名なSeth MacFarlanの小説を読んでみたりもしたのですが、なんかイマイチな感じでありました。そんなことを考えているころ、出張で出かけたとある地方空港の本屋さんで「読んだことがある本が置いてあるかなぁ」なんてぶらぶらしていたら、"Humor"をいうコーナーがあるのを見つけました。なるほど、"Humor"でひとつのジャンルになっているのか。
そんなわけでアマゾンで"Humor"と検索してみたら、一番上に出てきたのがこの本でした。4000件近くもレビューがついているので、よく売れた本なのでしょう。で、読んでみました。かなり面白かったです。
内容を説明するのは難しいので、第1章の冒頭部分をそのまま引用します。
Call me Ishmael. I won't answer to it, because it's not my name, but it's much more agreeable than most of the things I've been called. "Call me 'that-weird-chick-who-says-"fuck"-a-lot'" is probably more accurate, but "Ismael" seems classier, and it makes a way more respectable beginning than the sentence I'd originally written, which was about how I'd just run into my gynecologist at Starbucks and she totally looked right past me like she didn't even know me. And so I stood there wondering whether that's something she does on purpose to make her clients feel less uncomfortable, or whether she just genuinely didn't recognize me without my vagina. Either way, it's very disconcerting when people who've been inside your vagina don't acknowledge your existence. Also, I just want to clarify that I don't mean "without my vagina" like I didn't have it with me at the time. I just meant that I wasn't, you know... displaying it while I was at Starbucks. That's probably understood, but I thought I should clarify, since it's the first chapter and you don't know that much about me. it's like my American Express card. (In that I don't leave home without it. Not that I use it to buy stuff with.)
何を言っているんでしょうかね、この人は。
とまぁ、こんな風に、ついついおかしなことばかり考えてしまうローソンさんの妄想日記みたいな趣の本です。
なので、学ぶべきこととか、そういうものはありません。ただ、若い頃にLSDを使ったときのエピソードとかは面白かったです。
A guy I knew had a house on the outskirts of town and offered to host a small LSD party for me and several other people in our group who'd never done acid before either. So we called Travis and asked him to bring over enough acid for six of us that night. Travis arrived and told us the drugs were on their way, and about fifteen minutes later a pizza delivery car pulled up. The delivery guy came to the door with a mushroom pizza and an uncut sheet of acid. The delivery guy was in his late teens, about two feet shorter than me, and very, very white, but he did have a piercing and a pager (which was very impressive, because this was still back in the early nineties, although probably the pager was just used for pizza orders). His name was Jacob. Travis told me later that anyone could by acid from Jacob if they knew the "secret code" to use when you called the pizza place. At the time I thought it was probably something all cloak-and dagger, like "One pepperoni pizza, hold the crust," or "A large cheesy bread and the bird flies at midnight," but in reality it was probably just "And tell Jacob to bring some acid," because honestly neither of them was very imaginative.
Jacob sold Travis the acid for four dollars a hit, and then Travis turned around and sold it to us for five dollars a hit, which was awkward and also a poor profit margin. We each took a hit and Travis said that for another ten bucks he'd stay and babysit us to make sure we didn't cut our hand off. This wasn't something I was actually worried about at all until he mentioned it, but now that the thought was implanted in our heads I became convinced that we would all cut our hands off as soon as he left, so I handed him a ten. Travis cautioned us that if we thought the house cats next door were sending us threatening messages, they probably weren't. And he warned us not to stare at the sun because we'd go blind (which might have been great advice if it hadn't been ten o'clock at night). "Ride the beast... don't let the beast ride you," our wise sage advised us.
このあと、実際にLSDを使ってみて、なんだかんだとバタバタとした展開があります。
ローソンさんのことですから、全部が全部本当というわけじゃないと思いますけど、こんな感じの軽いトーンでドラッグパーティーが開かれるもんなんだなという点が興味深い。知り合いの知り合いみたいな距離感の交友関係から、ドラッグを使うことを目的としたパーティーを開くというお誘いがあって、ちょっと不安だななんて思いながらも、値段もそんなに高くないし、友達もやるっていうし、ちゃんとした「保護者役」もいてくれるというから、ちょっと使ってみようかっていうノリですね。
米国では薬物依存が大きな問題になっているわけですが、今の若者の間でもこんな雰囲気のパーティーが開かれているのだとすれば、好奇心の方が勝ってしまうというのも分からんでもないです。ローソンさんはことのきのLSDでみた幻覚から醒めた後で、幻覚中に自分がとった行動を知って、もうLSDはやらないと思ったそうです。だからまぁ実際の話、一度使えば絶対に後戻りできないというものでもないんじゃないかとも思います。もちろん「ダメ、絶対」ですけどね。最初のLSDの経験が良い記憶として残ってしまえば、常習化していくでしょうし、常習化すれば依存にもつながるのでしょう。でも、「ダメ、絶対」にも関わらず、「ダメ、絶対」になっていない事情の裏には、こんな雰囲気があるんだなということです。
いや「ダメ、絶対」ですからね。ダメですよ、本当に。
2017年9月19日火曜日
2017年8月30日水曜日
"The Curse of Cash"
"The Curse of Cash: How Large-Denomination Bills Aid Crime and Tax Evasion and Constrain Monetary Policy"という本を読んだ。2016年にハーバード大学のケネス・ロゴフ教授が出した、100ドルとか1万円みたいな高額紙幣がいかに犯罪や脱税に使われていて、金融政策の足かせにもなっているかということを解説した本です。タイトルそのまんまですね。
ロゴフ教授といえば、"This Time is Different"という国家の財政破綻の歴史について書いた本で有名になった人です。留学中にとった授業で教科書に指定されていたことと、その授業でBをとってしまったことが懐かしい。バーマン教授には心から御礼申し上げます。
で、この本でいわんとすることはさきほど書いた通りです。実際には高額紙幣がどのぐらい使われていて、それがどのぐらい犯罪や脱税に関わっているかなんていうことはオフィシャルな統計で示せるわけではないのですが、ロゴフ教授は入手可能なデータを駆使して、さらにそこに色んな仮定を重ねて、自説を補強していきます。現金がいかに闇経済で使われているかというのは、以前に読んだExorbitant Privilegeでも触れられていました。まぁ、具体的な規模は分かりませんが、そりゃそうだろうなという気はします。
あと、金融政策については、マイナス金利政策の効果が高額紙幣によって損なわれると主張します。中央銀行は景気を刺激するために金利を引き下げるわけですが、政策金利がゼロにまで到達してしまうと、そこから先は金利を引き下げることはできない。そこで量的緩和政策なんていうのが発案されたわけですが、それがどのぐらい景気を刺激する効果があったかどうかはよく分からないわけです。そこで、日本や欧州はマイナス金利を採用するようになりました。ところが中央銀行がマイナス金利をかけて景気を刺激しようとしても、預金者が銀行口座のお金を現金化してしまえば、そこにはマイナス金利の影響は及ばないわけです。だから、大きなお金の金額の現金化のツールである高額紙幣が金融政策のあしかせになっているといえるという主張です。
ロゴフ教授はここから、だから高額紙幣は廃止するべきだ。各種カードによる電子決済が普及している先進国だったら十分に可能だし、それで犯罪を抑え込み、金融政策の効果も大きくなるんだったら、いいことじゃないかと話を進めます。
こういう主張をすると、中央銀行の通貨発行益(シニョレッジ)が失われるからだめだとか、低所得者はカードなんて持っていないんだから困るだろうとか、犯罪者は高額紙幣が廃止されたって別の抜け道を見つけるだろうとか、マイナス金利みたいな銀行から強制的にお金を巻き上げるようなことをしていいのかとか、いろんな反論が出るそうです。で、ロゴフ教授は、そうした反論の有効性をひとつひとつ検証して、やっぱり高額紙幣廃止によるメリットの方が大きいですよね、と結論づけます。
まぁ、それだけの本です。ハーバードの教授が高額紙幣を廃止したらいいんじゃないのと思いついて、自説の正しさを証明するために反論を丁寧につぶしていく。ただ、個人的には高額紙幣廃止で犯罪が抑制できるんだからそれでいいじゃないかと思うんですが、別にそこまで説明してくれなくてもいいよっていう感じもします。「電子決済が普及しているんで、高額紙幣はなくてもいいですよね」って一言だけ言ってくれれば、みんなそれで納得するんじゃないか。
ただしシヨレッジについて丁寧に説明してくれるのはありがたかったです。中央銀行は通貨を発行することで利益を得られるっていうのはいろんなところで見聞きするんですが、具体的にはどういうことが行われているのかよく分からなかったからです。「何か物が欲しいときに印刷機を動かして好きなだけ紙幣を作っているの?」なんていう風にも思えるわけですが、実際には以下のような手順を踏んでいるそうです。
1.政府が収入以上にお金を使って、それを賄うために債券(debt)を発行する
2.中央銀行が市中からdebtを買い取る。この際、electric bank reserve (which are the electric equivalent of cash)を発行する
3.bank reserveに対して中央銀行が払う利息よりも、debtから得られる利息の方が大きいので中央銀行には長期的に利益が出る
2のところがミソなんでしょうけど、中央銀行は市中からdebtを買い取るときに売り手である銀行に現金を渡すわけじゃなくて、銀行の当座預金の残高の数字を変更するだけなわけですね。これが現代における通貨の発行だというわけです。で、いつでも引き出し可能な当座預金につく利息は、政府が発行した債券につく利息よりも小さい。だから3のところで中央銀行に利益が出る。これがいわゆるシニョレッジ(通貨発行益)というわけです。
だから、高額紙幣が廃止されて、印刷機を動かせなくなっても、中央銀行は利益を出すことができます。ロゴフ教授は"even if paper money revenue disappeared completely, the central bank would still earn money from electronic reserves"と明言しています。
ちなみにこの通貨発行益は中央銀行から政府に納められます。結局、政府は一切損をしていないようにも思ってしまいそうですが、実際には当座預金についた利息分は政府の負担が生じているのだと思います。ここは私の勝手な理解です。
また、ロゴフ氏は高額紙幣を廃止する際には、政府・中央銀行は債券を発行して高額紙幣を買い取らねばならない(it will have to issue ordinary interest-bearing debt to buy back the currency it is retiring)と書いています。
ここのところは直感的によく分からなかったのですが、多分、こういうことです。
1.「高額紙幣を廃止するぞ」とのお達しに従って、銀行が金庫に入っている大量の1万円札を中央銀行に持ち込む
2.中央銀行は銀行から受け取った金額を銀行の当座預金に電子的に記入する
3.でも、この受け取った大量の1万円札は無効になったただの紙切れだから、現金としてはもう使えない
4.だから、中央銀行の損失を埋めるために、政府は債券を発行して資金を調達せねばならない
どうでしょう。これで正しいんでしょうか?
とまぁ、こんなことをつらつらと説明している本です。
This time is differentのときは「そうか。やっぱり政府が負債を積み上げすぎるのは問題だな」という気がしましたが、今回は「知らんがな」という感は否めません。
ロゴフ教授といえば、"This Time is Different"という国家の財政破綻の歴史について書いた本で有名になった人です。留学中にとった授業で教科書に指定されていたことと、その授業でBをとってしまったことが懐かしい。バーマン教授には心から御礼申し上げます。
で、この本でいわんとすることはさきほど書いた通りです。実際には高額紙幣がどのぐらい使われていて、それがどのぐらい犯罪や脱税に関わっているかなんていうことはオフィシャルな統計で示せるわけではないのですが、ロゴフ教授は入手可能なデータを駆使して、さらにそこに色んな仮定を重ねて、自説を補強していきます。現金がいかに闇経済で使われているかというのは、以前に読んだExorbitant Privilegeでも触れられていました。まぁ、具体的な規模は分かりませんが、そりゃそうだろうなという気はします。
あと、金融政策については、マイナス金利政策の効果が高額紙幣によって損なわれると主張します。中央銀行は景気を刺激するために金利を引き下げるわけですが、政策金利がゼロにまで到達してしまうと、そこから先は金利を引き下げることはできない。そこで量的緩和政策なんていうのが発案されたわけですが、それがどのぐらい景気を刺激する効果があったかどうかはよく分からないわけです。そこで、日本や欧州はマイナス金利を採用するようになりました。ところが中央銀行がマイナス金利をかけて景気を刺激しようとしても、預金者が銀行口座のお金を現金化してしまえば、そこにはマイナス金利の影響は及ばないわけです。だから、大きなお金の金額の現金化のツールである高額紙幣が金融政策のあしかせになっているといえるという主張です。
ロゴフ教授はここから、だから高額紙幣は廃止するべきだ。各種カードによる電子決済が普及している先進国だったら十分に可能だし、それで犯罪を抑え込み、金融政策の効果も大きくなるんだったら、いいことじゃないかと話を進めます。
こういう主張をすると、中央銀行の通貨発行益(シニョレッジ)が失われるからだめだとか、低所得者はカードなんて持っていないんだから困るだろうとか、犯罪者は高額紙幣が廃止されたって別の抜け道を見つけるだろうとか、マイナス金利みたいな銀行から強制的にお金を巻き上げるようなことをしていいのかとか、いろんな反論が出るそうです。で、ロゴフ教授は、そうした反論の有効性をひとつひとつ検証して、やっぱり高額紙幣廃止によるメリットの方が大きいですよね、と結論づけます。
まぁ、それだけの本です。ハーバードの教授が高額紙幣を廃止したらいいんじゃないのと思いついて、自説の正しさを証明するために反論を丁寧につぶしていく。ただ、個人的には高額紙幣廃止で犯罪が抑制できるんだからそれでいいじゃないかと思うんですが、別にそこまで説明してくれなくてもいいよっていう感じもします。「電子決済が普及しているんで、高額紙幣はなくてもいいですよね」って一言だけ言ってくれれば、みんなそれで納得するんじゃないか。
ただしシヨレッジについて丁寧に説明してくれるのはありがたかったです。中央銀行は通貨を発行することで利益を得られるっていうのはいろんなところで見聞きするんですが、具体的にはどういうことが行われているのかよく分からなかったからです。「何か物が欲しいときに印刷機を動かして好きなだけ紙幣を作っているの?」なんていう風にも思えるわけですが、実際には以下のような手順を踏んでいるそうです。
1.政府が収入以上にお金を使って、それを賄うために債券(debt)を発行する
2.中央銀行が市中からdebtを買い取る。この際、electric bank reserve (which are the electric equivalent of cash)を発行する
3.bank reserveに対して中央銀行が払う利息よりも、debtから得られる利息の方が大きいので中央銀行には長期的に利益が出る
2のところがミソなんでしょうけど、中央銀行は市中からdebtを買い取るときに売り手である銀行に現金を渡すわけじゃなくて、銀行の当座預金の残高の数字を変更するだけなわけですね。これが現代における通貨の発行だというわけです。で、いつでも引き出し可能な当座預金につく利息は、政府が発行した債券につく利息よりも小さい。だから3のところで中央銀行に利益が出る。これがいわゆるシニョレッジ(通貨発行益)というわけです。
だから、高額紙幣が廃止されて、印刷機を動かせなくなっても、中央銀行は利益を出すことができます。ロゴフ教授は"even if paper money revenue disappeared completely, the central bank would still earn money from electronic reserves"と明言しています。
ちなみにこの通貨発行益は中央銀行から政府に納められます。結局、政府は一切損をしていないようにも思ってしまいそうですが、実際には当座預金についた利息分は政府の負担が生じているのだと思います。ここは私の勝手な理解です。
また、ロゴフ氏は高額紙幣を廃止する際には、政府・中央銀行は債券を発行して高額紙幣を買い取らねばならない(it will have to issue ordinary interest-bearing debt to buy back the currency it is retiring)と書いています。
ここのところは直感的によく分からなかったのですが、多分、こういうことです。
1.「高額紙幣を廃止するぞ」とのお達しに従って、銀行が金庫に入っている大量の1万円札を中央銀行に持ち込む
2.中央銀行は銀行から受け取った金額を銀行の当座預金に電子的に記入する
3.でも、この受け取った大量の1万円札は無効になったただの紙切れだから、現金としてはもう使えない
4.だから、中央銀行の損失を埋めるために、政府は債券を発行して資金を調達せねばならない
どうでしょう。これで正しいんでしょうか?
とまぁ、こんなことをつらつらと説明している本です。
This time is differentのときは「そうか。やっぱり政府が負債を積み上げすぎるのは問題だな」という気がしましたが、今回は「知らんがな」という感は否めません。
2017年8月17日木曜日
"The Healing of America"
"The Healing of America: A Global Quest for Better, Cheaper, and Fairer Health Care"という本を読んだ。T. R. Reidという、慢性的な肩の痛みを抱えるジャーナリストが世界各国の医者にかかりながら、各国の医療制度について探求し、米国の医療保険制度の問題点をあぶり出すという内容です。2010年8月出版。オバマケア関連法案成立して間もないころですね。
とても面白かった。American Sicknessよりも格段に読みやすい。米国医療がいかにしてダメになっていったかということはAmerican Sicknessでこれでもかと言わんばかりに書かれていたわけですが、こちらのThe Healing of Americaでは、他の国はどうしてダメになっていないのかということが書かれています。さらに、かつてはダメな制度だったのに改革に成功した、台湾とスイスのケースも紹介しています。なのでAmerican Sicknessよりも救いがあります。
書かれていることは単純。米国の医療制度をまともなものにするには、国民が「全員が医療保険に加入できるべきだ」という考え方で一致できるかどうかがキモだということです。世界の医療保険制度はいろんな仕組みがありますが、米国以外の先進国はすべてこの考え方に基づいています。
ところが米国ではこういう主張をすると、必ず「社会主義化された医療制度だ! ムダだらけで、革新も生まれない。国民の医療への選択肢も狭められる。自由を尊ぶ米国の理念に反する」という反発が出ます。そういった主張に、現在の医療保険制度で恩恵を受けている医療保険会社や医療機関、製薬会社が乗っかってロビー活動を展開するので、議会は動きがとれなくなります。オバマ大統領に上院60議席、下院過半数の議席を与えたって、問題は解決できなかったわけですからなかなか根深い問題です。
そこでリードさんは、こうした「社会主義化された医療制度だ!」という批判は的外れだと繰り返し説明します。
まず、他の先進国の医療制度は別に社会主義化されているわけではないという点です。
リードさんは先進国の医療制度を以下のように分類します。
ビスマルク型(ドイツ、日本など)=医療保険提供者が民間、医療サービス提供者も民間
ベバリッジ型(英国、北欧など)=医療保険提供者が国、医療サービス提供者も国
国民健康保険型(カナダ、韓国など)=医療保険提供者は国、医療サービス提供者は民間
まぁ、ベバレッジ型は国が全面的に関与していますから、バリバリの自由経済主義者からみれば「社会主義的」といえるかもしれません。でも英国を社会主義国だと思う人は多くはないです。あとビスマルク型や国民健康保険型は民間が関与していますから、社会主義ってわけじゃないですよね。
ただし、こうした民間が関与する仕組みでも規制はきついです。例えばビスマルク型として取り上げられている日本は、医療保険は主に企業別の医療保険組合が提供していて、医療サービスも民間がやっているわけですが、医薬品の価格なんかは政府がコントロールしているわけです。それは「すべての国民が医療保険に加入できるべきだ」との考え方から正当化されます。こうした厳しい規制のおかげで日本の医療費は国際的にみて安いですし、しかも患者は自由に医療機関を選べる。
ベバレッジ型は医療保険も医療サービスも国が主体です。そのおかげで患者は病院に行っても請求書を受け取ることはありません。それだったら患者が好きなだけ病院に行くことになって医療費が高騰しそうなものですが、「国はすべての人を保険でカバーするけれど、すべての医療行為をカバーするわけじゃない」という立場をとっているため、たいしたことのない病気であったりすれば病院にかかる前に行くことになる"general practitioner"のオフィスの段階で「病院に行かなくていいですよ。様子をみましょう」ということになる。また、すべての医療費は国民の税金で負担することになりますから、有権者や政治家も医療費の無駄遣いには敏感です。「94歳の女性への人工関節手術を認めるべきか」「50歳以上の男性すべてに前立腺がんの検査を認めるべきか」といった問題が、医学的なエビデンスの基づいて議論されたりします。
国民健康保険型も医療保険を国が提供するわけですから、どんな治療に対しても費用を払うというわけではないです。医療サービスは民間ですから、民間同士の競争がありますし、国がいくらでも医療費を払ってくれるわけじゃないので、コスト意識が働きます。
もちろん、それぞれの制度には問題点があります。日本なんかは「医療従事者の報酬が低い」なんていう問題点も指摘されます。ベバレッジ型の英国や北欧は米国に比べて税金が高いです。国民健康保険型のカナダなんかは、緊急性がない治療の場合は、受診までに数カ月~1年以上も待たねばならないという問題があります。
ただ、それだって米国の医療制度よりは格段にいいわけです。一人あたり医療費は安いし、健康を維持できる年齢も高い。どこの国だって「米国みたいにはなりたくない」と思っています。それなのに、どうして米国が現在の米国の医療制度にこだわる必要があるのかというわけです。
リードさんはさらに、米国内の「他の国の医療制度は自由を尊ぶ米国の理念に反する」という意見も的外れだとします。それは米国の医療制度のなかには、すでにこれらの仕組みが根を張っているからです。
例えば、高齢者向け公的医療保険のメディケアは国が医療費を負担して民間が医療サービスを提供していますから国民健康保険型です。退役軍人向けには専門の病院もありますから、これは医療保険も医療サービスも国が提供するベバリッジ型です。そのほかの企業が提供する医療保険に加入している米国人にとっては、ビスマルク型の医療保険制度が存在しているわけです。
ただ、米国には「全員が医療保険に加入できるべきだ」という理念がないために、どの制度からもこぼれてしまっている人たちがいます。メディケアに入れるほど年寄りではないし、低所得者向けのメディケイドに入れるほど所得が低いわけでもないし、医療保険を提供してくれる会社に勤めているわけでもないし、退役軍人でもないという人たちですね。この人たちは行き所がないです。利益目的の保険会社に高い保険料や高い自己負担額を強いられ、病院からも高い医療費を請求されて、生活を維持できなくなってしまうような人たちです。さらに医療保険を提供してくれる会社に勤めていたけど、病気で仕事を続けられなくなって退職したら、医療保険がなくなったなんていう事態も起きるわけです。
また、こうした医療保険制度のパッチワーク状態が余計なコストを生みます。オバマケアはこのパッチワークに拍車をかけました。
リードさんはこう書いています。
Facing an entrenched army of well-financed and powerful interests determined to preserve the status quo, Obama declared from the start that he would not seek to replace the existing health care system with a simpler, cheaper model. "We have to build on what we've got already," Obama said. The result was an enormously expensive and complicated piece of legislation ---the "Obamacare" bill runs to 2,400 pages of legalese ---that retains most of the structure of the U.S. system ....
もちろんリードさんはオバマケアが結果的に無保険者を大幅に減らすであろうことや、保険会社が病歴のある人の加入を断ることを禁じる制度を作ったことは高く評価しているわけですが、根本的な問題解決にはほど遠いということなんでしょう。
あと、リードさんは医療保険制度の抜本的な改革に成功した台湾やスイスの取り組みも詳しく取り上げています。どちらも、まず最初にリベラル側が「全員が医療保険に加入できるべきだ」と声を上げ、それを国民が熱狂的に支持し、保守側が人気とりのためにそれを受け入れたという展開だったようです。あと、どちらも経済が好調だったという背景もあるそうです。
米国では2016年に民主党の大統領候補指名争いで健闘したバーニー・サンダース上院議員が"single-payer"のシステムを目指しています。これは医療保険を国が提供するという意味です。オバマケアの失敗を踏まえたうえで、より抜本的な改革を実現させるということなのでしょう。
じゃあ、2020年の大統領選で79歳になったサンダース氏が当選。そのときには2018年の中間選挙と大統領選と同時に行われる議会選挙で、上下両院ともに民主党が過半数を握っていて、サンダース氏が訴える抜本的な医療保険制度改革をトランプ政権にこりた共和党も受け入れる。そんなシナリオはどうでしょうか。
どうでしょうか。米国人のみなさん。
とても面白かった。American Sicknessよりも格段に読みやすい。米国医療がいかにしてダメになっていったかということはAmerican Sicknessでこれでもかと言わんばかりに書かれていたわけですが、こちらのThe Healing of Americaでは、他の国はどうしてダメになっていないのかということが書かれています。さらに、かつてはダメな制度だったのに改革に成功した、台湾とスイスのケースも紹介しています。なのでAmerican Sicknessよりも救いがあります。
書かれていることは単純。米国の医療制度をまともなものにするには、国民が「全員が医療保険に加入できるべきだ」という考え方で一致できるかどうかがキモだということです。世界の医療保険制度はいろんな仕組みがありますが、米国以外の先進国はすべてこの考え方に基づいています。
ところが米国ではこういう主張をすると、必ず「社会主義化された医療制度だ! ムダだらけで、革新も生まれない。国民の医療への選択肢も狭められる。自由を尊ぶ米国の理念に反する」という反発が出ます。そういった主張に、現在の医療保険制度で恩恵を受けている医療保険会社や医療機関、製薬会社が乗っかってロビー活動を展開するので、議会は動きがとれなくなります。オバマ大統領に上院60議席、下院過半数の議席を与えたって、問題は解決できなかったわけですからなかなか根深い問題です。
そこでリードさんは、こうした「社会主義化された医療制度だ!」という批判は的外れだと繰り返し説明します。
まず、他の先進国の医療制度は別に社会主義化されているわけではないという点です。
リードさんは先進国の医療制度を以下のように分類します。
ビスマルク型(ドイツ、日本など)=医療保険提供者が民間、医療サービス提供者も民間
ベバリッジ型(英国、北欧など)=医療保険提供者が国、医療サービス提供者も国
国民健康保険型(カナダ、韓国など)=医療保険提供者は国、医療サービス提供者は民間
まぁ、ベバレッジ型は国が全面的に関与していますから、バリバリの自由経済主義者からみれば「社会主義的」といえるかもしれません。でも英国を社会主義国だと思う人は多くはないです。あとビスマルク型や国民健康保険型は民間が関与していますから、社会主義ってわけじゃないですよね。
ただし、こうした民間が関与する仕組みでも規制はきついです。例えばビスマルク型として取り上げられている日本は、医療保険は主に企業別の医療保険組合が提供していて、医療サービスも民間がやっているわけですが、医薬品の価格なんかは政府がコントロールしているわけです。それは「すべての国民が医療保険に加入できるべきだ」との考え方から正当化されます。こうした厳しい規制のおかげで日本の医療費は国際的にみて安いですし、しかも患者は自由に医療機関を選べる。
ベバレッジ型は医療保険も医療サービスも国が主体です。そのおかげで患者は病院に行っても請求書を受け取ることはありません。それだったら患者が好きなだけ病院に行くことになって医療費が高騰しそうなものですが、「国はすべての人を保険でカバーするけれど、すべての医療行為をカバーするわけじゃない」という立場をとっているため、たいしたことのない病気であったりすれば病院にかかる前に行くことになる"general practitioner"のオフィスの段階で「病院に行かなくていいですよ。様子をみましょう」ということになる。また、すべての医療費は国民の税金で負担することになりますから、有権者や政治家も医療費の無駄遣いには敏感です。「94歳の女性への人工関節手術を認めるべきか」「50歳以上の男性すべてに前立腺がんの検査を認めるべきか」といった問題が、医学的なエビデンスの基づいて議論されたりします。
国民健康保険型も医療保険を国が提供するわけですから、どんな治療に対しても費用を払うというわけではないです。医療サービスは民間ですから、民間同士の競争がありますし、国がいくらでも医療費を払ってくれるわけじゃないので、コスト意識が働きます。
もちろん、それぞれの制度には問題点があります。日本なんかは「医療従事者の報酬が低い」なんていう問題点も指摘されます。ベバレッジ型の英国や北欧は米国に比べて税金が高いです。国民健康保険型のカナダなんかは、緊急性がない治療の場合は、受診までに数カ月~1年以上も待たねばならないという問題があります。
ただ、それだって米国の医療制度よりは格段にいいわけです。一人あたり医療費は安いし、健康を維持できる年齢も高い。どこの国だって「米国みたいにはなりたくない」と思っています。それなのに、どうして米国が現在の米国の医療制度にこだわる必要があるのかというわけです。
リードさんはさらに、米国内の「他の国の医療制度は自由を尊ぶ米国の理念に反する」という意見も的外れだとします。それは米国の医療制度のなかには、すでにこれらの仕組みが根を張っているからです。
例えば、高齢者向け公的医療保険のメディケアは国が医療費を負担して民間が医療サービスを提供していますから国民健康保険型です。退役軍人向けには専門の病院もありますから、これは医療保険も医療サービスも国が提供するベバリッジ型です。そのほかの企業が提供する医療保険に加入している米国人にとっては、ビスマルク型の医療保険制度が存在しているわけです。
ただ、米国には「全員が医療保険に加入できるべきだ」という理念がないために、どの制度からもこぼれてしまっている人たちがいます。メディケアに入れるほど年寄りではないし、低所得者向けのメディケイドに入れるほど所得が低いわけでもないし、医療保険を提供してくれる会社に勤めているわけでもないし、退役軍人でもないという人たちですね。この人たちは行き所がないです。利益目的の保険会社に高い保険料や高い自己負担額を強いられ、病院からも高い医療費を請求されて、生活を維持できなくなってしまうような人たちです。さらに医療保険を提供してくれる会社に勤めていたけど、病気で仕事を続けられなくなって退職したら、医療保険がなくなったなんていう事態も起きるわけです。
また、こうした医療保険制度のパッチワーク状態が余計なコストを生みます。オバマケアはこのパッチワークに拍車をかけました。
リードさんはこう書いています。
Facing an entrenched army of well-financed and powerful interests determined to preserve the status quo, Obama declared from the start that he would not seek to replace the existing health care system with a simpler, cheaper model. "We have to build on what we've got already," Obama said. The result was an enormously expensive and complicated piece of legislation ---the "Obamacare" bill runs to 2,400 pages of legalese ---that retains most of the structure of the U.S. system ....
もちろんリードさんはオバマケアが結果的に無保険者を大幅に減らすであろうことや、保険会社が病歴のある人の加入を断ることを禁じる制度を作ったことは高く評価しているわけですが、根本的な問題解決にはほど遠いということなんでしょう。
あと、リードさんは医療保険制度の抜本的な改革に成功した台湾やスイスの取り組みも詳しく取り上げています。どちらも、まず最初にリベラル側が「全員が医療保険に加入できるべきだ」と声を上げ、それを国民が熱狂的に支持し、保守側が人気とりのためにそれを受け入れたという展開だったようです。あと、どちらも経済が好調だったという背景もあるそうです。
米国では2016年に民主党の大統領候補指名争いで健闘したバーニー・サンダース上院議員が"single-payer"のシステムを目指しています。これは医療保険を国が提供するという意味です。オバマケアの失敗を踏まえたうえで、より抜本的な改革を実現させるということなのでしょう。
じゃあ、2020年の大統領選で79歳になったサンダース氏が当選。そのときには2018年の中間選挙と大統領選と同時に行われる議会選挙で、上下両院ともに民主党が過半数を握っていて、サンダース氏が訴える抜本的な医療保険制度改革をトランプ政権にこりた共和党も受け入れる。そんなシナリオはどうでしょうか。
どうでしょうか。米国人のみなさん。
2017年7月21日金曜日
"An American Sickness"
"An American Sickness: How Healthcare Became Big Business and How You Can Take It Back"という本を読んだ。医師として働いたこともあるニューヨーク・タイムズの元記者、Elisabeth Rosenthalが米国の医療制度が抱える問題について書いた本です。2017年4月発売。
5月にニューヨーク・タイムズの書評で米国の医療制度を理解するための本として紹介されてたので、ちょっと読んでみた。聞き慣れない医療用語の多さとか、医療制度に関する基本的な知識の欠如もあって、なかなかスムーズには読めませんでした。でも考えさせられるところが多くて、面白かった。
米国の医療制度は悪名高いです。OECDのデータによると、2015年の米国の1人あたり医療費(実質、購買力平価ベース)は8748ドルで世界1位。2位のスイス(6493ドル)に大差をつけています。日本は4036ドルですから、米国は日本の2倍以上の医療費がかかっていることになります。
OECDのページ
医療費が高いと、医療保険の保険料は高くなります。そうなると医療保険に入れなかったり、入りたくなくなったりする人が出てきます。
そういう状況に対応しようとしたのが2010年に成立したオバマケアだったわけです。でもオバマケア後も米国の医療費は上がり続けています。オバマケアが2014年に個人に保険加入を義務づけるなどしてから無保険者は1900万人減っていますが、それは保険料を連邦政府として負担したからであって、米国の医療費が世界的にみて例外的に高いという根本的な問題を解決できたわけではありません。
で、この本はどうしてこんなことになっているのかを説明しようとした本です。ただ、話が話だけに事は単純ではありません。
エピローグの言葉を引用すると、
No one player created the mess that is the $3 trillion American medical system in 2017. People in every sector of medicine are feeding trough: insurers, hospitals, doctors, manufacturers, politicians, regulators, charities, and more.
とのことです。この本は医療費や保険料の高騰の背景を象徴するいろんなエピソードを紹介しながら進みます。だからまとまりはないです。ただし、ローゼンタールさんは冒頭で、米国の医療制度がまともに機能していないことを象徴する、米国の医療がこだわる10の原則なるものを示しています。
1.常に治療せよ。最初の選択肢は最も高価な治療法。
2.一生治療を続けることは、治癒することよりも好ましい。
3.治療そのものよりも、快適さやマーケティングが大切。
4.技術革新の時代において、医療価格は上がり続ける。
5.患者は常に言いなり。常に米国の医療を購入する。
6.医療では競合があっても価格はさがらず、むしろ上がる。
7.医療機関は規模が大きくなっても価格は下げない。ただ稼ぎを増やすだけ。
8.適正価格などない。無保険者が最も高い医療費を払う。
9.請求書に基準はない。あらゆるものにお金がかかる。
10.患者が負担するギリギリまで価格は上がる。
まぁ、なんとなく分かるような内容です。
そもそも医療というのは病気の人を相手にしているわけです。で、病気の人は働けないわけですから、お金なんかもっていない。だから本来、医者なんていう仕事は儲かるハズがない。ローゼンタールさんによると、100年ほど前には、そもそも医療というのは簡素なもので、安くて、多くの場合は宗教関係者によって運営されていました。病院というのは人々が死ぬための場所でもあったのです。
一方で、19世紀後半には、企業が従業員の医療費を負担する仕組みが生まれます。従業員が働けなくなることは、会社にとって損失だからです。1890年代、ワシントン州の木材会社は従業員が医師にかかる際に1カ月あたり50セントを負担したそうで、こうした仕組みが今の米国における企業負担型の医療保険のはしりだそうです。
現在の医療保険の元祖は1920年代までにテキサス州ダラスで生まれました。教職員組合の加入者を対象に、年間6ドルを払えば、21日分の入院治療が受けられるというものです。ただし保険の支払いは、最初に1日あたり5ドルの自己負担を1週間続けた後で発動されるという仕組みでした。21日という期間は、当時の医療水準では21日もあれば患者の多くは治るか、死ぬかのどちらになるという判断で決められました。
第二次世界大戦が終わると、企業は人手不足に陥ります。そこで企業は従業員に医療保険を提供することで人を集めようとします。連邦政府もこれを後押しして、従業員の医療費は非課税とすることにしました。すると1940年から1955年にかけて、米国の保険加入者は人口の10%から60%まで急増しました。保険を提供していたのはBlueCrossのようは非営利組織で、年齢や健康状態に関わらず、すべての加入者は同じ額の保険料を払っていました。
こんな風にして医療保険への需要が高まってくると、営利目的の保険会社が医療保険に参入してきます。こうした保険会社は年齢によって保険料を変えたり、カバーの範囲を変えたりして、より安い保険料を提示するようになります。1951年までにはAetnaやCignaがシェアを伸ばし、BlueCrossのようなすべての保険加入者を平等に扱う非営利組織は不利になっていきます。そして1994年、BlueCrossは営利組織になることを容認。社会的な使命を意識する保険会社が駆逐されてしまった形になりました。
1993年、保険会社は保険料の95%を医療費に使っていましたが、現在では80%近くまで下がっています。なかには64.4%なんていう保険会社もあるそうです。オバマケアは保険会社に対して、この比率(medical loss ratio)を80~85%にするよう求めました。ただ、高齢者向け公的医療保険のメディケアのmedical loss ratioは98%ですから、オバマケアは十分甘いともいえます。
つまり保険会社は公的な使命を忘れてしまっていて、オバマケアもそれを容認してしまったということです。
医療機関にも問題があります。そもそもほとんどの医療機関は非営利組織として運営されているため、利益を上げることができません。すると医療費として集めたお金が実際にかかったコストよりも大きくなると、余ったお金を無駄遣いする構造になっています。つまり節約するという意識がない。1960年代にメディケアが登場すると、65歳以下の世代でも保険加入が進みます。すると患者の方でも自分がいくら負担するかを気にしなくなってきて、医療機関は好き勝手な医療費を請求するようになります。1967年から1983年にかけて、メディケアの支払い額は30億ドルから370億ドルまで増えました。
メディケアも対応に乗り出します。1980年代の半ばにはdiagnosis related group (DRG)という仕組みを導入し、治療の種類に応じて支払い額を固定するよう決めました。一方、民間の保険会社はDRGでは医療費が高止まりする可能性があるとして、ケアマネジャーを雇って適正な医療費の価格をはじき出して、医療機関と交渉する仕組みを採用します。
すると、医療機関はメディケアや交渉力のある保険会社が手強くなってきたと判断し、小さな保険会社や無保険の患者に高い医療費を請求するようになります。さらに医療機関は収入を増やすためにコンサルタントを雇い、戦略的な医療費設定(strategic pricing)を始めます。コンサルタントは保険会社が支払いに応じないような品目での請求を止め、酸素吸入や処方薬のような保険会社が支払いに応じることが多い品目での請求を増やし、その結果、こうした品目として請求される医療費が実際の費用からかけ離れた高額になるといった事態が生じます。大手の医療コンサルタント企業は年間342億ドルもの売上を稼いでいるんだそうです。
さらに医療機関のなかには医師に対して固定給ではなく、行った治療の収益性に応じて報酬を払うケースもあります。治療や検査の複雑さを示すレベル1~5までの分類に応じて、医師が受け取る報酬が決まっているわけです。普通にひざの関節への注射をすれば1200ドルの収入になるけれど、その際に超音波で針を刺す場所を特定すればさらに300ドルの収入になる。ひざへの注射は特段難しいわけじゃないので、超音波による検査は必要ないんだけれど、医師は報酬を増やすために超音波を使うようになるといった具合で医療費が上がっていきます。
メディケアにまわされた請求を分析したところ、緊急治療室で治療を受けた患者のうちレベル4と5の治療を受けた患者の割合は2001年には4分の1ですたが、2008年には半分にまで増えていた。一方、レベル2の請求は15%まで半減。医療機関2400カ所のうち500カ所では、患者の60%に対してレベル4と5の治療が行われていました。
つまり医療機関は保険会社やメディケアなんかの監視の目をかいくぐるようにして、患者から医療費をむしりとっているという構図です。病院の経営者の収入は2011年から2012年にかけて24.2%増えました。オバマケア成立後のことです。医師の報酬も2009年以降、増え続けています。医師以外の職業ではみられない現象だそうです。ローゼンタールさんが医療現場で働いていた1990年台、医師たちは「時給で考えたら、配管工より給料が安い」なんて文句を言っていたそうです。でも、今はNBAのレブロン・ジェームズやゴールドマン・サックスの会長が比較の対象になっているようだと、ローゼンタールさんは書いています。
メディケアの方にも間抜けなところがあります。メディケアは地域ごとに支払い額を決めているのですが、その支払い額はその地域の医療機関による過去の請求額などを基準に決められています。しかし、ある地域で特定の治療を行う医療機関が少数であれば、それらの医療機関はお互いに競争するのではなく、そろって請求額を上げていこうという動機が生まれます。その結果、2014年段階で、ニューヨークのクイーンズでの胆嚢手術のコストは2000ドルであるにも関わらず、20マイル離れたロングアイランドのナッソー郡での胆嚢手術は2万5000ドルと計上される。そんなおかしな事態が起きています。
メディケアは1980年代に医療行為の時間や管理コスト、医師育成にかかるコスト、過誤によるコストをもとにしてrelative value units(RVUs)を算出。これをもとに医療機関への支払い額を決めるアルゴリズムを作ります。こうしたアルゴリズムは常にアップデートする必要があるわけですが、メディケアはこの任務をAmerican Medical Associationに委ねてしまします。医療行為の適正価格を医療機関自身に決めさせてしまうようなものです。AMAは3年に一度、Relative Value Scale Update Committeeを開いて見直しを進めるのですが、この委員会は各医療関連団体のロビーイング競争の場になっています。
もちろん製薬会社も無茶苦茶です。最近でも、安い値段で売られている薬の販売に関わる権利を買い集めて、一気に大幅に値上げするといった悪行がニュースになります。
かつて医薬品を開発した研究者は特許をとろうとはしませんでした。ポリオワクチンの開発に力を尽くしたJonas Salkeは「誰がポリオワクチンの特許を持っているのか」と問われて、"Well, the people, I would say. There is no patent. Could you patent the sun?"と答えたそうです。実際、当時の法制度では、多くの研究者が関わったポリオワクチンは特許をとることができないと判断されていたそうです。
しかし1980年のBayh-Dole Actで政府の資金援助を受けた研究から得られた成果でも特許を取ることが認められるようになりました。今ではひとつの医薬品に対して3.5件の特許がかかっています。1984年の別の法律改正(Hatch-Waxman)ではジェネリック医薬品の導入促進のための規制緩和が実現しましたが、同時に大手製薬会社を納得させるために、一部のケースで特許期間の延長を認めました。こうしたジェネリック企業と大手製薬会社の軋轢が法廷闘争に発展すると、その間はジェネリック医薬品の導入が遅れるケースも出ることになります。米国は欧州に比べて特許の力が強く、医薬品の価格にも規制がかかっていないため、多くの製薬企業が米国に投資するようになっています。
大手製薬会社は自社の医薬品が特許切れに寸前になると、わずかに仕様や成分を変えた医薬品を開発して新たに特許を取り直すという戦略も採ります。例えばワーナーチルコットは経口避妊薬Loestrin24 Feが特許切れになる前に、「噛めるタイプ」のMinastrin24 Feを販売。Loestrin24 Feの販売を取りやめます。新薬の方は旧薬よりも3割ほど高い価格設定ですが、まだジェネリックは出ていないので、利用者は新薬に乗り換えざるを得ません。
1994年に特許を得たスプレータイプの処方薬Flonaseの場合、2006年にジェネリック版が登場。Flonaseを販売していたグラクソスミソクラインは訴訟を起こすなどして抵抗しましたが、2010年にはジェネリック版が市販薬として20ドルの価格でドラッグストアの店頭に並ぶようになりました。処方薬であるFlonaseは医療保険の対象となる分、価格は高く設定されていますから、ジェネリック版に市場を奪われることは必至です。しかしそこでグラクソスミソクラインはFlonaseを市販薬に変更し、市場に投入。すると米国法では、同じ医薬品がひとつの市場で同時に売られることを禁じているため、ジェネリック版のメーカーは在庫を売り切って工場を閉鎖するよう要求されることになりました。さらに米国では、処方薬を市販薬に変更した場合には、3年間の市場独占期間が保障されていて、新規の参入もブロックすることができます。グラクソスミソクラインはこの市販薬版のFlonaseを40ドルで売ったとのことです。
とまぁですね、こんなややこしいエピソードが山ほど書かれている本です。ややこしいので、ここまでに書いた文章にも誤解があるかもしれません。このほか患者の側のかわいそうな話も満載です。
本の後半では、医療の消費者である患者の側はどのように対応すればいいかといった話も出てくるのですが、正直、これだけ根深い問題を見せられた後ではなかなか明るい希望は抱けません。多分、政策上とか理論上ではできることはいくらでもあるのでしょう。でも、政治の状況を考えれば、なんか絶望的です。
オバマケア(Affordable Care Act)についてこんな記述があります。
The ACA did little directly, however, to control run-away spending. President Obama had initially included several ideas in the bill that would have done so ---like national negotiation for pharmaceutical prices. To get a healthcare bill passed and to win support from powerful groups like PhRMA, the AMA, the American Hospital Association, and America's Health Insurance Plans, the administration had to cave on anything that would directly limit the industry's ability to profit.
医療業界によるロビイングは共和党だけでなく、もちろん民主党にも浸透しています。ハリー・リードとかチャック・シューマーのようないかにも悪そうな人たちだけならまだしも、エリザベス・ウォレンやエイミー・クローブシャーのような、いかにも「庶民の味方」といったイメージの議員まで医療業界の世話になっているようです。そんなことになっていたら、オバマ大統領だって法律を通そうと思えば、妥協せざるをえなかったということなのかもしれません。
トランプ大統領だったら、医療業界ごとぶっとばしてくれる。そんな期待もあるかもしれません。でもトランプ大統領だって法律を通すには議会の協力を得ねばなりません。予算編成で強い影響力を持つ上院財政委員会の委員長は医薬品業界とのつながりで有名なオリン・ハッチです。他の共和党議員だって、医療業界にお世話になっているだろうことは想像に難くありません。
まぁ、病気にならないように気をつけるしかないですかね。100年前と同じですね。
5月にニューヨーク・タイムズの書評で米国の医療制度を理解するための本として紹介されてたので、ちょっと読んでみた。聞き慣れない医療用語の多さとか、医療制度に関する基本的な知識の欠如もあって、なかなかスムーズには読めませんでした。でも考えさせられるところが多くて、面白かった。
米国の医療制度は悪名高いです。OECDのデータによると、2015年の米国の1人あたり医療費(実質、購買力平価ベース)は8748ドルで世界1位。2位のスイス(6493ドル)に大差をつけています。日本は4036ドルですから、米国は日本の2倍以上の医療費がかかっていることになります。
OECDのページ
医療費が高いと、医療保険の保険料は高くなります。そうなると医療保険に入れなかったり、入りたくなくなったりする人が出てきます。
そういう状況に対応しようとしたのが2010年に成立したオバマケアだったわけです。でもオバマケア後も米国の医療費は上がり続けています。オバマケアが2014年に個人に保険加入を義務づけるなどしてから無保険者は1900万人減っていますが、それは保険料を連邦政府として負担したからであって、米国の医療費が世界的にみて例外的に高いという根本的な問題を解決できたわけではありません。
で、この本はどうしてこんなことになっているのかを説明しようとした本です。ただ、話が話だけに事は単純ではありません。
エピローグの言葉を引用すると、
No one player created the mess that is the $3 trillion American medical system in 2017. People in every sector of medicine are feeding trough: insurers, hospitals, doctors, manufacturers, politicians, regulators, charities, and more.
とのことです。この本は医療費や保険料の高騰の背景を象徴するいろんなエピソードを紹介しながら進みます。だからまとまりはないです。ただし、ローゼンタールさんは冒頭で、米国の医療制度がまともに機能していないことを象徴する、米国の医療がこだわる10の原則なるものを示しています。
1.常に治療せよ。最初の選択肢は最も高価な治療法。
2.一生治療を続けることは、治癒することよりも好ましい。
3.治療そのものよりも、快適さやマーケティングが大切。
4.技術革新の時代において、医療価格は上がり続ける。
5.患者は常に言いなり。常に米国の医療を購入する。
6.医療では競合があっても価格はさがらず、むしろ上がる。
7.医療機関は規模が大きくなっても価格は下げない。ただ稼ぎを増やすだけ。
8.適正価格などない。無保険者が最も高い医療費を払う。
9.請求書に基準はない。あらゆるものにお金がかかる。
10.患者が負担するギリギリまで価格は上がる。
まぁ、なんとなく分かるような内容です。
そもそも医療というのは病気の人を相手にしているわけです。で、病気の人は働けないわけですから、お金なんかもっていない。だから本来、医者なんていう仕事は儲かるハズがない。ローゼンタールさんによると、100年ほど前には、そもそも医療というのは簡素なもので、安くて、多くの場合は宗教関係者によって運営されていました。病院というのは人々が死ぬための場所でもあったのです。
一方で、19世紀後半には、企業が従業員の医療費を負担する仕組みが生まれます。従業員が働けなくなることは、会社にとって損失だからです。1890年代、ワシントン州の木材会社は従業員が医師にかかる際に1カ月あたり50セントを負担したそうで、こうした仕組みが今の米国における企業負担型の医療保険のはしりだそうです。
現在の医療保険の元祖は1920年代までにテキサス州ダラスで生まれました。教職員組合の加入者を対象に、年間6ドルを払えば、21日分の入院治療が受けられるというものです。ただし保険の支払いは、最初に1日あたり5ドルの自己負担を1週間続けた後で発動されるという仕組みでした。21日という期間は、当時の医療水準では21日もあれば患者の多くは治るか、死ぬかのどちらになるという判断で決められました。
第二次世界大戦が終わると、企業は人手不足に陥ります。そこで企業は従業員に医療保険を提供することで人を集めようとします。連邦政府もこれを後押しして、従業員の医療費は非課税とすることにしました。すると1940年から1955年にかけて、米国の保険加入者は人口の10%から60%まで急増しました。保険を提供していたのはBlueCrossのようは非営利組織で、年齢や健康状態に関わらず、すべての加入者は同じ額の保険料を払っていました。
こんな風にして医療保険への需要が高まってくると、営利目的の保険会社が医療保険に参入してきます。こうした保険会社は年齢によって保険料を変えたり、カバーの範囲を変えたりして、より安い保険料を提示するようになります。1951年までにはAetnaやCignaがシェアを伸ばし、BlueCrossのようなすべての保険加入者を平等に扱う非営利組織は不利になっていきます。そして1994年、BlueCrossは営利組織になることを容認。社会的な使命を意識する保険会社が駆逐されてしまった形になりました。
1993年、保険会社は保険料の95%を医療費に使っていましたが、現在では80%近くまで下がっています。なかには64.4%なんていう保険会社もあるそうです。オバマケアは保険会社に対して、この比率(medical loss ratio)を80~85%にするよう求めました。ただ、高齢者向け公的医療保険のメディケアのmedical loss ratioは98%ですから、オバマケアは十分甘いともいえます。
つまり保険会社は公的な使命を忘れてしまっていて、オバマケアもそれを容認してしまったということです。
医療機関にも問題があります。そもそもほとんどの医療機関は非営利組織として運営されているため、利益を上げることができません。すると医療費として集めたお金が実際にかかったコストよりも大きくなると、余ったお金を無駄遣いする構造になっています。つまり節約するという意識がない。1960年代にメディケアが登場すると、65歳以下の世代でも保険加入が進みます。すると患者の方でも自分がいくら負担するかを気にしなくなってきて、医療機関は好き勝手な医療費を請求するようになります。1967年から1983年にかけて、メディケアの支払い額は30億ドルから370億ドルまで増えました。
メディケアも対応に乗り出します。1980年代の半ばにはdiagnosis related group (DRG)という仕組みを導入し、治療の種類に応じて支払い額を固定するよう決めました。一方、民間の保険会社はDRGでは医療費が高止まりする可能性があるとして、ケアマネジャーを雇って適正な医療費の価格をはじき出して、医療機関と交渉する仕組みを採用します。
すると、医療機関はメディケアや交渉力のある保険会社が手強くなってきたと判断し、小さな保険会社や無保険の患者に高い医療費を請求するようになります。さらに医療機関は収入を増やすためにコンサルタントを雇い、戦略的な医療費設定(strategic pricing)を始めます。コンサルタントは保険会社が支払いに応じないような品目での請求を止め、酸素吸入や処方薬のような保険会社が支払いに応じることが多い品目での請求を増やし、その結果、こうした品目として請求される医療費が実際の費用からかけ離れた高額になるといった事態が生じます。大手の医療コンサルタント企業は年間342億ドルもの売上を稼いでいるんだそうです。
さらに医療機関のなかには医師に対して固定給ではなく、行った治療の収益性に応じて報酬を払うケースもあります。治療や検査の複雑さを示すレベル1~5までの分類に応じて、医師が受け取る報酬が決まっているわけです。普通にひざの関節への注射をすれば1200ドルの収入になるけれど、その際に超音波で針を刺す場所を特定すればさらに300ドルの収入になる。ひざへの注射は特段難しいわけじゃないので、超音波による検査は必要ないんだけれど、医師は報酬を増やすために超音波を使うようになるといった具合で医療費が上がっていきます。
メディケアにまわされた請求を分析したところ、緊急治療室で治療を受けた患者のうちレベル4と5の治療を受けた患者の割合は2001年には4分の1ですたが、2008年には半分にまで増えていた。一方、レベル2の請求は15%まで半減。医療機関2400カ所のうち500カ所では、患者の60%に対してレベル4と5の治療が行われていました。
つまり医療機関は保険会社やメディケアなんかの監視の目をかいくぐるようにして、患者から医療費をむしりとっているという構図です。病院の経営者の収入は2011年から2012年にかけて24.2%増えました。オバマケア成立後のことです。医師の報酬も2009年以降、増え続けています。医師以外の職業ではみられない現象だそうです。ローゼンタールさんが医療現場で働いていた1990年台、医師たちは「時給で考えたら、配管工より給料が安い」なんて文句を言っていたそうです。でも、今はNBAのレブロン・ジェームズやゴールドマン・サックスの会長が比較の対象になっているようだと、ローゼンタールさんは書いています。
メディケアの方にも間抜けなところがあります。メディケアは地域ごとに支払い額を決めているのですが、その支払い額はその地域の医療機関による過去の請求額などを基準に決められています。しかし、ある地域で特定の治療を行う医療機関が少数であれば、それらの医療機関はお互いに競争するのではなく、そろって請求額を上げていこうという動機が生まれます。その結果、2014年段階で、ニューヨークのクイーンズでの胆嚢手術のコストは2000ドルであるにも関わらず、20マイル離れたロングアイランドのナッソー郡での胆嚢手術は2万5000ドルと計上される。そんなおかしな事態が起きています。
メディケアは1980年代に医療行為の時間や管理コスト、医師育成にかかるコスト、過誤によるコストをもとにしてrelative value units(RVUs)を算出。これをもとに医療機関への支払い額を決めるアルゴリズムを作ります。こうしたアルゴリズムは常にアップデートする必要があるわけですが、メディケアはこの任務をAmerican Medical Associationに委ねてしまします。医療行為の適正価格を医療機関自身に決めさせてしまうようなものです。AMAは3年に一度、Relative Value Scale Update Committeeを開いて見直しを進めるのですが、この委員会は各医療関連団体のロビーイング競争の場になっています。
もちろん製薬会社も無茶苦茶です。最近でも、安い値段で売られている薬の販売に関わる権利を買い集めて、一気に大幅に値上げするといった悪行がニュースになります。
かつて医薬品を開発した研究者は特許をとろうとはしませんでした。ポリオワクチンの開発に力を尽くしたJonas Salkeは「誰がポリオワクチンの特許を持っているのか」と問われて、"Well, the people, I would say. There is no patent. Could you patent the sun?"と答えたそうです。実際、当時の法制度では、多くの研究者が関わったポリオワクチンは特許をとることができないと判断されていたそうです。
しかし1980年のBayh-Dole Actで政府の資金援助を受けた研究から得られた成果でも特許を取ることが認められるようになりました。今ではひとつの医薬品に対して3.5件の特許がかかっています。1984年の別の法律改正(Hatch-Waxman)ではジェネリック医薬品の導入促進のための規制緩和が実現しましたが、同時に大手製薬会社を納得させるために、一部のケースで特許期間の延長を認めました。こうしたジェネリック企業と大手製薬会社の軋轢が法廷闘争に発展すると、その間はジェネリック医薬品の導入が遅れるケースも出ることになります。米国は欧州に比べて特許の力が強く、医薬品の価格にも規制がかかっていないため、多くの製薬企業が米国に投資するようになっています。
大手製薬会社は自社の医薬品が特許切れに寸前になると、わずかに仕様や成分を変えた医薬品を開発して新たに特許を取り直すという戦略も採ります。例えばワーナーチルコットは経口避妊薬Loestrin24 Feが特許切れになる前に、「噛めるタイプ」のMinastrin24 Feを販売。Loestrin24 Feの販売を取りやめます。新薬の方は旧薬よりも3割ほど高い価格設定ですが、まだジェネリックは出ていないので、利用者は新薬に乗り換えざるを得ません。
1994年に特許を得たスプレータイプの処方薬Flonaseの場合、2006年にジェネリック版が登場。Flonaseを販売していたグラクソスミソクラインは訴訟を起こすなどして抵抗しましたが、2010年にはジェネリック版が市販薬として20ドルの価格でドラッグストアの店頭に並ぶようになりました。処方薬であるFlonaseは医療保険の対象となる分、価格は高く設定されていますから、ジェネリック版に市場を奪われることは必至です。しかしそこでグラクソスミソクラインはFlonaseを市販薬に変更し、市場に投入。すると米国法では、同じ医薬品がひとつの市場で同時に売られることを禁じているため、ジェネリック版のメーカーは在庫を売り切って工場を閉鎖するよう要求されることになりました。さらに米国では、処方薬を市販薬に変更した場合には、3年間の市場独占期間が保障されていて、新規の参入もブロックすることができます。グラクソスミソクラインはこの市販薬版のFlonaseを40ドルで売ったとのことです。
とまぁですね、こんなややこしいエピソードが山ほど書かれている本です。ややこしいので、ここまでに書いた文章にも誤解があるかもしれません。このほか患者の側のかわいそうな話も満載です。
本の後半では、医療の消費者である患者の側はどのように対応すればいいかといった話も出てくるのですが、正直、これだけ根深い問題を見せられた後ではなかなか明るい希望は抱けません。多分、政策上とか理論上ではできることはいくらでもあるのでしょう。でも、政治の状況を考えれば、なんか絶望的です。
オバマケア(Affordable Care Act)についてこんな記述があります。
The ACA did little directly, however, to control run-away spending. President Obama had initially included several ideas in the bill that would have done so ---like national negotiation for pharmaceutical prices. To get a healthcare bill passed and to win support from powerful groups like PhRMA, the AMA, the American Hospital Association, and America's Health Insurance Plans, the administration had to cave on anything that would directly limit the industry's ability to profit.
医療業界によるロビイングは共和党だけでなく、もちろん民主党にも浸透しています。ハリー・リードとかチャック・シューマーのようないかにも悪そうな人たちだけならまだしも、エリザベス・ウォレンやエイミー・クローブシャーのような、いかにも「庶民の味方」といったイメージの議員まで医療業界の世話になっているようです。そんなことになっていたら、オバマ大統領だって法律を通そうと思えば、妥協せざるをえなかったということなのかもしれません。
トランプ大統領だったら、医療業界ごとぶっとばしてくれる。そんな期待もあるかもしれません。でもトランプ大統領だって法律を通すには議会の協力を得ねばなりません。予算編成で強い影響力を持つ上院財政委員会の委員長は医薬品業界とのつながりで有名なオリン・ハッチです。他の共和党議員だって、医療業界にお世話になっているだろうことは想像に難くありません。
まぁ、病気にならないように気をつけるしかないですかね。100年前と同じですね。
2017年6月16日金曜日
"The Ax"
"The Ax"という小説を読んだ。Donald Westlakeが1997年に書いた作品です。ウエストレイクはエドガー賞を3度獲ったほどの著名作家です。私は全然知りませんでしたが。
私はもともとミステリーが好きで、これまでJ.A. Konrathの本を読んでいたのですが、どうもこの人の本はジョーク満載で面白いんだけど、描写がグロいところがあって、なんか食傷気味になってきたところでした。
そこで、以前読んだ本のなかで、Konrath自身が好きだと書いていた作家をピックアップして、そのなかから、私が気に入るような作家を捜してみようと思ったのです。
Konrathが好きだと書いていた作家は6人。
Janet Evanovich
Rovert Parker
Lawrence Block
Robert Crais
Donald Westlake
Ridley Pearson
一人も読んだことがないので「このミステリーがすごい!」の過去のランキングを調べてみたところ、このうち、ローレンス・ブロックと、ウエストレイクは過去に何度もトップ10に入っています。
2013年10位のローレンス・ブロック「償いの報酬」A Drop of the Hard Stuff (Matthew Scudder 17)
2004年5位のドナルド・ウエストレイク「鉤」The Hook(2000, シリーズなし)
2002年4位のドナルド・ウエストレイク「斧」The Ax(1997, シリーズなし)
1998年9位のドナルド・ウエストレイク「天から降ってきた泥棒」Good Behavior (1985, Dortmunder)
1995年3位のドナルド・ウエストレイク「踊る黄金像」Dancing Aztecs(1976, シリーズなし)
1994年6位のローレンス・ブロック「倒錯の舞踏」A Dance at the Slaughterhouse (Matthew Scudder 9)
1993年2位のローレンス・ブロック「墓場への切符」A Ticket to the Boneyard (Matthew Scudder 8)
じゃぁ、このなかからどれを読むかということですが、シリーズものじゃない、比較的新しいという基準で"The Ax"を選んだ。"The Hook"を選ばなかった理由は忘れた。
で、肝心の読んでみた感想ですが、Konrathの作品とは正反対で「ジョークは一切無く、グロさもほとんどない」といった作風です。1990年台半ばのコネチカット、ニューヨーク、マサチューセッツを舞台にして、製紙メーカーをリストラされた男が殺人を繰り返すという話。一貫して犯人の視点で書かれているので、ミステリーではありません。本当に淡々と話が進んでいきます。
じゃぁ、面白くないかというと、そうではなくて、なかなか読ませます。リストラされた男が殺人を始めるまでの屈折した心理とか、家族との関係とか、ターゲットに対する心情とか、だんだんと犯罪慣れしていく様子とかが詳細に描かれていきます。描写がグロいわけじゃないですが、犯人の身勝手な理屈はなかなかにグロテスクです。また、この男をリストラした会社はコネチカットの工場を閉めて、カナダに製造拠点を移したという設定になっています。NAFTA(1994年発効)なんかも言及されていて、今日的な話題である「米国における製造業の衰退」なんていうテーマも重ね合わせてしまいますね。
淡々と話は進みますが、ラストにどうなるかは最後まで分かりません。そういった意味でも面白い。
ウエストレイクは多作な人みたいなので、しばらく楽しめそう。
私はもともとミステリーが好きで、これまでJ.A. Konrathの本を読んでいたのですが、どうもこの人の本はジョーク満載で面白いんだけど、描写がグロいところがあって、なんか食傷気味になってきたところでした。
そこで、以前読んだ本のなかで、Konrath自身が好きだと書いていた作家をピックアップして、そのなかから、私が気に入るような作家を捜してみようと思ったのです。
Konrathが好きだと書いていた作家は6人。
Janet Evanovich
Rovert Parker
Lawrence Block
Robert Crais
Donald Westlake
Ridley Pearson
一人も読んだことがないので「このミステリーがすごい!」の過去のランキングを調べてみたところ、このうち、ローレンス・ブロックと、ウエストレイクは過去に何度もトップ10に入っています。
2013年10位のローレンス・ブロック「償いの報酬」A Drop of the Hard Stuff (Matthew Scudder 17)
2004年5位のドナルド・ウエストレイク「鉤」The Hook(2000, シリーズなし)
2002年4位のドナルド・ウエストレイク「斧」The Ax(1997, シリーズなし)
1998年9位のドナルド・ウエストレイク「天から降ってきた泥棒」Good Behavior (1985, Dortmunder)
1995年3位のドナルド・ウエストレイク「踊る黄金像」Dancing Aztecs(1976, シリーズなし)
1994年6位のローレンス・ブロック「倒錯の舞踏」A Dance at the Slaughterhouse (Matthew Scudder 9)
1993年2位のローレンス・ブロック「墓場への切符」A Ticket to the Boneyard (Matthew Scudder 8)
じゃぁ、このなかからどれを読むかということですが、シリーズものじゃない、比較的新しいという基準で"The Ax"を選んだ。"The Hook"を選ばなかった理由は忘れた。
で、肝心の読んでみた感想ですが、Konrathの作品とは正反対で「ジョークは一切無く、グロさもほとんどない」といった作風です。1990年台半ばのコネチカット、ニューヨーク、マサチューセッツを舞台にして、製紙メーカーをリストラされた男が殺人を繰り返すという話。一貫して犯人の視点で書かれているので、ミステリーではありません。本当に淡々と話が進んでいきます。
じゃぁ、面白くないかというと、そうではなくて、なかなか読ませます。リストラされた男が殺人を始めるまでの屈折した心理とか、家族との関係とか、ターゲットに対する心情とか、だんだんと犯罪慣れしていく様子とかが詳細に描かれていきます。描写がグロいわけじゃないですが、犯人の身勝手な理屈はなかなかにグロテスクです。また、この男をリストラした会社はコネチカットの工場を閉めて、カナダに製造拠点を移したという設定になっています。NAFTA(1994年発効)なんかも言及されていて、今日的な話題である「米国における製造業の衰退」なんていうテーマも重ね合わせてしまいますね。
淡々と話は進みますが、ラストにどうなるかは最後まで分かりません。そういった意味でも面白い。
ウエストレイクは多作な人みたいなので、しばらく楽しめそう。
2017年5月31日水曜日
"A Million Ways To Die In The West"
"A Million Ways To Die In The West"という本を読んだ。"Family Guy"で有名なSeth MacFarlaneの同名の映画の小説版です。
ちょっと前にシンプソンズの脚本に参加したことがあるというライターのエッセイを読んだのですが、これが面白くかつ読みやすかった。
https://www.wsj.com/articles/the-prom-a-survival-guide-for-parents-1494593931?tesla=y
で、このライターが何か本を出していないかと思って探してみたけど見つからなかったもので、それならファミリー・ガイのセス・マクファーレンの本だったら面白いんじゃないかと思って読んでみた次第です。
まぁ、面白かったことは間違いないですが、「お勧め!」っていうほどのものでもないです。
1882年のアリゾナを舞台に繰り広げられるコメディです。主人公はアルバートという男で、ヒツジ牧場を経営する気の優しい男。このアルバートと、美人の彼女ルイーズ、親友のエドワードとその恋人のルス、金持ちのフォイ、お尋ね者のクリンチ、その妻のアナたちが主要な登場人物で、まぁ、なんだかんだとドタバタするという話です。
ストーリーは単純です。まぁ、ちょっと凝った昔話みたいなもんです。だから話の筋道というよりは、主人公たちのキャラとか会話とかを楽しむタイプの本です。
例えば、エドワードとルスは実に仲の良いカップルなのですが、ルスは売春婦でエドワードもそのことを知っています。しかもルスとエドワードはそういった関係には至っていない。エドワードはなんとかそういう関係に持ち込みたいと思わないでもないのですが、ルスから「私たちはクリスチャンだから、婚前交渉は持つべきじゃない」と言われると、「そんなもんかなぁ」と思ってしまう。まぁ、そんなおかしなシチュエーションが面白いっていう本です。
だから面白いんです。でも、2時間ほどの映画と本にまとめたわけだから、映画で見た方が面白いんだと思います。
本を読むときに期待するほどの面白さではないと思います。
すぐに読める点はよかったです。
ちょっと前にシンプソンズの脚本に参加したことがあるというライターのエッセイを読んだのですが、これが面白くかつ読みやすかった。
https://www.wsj.com/articles/the-prom-a-survival-guide-for-parents-1494593931?tesla=y
で、このライターが何か本を出していないかと思って探してみたけど見つからなかったもので、それならファミリー・ガイのセス・マクファーレンの本だったら面白いんじゃないかと思って読んでみた次第です。
まぁ、面白かったことは間違いないですが、「お勧め!」っていうほどのものでもないです。
1882年のアリゾナを舞台に繰り広げられるコメディです。主人公はアルバートという男で、ヒツジ牧場を経営する気の優しい男。このアルバートと、美人の彼女ルイーズ、親友のエドワードとその恋人のルス、金持ちのフォイ、お尋ね者のクリンチ、その妻のアナたちが主要な登場人物で、まぁ、なんだかんだとドタバタするという話です。
ストーリーは単純です。まぁ、ちょっと凝った昔話みたいなもんです。だから話の筋道というよりは、主人公たちのキャラとか会話とかを楽しむタイプの本です。
例えば、エドワードとルスは実に仲の良いカップルなのですが、ルスは売春婦でエドワードもそのことを知っています。しかもルスとエドワードはそういった関係には至っていない。エドワードはなんとかそういう関係に持ち込みたいと思わないでもないのですが、ルスから「私たちはクリスチャンだから、婚前交渉は持つべきじゃない」と言われると、「そんなもんかなぁ」と思ってしまう。まぁ、そんなおかしなシチュエーションが面白いっていう本です。
だから面白いんです。でも、2時間ほどの映画と本にまとめたわけだから、映画で見た方が面白いんだと思います。
本を読むときに期待するほどの面白さではないと思います。
すぐに読める点はよかったです。
2017年5月20日土曜日
"Courage to Soar: A Body in Motion, A Life in Balance"
"Courage to Soar: A body in Motion, A Life in Balance"という本を読んだ。リオ五輪の女子体操で団体と個人総合、跳馬、床で金メダル。平均台で銅メダルをとったシモン・バイルズの回想録です。まだ20歳。痛快なお話でした。
前のトレバー・ノアの本が大変な子供時代を過ごした話でした。シモン・バイルスも母親がドラッグ中毒で、子供のころに祖父母に引き取られたという話を聞いたことがあったもので、どんなサクセスストーリーなのかと思って読んでみた。
ただ、あまり子供時代に家族のことで苦労したというわけではなさそうです。というのも、シモンは実の母親との生活をよく覚えていないんだそうです。
実の母親のシャノンさんは祖父の前妻との間の子供。シャノンさんは前妻のもとで育ち、シモンの姉(7歳上)、兄(3歳上)、シモン、妹(2歳下)を生みました。しかしドラッグなどへの依存症で、行政から育児放棄と認定されてしまいます。で、シモンが3歳のとき4人の子供たちは保護施設を通じて、ボランティアの里親のもとに引き取られる。しばらくして、テキサス州に住む祖父母が4人のきょうだいを引き取ることになります。
その後、4人は一度、オハイオ州に住むシャノンさんのもとに戻りますが、シャノンさんはドラッグをやめられなかった。それでも姉と兄は実の母親であるシャノンさんと暮らしたがったので、結局、2人はオハイオ州に住む祖父の姉のもとに、シモンと妹は祖父母のもとに戻ることになります。2002年12月24日、シモンが5歳のときのことです。そして2003年11月に、祖父母は2人と正式に養子縁組みし、シモンと妹の両親となります。この日からシモンは祖父母のことを、"Dad"、"Mom"と呼ぶようになります。
オハイオ州の話ですから、ヒルビリー・エレジーを思い出してしまいますが、シモンはどうもこのシャノンさんという女性にシンパシーを感じられないみたいです。
こんな一文があります。
Shanon still calls Adria and me on birthdays and holidays, but we don't have much contact beyond that. Some days, I feel a little bit sad for her. It's not that I ever wanted to go back to live in Ohio, but I do wish she'd been able to make better decisions when she was younger.
笑っちゃうぐらい、あっさりしています。シャノンさんにもいろいろ事情があったんだろうと思いますけどね。まぁ、だからといってシモンに何ができるっていうわけじゃないでしょうけど。
祖母は一番最初に4人のきょうだいを引き受けるとき、かなり不安だったそうです。4人は自分とは血のつながりがない子供たちだし、上の2人は物心がついていてシャノンさんに懐いている。しかも自分自身の2人の息子がどちらも高校生になって、子育てが一段落ついたばかり。そんなところに、また複雑な事情を抱えた幼い子供たちの面倒をみなければならないわけで、尻込みする気持ちも分かります。
ただ、そのとき、祖母の相談に乗っていた養子を育てた経験がある女性が、祖母にこんなことを言ったそうです。
"the Lord doesn't make any mistakes. And he never gives you more than you can handle."
この言葉に勇気づけられて、祖母は4人の面倒を見ることを決意したんだとのこと。ベリーズ出身の祖母はなかなか信仰に篤い人みたいです。
そんなシモンが体操を始めるきっかけは、祖父母の家にトランポリンがあったからだそうです。最初の里親の家にもトランポリンがあったんですが、そのときはシモンがケガをすることを心配する里親がトランポリンで遊ぶことを許してくれなかった。でも、祖父母の家だと、高校生の兄2人が見守るなかで遊ばしてもらえた。そのトランポリンが大好きで、ピョンピョンピョンピョン跳んでいたそうです。
で、6歳のときの保育園の遠足の行き先が、雨のため、牧場から体操クラブがある体育館に変更になった。その体育館でシモンがピョンピョンピョンピョン飛び跳ねているのをみて、体操クラブのコーチがクラブにスカウトしたんだそうです。このとき、遠足の行き先を体操クラブに変更したのは、保育園でバイトをしていた兄たちだった。まぁ、なんかマンガみたいな展開があるもんです。
あとは怒濤のサクセスストーリーになります。もちろんジュニアの米国代表に僅差で入れなかったとか、プレッシャーがきつかったとか、高校に通うかホームスクーリングにするかで悩んだとか、段違い平行棒が苦手でトカチェフをマスターするのに7カ月かかったとか、ケガしたとか、トップアスリートならではの苦労はあります。それぞれがほんの数年前の出来事だったりするわけで、10台の女の子としての実感がこもっています。大変だったでしょう。
ただ、やっぱり超恵まれた展開もあります。
特に最初の世界選手権制覇の後の2014年2月、体操を始めてからずっとコーチをしてくれた女性が突然、体操クラブを辞めることになったときのエピソードはすごい。シモンはこの女性コーチのもとでずっと練習したいと思うわけですが、女性コーチの移籍先が決まっているわけじゃないし、移籍先が決まったところでシモンが通える場所になるかどうかは分からない。今の体操クラブに残留するのが一番の安全策ですが、やっぱりシモンのことを一番理解してくれいるのはこの女性コーチだというジレンマがあります。
子供のころから夢見てきたオリンピックまで2年あまりというなかでのこのピンチ。これを切り抜けた方法は、
「祖母(養母)が女性コーチのために新しい体育館と体操クラブを作る」
というもの。
祖母は看護師としてキャリアを積んできた人で、14カ所の老人ホームを共同経営するほどにまで成功した人だそうです。で、その持ち分を売却して資金を作り、体育館を建て、新しい体操クラブを作ってしまった。その名もワールド・チャンピオン・センターです。もちろん、すぐに体育館ができるわけじゃないですから、シモンは最初の半年は元の体操クラブの体育館に間借りして、その後は倉庫を改装した仮の体育館を使って練習を続けたんだそうです。マンガ的ですが、本当の話です。
ということで、期待していた苦労話ではなかったですが、小柄でも体操が大好きな天才少女がいろんな苦労をしながらも、優しい祖父母や兄や妹に支えられながらマンガ的な展開で連戦連勝を重ね、最後にはオリンピックでの勝利をつかみ取るという痛快なストーリーではあります。
これはこれで面白かった。
前のトレバー・ノアの本が大変な子供時代を過ごした話でした。シモン・バイルスも母親がドラッグ中毒で、子供のころに祖父母に引き取られたという話を聞いたことがあったもので、どんなサクセスストーリーなのかと思って読んでみた。
ただ、あまり子供時代に家族のことで苦労したというわけではなさそうです。というのも、シモンは実の母親との生活をよく覚えていないんだそうです。
実の母親のシャノンさんは祖父の前妻との間の子供。シャノンさんは前妻のもとで育ち、シモンの姉(7歳上)、兄(3歳上)、シモン、妹(2歳下)を生みました。しかしドラッグなどへの依存症で、行政から育児放棄と認定されてしまいます。で、シモンが3歳のとき4人の子供たちは保護施設を通じて、ボランティアの里親のもとに引き取られる。しばらくして、テキサス州に住む祖父母が4人のきょうだいを引き取ることになります。
その後、4人は一度、オハイオ州に住むシャノンさんのもとに戻りますが、シャノンさんはドラッグをやめられなかった。それでも姉と兄は実の母親であるシャノンさんと暮らしたがったので、結局、2人はオハイオ州に住む祖父の姉のもとに、シモンと妹は祖父母のもとに戻ることになります。2002年12月24日、シモンが5歳のときのことです。そして2003年11月に、祖父母は2人と正式に養子縁組みし、シモンと妹の両親となります。この日からシモンは祖父母のことを、"Dad"、"Mom"と呼ぶようになります。
オハイオ州の話ですから、ヒルビリー・エレジーを思い出してしまいますが、シモンはどうもこのシャノンさんという女性にシンパシーを感じられないみたいです。
こんな一文があります。
Shanon still calls Adria and me on birthdays and holidays, but we don't have much contact beyond that. Some days, I feel a little bit sad for her. It's not that I ever wanted to go back to live in Ohio, but I do wish she'd been able to make better decisions when she was younger.
笑っちゃうぐらい、あっさりしています。シャノンさんにもいろいろ事情があったんだろうと思いますけどね。まぁ、だからといってシモンに何ができるっていうわけじゃないでしょうけど。
祖母は一番最初に4人のきょうだいを引き受けるとき、かなり不安だったそうです。4人は自分とは血のつながりがない子供たちだし、上の2人は物心がついていてシャノンさんに懐いている。しかも自分自身の2人の息子がどちらも高校生になって、子育てが一段落ついたばかり。そんなところに、また複雑な事情を抱えた幼い子供たちの面倒をみなければならないわけで、尻込みする気持ちも分かります。
ただ、そのとき、祖母の相談に乗っていた養子を育てた経験がある女性が、祖母にこんなことを言ったそうです。
"the Lord doesn't make any mistakes. And he never gives you more than you can handle."
この言葉に勇気づけられて、祖母は4人の面倒を見ることを決意したんだとのこと。ベリーズ出身の祖母はなかなか信仰に篤い人みたいです。
そんなシモンが体操を始めるきっかけは、祖父母の家にトランポリンがあったからだそうです。最初の里親の家にもトランポリンがあったんですが、そのときはシモンがケガをすることを心配する里親がトランポリンで遊ぶことを許してくれなかった。でも、祖父母の家だと、高校生の兄2人が見守るなかで遊ばしてもらえた。そのトランポリンが大好きで、ピョンピョンピョンピョン跳んでいたそうです。
で、6歳のときの保育園の遠足の行き先が、雨のため、牧場から体操クラブがある体育館に変更になった。その体育館でシモンがピョンピョンピョンピョン飛び跳ねているのをみて、体操クラブのコーチがクラブにスカウトしたんだそうです。このとき、遠足の行き先を体操クラブに変更したのは、保育園でバイトをしていた兄たちだった。まぁ、なんかマンガみたいな展開があるもんです。
あとは怒濤のサクセスストーリーになります。もちろんジュニアの米国代表に僅差で入れなかったとか、プレッシャーがきつかったとか、高校に通うかホームスクーリングにするかで悩んだとか、段違い平行棒が苦手でトカチェフをマスターするのに7カ月かかったとか、ケガしたとか、トップアスリートならではの苦労はあります。それぞれがほんの数年前の出来事だったりするわけで、10台の女の子としての実感がこもっています。大変だったでしょう。
ただ、やっぱり超恵まれた展開もあります。
特に最初の世界選手権制覇の後の2014年2月、体操を始めてからずっとコーチをしてくれた女性が突然、体操クラブを辞めることになったときのエピソードはすごい。シモンはこの女性コーチのもとでずっと練習したいと思うわけですが、女性コーチの移籍先が決まっているわけじゃないし、移籍先が決まったところでシモンが通える場所になるかどうかは分からない。今の体操クラブに残留するのが一番の安全策ですが、やっぱりシモンのことを一番理解してくれいるのはこの女性コーチだというジレンマがあります。
子供のころから夢見てきたオリンピックまで2年あまりというなかでのこのピンチ。これを切り抜けた方法は、
「祖母(養母)が女性コーチのために新しい体育館と体操クラブを作る」
というもの。
祖母は看護師としてキャリアを積んできた人で、14カ所の老人ホームを共同経営するほどにまで成功した人だそうです。で、その持ち分を売却して資金を作り、体育館を建て、新しい体操クラブを作ってしまった。その名もワールド・チャンピオン・センターです。もちろん、すぐに体育館ができるわけじゃないですから、シモンは最初の半年は元の体操クラブの体育館に間借りして、その後は倉庫を改装した仮の体育館を使って練習を続けたんだそうです。マンガ的ですが、本当の話です。
ということで、期待していた苦労話ではなかったですが、小柄でも体操が大好きな天才少女がいろんな苦労をしながらも、優しい祖父母や兄や妹に支えられながらマンガ的な展開で連戦連勝を重ね、最後にはオリンピックでの勝利をつかみ取るという痛快なストーリーではあります。
これはこれで面白かった。
2017年3月2日木曜日
“Death by China: Confronting The Dragon--- A Global Call to Action”
“Death by China: Confronting The Dragon--- A Global Call to Action”を読んだ。トランプ大統領が新設したNational Trade CouncilのDirectorに任命されたPeter Navarroカリフォルニア大学アーバイン校教授が書いた本です。南カリフォルニア大学の非常勤教授だったGreg Autryとの共著です。2011年5月に出版されました。
トランプ大統領は2016年12月21日にナバロ氏をNTCのトップに任命すると発表したときの声明で、こんな風に述べています。
“I read one of Peter’s books on America’s trade problems years ago and was impressed by the clarity of his arguments and thoroughness of his research,"
"He has presciently documented the harms inflicted by globalism on American workers, and laid out a path forward to restore our middle class. He will fulfill an essential role in my administration as a trade advisor."
出版のタイミングからみて、トランプ大統領はこの本を読んで感銘を受けたのだと思います。
この本があることは数年前から知っていたのですが、タイトルが過激なものですから「ちょっとトンデモ系の本なのかな」と思って敬遠していました。でも、ちょっとトンデモな人が大統領になって、しかも著者が重用されているということなので、急いで読んでみた次第です。
いかに中国が悪い国かということを啓蒙するために書いた本のようです。”Death by China”というタイトルは誇張して付けたわけではないようで、実際に中国製品の欠陥でたくさんの人が死んでいるとか、中国国内の人権弾圧でたくさんの人が死んでいるとか、中国の環境汚染はたくさんの人を殺しているとか、そういった話がたくさん出てきます。天安門広場の事件もその一例です。さらに中国の軍事力拡大や宇宙開発の促進が米国にとっての安全保障上の脅威になっているという分析もされています。
で、そういった例のなかに、中国が為替操作や企業に対する補助金で輸出価格を不正に引き下げて、米国の製造業に大きな打撃を与えてきたという批判も含まれています。ナバロ氏は中国の経済政策には外国の製造業を破壊する狙いがあるとして、”Eight Weapons of Job Destruction”と名付けた8つの問題点を挙げています。
・違法な輸出補助金
・為替操作
・知的財産の盗用
・緩い環境規制
・緩い労働規制
・違法な関税、輸入割当などの障壁
・ダンピング
・外国企業の進出を拒む規制
こういった話は別にナバロ氏だけが指摘しているわけじゃなくて、オバマ政権下での対中国外交でも繰り返し問題にされてきました。中国の経済政策について詳しいわけじゃないですが、米国企業からそういった不満が出ていることは間違いないです。
ただ、オバマ政権下では「そういった問題はあるけれども、時間をかけて解決を探っていきましょう。気候変動問題とかでは協力できる余地はあるよね」という立場でしたが、ナバロ氏は「こうした問題は非常に大事なことだから、時間をかけて解決するなんていう生ぬるいことではないけない。即刻解決するべきだ」という立場をとっています。もう中国のことなんて、1ミリも信用していないという感じです。
ナバロ氏はこうした問題点がある中国に対して、米国が自由貿易の精神で関わることは大きな間違いだとしています。
“While free trade is great in theory, it rarely exists in the real world. Such conditions are no more found on Earth than the airless, frictionless realm assumed by high-school physics text. In the case of China v. the United States, this seductive free trade theory is very much like a marriage: It doesn’t work if one country cheats on the other.”
ということです。ナバロ氏の結婚生活も気になるところですが、「自由貿易なんてものは存在しないんだ」という主張は分かります。”The Undoing Project”でも経済学の前提自体が間違っているという話があっただけに、経済学の理論ばかりを重視するのもどうかなと思います。
また、ナバロ氏は製造業というのは国家にとって極めて重要だとして、4つの理由を挙げています。
・製造業はサービス業よりも雇用創出効果が大きい。建設とか金融とか小売りとか運輸とかにも影響が広がっていくから。
・製造業の賃金は平均よりも高い。特に女性やマイノリティへのチャンスとなる。
・製造業が強いと、技術革新も進む。長期的に強い経済を維持できるようになる。
・ボーイング、キャタピラー、GMなどの巨大な製造業企業に依存する中小企業がたくさんある。
こういった主張もよくあります。何もナバロ氏だけが極端な話をしているわけではありません。
あと、これまでに読んだ本のなかでも、米国の製造業で働く人たちが高い誇りを抱いているっていう話もよく出てきました。「製造業が衰退すれば、サービス業で働けばいいじゃないか」っていうのは理屈としてはそうかもしれませんが、製造業で働くのが性に合っている人もいます。「製造業は大事」というのはその通りだと思います。
つまり、製造業はものすごく大事なのに、米国の製造業が中国の不正によって衰退させられているから、これは何としてでも解決せねばならないということですね。うん。分かります。
ナバロ氏はこんなことも言っています。
“When America runs a chronic trade deficit with China, this shaves critical points off our economic growth rate. This slower growth rate, in turn, thereby reduces the number of jobs America creates.”
“If America wants to reduce its overall trade deficit to increase its growth rate and create more jobs, the best place to start is with currency reform with China!”
貿易赤字が成長率を引き下げる要因であることは分かります。これは統計上の定義の話です。ただ、成長率が低ければ雇用増のペースが鈍るとか、中国の為替操作をやめさせれば貿易赤字が減るといった理屈が正しいのかどうかは分かりません。それこそ経済学の理論ではそういうことになるのかもしれませんが、実際の世界ではそんなことにはならないなんていう反論もあるんじゃないでしょうか。
まぁ、とはいえ、トランプ大統領に重用されている人物がこう考えているということは間違いないです。
あと、中国政府が多くの米国債を保有するために、以下のような手法をとっているとも指摘しています。
・中国企業は米国への輸出で多くのドルを受け取っている
・中国政府は中国企業に、ドル建ての中国政府債の購入を強要して、ドルを蓄える
・中国政府がドル建ての米国債を購入する
で、中国が米国債をたくさん保有していることは、いざとなったら「米国債を売って、ドル相場を急落させたり、米国の金利を急上昇させてやるぞ」と脅迫できることを意味します。これも割とよく言われることです。また、中国政府が米国債を購入しなければ、米国にとって国債発行の負担が増すわけですから、そもそも米国の財政は中国に依存しているということにもなります。
ナバロ氏は中国が世界中の企業にとっての生産拠点になったきっかけを、1978年に中国共産党が”opened China’s Worker’s Paradise to the West”したことだとしています。中国が何をしたのかは詳しく書いていないですが、カーター政権下で米中共同宣言が出された年ですね。何かあったんだと思いますが、これをきっかけに、おもちゃとかスニーカーとか自転車とか、そういった業種が中国の安い労働力を目当てに製造拠点を移し始めたそうです。
で、2001年に中国がWTOに加盟すると、さらに製造業の移転が進みます。ナバロ氏はこのときは1978年以降とは違い、米国企業は安い労働力だけでなく、中国の補助金とか環境規制の緩さもメリットとして考えていたと主張します。労働力が安い国なら、バングラディシュやカンボジアやベトナムなんていう国もあったことを理由としてあげています。つまりナバロ氏にすれば、米国企業も最初から中国の不正をあてにしていたという意味で、中国と同罪だということです。
そして中国への製造業の移転は現在も続いています。WTO加盟時は生産拠点としての魅力でしたが、今は中国の市場としての魅力も加わっています。中国政府は、外国企業に”minority ownership”しか認めず、”technology transfer”を強要し、研究開発拠点を中国に移すことを強いています。
ナバロ氏はこういう中国の不正な経済活動に対してどんな対応をとればいいのかという提言もしています。
まず、出てくるのが、
“Congress and the President must tell China in no uncertain terms that the United States will no longer tolerate its anything-but-free trade assault on our manufacturing base”
そのうえで、”American Free and Fair Trade Act”を制定するよう求めています。この法律が定めるところは、
“Any nation wishing to trade freely in manufactured goods with the United States must abandon all illegal export subsidies, maintain a fairly valued currency, offer strict protections for intellectual property, uphold environmental and health and safety standards that meet international norms, provide for an unrestricted global market in energy and raw materials, and offer free and open access to its domestic markets, including media and Internet services”
ということだそうです。
ナバロ氏は中国を名指ししているわけじゃなから、直接的な対決は避けられるとしていますが、これまでのナバロ氏の主張からして、「中国とは自由貿易できません」と宣言するのと同じことだと思います。
あと、ナバロ氏は欧州、ブラジル、日本、インド、その他の中国の不正な経済政策の被害にあっている国々と共に、WTOに対して中国にルールを遵守させるよう訴えるともしています。
さらに為替操作については、中国がそう簡単に止めるわけもないと認めていて、水面下での米中交渉を進めるべきだとしています。で、この際に、中国に伝える内容は、
“The United States will have no other choice than to brand China a currency manipulator at the next biennial Treasury Review and impose appropriate countervailing duties unless China strengthens its currency to fair value on its own”
ということです。つまり中国に対して自ら人民元安を是正しないなら、対抗措置として関税をかけるぞと脅すということですね。
でも、中国が脅しに応じない可能性だってあるわけです。その場合は、
“Of course, if China fails to act in a timely manner, the Department of the Treasury must follow through on branding China a currency manipulator and impose appropriate defensive duties to bring the Chinese yuan to fair value”
だそうです。もう貿易戦争やむなしって感じですね。
こうしたナバロ氏の立場に対しては、「米国の製造業が安価な労働力を求めて海外に流出することは避けられないことだし、中国との貿易赤字を解消したって、どうせベトナムとかインドとかバングラみたいな国の製造業が儲かるだけでしょ」なんていう批判があります。まぁ、そうなんだろうな、とも思います。
しかしナバロ氏は反論します。
“We believe the American companies and workers can compete with any in the world on a level playing field, particularly manufacturing where automation and ingenuity often trump manual labor”
そして例え、中国に不正を改めさせることがベトナムとかインドとかバングラに潤いをもたらすだけだったとしても、それはそれで素晴らしいことじゃないかとも言っています。とにかく不正なことをしている中国が世界経済の真ん中に居座っていることは、極めて不健全で、危険なことだというわけです。
この本では中国のサイバー攻撃とか人権問題とか通商政策以外の点についても解決策を提言しています。それぞれ過激だったり、面白かったりしますが、割愛。
まとめますと、ナバロ氏は中国のことを全く信頼していません。後書きでは1989年の天安門事件以降の中国を、ナチ政権下のドイツやスターリン政権下のソ連と同じ扱いにしています。さらに中国による宇宙開発の章なんかでは、”There’s a Death Star Pointing at Chicago”なんていうタイトルもあったりして、中国は銀河帝国と同じぐらい悪いわけです。だから貿易戦争も辞さないというのも当然といえば当然の話です。ちょっと言い過ぎなんじゃないかという気もします。
ただ、「米国に製造業を取り戻す」というのはまともな主張だと思います。グローバリゼーションの進展していった時期と、先進国経済が元気がなくなっていった時期は重なっているわけで、何かしらの関係があるんじゃないかと主張する気持ちは分かります。そんななかでも米国経済は頑張ってきたわけですけど、ここにきてトランプ大統領という強烈なキャラクターが登場したことで、「中国みたいな国があることを考えれば、グローバリズムが常に正しいわけではない」という考え方が表に出てきたということになるんだと思います。
ただ、中国にとっては現在の状況は居心地のいいものであるわけで、中国は現状の変更は望んでいない。日米欧が結束して、中国をWTOから追い出すとか、逆にWTOから出て行って新しい通商圏を作ってしまうとか、そんな「貿易大戦争」っていうシナリオもあるのかもしれませんが、そうなっちゃうと、どうなっちゃうんだという感じもします。
トランプ大統領が「ソ連を崩壊させたレーガン」のイメージを追って、「中国共産党による経済支配を終わらせたトランプ」みたいな路線を目指したりして。実際にそうするかどうかは別にして、トランプ大統領の脳裏にそんなシナリオがないわけじゃないんだと思います。
トランプ大統領は2016年12月21日にナバロ氏をNTCのトップに任命すると発表したときの声明で、こんな風に述べています。
“I read one of Peter’s books on America’s trade problems years ago and was impressed by the clarity of his arguments and thoroughness of his research,"
"He has presciently documented the harms inflicted by globalism on American workers, and laid out a path forward to restore our middle class. He will fulfill an essential role in my administration as a trade advisor."
出版のタイミングからみて、トランプ大統領はこの本を読んで感銘を受けたのだと思います。
この本があることは数年前から知っていたのですが、タイトルが過激なものですから「ちょっとトンデモ系の本なのかな」と思って敬遠していました。でも、ちょっとトンデモな人が大統領になって、しかも著者が重用されているということなので、急いで読んでみた次第です。
いかに中国が悪い国かということを啓蒙するために書いた本のようです。”Death by China”というタイトルは誇張して付けたわけではないようで、実際に中国製品の欠陥でたくさんの人が死んでいるとか、中国国内の人権弾圧でたくさんの人が死んでいるとか、中国の環境汚染はたくさんの人を殺しているとか、そういった話がたくさん出てきます。天安門広場の事件もその一例です。さらに中国の軍事力拡大や宇宙開発の促進が米国にとっての安全保障上の脅威になっているという分析もされています。
で、そういった例のなかに、中国が為替操作や企業に対する補助金で輸出価格を不正に引き下げて、米国の製造業に大きな打撃を与えてきたという批判も含まれています。ナバロ氏は中国の経済政策には外国の製造業を破壊する狙いがあるとして、”Eight Weapons of Job Destruction”と名付けた8つの問題点を挙げています。
・違法な輸出補助金
・為替操作
・知的財産の盗用
・緩い環境規制
・緩い労働規制
・違法な関税、輸入割当などの障壁
・ダンピング
・外国企業の進出を拒む規制
こういった話は別にナバロ氏だけが指摘しているわけじゃなくて、オバマ政権下での対中国外交でも繰り返し問題にされてきました。中国の経済政策について詳しいわけじゃないですが、米国企業からそういった不満が出ていることは間違いないです。
ただ、オバマ政権下では「そういった問題はあるけれども、時間をかけて解決を探っていきましょう。気候変動問題とかでは協力できる余地はあるよね」という立場でしたが、ナバロ氏は「こうした問題は非常に大事なことだから、時間をかけて解決するなんていう生ぬるいことではないけない。即刻解決するべきだ」という立場をとっています。もう中国のことなんて、1ミリも信用していないという感じです。
ナバロ氏はこうした問題点がある中国に対して、米国が自由貿易の精神で関わることは大きな間違いだとしています。
“While free trade is great in theory, it rarely exists in the real world. Such conditions are no more found on Earth than the airless, frictionless realm assumed by high-school physics text. In the case of China v. the United States, this seductive free trade theory is very much like a marriage: It doesn’t work if one country cheats on the other.”
ということです。ナバロ氏の結婚生活も気になるところですが、「自由貿易なんてものは存在しないんだ」という主張は分かります。”The Undoing Project”でも経済学の前提自体が間違っているという話があっただけに、経済学の理論ばかりを重視するのもどうかなと思います。
また、ナバロ氏は製造業というのは国家にとって極めて重要だとして、4つの理由を挙げています。
・製造業はサービス業よりも雇用創出効果が大きい。建設とか金融とか小売りとか運輸とかにも影響が広がっていくから。
・製造業の賃金は平均よりも高い。特に女性やマイノリティへのチャンスとなる。
・製造業が強いと、技術革新も進む。長期的に強い経済を維持できるようになる。
・ボーイング、キャタピラー、GMなどの巨大な製造業企業に依存する中小企業がたくさんある。
こういった主張もよくあります。何もナバロ氏だけが極端な話をしているわけではありません。
あと、これまでに読んだ本のなかでも、米国の製造業で働く人たちが高い誇りを抱いているっていう話もよく出てきました。「製造業が衰退すれば、サービス業で働けばいいじゃないか」っていうのは理屈としてはそうかもしれませんが、製造業で働くのが性に合っている人もいます。「製造業は大事」というのはその通りだと思います。
つまり、製造業はものすごく大事なのに、米国の製造業が中国の不正によって衰退させられているから、これは何としてでも解決せねばならないということですね。うん。分かります。
ナバロ氏はこんなことも言っています。
“When America runs a chronic trade deficit with China, this shaves critical points off our economic growth rate. This slower growth rate, in turn, thereby reduces the number of jobs America creates.”
“If America wants to reduce its overall trade deficit to increase its growth rate and create more jobs, the best place to start is with currency reform with China!”
貿易赤字が成長率を引き下げる要因であることは分かります。これは統計上の定義の話です。ただ、成長率が低ければ雇用増のペースが鈍るとか、中国の為替操作をやめさせれば貿易赤字が減るといった理屈が正しいのかどうかは分かりません。それこそ経済学の理論ではそういうことになるのかもしれませんが、実際の世界ではそんなことにはならないなんていう反論もあるんじゃないでしょうか。
まぁ、とはいえ、トランプ大統領に重用されている人物がこう考えているということは間違いないです。
あと、中国政府が多くの米国債を保有するために、以下のような手法をとっているとも指摘しています。
・中国企業は米国への輸出で多くのドルを受け取っている
・中国政府は中国企業に、ドル建ての中国政府債の購入を強要して、ドルを蓄える
・中国政府がドル建ての米国債を購入する
で、中国が米国債をたくさん保有していることは、いざとなったら「米国債を売って、ドル相場を急落させたり、米国の金利を急上昇させてやるぞ」と脅迫できることを意味します。これも割とよく言われることです。また、中国政府が米国債を購入しなければ、米国にとって国債発行の負担が増すわけですから、そもそも米国の財政は中国に依存しているということにもなります。
ナバロ氏は中国が世界中の企業にとっての生産拠点になったきっかけを、1978年に中国共産党が”opened China’s Worker’s Paradise to the West”したことだとしています。中国が何をしたのかは詳しく書いていないですが、カーター政権下で米中共同宣言が出された年ですね。何かあったんだと思いますが、これをきっかけに、おもちゃとかスニーカーとか自転車とか、そういった業種が中国の安い労働力を目当てに製造拠点を移し始めたそうです。
で、2001年に中国がWTOに加盟すると、さらに製造業の移転が進みます。ナバロ氏はこのときは1978年以降とは違い、米国企業は安い労働力だけでなく、中国の補助金とか環境規制の緩さもメリットとして考えていたと主張します。労働力が安い国なら、バングラディシュやカンボジアやベトナムなんていう国もあったことを理由としてあげています。つまりナバロ氏にすれば、米国企業も最初から中国の不正をあてにしていたという意味で、中国と同罪だということです。
そして中国への製造業の移転は現在も続いています。WTO加盟時は生産拠点としての魅力でしたが、今は中国の市場としての魅力も加わっています。中国政府は、外国企業に”minority ownership”しか認めず、”technology transfer”を強要し、研究開発拠点を中国に移すことを強いています。
ナバロ氏はこういう中国の不正な経済活動に対してどんな対応をとればいいのかという提言もしています。
まず、出てくるのが、
“Congress and the President must tell China in no uncertain terms that the United States will no longer tolerate its anything-but-free trade assault on our manufacturing base”
そのうえで、”American Free and Fair Trade Act”を制定するよう求めています。この法律が定めるところは、
“Any nation wishing to trade freely in manufactured goods with the United States must abandon all illegal export subsidies, maintain a fairly valued currency, offer strict protections for intellectual property, uphold environmental and health and safety standards that meet international norms, provide for an unrestricted global market in energy and raw materials, and offer free and open access to its domestic markets, including media and Internet services”
ということだそうです。
ナバロ氏は中国を名指ししているわけじゃなから、直接的な対決は避けられるとしていますが、これまでのナバロ氏の主張からして、「中国とは自由貿易できません」と宣言するのと同じことだと思います。
あと、ナバロ氏は欧州、ブラジル、日本、インド、その他の中国の不正な経済政策の被害にあっている国々と共に、WTOに対して中国にルールを遵守させるよう訴えるともしています。
さらに為替操作については、中国がそう簡単に止めるわけもないと認めていて、水面下での米中交渉を進めるべきだとしています。で、この際に、中国に伝える内容は、
“The United States will have no other choice than to brand China a currency manipulator at the next biennial Treasury Review and impose appropriate countervailing duties unless China strengthens its currency to fair value on its own”
ということです。つまり中国に対して自ら人民元安を是正しないなら、対抗措置として関税をかけるぞと脅すということですね。
でも、中国が脅しに応じない可能性だってあるわけです。その場合は、
“Of course, if China fails to act in a timely manner, the Department of the Treasury must follow through on branding China a currency manipulator and impose appropriate defensive duties to bring the Chinese yuan to fair value”
だそうです。もう貿易戦争やむなしって感じですね。
こうしたナバロ氏の立場に対しては、「米国の製造業が安価な労働力を求めて海外に流出することは避けられないことだし、中国との貿易赤字を解消したって、どうせベトナムとかインドとかバングラみたいな国の製造業が儲かるだけでしょ」なんていう批判があります。まぁ、そうなんだろうな、とも思います。
しかしナバロ氏は反論します。
“We believe the American companies and workers can compete with any in the world on a level playing field, particularly manufacturing where automation and ingenuity often trump manual labor”
そして例え、中国に不正を改めさせることがベトナムとかインドとかバングラに潤いをもたらすだけだったとしても、それはそれで素晴らしいことじゃないかとも言っています。とにかく不正なことをしている中国が世界経済の真ん中に居座っていることは、極めて不健全で、危険なことだというわけです。
この本では中国のサイバー攻撃とか人権問題とか通商政策以外の点についても解決策を提言しています。それぞれ過激だったり、面白かったりしますが、割愛。
まとめますと、ナバロ氏は中国のことを全く信頼していません。後書きでは1989年の天安門事件以降の中国を、ナチ政権下のドイツやスターリン政権下のソ連と同じ扱いにしています。さらに中国による宇宙開発の章なんかでは、”There’s a Death Star Pointing at Chicago”なんていうタイトルもあったりして、中国は銀河帝国と同じぐらい悪いわけです。だから貿易戦争も辞さないというのも当然といえば当然の話です。ちょっと言い過ぎなんじゃないかという気もします。
ただ、「米国に製造業を取り戻す」というのはまともな主張だと思います。グローバリゼーションの進展していった時期と、先進国経済が元気がなくなっていった時期は重なっているわけで、何かしらの関係があるんじゃないかと主張する気持ちは分かります。そんななかでも米国経済は頑張ってきたわけですけど、ここにきてトランプ大統領という強烈なキャラクターが登場したことで、「中国みたいな国があることを考えれば、グローバリズムが常に正しいわけではない」という考え方が表に出てきたということになるんだと思います。
ただ、中国にとっては現在の状況は居心地のいいものであるわけで、中国は現状の変更は望んでいない。日米欧が結束して、中国をWTOから追い出すとか、逆にWTOから出て行って新しい通商圏を作ってしまうとか、そんな「貿易大戦争」っていうシナリオもあるのかもしれませんが、そうなっちゃうと、どうなっちゃうんだという感じもします。
トランプ大統領が「ソ連を崩壊させたレーガン」のイメージを追って、「中国共産党による経済支配を終わらせたトランプ」みたいな路線を目指したりして。実際にそうするかどうかは別にして、トランプ大統領の脳裏にそんなシナリオがないわけじゃないんだと思います。
2016年12月18日日曜日
Exorbitant Privilege
“Exorbitant Privilege”という本を読んだ。Barry Eichengreenというカリフォルニア大学バークリー校の教授(政治経済史)が書いた、米ドルが国際基軸通貨であることの意味と今後について書いた本です。非常に面白かった。
読み終わったのは10月のなかばごろです。とてもためになる本だったので、なるべく詳しく内容をまとめておこうと思ったのですが、書いているうちに膨大な量になることに気づいてほったらかしになっていました。とりあえず、途中までの内容を仕上げておきます。
国際基軸通貨というと、分かったような分からないような概念なわけですが、要は「世界中の人が安心して受け取ってくれる通貨」ということです。著者は冒頭で、このことを分かりやすい例を挙げて説明しています。
それは、
・1940年代を舞台にした映画で、ホロコーストの生還者がモンテカルロのカジノにスーツケース一杯の現金を持ち込むシーンがある。その現金は当時のモンテカルロの公式な通貨であったフランではなくて、米ドルだった。
・現在でもブラックマーケットで通用する通貨といえば米ドルでしかない。
分かりやすいですね。第二次世界大戦のころの欧州のような政治的にも経済的にも混乱している場所で、人々が安心して価値を認めるものといえば米ドルだった。また、ブラックマーケットのような公式な権威がない世界でもやはり米ドルが信頼される。そりゃそうでしょう。ブラックマーケットでドラッグを取引するとき、北朝鮮かなんかの通貨で支払いをするといったら怒られますよね。
で、なんで米ドルが信頼されるかというと、世界中のどこででも受け取ってもらえるからです。ドラッグを売ったギャングが受け取った米ドルでマシンガンを買おうと思ったら、やっぱり米ドルでの支払いを要求されるわけですね。米ドルの価値は他の通貨に比較的安定した価値で交換してもらえると信じられていることも理由です。ギャングがフランスのニースかなんかで別荘を買おうと思ったとき、米ドルをユーロに交換してもらうことは難しくない。それにギャングは為替レートがそんなに急激に米ドル安に触れることはないだろうとも考えているわけです。もちろん実際には米ドルが安くなることはあるわけですが、それでもユーロを含めた他の通貨よりも安定しているということですね。
で、著者は、
“What is true of illicit transaction is true equally of legitimate business.”
と続けます。米ドルが国際通貨であるこということは、世界中の政府や中央銀行や企業や消費者が、ギャングたちと同じように考えているということです。なるほど。
実際の話として、世界の中央銀行が保有している準備資産の多くは米ドルです。米ドルの価値が安定してると考えられているからですね。世界で行われている商取引の多くが米ドルなのも、米ドルを受け取れば、それを支払いにも使えるからです。
で、なんでそんな風になっているかというと、米国の経済が大きいからです。
米国企業はたくさんの製品や資源を輸入しています。このとき、米国は米ドル建てで支払いをしたい。なぜなら、米国企業は米国内での経済活動で米国の消費者からたくさんの米ドルを集めていて、手元にたくさん米ドルがあるからです。もちろん米ドルを他国の通貨に交換したうえで支払うことも可能ですが、それには手間がかかるし、金融機関に手数料もとられます。
一方、製品や資源を米国に輸出する側の国は、できれば自分たちの国の通貨でお金を受け取りたい。米ドルを受け取っても、自国で働いている従業員の賃金支払いには使えないし、自国の生産拠点の設備投資には使えないからです。そのためには、米ドルを自国通貨に交換しなければならないわけですが、それには手間もかかるし、金融機関に手数料もとられます。
で、どっちの主張が通るかというと、米国なのです。というのは、米国はたくさんの製品や資源やサービスを輸出している国でもあるからです。米国に製品や資源を輸出する側が米ドル建てで代金を受け取った場合、今度はその米ドルを米国から製品や資源やサービスを輸入するときに使える。だから、米ドルを受け取ることへの抵抗感が比較的少ないわけです。
つまり、米国にモノを売る国が米国から「米ドルで支払っていい?」と聞かれたら、「いいよ。受けとった米ドルは次に米国からモノを買うときに使えるからね」と答えることが多いということですね。
これが米ドルが国際基軸通貨であるという状況です。この結果、米国企業は米ドルを他国通貨に交換する手間やその際の手数料を省くことができます。これが著者のいう”exorbitant privilege”のひとつです。この言葉は、フランスのジスカール・デスダンが言い出した言葉だそうです。
こうした米国の特権はほかにもあります。それは米ドルが国際基軸通貨であることで、米国の政府や企業は安い金利で資金を調達できるということです。
どういうことかというと、米ドルは国際的に流通して、他の通貨との交換も容易で、すでに各国に蓄えられていますから、米国がドル建てでお金を借りたくなったとき、世界中から「貸してもいいよ」という人たちがたくさん現れます。だから、米国側はそのなかから一番安い金利で貸してくれる人をみつけることができるというわけです。
一方で米国は他国に対して投資もしていて、その結果として利子や配当などのリターンを得ています。つまりは米国は全体として、他国からお金を調達しながら、他国へお金を投資しているわけですが、調達するときのコストが安いために、全体としての勘定がプラスになります。著者によると、「米国が支払う利子は、米国が受け取る利回りよりも2~3%低い」とのことです。
著者はこの説明のあと、”The U.S. can run an external deficit in the amount of this difference, importing more than it exports and consuming more than it produces year after year without becoming more indebted to the rest of the world. Or it can scoop up foreign companies in the amount as the result of the dollar’s singular status as the world’s currency.”と続けています。
ここは国際収支統計上の、経常収支赤字=資本収支黒字+外貨準備増減っていう関係の話をしているように思います。でも、「米ドルは基軸通貨で調達コストが安いから、経常赤字を出すことができる」っていうロジックになるのかどうかはよく分かりません。大事なところですけどね。また勉強します。
とまぁ、こういう風に米国は米ドルが国際基軸通貨であることで、さまざまな特権を得ているということになります。ただ米ドルが国際基軸通貨である理由は、米国経済が大きいからです。だから、米国は何もズルをしているわけじゃなくて、強い国だから特をしているんだというわけですね。
では、この米ドル国際基軸通貨体制が今後も続いていくかということになるわけですが、それを判断するには歴史をひもとく必要があります。なぜなら米ドルは世界が始まったときから国際基軸通貨だったわけではないからです。
当たり前の話ですが、北米大陸に欧州から人々が移住し始めたころには米ドルという通貨はありませんでした。1600年代の初めごろは、先住民との交易には”wampum”(貝殻)を公式な通貨として使っていたそうです。
ところが貝殻が足りなくなってくると、トウモロコシやタバコが使われるようになります。そして、そうなると、入植者たちには低い品質のタバコをたくさん栽培し始めます。そうすると、タバコを受け取る方は「こんな低い品質のタバコはいらないな」なんていうことになって、タバコの価値が低下する。となると一部の入植者が他の人のタバコ畑を荒らしたりする。そんな時代だったそうです。
当時の英国は植民地で貨幣を鋳造することを禁止していました。だから入植者たちが貨幣を手に入れるには、英国などに農産品とか魚などを輸出するのが公式な手段でした。また海賊行為で貨幣を手に入れるというパターンもあった。こうして北米大陸ではスペインの通貨が流通するようになります。このスペインの通貨がロンドンでは”Spanish dollar”と呼ばれていて、これが米ドルの始まりです。さらに貨幣が足りなくなってくると、”bills of credit”つまりは支払手形も通貨の代わりとして流通するようになります。ただし、英国の議会は1751年、借用書を通貨として使うことを禁止。このことが米国の独立戦争につながっていきます。
ここは勝手な解釈ですけど、「貝殻が足りない」とか「貨幣が足りない」とかいう状況がどんなものかを考えてみます。
例えば、入植者たちが先住民にビーバーの毛皮が欲しいと話しを持ちかけたところ、先住民たちが「貝殻とだったら交換してもいい」と言ったとします。さらに入植者たちはトウモロコシなら持っているけど、貝殻は持っていないとします。となると、入植者たちはどこかでトウモロコシを貝殻に交換してこなければならないわけですが、近くにトウモロコシと貝殻を交換したいと思っている先住民や入植者がいないことだってある。そんな場合は、入植者が先住民に対して、「申し訳ないけど、貝殻はないんだ。でもトウモロコシならあるから、トウモロコシとビーバーの毛皮を交換してくれないか」と持ちかけるしかない。そこで先住民側が「いいよ。トウモロコシと貝殻を交換したがっている友達がいるからね」ということになれば、「貝殻が足りなかったけど、トウモロコシが貝殻の代わりになって取引が成立した」ということになる。こんな感じでしょうか。
貨幣が足りないという状況も勝手に解釈してみると、陶器作りが得意な入植者が別の入植者からパンを買おうと思ったけれど、手元に貨幣がない。でも、何日か前に陶器を売ったとき、買い手から「1週間後に払うよ」と約束してもらった際の支払い手形なら手元にある。そこでパンを売っている入植者に、「この支払い手形を受け取ってくれないか。貨幣は1週間後に陶器を買った人から回収してよ」ということになる。そこでパンの売り手が「いいよ。その陶器を買った人は信用できる人だからね」ということになれば、「支払い手形が貨幣の代わりになって取引が成立した」ということになる。こんな感じじゃないですかね。
でも、本来ならトウモロコシは貨幣じゃないし、支払い手形も貨幣じゃない。だから受け取る側が「そんなもの受け取れないよ」ということだってありえる。そうなると、ビーバーの毛皮を買おうと思った入植者や、パンを買おうと思った入植者は困ってしまうわけです。その結果、取引ができなくなるわけだから、入植地の経済活動全体が停滞してしまう。トウモロコシや支払い手形をすぐに貝殻や貨幣に交換してくれるだけの市場があればいいんですけどね。
で、そんなこんなしているうちに米国が1776年に独立。1785年に連邦議会が米国の通貨単位は「ドル」ですと宣言します。銀や金との交換比率も純度に応じて定められました。議会のみが貨幣を鋳造することができ、州政府がIOU(借用書)を紙幣として発行することは禁じられます。
そして当たり前の話ですが、当時の米ドルは国際通貨ではありません。
19世紀まで世界経済の中心はロンドンでした。英国人は世界各国に投資しています。外国の誰かがお金を借りたいと思ったら、ロンドンに行ってポンド建てでお金を借ります。外国政府がロンドンで資金を調達したいと思ったら、ロンドンの銀行に口座を開いて、借り入れや返済の手続きをすることになります。こうした口座は”reserve”と呼ばれるようになります。
英国は各国から綿花などさまざまな産品を輸入していました。あと、海運やそれに関連する保険業務などを行う会社もロンドンに拠点を置いています。こうした会社は決済のためにロンドンの銀行に口座を開きます。もちろんポンド建てです。
こうしたロンドン中心の商取引は米国の企業家にとっては不便なものでした。例えば、ニューヨークの企業家がブラジルからコーヒー豆を輸入しようと思ったら、ニューヨークの銀行とロンドンの銀行とブラジルの銀行の間で、ものすごく煩雑な手続きが必要になり、その度に手数料や何やらをとられてしまいます。しかも、これらの取引はポンド建てですから、ポンドの価値がドルに対して下がった場合には損が出る可能性もあります。また、米国の銀行や保険会社がこうした商取引に関連する業務に参入しようとしても、英国の銀行や保険会社には敵いません。取引はロンドンでポンド建てで行われているからです。
一方、米国は急速に経済力をつけていきます。1870年までに米国のモノやサービスの生産量は英国を追い抜き、1912年までには輸出量でも英国をしのぎます。でも、英ポンドは国際基軸通貨であり続けます。
その理由はいろいろありますが、金融サービスの業務が英国に集中し、資金を集めようとする人が投資をしようとする人たちがロンドンに集まっていること自体が、ロンドンの優位性を高めていたという事情が大きかった。つまり市場参加者が多いために、調達する側はより安い金利で調達できるし、投資する側も優良な投資先を見つけられるということです。「現役王者の強み」ですね。
また、米国は銀行が海外に支店を持つことを禁じていました。さらに米国では中央銀行すらないという状況だった。ロンドンでは銀行が現金を必要とするようになれば、手持ちの債券をBOEに引き受けてもらって現金を手にすることができましたが、米国ではそうしたことができなかったわけです。
米国では1791年、ハミルトンが主導してフィラデルフィアにthe Bank of the United Statesが設立されました。州をまたいで営業できる唯一の銀行で、連邦政府の財政も管理することになります。ハミルトンの狙いはBOEのような中央銀行を作ることでした。しかしジェファーソンやマディソンは、一部の銀行に特権的な地位を与えることについて、「エリートによる米国金融業界の独占支配」の危険を感じ取ります。The Bank of the United Statesが提示するレートが悪かったり、一部の銀行の独占的な地位に監視の目をきかせるようになると、「エリートによる介入だ」と不満を感じるようになったわけです。
そんなわけで、1810年に迎えたThe Bank of the United Statesの認可の更新は、ジェファーソンが主導する民主党の反対で否決されました。
しかしその結果、各州の銀行が勝手に紙幣を発行したりして空前の貸出ブームとなり、インフレが起き、景気はクラッシュします。で、1816年になって、Second Bank of the United Statesがフィラデルフィアに設立されることになりました。しかしこのSecond Bankもジャクソン大統領と金融業界の反対で1836年に認可の更新に失敗。米国は再び中央銀行がない時代に入ります。1907年に起きた金融危機の収束に際して、民間銀行のトップだったJ. Pierpont Morganが大きな役割を果たしたのには、こうした米国の事情がありました。
で、やっぱり中央銀行が必要だろうという機運が盛り上がり、中央銀行支持のNelson Aldrich上院議員らのグループがドイツ生まれのPaul Warburgに計画策定を託します。一部の銀行にだけ特権を与えるような制度には反対が強いことを考慮して、ウォーバーグは1911年、それぞれが債券引き受けの権限を持った15の地域銀行で構成されるNational Reserve Associationの設立計画を発表。各銀行のトップは地域の民間銀行によって選ばれるという仕組みを公表しました。
ただ、Aldrichの娘がロックフェラー家に嫁いでいたことから、この計画には「ロックフェラーを利するだけのものだろう」という印象を持たれてしまいます。また計画を策定したグループのなかにNational City Bank(シティグループの前身)のトップが含まれていたことも疑念をかきたてました。しかしその後、約2年間の審議を経て、トップが民間銀行によって選ばれる地区銀行の連合体を作り、それにFederal Reserve Boardが監視の目を光らせるという体制が作られることになりました。1913年のことです。同時に米国の銀行が海外に支店を持つことも認められるようになりました。
その後、第一次世界大戦が始まると、米国の輸出は急増。世界経済における米国の存在感は急速に大きくなって、米国は債務国から債権国に転じます。戦争で現金が足りなくなったドイツや英国は債券の引き受けをニューヨークの銀行に頼むようになります。この取引はドル建てで行われるようになりました。1915年ごろにはポンドと金の交換レートが不安定になる一方で、米ドルは金との交換レートが強く固定されていました。すると世界中の市場参加者が「ビジネスをするにはドル建てが一番だ」と考えるようになります。
米国政府はとりあえずはドル・ポンドレートの維持に協力しますが、英国の戦費拡大やインフレを背景にポンドに対する信頼は失墜。戦後になって米国がレート維持への協力を取り下げると、ポンドのレートは弱くなっていきます。こうしたなかで、National City Bankなど米国の銀行が海外業務を拡大していきます。
ただ、それでもニューヨークの債券市場の深みは、現役王者のロンドンには敵いません。そこでニューヨーク連銀の総裁だったBenjamin Strongが各地区連銀に対して債券を活発に引き受けるように指示。海外の中央銀行などからも債券を引き受けるようになります。こうした取り組みの結果、ドル建て取引の人気は高まり、1920年代後半には米国の輸出入の半分以上がドル建てとなり、米国を介さない第三国同士での取引でもドル建ての比率が増していきます。
また米国は欧州の復興資金を供給するようになります。英国は欧州各国に「米国ではなく、国際連盟(米国は非加盟)を通じて資金を調達しよう」と呼びかけますが、ストロングは欧州への貸出を積極的に推進することで対抗し、ドルの国際化がどんどん進んでいくことになりました。
しかし経験不足の米国の銀行は欧州の質の悪いプロジェクトにも資金を供給してしまい不良債権化が進行。1920年代の終わりには借り換えも続けられないようになって、世界恐慌につながっていくことになります。
世界恐慌の時代、各国政府は関税引き上げなどの保護主義的な政策をとり、世界の貿易量が減っていきます。貸し付けを回収できなくなった銀行は世界中で破綻。世界中というのは、アルゼンチン、メキシコ、オーストリア、ベルギー、フランス、ドイツ、ハンガリー、ルーマニア、バルト各国、エジプト、トルコ、英国っていうことですから、本当に世界中です。
英国なんかは資金流出を防ぐために利上げをしたいところでしたが、利上げをすると景気に悪影響が出ます。英国のためらいを察した投資家はポンド売りを加速させ、英国は1931年9月にポンドの金兌換を停止します。一方、ニューヨーク連銀はドル防衛のため、利上げを実施。結果、ドルの資金流出の危機は収まりますが、調達コストが増した金融機関は数多く破綻することになります。
英米の異なる金融政策の結果、1ポンド=4.86ドルだったレートは、1931年12月には1ポンド=3.25ドルまでポンド安が進みました。すると英国にとっては輸出が楽になるわけで、英国で緩やかな景気回復が始まります。英国はこれを好機とみて、利下げに踏み切って"cheap money"政策をとります。米国も1933年に金兌換を停止。1936年までには各国も同様の政策をとります。世界恐慌のダメージは英国よりも米国の方が大きく、長かったため、国際経済におけるドルの地位は後退しました。
しかし第二次世界大戦後の世界は別です。世界の主要国のなかで強さを維持できたのは米国だけだったからです。米国は金1オンスを35ドルで売ると約束したため、価値が保証されたドルは世界中の取引で使用されることになります。また、各国の中央銀行は金を蓄えるという選択肢もありましたが、当時の主な金の産出国はソ連と南アフリカで、金は十分に供給されていませんでした。
で、ここがキモですが、著者は
American consumers and investors could acquire foreign goods and companies without their government having to worry that the dollar used in their purchases would be presented for conversion into gold. Instead those dollars were hoarded by central banks, for which they were the only significant source of additional international reserves. America was able to run a balance-of-payments deficit "without tears," in the words of the French economist Jacques Rueff. This ability to purchase foreign goods and companies using resources conjured out of thin air was the exorbitant privilege of which French Finance Minister Valery Giscard d'Estaing so vociferously complained.
と書いています。
訳しますと、
米国の消費者や投資家が外国の製品や企業を買った場合でも、米国政府は(海外の売り手から)支払いに使われたドルを金に交換するように要求されることを心配する必要もなかった。むしろ、支払いに使われたドルは海外の中央銀行に蓄えられた。こうした取引は海外の中央銀行にとって、準備資金を調達するための唯一の手段だった。フランスの経済学者、ジャック・ルエフの言葉を借りるなら、米国は「涙を流すことなしに」貿易赤字を出すことができる。空気のなかから魔法のように取り出された資金を使って外国の製品や企業を買うことができる能力は、フランスのジスカール・デスタン財務相が強く不満を示した途方もない特権だった。
ということですね。
つまり、米国だけが自国通貨であるドルを発行しさえすれば、自由に他国から物資を買うことができるという状況です。
ただし第二次世界大戦後の各国は米国に売るような製品を作ることはできない状況です。なので米国はマーシャルプランやドッジプランのようなかたちで、欧州や日本の復興のための資金を拠出します。マーシャルプランは1年目、米国の連邦予算の10%を占める規模でしたから、とんでもない大盤振る舞いでした。この結果、1950年代の終わりには「ドル不足」は解消されます。
それと並行して、1960年には、各国が保有するドルの額は米国が保有する金の量を超えました。各国のドル保有者が一斉に金への兌換を求めれば、米国は対応しきれない状況で、このままでは各国が保有するドルの価値が値下がりする恐れがあります。一方、だからといって米国がドルの供給を止めてしまえば、ドル不足が再燃して世界の経済活動が停滞してしまう。いわゆる「トリフィンのジレンマ」です。
こうしたなか、各国には「米国はドルの金への兌換に応じられるように、先手を打って金の価格を引き上げる(ドル金レートを引き下げる)のではないか」という観測が生じます。そうなると各国は「今のうちにドルを金に交換してしまおう」という誘惑にかられます。
つまり、米国が1オンス=35ドルでの交換を保証しているなか、ロンドン市場での金の取引価格は1オンス=35ドルで推移しています。しかし将来的に米国が金の価格を引き上げるのであれば、今のうちにロンドン市場で金を買っておいて、後になって金を米国に持ち込めば利益を出すことができます。こうした思惑のなかで、ロンドン市場では金の価格が値上がりします。ウィキペディアによると、大統領選があった1960年の終わりにはロンドン市場の金価格は1オンス=40ドルを超えました。
そこで米国は1961年に「金プール」を提案します。各国が金をプールに拠出し、金を買う動きが強まった場合に「金売りドル買い」を浴びせることで、市場での金とドルの交換レートを維持しようという狙いです。こうしたプールを作るだけで、各国の「金買いドル売り」の誘惑を抑え込むこともできます。
しかし1965年になってソ連や南アフリカによる金の供給が落ち込むと、金買いの圧力が強まり、各国は実際に金売りを始めざるをえなくなります。となると、値下がりが続くドルを買い続けることになるわけですから、各国は厳しい状況に追い込まれ、1967年にはフランスがプールから脱退します。
また1967年には第三次中東戦争が起きて、スエズ運河が閉鎖される事態に発展。アラブ各国はイスラエルを支援していた英国への報復としてポンド売りを始め、英国はポンドの14%切り下げに追い込まれます。するとドルへの不安も高まり、ドルを売って金を買う動きが進みます。金プール参加国はドルの防衛を続けることができず、米国は1968年3月、英国に対してロンドンの金市場を閉鎖するように提案。金市場を自由に取引できる市場と、各国の中央銀行が1オンス=35ドルでの交換を保証する市場に分けることになります。ただ、これは単なる弥縫策にすぎません。
一方、1969年にニクソン大統領が就任した米国は、ドル危機は欧州各国が米国の防衛費を負担し、米国に市場を開放することで解消されるべきだという立場をとります。
いまいち、よく分からない理屈ですが、「第二次世界大戦後、米国が世界にドルを供給してきたことがドルの信任低下につながったのだから、ドルを米国に環流させればドル危機も解消される」ということだったのでしょうか。
さらに米国は、欧州が要求に応じない場合には、次の手段をとると脅迫します。すると、こうした米欧の対立は投資家の不安をあおり、米国の思惑とは裏腹にドルを売って金を買う動きが加速。この結果、1971年8月、米国はドルの金兌換停止を発表しました。ニクソン・ショックです。
このとき、ニクソンは同時に米国企業を守るために10%の関税引き上げを発表します。米国が通貨防衛に敗れたとの印象を避ける効果も狙っていました。
ニクソンは1971年12月のスミソニアン協定で、この上乗せ関税を取り下げることと引き替えに、各国に対してドル安水準での固定相場を維持することを約束させます。さらにニクソンは1972年の大統領選前に景気を浮揚させることを狙って、FRBに対して金融緩和するよう圧力をかけます。この結果、米国でインフレが始まり、ドル売り圧力も高まります。スミソニアン体制は1973年に終焉を迎え、各国は変動相場制に移行していきます。
こうなると、「ドルの信頼はガタ落ちじゃないか。ドルは国際基軸通貨の座を追われてしまうの?」っていう気もしますが、実際にはそうはなりませんでした。ゴルのレートは引き下げられたものの、各国の中央銀行に占めるドルの割合は大きく変化しませんでした。変動相場になったといっても、一方的にずーっとドルが値下がりを続けたわけではなかったからです。
ただし、1970年代後半になると、米国でインフレが始まります。ドル安要因です。一方、カーター政権のブルーメンソール財務長官は1977年夏に「ドルが強すぎる」と発言。ドル安を望んでいることを示唆しました。つまり、ドル安を容認するということです。すると、欧州から「ドル安になったら、欧州の輸出が苦しくなる。米国はドル安容認を止めろ」という声があがり、ブルーメンソールは一転して「強いドル」の支持を表明します。
1978年3月にFRB議長になったウィリアム・ミラーはとにかく雇用の増大を重視すべきだという人で、中央銀行がインフレを抑制する能力は乏しいと考えている人でした。FRB外のアラン・グリーンスパンやチャールズ・シュルツらはインフレを抑えるために金融を引き締めるべきだとの声が上がっていましたが、ミラーは抵抗します。すると、当然ながら、ドルが安くなっていきます。ドルが安くなると、欧州に駐留する米軍の負担が大きくなるという問題が起きますし、もちろん米国外のドル保有者にも損が出ます。
そんなわけで1979年8月、ポール・ボルカーがFRB議長に就任します。利上げを行って、ドル高が始まります。やはりドルは基軸通貨であり続けます。そもそも、ドル以外の通貨に、基軸通貨となるような実力がないのが実情です。
で、ここまでが第3章です。この本は第7章まであります。非常に長くなってきたので、このあたりで止めます。
第4章以降では、欧州でユーロが創設される話やリーマン・ショックの話、ユーロや円がドルを凌駕する基軸通貨になりきれない理由などです。SDRの話も結構出てきます。
中国の人民元については第3章までも折に触れて言及されていますが、「国際通貨としての存在感を増してはいるし、中国政府も基軸通貨にしようと努力を続けている。このあたりはかつての米国とよく似ている。ただし、ドルがポンドをしのぐ基軸通貨となれたのは、第二次世界大戦後の英国経済の失墜という要因があった。米国経済が健全さを保ち続けることができれば、現役王者であるドルが人民元に完全に負けてしまうことはない」という話です。
あと、今になってざっとチェックしてたところ、レーガン政権下での1985年のプラザ合意の話が出てきません。日本にとっては非常に大事な話なので残念ですけど、また別の機会に勉強します。
いずれにしろ大変勉強になりました。
読み終わったのは10月のなかばごろです。とてもためになる本だったので、なるべく詳しく内容をまとめておこうと思ったのですが、書いているうちに膨大な量になることに気づいてほったらかしになっていました。とりあえず、途中までの内容を仕上げておきます。
国際基軸通貨というと、分かったような分からないような概念なわけですが、要は「世界中の人が安心して受け取ってくれる通貨」ということです。著者は冒頭で、このことを分かりやすい例を挙げて説明しています。
それは、
・1940年代を舞台にした映画で、ホロコーストの生還者がモンテカルロのカジノにスーツケース一杯の現金を持ち込むシーンがある。その現金は当時のモンテカルロの公式な通貨であったフランではなくて、米ドルだった。
・現在でもブラックマーケットで通用する通貨といえば米ドルでしかない。
分かりやすいですね。第二次世界大戦のころの欧州のような政治的にも経済的にも混乱している場所で、人々が安心して価値を認めるものといえば米ドルだった。また、ブラックマーケットのような公式な権威がない世界でもやはり米ドルが信頼される。そりゃそうでしょう。ブラックマーケットでドラッグを取引するとき、北朝鮮かなんかの通貨で支払いをするといったら怒られますよね。
で、なんで米ドルが信頼されるかというと、世界中のどこででも受け取ってもらえるからです。ドラッグを売ったギャングが受け取った米ドルでマシンガンを買おうと思ったら、やっぱり米ドルでの支払いを要求されるわけですね。米ドルの価値は他の通貨に比較的安定した価値で交換してもらえると信じられていることも理由です。ギャングがフランスのニースかなんかで別荘を買おうと思ったとき、米ドルをユーロに交換してもらうことは難しくない。それにギャングは為替レートがそんなに急激に米ドル安に触れることはないだろうとも考えているわけです。もちろん実際には米ドルが安くなることはあるわけですが、それでもユーロを含めた他の通貨よりも安定しているということですね。
で、著者は、
“What is true of illicit transaction is true equally of legitimate business.”
と続けます。米ドルが国際通貨であるこということは、世界中の政府や中央銀行や企業や消費者が、ギャングたちと同じように考えているということです。なるほど。
実際の話として、世界の中央銀行が保有している準備資産の多くは米ドルです。米ドルの価値が安定してると考えられているからですね。世界で行われている商取引の多くが米ドルなのも、米ドルを受け取れば、それを支払いにも使えるからです。
で、なんでそんな風になっているかというと、米国の経済が大きいからです。
米国企業はたくさんの製品や資源を輸入しています。このとき、米国は米ドル建てで支払いをしたい。なぜなら、米国企業は米国内での経済活動で米国の消費者からたくさんの米ドルを集めていて、手元にたくさん米ドルがあるからです。もちろん米ドルを他国の通貨に交換したうえで支払うことも可能ですが、それには手間がかかるし、金融機関に手数料もとられます。
一方、製品や資源を米国に輸出する側の国は、できれば自分たちの国の通貨でお金を受け取りたい。米ドルを受け取っても、自国で働いている従業員の賃金支払いには使えないし、自国の生産拠点の設備投資には使えないからです。そのためには、米ドルを自国通貨に交換しなければならないわけですが、それには手間もかかるし、金融機関に手数料もとられます。
で、どっちの主張が通るかというと、米国なのです。というのは、米国はたくさんの製品や資源やサービスを輸出している国でもあるからです。米国に製品や資源を輸出する側が米ドル建てで代金を受け取った場合、今度はその米ドルを米国から製品や資源やサービスを輸入するときに使える。だから、米ドルを受け取ることへの抵抗感が比較的少ないわけです。
つまり、米国にモノを売る国が米国から「米ドルで支払っていい?」と聞かれたら、「いいよ。受けとった米ドルは次に米国からモノを買うときに使えるからね」と答えることが多いということですね。
これが米ドルが国際基軸通貨であるという状況です。この結果、米国企業は米ドルを他国通貨に交換する手間やその際の手数料を省くことができます。これが著者のいう”exorbitant privilege”のひとつです。この言葉は、フランスのジスカール・デスダンが言い出した言葉だそうです。
こうした米国の特権はほかにもあります。それは米ドルが国際基軸通貨であることで、米国の政府や企業は安い金利で資金を調達できるということです。
どういうことかというと、米ドルは国際的に流通して、他の通貨との交換も容易で、すでに各国に蓄えられていますから、米国がドル建てでお金を借りたくなったとき、世界中から「貸してもいいよ」という人たちがたくさん現れます。だから、米国側はそのなかから一番安い金利で貸してくれる人をみつけることができるというわけです。
一方で米国は他国に対して投資もしていて、その結果として利子や配当などのリターンを得ています。つまりは米国は全体として、他国からお金を調達しながら、他国へお金を投資しているわけですが、調達するときのコストが安いために、全体としての勘定がプラスになります。著者によると、「米国が支払う利子は、米国が受け取る利回りよりも2~3%低い」とのことです。
著者はこの説明のあと、”The U.S. can run an external deficit in the amount of this difference, importing more than it exports and consuming more than it produces year after year without becoming more indebted to the rest of the world. Or it can scoop up foreign companies in the amount as the result of the dollar’s singular status as the world’s currency.”と続けています。
ここは国際収支統計上の、経常収支赤字=資本収支黒字+外貨準備増減っていう関係の話をしているように思います。でも、「米ドルは基軸通貨で調達コストが安いから、経常赤字を出すことができる」っていうロジックになるのかどうかはよく分かりません。大事なところですけどね。また勉強します。
とまぁ、こういう風に米国は米ドルが国際基軸通貨であることで、さまざまな特権を得ているということになります。ただ米ドルが国際基軸通貨である理由は、米国経済が大きいからです。だから、米国は何もズルをしているわけじゃなくて、強い国だから特をしているんだというわけですね。
では、この米ドル国際基軸通貨体制が今後も続いていくかということになるわけですが、それを判断するには歴史をひもとく必要があります。なぜなら米ドルは世界が始まったときから国際基軸通貨だったわけではないからです。
当たり前の話ですが、北米大陸に欧州から人々が移住し始めたころには米ドルという通貨はありませんでした。1600年代の初めごろは、先住民との交易には”wampum”(貝殻)を公式な通貨として使っていたそうです。
ところが貝殻が足りなくなってくると、トウモロコシやタバコが使われるようになります。そして、そうなると、入植者たちには低い品質のタバコをたくさん栽培し始めます。そうすると、タバコを受け取る方は「こんな低い品質のタバコはいらないな」なんていうことになって、タバコの価値が低下する。となると一部の入植者が他の人のタバコ畑を荒らしたりする。そんな時代だったそうです。
当時の英国は植民地で貨幣を鋳造することを禁止していました。だから入植者たちが貨幣を手に入れるには、英国などに農産品とか魚などを輸出するのが公式な手段でした。また海賊行為で貨幣を手に入れるというパターンもあった。こうして北米大陸ではスペインの通貨が流通するようになります。このスペインの通貨がロンドンでは”Spanish dollar”と呼ばれていて、これが米ドルの始まりです。さらに貨幣が足りなくなってくると、”bills of credit”つまりは支払手形も通貨の代わりとして流通するようになります。ただし、英国の議会は1751年、借用書を通貨として使うことを禁止。このことが米国の独立戦争につながっていきます。
ここは勝手な解釈ですけど、「貝殻が足りない」とか「貨幣が足りない」とかいう状況がどんなものかを考えてみます。
例えば、入植者たちが先住民にビーバーの毛皮が欲しいと話しを持ちかけたところ、先住民たちが「貝殻とだったら交換してもいい」と言ったとします。さらに入植者たちはトウモロコシなら持っているけど、貝殻は持っていないとします。となると、入植者たちはどこかでトウモロコシを貝殻に交換してこなければならないわけですが、近くにトウモロコシと貝殻を交換したいと思っている先住民や入植者がいないことだってある。そんな場合は、入植者が先住民に対して、「申し訳ないけど、貝殻はないんだ。でもトウモロコシならあるから、トウモロコシとビーバーの毛皮を交換してくれないか」と持ちかけるしかない。そこで先住民側が「いいよ。トウモロコシと貝殻を交換したがっている友達がいるからね」ということになれば、「貝殻が足りなかったけど、トウモロコシが貝殻の代わりになって取引が成立した」ということになる。こんな感じでしょうか。
貨幣が足りないという状況も勝手に解釈してみると、陶器作りが得意な入植者が別の入植者からパンを買おうと思ったけれど、手元に貨幣がない。でも、何日か前に陶器を売ったとき、買い手から「1週間後に払うよ」と約束してもらった際の支払い手形なら手元にある。そこでパンを売っている入植者に、「この支払い手形を受け取ってくれないか。貨幣は1週間後に陶器を買った人から回収してよ」ということになる。そこでパンの売り手が「いいよ。その陶器を買った人は信用できる人だからね」ということになれば、「支払い手形が貨幣の代わりになって取引が成立した」ということになる。こんな感じじゃないですかね。
でも、本来ならトウモロコシは貨幣じゃないし、支払い手形も貨幣じゃない。だから受け取る側が「そんなもの受け取れないよ」ということだってありえる。そうなると、ビーバーの毛皮を買おうと思った入植者や、パンを買おうと思った入植者は困ってしまうわけです。その結果、取引ができなくなるわけだから、入植地の経済活動全体が停滞してしまう。トウモロコシや支払い手形をすぐに貝殻や貨幣に交換してくれるだけの市場があればいいんですけどね。
で、そんなこんなしているうちに米国が1776年に独立。1785年に連邦議会が米国の通貨単位は「ドル」ですと宣言します。銀や金との交換比率も純度に応じて定められました。議会のみが貨幣を鋳造することができ、州政府がIOU(借用書)を紙幣として発行することは禁じられます。
そして当たり前の話ですが、当時の米ドルは国際通貨ではありません。
19世紀まで世界経済の中心はロンドンでした。英国人は世界各国に投資しています。外国の誰かがお金を借りたいと思ったら、ロンドンに行ってポンド建てでお金を借ります。外国政府がロンドンで資金を調達したいと思ったら、ロンドンの銀行に口座を開いて、借り入れや返済の手続きをすることになります。こうした口座は”reserve”と呼ばれるようになります。
英国は各国から綿花などさまざまな産品を輸入していました。あと、海運やそれに関連する保険業務などを行う会社もロンドンに拠点を置いています。こうした会社は決済のためにロンドンの銀行に口座を開きます。もちろんポンド建てです。
こうしたロンドン中心の商取引は米国の企業家にとっては不便なものでした。例えば、ニューヨークの企業家がブラジルからコーヒー豆を輸入しようと思ったら、ニューヨークの銀行とロンドンの銀行とブラジルの銀行の間で、ものすごく煩雑な手続きが必要になり、その度に手数料や何やらをとられてしまいます。しかも、これらの取引はポンド建てですから、ポンドの価値がドルに対して下がった場合には損が出る可能性もあります。また、米国の銀行や保険会社がこうした商取引に関連する業務に参入しようとしても、英国の銀行や保険会社には敵いません。取引はロンドンでポンド建てで行われているからです。
一方、米国は急速に経済力をつけていきます。1870年までに米国のモノやサービスの生産量は英国を追い抜き、1912年までには輸出量でも英国をしのぎます。でも、英ポンドは国際基軸通貨であり続けます。
その理由はいろいろありますが、金融サービスの業務が英国に集中し、資金を集めようとする人が投資をしようとする人たちがロンドンに集まっていること自体が、ロンドンの優位性を高めていたという事情が大きかった。つまり市場参加者が多いために、調達する側はより安い金利で調達できるし、投資する側も優良な投資先を見つけられるということです。「現役王者の強み」ですね。
また、米国は銀行が海外に支店を持つことを禁じていました。さらに米国では中央銀行すらないという状況だった。ロンドンでは銀行が現金を必要とするようになれば、手持ちの債券をBOEに引き受けてもらって現金を手にすることができましたが、米国ではそうしたことができなかったわけです。
米国では1791年、ハミルトンが主導してフィラデルフィアにthe Bank of the United Statesが設立されました。州をまたいで営業できる唯一の銀行で、連邦政府の財政も管理することになります。ハミルトンの狙いはBOEのような中央銀行を作ることでした。しかしジェファーソンやマディソンは、一部の銀行に特権的な地位を与えることについて、「エリートによる米国金融業界の独占支配」の危険を感じ取ります。The Bank of the United Statesが提示するレートが悪かったり、一部の銀行の独占的な地位に監視の目をきかせるようになると、「エリートによる介入だ」と不満を感じるようになったわけです。
そんなわけで、1810年に迎えたThe Bank of the United Statesの認可の更新は、ジェファーソンが主導する民主党の反対で否決されました。
しかしその結果、各州の銀行が勝手に紙幣を発行したりして空前の貸出ブームとなり、インフレが起き、景気はクラッシュします。で、1816年になって、Second Bank of the United Statesがフィラデルフィアに設立されることになりました。しかしこのSecond Bankもジャクソン大統領と金融業界の反対で1836年に認可の更新に失敗。米国は再び中央銀行がない時代に入ります。1907年に起きた金融危機の収束に際して、民間銀行のトップだったJ. Pierpont Morganが大きな役割を果たしたのには、こうした米国の事情がありました。
で、やっぱり中央銀行が必要だろうという機運が盛り上がり、中央銀行支持のNelson Aldrich上院議員らのグループがドイツ生まれのPaul Warburgに計画策定を託します。一部の銀行にだけ特権を与えるような制度には反対が強いことを考慮して、ウォーバーグは1911年、それぞれが債券引き受けの権限を持った15の地域銀行で構成されるNational Reserve Associationの設立計画を発表。各銀行のトップは地域の民間銀行によって選ばれるという仕組みを公表しました。
ただ、Aldrichの娘がロックフェラー家に嫁いでいたことから、この計画には「ロックフェラーを利するだけのものだろう」という印象を持たれてしまいます。また計画を策定したグループのなかにNational City Bank(シティグループの前身)のトップが含まれていたことも疑念をかきたてました。しかしその後、約2年間の審議を経て、トップが民間銀行によって選ばれる地区銀行の連合体を作り、それにFederal Reserve Boardが監視の目を光らせるという体制が作られることになりました。1913年のことです。同時に米国の銀行が海外に支店を持つことも認められるようになりました。
その後、第一次世界大戦が始まると、米国の輸出は急増。世界経済における米国の存在感は急速に大きくなって、米国は債務国から債権国に転じます。戦争で現金が足りなくなったドイツや英国は債券の引き受けをニューヨークの銀行に頼むようになります。この取引はドル建てで行われるようになりました。1915年ごろにはポンドと金の交換レートが不安定になる一方で、米ドルは金との交換レートが強く固定されていました。すると世界中の市場参加者が「ビジネスをするにはドル建てが一番だ」と考えるようになります。
米国政府はとりあえずはドル・ポンドレートの維持に協力しますが、英国の戦費拡大やインフレを背景にポンドに対する信頼は失墜。戦後になって米国がレート維持への協力を取り下げると、ポンドのレートは弱くなっていきます。こうしたなかで、National City Bankなど米国の銀行が海外業務を拡大していきます。
ただ、それでもニューヨークの債券市場の深みは、現役王者のロンドンには敵いません。そこでニューヨーク連銀の総裁だったBenjamin Strongが各地区連銀に対して債券を活発に引き受けるように指示。海外の中央銀行などからも債券を引き受けるようになります。こうした取り組みの結果、ドル建て取引の人気は高まり、1920年代後半には米国の輸出入の半分以上がドル建てとなり、米国を介さない第三国同士での取引でもドル建ての比率が増していきます。
また米国は欧州の復興資金を供給するようになります。英国は欧州各国に「米国ではなく、国際連盟(米国は非加盟)を通じて資金を調達しよう」と呼びかけますが、ストロングは欧州への貸出を積極的に推進することで対抗し、ドルの国際化がどんどん進んでいくことになりました。
しかし経験不足の米国の銀行は欧州の質の悪いプロジェクトにも資金を供給してしまい不良債権化が進行。1920年代の終わりには借り換えも続けられないようになって、世界恐慌につながっていくことになります。
世界恐慌の時代、各国政府は関税引き上げなどの保護主義的な政策をとり、世界の貿易量が減っていきます。貸し付けを回収できなくなった銀行は世界中で破綻。世界中というのは、アルゼンチン、メキシコ、オーストリア、ベルギー、フランス、ドイツ、ハンガリー、ルーマニア、バルト各国、エジプト、トルコ、英国っていうことですから、本当に世界中です。
英国なんかは資金流出を防ぐために利上げをしたいところでしたが、利上げをすると景気に悪影響が出ます。英国のためらいを察した投資家はポンド売りを加速させ、英国は1931年9月にポンドの金兌換を停止します。一方、ニューヨーク連銀はドル防衛のため、利上げを実施。結果、ドルの資金流出の危機は収まりますが、調達コストが増した金融機関は数多く破綻することになります。
英米の異なる金融政策の結果、1ポンド=4.86ドルだったレートは、1931年12月には1ポンド=3.25ドルまでポンド安が進みました。すると英国にとっては輸出が楽になるわけで、英国で緩やかな景気回復が始まります。英国はこれを好機とみて、利下げに踏み切って"cheap money"政策をとります。米国も1933年に金兌換を停止。1936年までには各国も同様の政策をとります。世界恐慌のダメージは英国よりも米国の方が大きく、長かったため、国際経済におけるドルの地位は後退しました。
しかし第二次世界大戦後の世界は別です。世界の主要国のなかで強さを維持できたのは米国だけだったからです。米国は金1オンスを35ドルで売ると約束したため、価値が保証されたドルは世界中の取引で使用されることになります。また、各国の中央銀行は金を蓄えるという選択肢もありましたが、当時の主な金の産出国はソ連と南アフリカで、金は十分に供給されていませんでした。
で、ここがキモですが、著者は
American consumers and investors could acquire foreign goods and companies without their government having to worry that the dollar used in their purchases would be presented for conversion into gold. Instead those dollars were hoarded by central banks, for which they were the only significant source of additional international reserves. America was able to run a balance-of-payments deficit "without tears," in the words of the French economist Jacques Rueff. This ability to purchase foreign goods and companies using resources conjured out of thin air was the exorbitant privilege of which French Finance Minister Valery Giscard d'Estaing so vociferously complained.
と書いています。
訳しますと、
米国の消費者や投資家が外国の製品や企業を買った場合でも、米国政府は(海外の売り手から)支払いに使われたドルを金に交換するように要求されることを心配する必要もなかった。むしろ、支払いに使われたドルは海外の中央銀行に蓄えられた。こうした取引は海外の中央銀行にとって、準備資金を調達するための唯一の手段だった。フランスの経済学者、ジャック・ルエフの言葉を借りるなら、米国は「涙を流すことなしに」貿易赤字を出すことができる。空気のなかから魔法のように取り出された資金を使って外国の製品や企業を買うことができる能力は、フランスのジスカール・デスタン財務相が強く不満を示した途方もない特権だった。
ということですね。
つまり、米国だけが自国通貨であるドルを発行しさえすれば、自由に他国から物資を買うことができるという状況です。
ただし第二次世界大戦後の各国は米国に売るような製品を作ることはできない状況です。なので米国はマーシャルプランやドッジプランのようなかたちで、欧州や日本の復興のための資金を拠出します。マーシャルプランは1年目、米国の連邦予算の10%を占める規模でしたから、とんでもない大盤振る舞いでした。この結果、1950年代の終わりには「ドル不足」は解消されます。
それと並行して、1960年には、各国が保有するドルの額は米国が保有する金の量を超えました。各国のドル保有者が一斉に金への兌換を求めれば、米国は対応しきれない状況で、このままでは各国が保有するドルの価値が値下がりする恐れがあります。一方、だからといって米国がドルの供給を止めてしまえば、ドル不足が再燃して世界の経済活動が停滞してしまう。いわゆる「トリフィンのジレンマ」です。
こうしたなか、各国には「米国はドルの金への兌換に応じられるように、先手を打って金の価格を引き上げる(ドル金レートを引き下げる)のではないか」という観測が生じます。そうなると各国は「今のうちにドルを金に交換してしまおう」という誘惑にかられます。
つまり、米国が1オンス=35ドルでの交換を保証しているなか、ロンドン市場での金の取引価格は1オンス=35ドルで推移しています。しかし将来的に米国が金の価格を引き上げるのであれば、今のうちにロンドン市場で金を買っておいて、後になって金を米国に持ち込めば利益を出すことができます。こうした思惑のなかで、ロンドン市場では金の価格が値上がりします。ウィキペディアによると、大統領選があった1960年の終わりにはロンドン市場の金価格は1オンス=40ドルを超えました。
そこで米国は1961年に「金プール」を提案します。各国が金をプールに拠出し、金を買う動きが強まった場合に「金売りドル買い」を浴びせることで、市場での金とドルの交換レートを維持しようという狙いです。こうしたプールを作るだけで、各国の「金買いドル売り」の誘惑を抑え込むこともできます。
しかし1965年になってソ連や南アフリカによる金の供給が落ち込むと、金買いの圧力が強まり、各国は実際に金売りを始めざるをえなくなります。となると、値下がりが続くドルを買い続けることになるわけですから、各国は厳しい状況に追い込まれ、1967年にはフランスがプールから脱退します。
また1967年には第三次中東戦争が起きて、スエズ運河が閉鎖される事態に発展。アラブ各国はイスラエルを支援していた英国への報復としてポンド売りを始め、英国はポンドの14%切り下げに追い込まれます。するとドルへの不安も高まり、ドルを売って金を買う動きが進みます。金プール参加国はドルの防衛を続けることができず、米国は1968年3月、英国に対してロンドンの金市場を閉鎖するように提案。金市場を自由に取引できる市場と、各国の中央銀行が1オンス=35ドルでの交換を保証する市場に分けることになります。ただ、これは単なる弥縫策にすぎません。
一方、1969年にニクソン大統領が就任した米国は、ドル危機は欧州各国が米国の防衛費を負担し、米国に市場を開放することで解消されるべきだという立場をとります。
いまいち、よく分からない理屈ですが、「第二次世界大戦後、米国が世界にドルを供給してきたことがドルの信任低下につながったのだから、ドルを米国に環流させればドル危機も解消される」ということだったのでしょうか。
さらに米国は、欧州が要求に応じない場合には、次の手段をとると脅迫します。すると、こうした米欧の対立は投資家の不安をあおり、米国の思惑とは裏腹にドルを売って金を買う動きが加速。この結果、1971年8月、米国はドルの金兌換停止を発表しました。ニクソン・ショックです。
このとき、ニクソンは同時に米国企業を守るために10%の関税引き上げを発表します。米国が通貨防衛に敗れたとの印象を避ける効果も狙っていました。
ニクソンは1971年12月のスミソニアン協定で、この上乗せ関税を取り下げることと引き替えに、各国に対してドル安水準での固定相場を維持することを約束させます。さらにニクソンは1972年の大統領選前に景気を浮揚させることを狙って、FRBに対して金融緩和するよう圧力をかけます。この結果、米国でインフレが始まり、ドル売り圧力も高まります。スミソニアン体制は1973年に終焉を迎え、各国は変動相場制に移行していきます。
こうなると、「ドルの信頼はガタ落ちじゃないか。ドルは国際基軸通貨の座を追われてしまうの?」っていう気もしますが、実際にはそうはなりませんでした。ゴルのレートは引き下げられたものの、各国の中央銀行に占めるドルの割合は大きく変化しませんでした。変動相場になったといっても、一方的にずーっとドルが値下がりを続けたわけではなかったからです。
ただし、1970年代後半になると、米国でインフレが始まります。ドル安要因です。一方、カーター政権のブルーメンソール財務長官は1977年夏に「ドルが強すぎる」と発言。ドル安を望んでいることを示唆しました。つまり、ドル安を容認するということです。すると、欧州から「ドル安になったら、欧州の輸出が苦しくなる。米国はドル安容認を止めろ」という声があがり、ブルーメンソールは一転して「強いドル」の支持を表明します。
1978年3月にFRB議長になったウィリアム・ミラーはとにかく雇用の増大を重視すべきだという人で、中央銀行がインフレを抑制する能力は乏しいと考えている人でした。FRB外のアラン・グリーンスパンやチャールズ・シュルツらはインフレを抑えるために金融を引き締めるべきだとの声が上がっていましたが、ミラーは抵抗します。すると、当然ながら、ドルが安くなっていきます。ドルが安くなると、欧州に駐留する米軍の負担が大きくなるという問題が起きますし、もちろん米国外のドル保有者にも損が出ます。
そんなわけで1979年8月、ポール・ボルカーがFRB議長に就任します。利上げを行って、ドル高が始まります。やはりドルは基軸通貨であり続けます。そもそも、ドル以外の通貨に、基軸通貨となるような実力がないのが実情です。
で、ここまでが第3章です。この本は第7章まであります。非常に長くなってきたので、このあたりで止めます。
第4章以降では、欧州でユーロが創設される話やリーマン・ショックの話、ユーロや円がドルを凌駕する基軸通貨になりきれない理由などです。SDRの話も結構出てきます。
中国の人民元については第3章までも折に触れて言及されていますが、「国際通貨としての存在感を増してはいるし、中国政府も基軸通貨にしようと努力を続けている。このあたりはかつての米国とよく似ている。ただし、ドルがポンドをしのぐ基軸通貨となれたのは、第二次世界大戦後の英国経済の失墜という要因があった。米国経済が健全さを保ち続けることができれば、現役王者であるドルが人民元に完全に負けてしまうことはない」という話です。
あと、今になってざっとチェックしてたところ、レーガン政権下での1985年のプラザ合意の話が出てきません。日本にとっては非常に大事な話なので残念ですけど、また別の機会に勉強します。
いずれにしろ大変勉強になりました。
2016年9月29日木曜日
"American Immigration: a very short introduction"
"American Immigration: a very short introduction"という本を読んだ。David Gerverというニューヨーク州立大学バッファロー校の歴史学の教授が書いた本です。米国で何かと話題な移民問題について、歴史的な文脈をちゃんと調べておこうというつもりで読みました。簡潔で、分かりやすく、勉強になりました。
米国は1789年の建国後、3つの移民ブームがあったそうです。
1回目は1840年代から1850年代:欧州での食料危機をきっかけに、アイルランドやドイツからの移民が増える。400万人以上。農地開発が進んでいた北西部に向かう。多くはカトリック教徒だった。
2回目は1890年代から第一次世界大戦の時期:1890年代の不況をきっかけに、欧州からの移民が増える。1901年~1920年で1170万人。南欧、中欧、東欧からの移民の割合が急激に高まる。ユダヤ教とか、正教派、カトリックが含まれる。顔立ちもアングロ・アメリカンとは異なる。多くは独身の男性で、稼ぐだけ稼いで母国に帰ろうという意識が強かった。第一次大戦中は政府が移民たちに大して、米国債を買い、米軍に入隊するよう呼びかけた。
3回目は1965年の移民法の改正後の時代:第二次世界大戦後に移民の受け入れ割り当ての緩和が段階的に進められ、荒廃した欧州や共産主義化した国々から移民が増えた。西側唯一の超大国となった米国には移民への警戒も少なくなっていた。こうしたタイミングで1965年にImmigration and nationality Actが成立。各国別の移民受け入れ割り当てや人種の考慮を廃止した。東半球からの移民受け入れは年間17万人が上限(1カ国最大2万人)、西半球からは12万人が上限。ビザ発行は先着順。欧州以外からの移民が急増し、1980年代から1990年代の移民は13%が欧州からで、82%がアジアや南アメリカから。メキシコからの不法移民も増える。
もともと米国は広大な農地や資源を開発するため、大量の労働力を必要としています。産業化が始まると、工場で働く人たちも必要になる。一方、世界にはどの時代でも母国での生活に苦しんでいる人たちがたくさんいて、その人たちが米国での稼ぎや安定を夢見て自発的に米国に移り住むようになっていくわけです。日本だって、かつては大量の移民を送り出した時代がありました。そうすると次第に、米国内で出身地域別に働く業種に偏りが出てきます。アイルランド系は"ditch digger"、ポーランド系は鉄鋼業、スロバキア系は炭鉱、ユダヤ系は衣料、イタリア系は建設現場みたいな感じだったそうです。メキシコ系は農業、日本系はmarket farmer(青果とか野菜とか)、中国系は鉄道建設なんているイメージもあるみたいです。
どうしてこういう偏りが出るのかというと、各母国の重要産業みたいなものがあるのと、移民同士のネットワークがあるからです。例えば、米国で石炭を開発しようという事業家がいて、米国では人材が不足しているので労働力を海外から集めようとすれば、やはり炭鉱で働いたことがある人材を集めたいわけです。そうなると、欧州の石炭産業がある国から経験者を集めたくなる。またユダヤ人が不動産取引で差別された結果、小売りなどのビジネスに進出していったというようなパターンもあるらしい。そして、こうした移民が増えてくると、母国の仲間に手紙を出したりして、「米国なら稼げるぞ」みたいな話が広がって、さらにその国からの移民が増える。そのうち、働いている地域には移民のコミュニティーもできる。そのコミュニティーには、その国出身者向けの小売店もできたりする。そんな風にして、米国内に移民グループができてくるわけです。こうしたグループは移民の先輩から新人に対して、米国生活の習慣や文化などにについて教える「同化の教室」としての役割も果たしてきました。
そして、そうした移民グループの票を期待する政党ができたりもする。民主党は伝統的にアイルランド系やドイツ系の支持を受けてきたとのことです。1965年の移民制度改革を主導したのは、アイルランド系のケネディ大統領、ユダヤ系のEmanuel Celler下院議員、イタリア系のPeter Rodino下院議員、中国系のHiram Fong上院議員らだったとのこと。
その一方、米国にはいつの時代も反移民感情が存在します。移民は米国人の雇用を奪うとか、賃金水準を下げるとか、米国らしさを失わせるとか、そういった議論ですね。「米国は移民の国」といわれるわけですが、それだけに「反移民感情」の歴史も長いわけです。経営者たちは労働者がストライキを始めると、移民を雇うことでストライキに対抗したりします。移民たちは母国よりも条件が良ければ、喜んで働くわけです。でもそうなると労働組合は移民を敵視するようになる。やはり反移民感情が創出されるわけです。
すでに1798年にはAlien Eneimies Actが成立して、連邦政府が米国に敵対する国からの移民を逮捕し、強制送還することが認められたりしています。アイルランド系はカトリックなので、プロテスタントのアングロアメリカンからは敵視されたりもしたそうです。1864年から1917年にかけては、海外で働いたことがある労働者や犯罪者、売春婦、貧困者、乞食、結核患者、てんかん患者、精神病患者らの入国を禁じる法律が相次いで成立します。ただし、欧州からの渡航者のうち、実際に入国を拒否されたのは1%だけだったとのこと。
1921年と1924年には移民受け入れ数を各国別に割り当てる法律、Emergency Quota ActとJohson-Reed Actが成立します。ロシアで革命が起きると、移民たちの米国への愛国心が疑問視されたりもしました。あと、1930年代の世界恐慌下では数千人のメキシコ人やフィリピン人が米国人の雇用を優先させるとの理由で母国に帰されました。1954年のアイゼンハワー大統領による、"Operation Wetback"なんていうのもあります。不法移民が増えた1965年以降の反移民感情の高まりは、今のトランプ旋風の背景になるわけです。
アジア系への反発だけ抜き出してみると、1870年代にはゴールドラッシュが終息して景気が悪くなったカリフォルニアで、低賃金で働く中国人労働者への反感が高まりました。この運動を指揮したのはアイルランド生まれのDenis Kearneyという人物でWrokingmen's Partyを組織し、演説の最後は"And wahtever happens, the Chinese must go!"で締めるのが定番だったそうです。1882年には連邦政府がChinese Exclusion Actを成立させ、中国人労働者排斥の動きは1943年の同法の撤廃まで続きます。このころ、セオドア・ルーズベルトと日本政府との紳士協定で、日本からの米国本土への移民も3分の1にカットされました。日本は日露戦争後は大国として扱われていたので、中国人労働者のような一方的な法的規制にはならなかったとのこと。ただし第二次世界大戦が始まると、日系人11万人が収容所に入れられました。このうち62%は米国生まれの米国人だったそうです。ただ現在のアジア系には、教育水準が高く、倹約家で、家族やコミュニティーのつながりが強く、将来的な人種のヒエラルキーのトップには欧州系と並んでアジア系も加わるとの分析もあるそうです。
反移民感情は肌の色だけに基づくものではなく、欧州から来た白人の移民たちにも向けられます。移民たちがすでに米国にいる人たちの与える経済的な影響は肌の色には関係ないですからね。あと、移民たちがグループ化して、自分たちのコミュニティーを作るようになると、例え白人であっても「米国に馴染もうとしていない」という批判も出てくる。20世紀前半には、イタリア系移民が貧しい犯罪者の集団として蔑視されました。こういった反移民的なものの考え方は"nativism"と呼ばれます。現在でも、メキシコ系の移民が19世紀半ばに米国がメキシコから奪った領土を取り返そうとしているなんて考える人もいるらしい。
1894年に北東部の学者や政治家たちが設立したImmigration Restriction League(IRL)は、社会の不安定化の原因は野放図な移民の拡大が原因だと主張します。当時注目を集めていた優生学の影響も受けていたようです。IRLの活動は、移民への課税引き上げや、語学テストの実施、さらには移民受入数の制限につながります。また、反移民感情の裏側に人種差別があることも否定できません。筆者のGerberさんは1870年代のカリフォルニアでの反中国系移民運動の参加者たちは、中国系移民と同じ立場から経営側に賃金引き上げを求めるような運動に関わることはなかったと指摘しています。
ただ、nativistたちは全員が人種差別主義者というわけでなくて、既存の米国人たちの生活を守ろうとしているだけの人も多かったりするわけですね。だから、こうしたnativistたちの感情をくみ取ろうとする政治家が、移民の受け入れ数を制限したり、条件を厳しくするなんていう政策をとったりするわけです。そうなると、移民ブームが収束していく。でもやっぱり、労働力に対する需要は常にあって、、、、こうした繰り返しが米国の移民の歴史だということのようです。
現在の移民も経済的な理由で米国にわたってくる点では過去の移民と同じです。ただ、不法移民が多いという特徴もあります。あと非白人が多い。アジアとか南米とか、その他の途上国からの移民ですね。さらに移民が働く業種もかつての製造業から、サービス業にシフトしています。中国系ならチャイニーズレストランを始めたり、ソマリア系女性がホテルで働いたり、ジャマイカ系の看護婦とか、南アジア系のコンピューターサポートとか、そんな感じですね。結果、黒人奴隷の伝統から安価な労働力が豊富だった南部や、アッパー中西部、グレートプレーンのようなこれまで移民受け入れの経験が少なかった地域でも移民が増えています。
サミュエル・ハンチントンは、今の移民の傾向が続けば、"core Anglo-Protestant culture"が失われると懸念したそうです。ハンチントンはnativismと同一視されることを避けるため、これは人種的な意味合いではなくて米国の建国からこれまでの繁栄を支えてきた文化そのものだとしています。
ただ、筆者のGerberさんは、米国の文化は絶えず変化を続けてきたのであって、ひとつの文化によって米国の今の繁栄が成し遂げられたわけではないとします。また移民のなかに悪い人間がいることは確かですが、米国でお金を稼いで豊かになろうという移民たちが勤勉さという美徳をあわせもっていることを見過ごしてはならないとも主張しています。また米国自身も二重国籍を認めたり、資金の移動をしやすくしたりして、移民を積極的に受け入れてきたという歴史があります。そして移民たちが子供を産んで、定住するようになれば、何世代かにわたる時間をかけてでも同化が進んでいくことも明らかです。だから、こうした同化を支援するような政策をとることが重要であって、いたずらに移民を敵視するような態度は建設的ではないということです。
なんかJapanese LoverとかKen Liuの小説で読んだような話もあって面白かった。もちろん現在の米国におけるトランプ支持者の心情が何も特別なものではないということも分かります。
あと、移民を制限しようという運動は米国だけのものではなく、歴史的には豪州やニュージーランド、南アフリカ、カナダ、アルゼンチン、ブラジルなんかでもみられたという指摘もなるほどという感じです。日本だって人種的な差別感情から中国や朝鮮半島からの移民を禁止したりしています。
移民が外交政策に影響を与えたりするというのも面白いですね。何も今のイスラエル・ロビーだけの話じゃなくて、かつてはアイルランド系や東欧系が母国の独立を支援を求めたり、アラブ系がパレスチナ支援を求めたり、キューバ系がキューバ制裁を支持するよう求めたりといった歴史があるようです。第二次世界大戦中に中国系が日本への抗戦を支持し、日本製品のボイコットをしたりもした。台湾系の動きは、以前、Robert Sutterの本で出てきました。
最後にちょっと気になるのが本の終盤で出てきた、
"Yet such findings also suggest the depths of an ongoing crisis that is not sufficiently addressed: the stagnant position of members of America's largest domestic racial minority, African Americans, many of whom are being overtaken and passed by, as immigrants move into the mainstream. It remains a bitter irony in the midst of celebrations of immigrant achievements that programs, such as affirmative action in hiring or in college admissions, which were developed in the mid-twentieth century following civil rights protests to address long-standing institutional racism and to assist African Americans, have been utilized more successfully by non-white immigrants to speed their own entrance into the mainstream. The government has allowed the application of such programs to immigrants of color and their children in the service of the laudable goals of immigrant assimilation and multicultural diversity in workplaces and educational institutions. But the ongoing neglect of their original intentions is no credit to American policy."
という記述。
最後の一文は「米国の公共政策にとって名誉なことではない」という意味だと思うのですが、なんでこうした政策がもたらす影響が黒人と移民の間で差があるんですかね。「文化の違いだ」と言ってしまうと、なかなかギリギリな感じもしますけど、どうなんでしょう。今の米国では"Black Lives Matter"なんていう運動もあるわけですが、こちらもなかなか根深い問題ですね。また勉強します。
米国は1789年の建国後、3つの移民ブームがあったそうです。
1回目は1840年代から1850年代:欧州での食料危機をきっかけに、アイルランドやドイツからの移民が増える。400万人以上。農地開発が進んでいた北西部に向かう。多くはカトリック教徒だった。
2回目は1890年代から第一次世界大戦の時期:1890年代の不況をきっかけに、欧州からの移民が増える。1901年~1920年で1170万人。南欧、中欧、東欧からの移民の割合が急激に高まる。ユダヤ教とか、正教派、カトリックが含まれる。顔立ちもアングロ・アメリカンとは異なる。多くは独身の男性で、稼ぐだけ稼いで母国に帰ろうという意識が強かった。第一次大戦中は政府が移民たちに大して、米国債を買い、米軍に入隊するよう呼びかけた。
3回目は1965年の移民法の改正後の時代:第二次世界大戦後に移民の受け入れ割り当ての緩和が段階的に進められ、荒廃した欧州や共産主義化した国々から移民が増えた。西側唯一の超大国となった米国には移民への警戒も少なくなっていた。こうしたタイミングで1965年にImmigration and nationality Actが成立。各国別の移民受け入れ割り当てや人種の考慮を廃止した。東半球からの移民受け入れは年間17万人が上限(1カ国最大2万人)、西半球からは12万人が上限。ビザ発行は先着順。欧州以外からの移民が急増し、1980年代から1990年代の移民は13%が欧州からで、82%がアジアや南アメリカから。メキシコからの不法移民も増える。
もともと米国は広大な農地や資源を開発するため、大量の労働力を必要としています。産業化が始まると、工場で働く人たちも必要になる。一方、世界にはどの時代でも母国での生活に苦しんでいる人たちがたくさんいて、その人たちが米国での稼ぎや安定を夢見て自発的に米国に移り住むようになっていくわけです。日本だって、かつては大量の移民を送り出した時代がありました。そうすると次第に、米国内で出身地域別に働く業種に偏りが出てきます。アイルランド系は"ditch digger"、ポーランド系は鉄鋼業、スロバキア系は炭鉱、ユダヤ系は衣料、イタリア系は建設現場みたいな感じだったそうです。メキシコ系は農業、日本系はmarket farmer(青果とか野菜とか)、中国系は鉄道建設なんているイメージもあるみたいです。
どうしてこういう偏りが出るのかというと、各母国の重要産業みたいなものがあるのと、移民同士のネットワークがあるからです。例えば、米国で石炭を開発しようという事業家がいて、米国では人材が不足しているので労働力を海外から集めようとすれば、やはり炭鉱で働いたことがある人材を集めたいわけです。そうなると、欧州の石炭産業がある国から経験者を集めたくなる。またユダヤ人が不動産取引で差別された結果、小売りなどのビジネスに進出していったというようなパターンもあるらしい。そして、こうした移民が増えてくると、母国の仲間に手紙を出したりして、「米国なら稼げるぞ」みたいな話が広がって、さらにその国からの移民が増える。そのうち、働いている地域には移民のコミュニティーもできる。そのコミュニティーには、その国出身者向けの小売店もできたりする。そんな風にして、米国内に移民グループができてくるわけです。こうしたグループは移民の先輩から新人に対して、米国生活の習慣や文化などにについて教える「同化の教室」としての役割も果たしてきました。
そして、そうした移民グループの票を期待する政党ができたりもする。民主党は伝統的にアイルランド系やドイツ系の支持を受けてきたとのことです。1965年の移民制度改革を主導したのは、アイルランド系のケネディ大統領、ユダヤ系のEmanuel Celler下院議員、イタリア系のPeter Rodino下院議員、中国系のHiram Fong上院議員らだったとのこと。
その一方、米国にはいつの時代も反移民感情が存在します。移民は米国人の雇用を奪うとか、賃金水準を下げるとか、米国らしさを失わせるとか、そういった議論ですね。「米国は移民の国」といわれるわけですが、それだけに「反移民感情」の歴史も長いわけです。経営者たちは労働者がストライキを始めると、移民を雇うことでストライキに対抗したりします。移民たちは母国よりも条件が良ければ、喜んで働くわけです。でもそうなると労働組合は移民を敵視するようになる。やはり反移民感情が創出されるわけです。
すでに1798年にはAlien Eneimies Actが成立して、連邦政府が米国に敵対する国からの移民を逮捕し、強制送還することが認められたりしています。アイルランド系はカトリックなので、プロテスタントのアングロアメリカンからは敵視されたりもしたそうです。1864年から1917年にかけては、海外で働いたことがある労働者や犯罪者、売春婦、貧困者、乞食、結核患者、てんかん患者、精神病患者らの入国を禁じる法律が相次いで成立します。ただし、欧州からの渡航者のうち、実際に入国を拒否されたのは1%だけだったとのこと。
1921年と1924年には移民受け入れ数を各国別に割り当てる法律、Emergency Quota ActとJohson-Reed Actが成立します。ロシアで革命が起きると、移民たちの米国への愛国心が疑問視されたりもしました。あと、1930年代の世界恐慌下では数千人のメキシコ人やフィリピン人が米国人の雇用を優先させるとの理由で母国に帰されました。1954年のアイゼンハワー大統領による、"Operation Wetback"なんていうのもあります。不法移民が増えた1965年以降の反移民感情の高まりは、今のトランプ旋風の背景になるわけです。
アジア系への反発だけ抜き出してみると、1870年代にはゴールドラッシュが終息して景気が悪くなったカリフォルニアで、低賃金で働く中国人労働者への反感が高まりました。この運動を指揮したのはアイルランド生まれのDenis Kearneyという人物でWrokingmen's Partyを組織し、演説の最後は"And wahtever happens, the Chinese must go!"で締めるのが定番だったそうです。1882年には連邦政府がChinese Exclusion Actを成立させ、中国人労働者排斥の動きは1943年の同法の撤廃まで続きます。このころ、セオドア・ルーズベルトと日本政府との紳士協定で、日本からの米国本土への移民も3分の1にカットされました。日本は日露戦争後は大国として扱われていたので、中国人労働者のような一方的な法的規制にはならなかったとのこと。ただし第二次世界大戦が始まると、日系人11万人が収容所に入れられました。このうち62%は米国生まれの米国人だったそうです。ただ現在のアジア系には、教育水準が高く、倹約家で、家族やコミュニティーのつながりが強く、将来的な人種のヒエラルキーのトップには欧州系と並んでアジア系も加わるとの分析もあるそうです。
反移民感情は肌の色だけに基づくものではなく、欧州から来た白人の移民たちにも向けられます。移民たちがすでに米国にいる人たちの与える経済的な影響は肌の色には関係ないですからね。あと、移民たちがグループ化して、自分たちのコミュニティーを作るようになると、例え白人であっても「米国に馴染もうとしていない」という批判も出てくる。20世紀前半には、イタリア系移民が貧しい犯罪者の集団として蔑視されました。こういった反移民的なものの考え方は"nativism"と呼ばれます。現在でも、メキシコ系の移民が19世紀半ばに米国がメキシコから奪った領土を取り返そうとしているなんて考える人もいるらしい。
1894年に北東部の学者や政治家たちが設立したImmigration Restriction League(IRL)は、社会の不安定化の原因は野放図な移民の拡大が原因だと主張します。当時注目を集めていた優生学の影響も受けていたようです。IRLの活動は、移民への課税引き上げや、語学テストの実施、さらには移民受入数の制限につながります。また、反移民感情の裏側に人種差別があることも否定できません。筆者のGerberさんは1870年代のカリフォルニアでの反中国系移民運動の参加者たちは、中国系移民と同じ立場から経営側に賃金引き上げを求めるような運動に関わることはなかったと指摘しています。
ただ、nativistたちは全員が人種差別主義者というわけでなくて、既存の米国人たちの生活を守ろうとしているだけの人も多かったりするわけですね。だから、こうしたnativistたちの感情をくみ取ろうとする政治家が、移民の受け入れ数を制限したり、条件を厳しくするなんていう政策をとったりするわけです。そうなると、移民ブームが収束していく。でもやっぱり、労働力に対する需要は常にあって、、、、こうした繰り返しが米国の移民の歴史だということのようです。
現在の移民も経済的な理由で米国にわたってくる点では過去の移民と同じです。ただ、不法移民が多いという特徴もあります。あと非白人が多い。アジアとか南米とか、その他の途上国からの移民ですね。さらに移民が働く業種もかつての製造業から、サービス業にシフトしています。中国系ならチャイニーズレストランを始めたり、ソマリア系女性がホテルで働いたり、ジャマイカ系の看護婦とか、南アジア系のコンピューターサポートとか、そんな感じですね。結果、黒人奴隷の伝統から安価な労働力が豊富だった南部や、アッパー中西部、グレートプレーンのようなこれまで移民受け入れの経験が少なかった地域でも移民が増えています。
サミュエル・ハンチントンは、今の移民の傾向が続けば、"core Anglo-Protestant culture"が失われると懸念したそうです。ハンチントンはnativismと同一視されることを避けるため、これは人種的な意味合いではなくて米国の建国からこれまでの繁栄を支えてきた文化そのものだとしています。
ただ、筆者のGerberさんは、米国の文化は絶えず変化を続けてきたのであって、ひとつの文化によって米国の今の繁栄が成し遂げられたわけではないとします。また移民のなかに悪い人間がいることは確かですが、米国でお金を稼いで豊かになろうという移民たちが勤勉さという美徳をあわせもっていることを見過ごしてはならないとも主張しています。また米国自身も二重国籍を認めたり、資金の移動をしやすくしたりして、移民を積極的に受け入れてきたという歴史があります。そして移民たちが子供を産んで、定住するようになれば、何世代かにわたる時間をかけてでも同化が進んでいくことも明らかです。だから、こうした同化を支援するような政策をとることが重要であって、いたずらに移民を敵視するような態度は建設的ではないということです。
なんかJapanese LoverとかKen Liuの小説で読んだような話もあって面白かった。もちろん現在の米国におけるトランプ支持者の心情が何も特別なものではないということも分かります。
あと、移民を制限しようという運動は米国だけのものではなく、歴史的には豪州やニュージーランド、南アフリカ、カナダ、アルゼンチン、ブラジルなんかでもみられたという指摘もなるほどという感じです。日本だって人種的な差別感情から中国や朝鮮半島からの移民を禁止したりしています。
移民が外交政策に影響を与えたりするというのも面白いですね。何も今のイスラエル・ロビーだけの話じゃなくて、かつてはアイルランド系や東欧系が母国の独立を支援を求めたり、アラブ系がパレスチナ支援を求めたり、キューバ系がキューバ制裁を支持するよう求めたりといった歴史があるようです。第二次世界大戦中に中国系が日本への抗戦を支持し、日本製品のボイコットをしたりもした。台湾系の動きは、以前、Robert Sutterの本で出てきました。
最後にちょっと気になるのが本の終盤で出てきた、
"Yet such findings also suggest the depths of an ongoing crisis that is not sufficiently addressed: the stagnant position of members of America's largest domestic racial minority, African Americans, many of whom are being overtaken and passed by, as immigrants move into the mainstream. It remains a bitter irony in the midst of celebrations of immigrant achievements that programs, such as affirmative action in hiring or in college admissions, which were developed in the mid-twentieth century following civil rights protests to address long-standing institutional racism and to assist African Americans, have been utilized more successfully by non-white immigrants to speed their own entrance into the mainstream. The government has allowed the application of such programs to immigrants of color and their children in the service of the laudable goals of immigrant assimilation and multicultural diversity in workplaces and educational institutions. But the ongoing neglect of their original intentions is no credit to American policy."
という記述。
最後の一文は「米国の公共政策にとって名誉なことではない」という意味だと思うのですが、なんでこうした政策がもたらす影響が黒人と移民の間で差があるんですかね。「文化の違いだ」と言ってしまうと、なかなかギリギリな感じもしますけど、どうなんでしょう。今の米国では"Black Lives Matter"なんていう運動もあるわけですが、こちらもなかなか根深い問題ですね。また勉強します。
2016年9月24日土曜日
"The Old Man and the Sea"
"The Old Man and the Sea"を読んだ。アーネスト・ヘミングウェイの「老人と海」です。とっさに読む本が思いつかなかったのですが、最近ネットフリックスで観ているドラマの登場人物が「俺はヘミングウェイになる」と言って小説を書き始めていたのを思い出して、読んでみた。ヘミングウェイなんて、これまで読もうと思ったこともなかったので、勉強になりました。
ヘミングウェイの小説のなかでも短いものを選んだので、わりとすぐに読み終わりました。英語もそんなに難しいものじゃないかったです。ただ、舟や釣りに関する細かな用語は意味がつかみにくかったです。このあたりは日本語で読んでも同じことかもしれません。
まぁ、戦い続けることこそが尊いんだという話でしょうか。主人公の老人が愚痴っぽいところがあったりするのも、普通の人っぽくてよかったです。
ヘミングウェイの小説のなかでも短いものを選んだので、わりとすぐに読み終わりました。英語もそんなに難しいものじゃないかったです。ただ、舟や釣りに関する細かな用語は意味がつかみにくかったです。このあたりは日本語で読んでも同じことかもしれません。
まぁ、戦い続けることこそが尊いんだという話でしょうか。主人公の老人が愚痴っぽいところがあったりするのも、普通の人っぽくてよかったです。
2016年8月31日水曜日
Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis
"Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis"という本を読んだ。J.D. Vanceさんという31歳の白人男性弁護士が、自らの半生を振り返った本です。
これだけだと、だからどうしたという話ですが、バンスさんはオハイオ州のミドルタウンというかつては鉄鋼業で栄えたものの、今はさびれつつある街で育ち、劣悪な家庭環境のなかから這い上がり、イエール大学のロースクール卒のエリート弁護士になったという経歴の持ち主です。そのアメリカン・ドリームの体現者が、かつては劣悪な環境を経験した者として、米国に存在する貧困の背景や、そうしたコミュニティーに育ったものたちが今の米国社会をどのようにみているのか、問題を解決するためには何が必要なのかという問題を論じています。
2016年6月28日に出版された本で、「多くの白人がドナルド・トランプ氏を支持する背景にはこういった事情がある」という文脈でたくさんのメディアで紹介されていました。インタビューに答えたバンスさんは、「私自身はトランプ氏を支持するわけではないが、支持している人たちの気持ちは理解できる」としています。
で、話はケンタッキー南東部の石炭の産地、ジャクソンから始まります。非常に緊密なコミュニティーで、見知らぬ人が雪道で車を動かせなくなっていると、住民たちがこぞって助けだそうとするような地域です。バンスさんの祖父母はこのジャクソンで育ちました。非常に心優しい人たちです。
ただし、こうしたアパラチア山脈のコミュニティーに住む人たちには、荒くれ者という一面もあります。祖母の兄の1人は建設業を営んでいたのですが、ビジネスの相手が"son of a bitch"と生意気な口をきいたときは、車のなかにいた相手を引きずり下ろしてチェーンソーで切りつけ、病院送りにしてしまうような人です。「家族に対する侮辱は絶対に許さない」という掟に従った行動だとのこと。別の兄は、自宅の裏庭でマリファナを育てています。祖母自身も、家族で育てている牛を盗もうとした男を見つけたときに、ライフルを持ち出して発砲し、脚をケガした相手の頭に向かってライフルをかまえ、とどめを刺そうとしたことがあるそうです。
祖母の家だけが荒くれ者だらけだったというわけではありません。ジャクソンがあるBrethitt Countyという地域は"Bloddy Breathitt"という異名があるほどで、とある強姦犯は裁判の数日前、背中に16発の銃弾を受けて殺されました。地元の警察はまともに捜査せず、新聞も「犯罪」があったようだと報じただけでした。真相は明らかではありませんが、被害者の家族が裁きを下したということのようです。祖母が少女時代にある男に侮辱された際にも、兄たちがその男を懲らしめたことがあったそうです。
で、子供のころにこうした話を親戚たちから聞いたバンスさんは、「家族のためなら法律でも犯す」といったカルチャーを誇りに感じていたそうです。親戚一同がこんなエピソードを面白おかしく話したりしていたら、「これが男というものだ」と思っていたということなのでしょう。
祖父母は1947年に17歳と14歳で結婚しました。そして第二次世界大戦での勝利に対する興奮がさめていくなかで、よりよい生活を求めて、オハイオ州ミドルタウンに引っ越します。ミドルタウンにはArmcoという鉄鋼会社が工場を構えていて、大量の労働者を雇うようになっていたからです。というと美しい話のようですが、実はできちゃった婚で、祖母の兄たちから懲らしめられることを恐れてミドルタウンに逃げていったという事情もあったようです。ちなみにこのときの子供は生後すぐに亡くなったとのこと。
ミドルタウンにはケンタッキー出身者が多く、"Middletucky"なんて呼ばれたりした。だから、ミドルタウンには、荒くれ者のカルチャーも持ち込まれて、元からオハイオにいた人たちとの間でトラブルも多かったそうです。祖母は、"You can take the boy out of Kentucky, but you can't take Kentucky out of the boy."なんて言っていた。アパラチアン魂百までってことでしょうか。
ただし生活が順調だったというわけではありません。祖父はジャクソンから離れたミドルタウンでの生活に馴染みきれないところがあったのか、バーから泥酔して帰宅したり、手にした給料を見栄をはるために浪費したりして、祖母を怒らせることも度々だった。祖母が泥水してソファーで眠っている祖父にガソリンをかけて、火をつけるということもあったらしい。バイオレントすぎるエピソードですが、家族の間ではそう伝えられているそうです。
で、そうした環境で育ったバンスさんの母親は、18歳で妊娠。19歳で離婚してシングルマザーになります。これが1980年ぐらいの話。母親の妹(バンスさんのおばさん)もその2年ほど前に16歳で高校を退学して、結婚しています。やはり結婚生活は厳しいものだったようです。こうした状況をなんとかせねばならないと決意したのか、祖父は1983年に禁酒し、別居状態だった祖母とも関係を修復するようになります。祖父は53歳、祖母は50歳ぐらいの計算ですね。祖父母は孫のケアや金銭的な援助を買って出るようになります。母親は1983年に再婚して、翌1984年にバンスさんが生まれます。
で、ここから先はバンスさん自身の話ですが、それはそれはなかなか過激なエピソードが満載です。
19歳でシングルマザーになってその4~5年後にバンスさんを生んだ母親は、その後も離婚と結婚を繰り返し、バンスさんが高校を卒業するまでに6人の男性と一緒に生活しています。バンスさんは、母親としては「子供たちに父親が必要だ」という思いで結婚相手を探していたのではないかと推測していますが、バンスさん自身の思いとしては「全く見知らぬ男が家の中に入ってきて、ようやく好きになったかなと思い始めたころに、離婚して家から出て行く」という状況が繰り返されることは子供時代の自分の心を深く傷つけていたとしています。また母親は看護師として働いてはいましたが、お酒におぼれ、バンスさんたちと大げんかをしては「ごめんなさい。もう二度とこんなことはしない」と謝罪するような生活を続けて来ました。バンスさんたちはそのたびに謝罪を受け入れるのですが、数日後には同じ状態に戻ってしまう。
バンスさんが12歳のときには、母親が反省の証としてバンスさんにフットボールカードを買ってくれると約束するのですが、車で高速道路を走っている最中にけんかになって、母親は「このまま車をクラッシュさせて、死んでやる」と言い出します。バンスさんは助手席から後部座席に移って、シートベルトを2つつければ生き延びられるんじゃないかと考えたりしましたが、母親はそうしたバンスさんの行為に怒りを増幅させて、車を止めてバンスさんに殴りかかります。止まった車から逃げ出したバンスさんは近くの民家にかけこんで、そこにいた女性に警察を呼ぶように依頼。母親は駆けつけた警察に逮捕されます。バンスさんはその後の裁判で、裁判官から日頃の母親の状況を聞かれ、「こうしたことは初めてのことです」と嘘をつききます。母親を刑務所には行かせたくないという思いからの嘘だったそうです。この後、バンスさんは、母親の家と祖父母の家の両方で暮らすようになります。自分の好きなときに、好きな方の家で暮らすことで、生活の安定と母親とのつながりを実現しようという狙いでした。
その後、バンスさんは実の父親と会うようになります。バンスさんは母親たちから父親が酒浸りになったから離婚したと聞かされて育ちましたが、実際にあった父親は敬虔なクリスチャンとして生活を立て直していました。ただ、既存の科学を否定するような極端なところもある信仰で、バンスさんも「2007年には世界が終わる」といった終末思想を信じるようになり、信仰と現実の狭間で悩んだりしたそうです。ただ、教会や父親のことも好きになったとのこと。信仰が人々の生活にあたえるポジティブな影響の大切さを感じるようになったといいます。
バンスさんが13歳のときには、心の支えの一人だった祖父が急死します。母親は動揺します。このころには看護師として働いていた病院にあった薬物に手を出したようで、奇行も目立つようになり、リハビリセンターの世話になるようになりました。バンスさんは実の父親と暮らそうとしたこともありましたが、母親に懇願されて家に戻ります。そこでは母親と当時の恋人とと一緒に暮らすのですが、「世界の終わりの最前線に座っている」ようなものだったそうです。2人の間のけっかは絶えません。しかも母親はこうした生活を続けるなかで、病院の上司の男性と結婚することを決めます。もうなんのこっちゃよく分かりません。
一方、いつもバンスさんを支えてくれた姉は祖父の急死の直後に結婚し、幸せな生活を送るようになります。しかしバンスさんは、荒れた母親と見知らぬ上司が暮らす家のなかに閉じ込められ、将来を見通すことができません。高校生になったころには、勤務先の病院から薬物検査のための尿の提出を求められた母親から、バンスさんの尿を提出することを頼まれます。自分の尿からは薬物が検出されるおそれがあるということのようでした。このときバンスさんは指示に従いましたが、「この朝、私のなかで何かが壊れた」と回想しています。高校2年生のとき、母親とバンスさんは上司の家を追い出されます。バンスさんは母親から離れて、祖母と一緒に暮らすことにします。
このころまでバンスさんの学校での成績は落第寸前でした。しかし祖母と暮らす生活を始めてからは、学校の宿題にも取り組むようになり、成績は上向くようになります。もともと祖父母は教育熱心なところがあったそうです。学校で良い先生とも出会い、SATで高得点をあげたりします。"I was happy --- I no longer feared the school bell at the end of the day, I knew where I'd be living the next month, and no one's romantic decisions affected my life. And out of that happiness came so many opportunities I've had for the past twelve years"という心境だったそうです。祖母の勧めでつきあう友達も変わり、大学進学も意識するようになり、オハイオ州立大学とマイアミ大学から合格通知を受け取ります。これまでの生活からの出口が見えたというわけですね。
でも、バンスさんは大学進学をとりやめます。「自分はまだ準備ができていない」と感じていたからです。成績は上向いていたけれど、十分だとはいえず、奨学金のための書類を理解するだけでも膨大な時間がかかるほどの世間知らずでもあります。結局、バンスさんが決断したのは海兵隊への入隊でした。1年前の米中枢同時テロも理由のひとつ。海兵隊のリクルーターはお金は稼げないだろうし、戦争に行かされるかもしれないと断りながらも、"They'll teach you about leadership, and they'll turn you into a disciplined young man."と説明したそうです。海兵隊で任務についた後で大学に入れば、学費の面でも大幅な援助が受けられることも魅力でした。
海兵隊でのエピソードもいろいろ紹介されていますが、ある海兵隊の教官はバンスさんに初めて3マイルを走らせた後、"If you're not puking, you're lazy! Stop being fucking lazy!"と怒鳴りつけて何度もダッシュをするように命じ、バンスさんが意識を失うんじゃないかと思ったころあいに、"That's how you should feel at the end of every run!"と怒鳴ったそうです。バンスさんは常に全力を尽くさなければならないことや、全力を尽くせば自分が思っている以上の成果を生み出せることを体で覚えるわけです。バンスさんは、白人の貧困層にもたらすべき変化について問われると、"The feeling that our choice don't matter"と答えるようにしているそうです。バンスさんはイラクにも派遣されました。海兵隊勤務中の2005年には最愛の祖母を喪っています。
この後は順風満帆な感じのエピソードです。2007年にオハイオ州立大学に入学したバンスさんは猛勉強して1年11カ月で2つの学位を優秀な成績で取得。その後、イエール大学のロースクールに進学します。そこで自分が育った環境と多くの同級生が育った環境の違いや認識のズレに驚いたりしながらも、楽しい生活を送ります。のちに結婚する彼女とも出会いました。一般の人たちが仕事を見つけようとしたら履歴書を埋めて会社に送るのに、彼らエリートたちは一流の企業や法律事務所で働いている家族や親戚、友人、先輩たちの紹介で面接を設定してもらい、高い給料の仕事についているといった社会の仕組みも学びます。就職の際には、イエール大教授のAmy Chuaからたくさんのアドバイスをもらったそうです。例の"The battle Hymn of the Tiger Mother"の著者ですね。もうこのころには、バンスさんは生まれ育ったミドルタウンを故郷だとは思えなくなります。
本の中でバンスさんはミドルタウンの経済状況や人々の感情についても描写しています。
バンスさんが大人になっていった時期はミドルタウンの経済を支えてきたArmcoの経営が悪化していった時期です。Armcoは1989年に川崎製鉄に吸収されて、Armco Kawasaki Steelと名称を変更。第二次世界大戦の敵国だった日本の企業に地元経済が救われたかたちで、米国の製造業の厳しい現実が明らかになっていきます。バンスさんの祖父は、かつては子供たちに「日本車を買ったら勘当する」と言っていたそうですが、川崎製鉄による救済後は「今となっては日本は友人だ。もしも戦う相手があるとすれば、それは中国の奴らだ」とバンスさんに話すようになったそうです。
最近、バンスさんがミドルタウンの高校の先生に話を聞いたところ、子供たちは自分たちがプロ野球選手になれないことに気づくと、「それならArmcoで働くよ。おじさんも働いているし」といったような返事をするそうです。実際には、Armcoはかつてのような安定的な職場ではないにも関わらず、子供たちはこうした厳しい現実に気づいていない。それでいて、勉強して生活をステップアップできるような仕事に就こうとも考えない。「成功できるのは幸運な人間か、生まれつき頭がいい人間だ」といったセンチメントが蔓延していて、まともに働こうという意識もないまま製造業が衰退していくミドルタウンに閉じ込められていく。
これは本の冒頭で紹介されているエピソードですが、バンスさんが数年前に学費を稼ぐためにミドルタウンの企業で重たいタイルを扱う仕事をしていたとき、経営者は人手不足で困っていたそうです。数年働けば時給は16ドルまで上がって、年収3万2000ドルにはなるような仕事で、景気が悪くなっていくミドルタウンでは悪い額じゃない。経営者が19歳の若者に仕事を与え、妊娠していた恋人にも事務職を割り当ててあげたことがあったそうですが、恋人の方は3日に1度は無断欠勤し、数カ月で辞めてしまった。若者の方も1週間に1度は欠勤し、遅刻も常習的で、1日に3度も4度も30分ほどのトイレ休憩をとるような態度だった。その結果、最終的には解雇を言い渡されるのですが、そのときこの若者は"How could you do this to me? Don't you know I've got a pregnant girlfriend?"と食ってかかったそうです。ダメな感じですよね。こういう、自分が怠け者であることにも気づかないようなムードが、米国の一部には存在するということです。
バンスさんは高校時代、祖父母から勧められてスーパーで働くようになり、そこで貧しい人から豊かな人までさまざまな人が暮らす社会の現実を目の当たりにします。貧しい人たちがフードスタンプで炭酸飲料を大量に買い込んで、ディスカウントストアで売って現金を手にする様子や、食品はフードスタンプで買って、現金で酒やタバコを買うといった様子も目撃します。バンスさんの給料からは税金が引かれていますが、フードスタンプでバンスさんには手が届かないようなステーキを買うような生活をしている「貧困層」もいます。一方で、こうした貧困層と自分たちの生活が似ていることにも気づきます。政府の補助を得て隣家に引っ越してきた家族は、バンスさんの一家と同じように、ケンタッキーからオハイオに移り住み、ケンタッキーなまりの英語を話し、夜中になれば家の中からケンカの声が聞こえてくるような家庭です。バンスさんの祖母は「あの女は怠け者の売女だ。強制的に仕事に就かせれば、あんな女にはならなかったろうに。政府があの女にカネを渡して、我が家の隣に引っ越させたと思うと腹がたって仕方がない」「私たちは懸命に働いても生活を切り詰めなければならないのに、ろくでなしどもが我々の税金で酒を買って、携帯電話を使っているのは許せない」と毒づいていたそうです。
一方で、バンスさんの内面にはこうした貧困層は自分の母親の姿であり、かつての自分でもあることを自覚しています。職が一切ないわけじゃないけれど、ひどい勤務態度で解雇される。子供がしっかりと勉強できるような家庭環境を与えず、「自分たちが働かないのは社会が不公平だからだ。オバマのせいで炭鉱は閉鎖され、工場の仕事は中国に行ってしまった」と言い訳する。朝ご飯にシナモンロールを食べ、昼ご飯にタコベルを食べ、晩ご飯にマクドナルドを食べるような生活を続け、ケンタッキーの一部での平均寿命は67歳でしかない地域もあるそうです。バンスさんには祖父母や姉という心の支えがあり、高校2年からは安定した生活が送れるようになった。でも、そうした環境が得られなかったら、どうなっていたか分かりません。
バンスさんはイエールに入った後も、自分が子供のころに負ったトラウマを背負っていることに気づきます。恋人との意見の違いに過剰に反応したり、運転中に割り込んできた車の運転手にケンカをふっかけようとしたり。自分の身を守るために、他人からの攻撃に身構えてしまうという生活習慣がついてしまっているわけです。こうした問題を克服していけているのも、恋人の存在があったからだとのことです。そして、バンスさんの母親も、子供のころは生活が乱れていた祖父母に育てられてきました。母親はバンスさんがイエール在学中、ヘロインに手を出し、今も薬物依存との戦いを続けているようです。
バンスさんは現在の政治状況について「ヒーローのいない時代だ」と指摘します。オバマ大統領は期待されたけど、多くの人からは懐疑的にみられている。ブッシュ前大統領の支持者は少なく、クリントン元大統領も倫理的な腐敗のシンボルだとみられている。レーガンは亡くなって久しい。米国は2つの戦争に多くの兵士を送り込んだけど、経済は安定した賃金を確保することもままならないとみられています。亡くなったとき72歳だったバンスさんの祖母が最も誇りにしていたのは、自分の家族が第二次世界大戦で戦ったことだったそうです。祖母にとっての神はイエス・キリストとアメリカ合衆国でした。しかしそのアメリカ合衆国は、多くの人からアメリカンドリームを体現する存在ではなくなってきているとみなされています。
多くの米国人はオバマ大統領に違和感を感じています。肌の色だけが原因ではなく、一流大学を優秀な成績で卒業し、聡明で、裕福で、憲法の教授のような完璧な英語を話す。親戚のなかに大卒者は一人もいない貧乏な家庭で、ケンタッキーなまりの英語を話し、酒や薬物におぼれる家族と暮らしているような生活を送っている人たちには何の共感もできない存在なのです。こうした人々は今の米国の社会は自分たちのための社会ではないと感じているし、自分たちの生活がうまくいっていないことも自覚しています。オバマ大統領はこうした人々の複雑な心情をかき乱します。
バンスさんはオバマ大統領について、こう書いています。
"He is a good father while many of us aren't. He wears suits to his job while we wear overalls, if we're lucky enough to have a job at all. His wife tells us that we shouldn't be feeding our children certain foods, and we hate her for it ---not because we think she's wrong but because we know she's right."
こうした人々は主要メディアも信用していません。保守系のFOXニュースでさえ、オバマ大統領はハワイ生まれだと言っているのに、世論調査では保守層の間では「オバマ大統領は外国生まれだ」との回答が32%に達し、19%は「定かではない」と答えています。一方で、インターネット上や保守系ラジオから流れる拠のない情報は信じ込みます。米中枢同時テロは米国政府の企み、オバマケアは米国民にマイクロチップを埋め込もうとしている、ニュータウンの乱射事件は銃規制に関心を向けるための政府の陰謀、オバマ大統領は戒厳令を発動して3期目を務めようとしている、といった情報です。どれだけの人がこうした情報を信じているかは定かでないですが、多くの人々がオバマ大統領が米国生まれでないと信じているなかでは、相当な数の人たちがこれらの情報を信じている可能性はあります。
一方で、保守系の政治家たちも、生活に苦しんでいる人々に一生懸命勉強して、真面目に働き、新しい生活を築くように訴えかけたりはしません。彼らの言説は"It's not your fault that you're a loser; it's the government fault."といったものです。
バンスさんは今の米国社会の仕組みや、貧しい人々が暮らす生活環境が厳しいものであることを否定するわけではありません。ただ、自身や姉のように生活を改善できる人もいることを踏まえて、"No person's childhood gives him or her a perpetual moral get-out-of-jail-free-card"だとしています。重要なのは身近にロールモデルがいることで、宗教上のコミュニティーがそうした役割を果たすことも指摘しています。またバンスさんのような家族にとっては、祖父母や親戚の役割が非常に大きともしています。そして、政府はコミュニテイーの問題を解決できるほど力があるわけではないとして、"Studies now show that working-class boys like me do much worse in school because they view schoolwork as a feminine endeavor. Can you change this with a new law or program? Probably not"とも疑問を投げかけます。
バンスさんは、自身の子供時代と同じような境遇にあるブライアンという15歳の少年について、このように考えたといいます。
"There are many cards left to deal: whether his community empowers him with a sense that he can control his own destiny or encourages him to take refuge in resentment at forces beyond his control; whether he can access a church that teaches him lessons of Christian love, family, and purpose; whether those people who do step uo to positively influence Brian find emotional and spiritual support from their neighbors"
まぁ、そうなんでしょうな。
このストーリーはあくまでバンスさん個人が経験した内容で、どこまで一般化できるかどうかは分かりません。バンスさんもこのことは冒頭で断っています。でも、実際にこうした生活を経験した本人が書いている話で、外部の人間はなかなか家庭内の事情までは踏み込んで知ることはできないだけに、傾聴に値する話なんだと思います。
家庭は大事だよね。
これだけだと、だからどうしたという話ですが、バンスさんはオハイオ州のミドルタウンというかつては鉄鋼業で栄えたものの、今はさびれつつある街で育ち、劣悪な家庭環境のなかから這い上がり、イエール大学のロースクール卒のエリート弁護士になったという経歴の持ち主です。そのアメリカン・ドリームの体現者が、かつては劣悪な環境を経験した者として、米国に存在する貧困の背景や、そうしたコミュニティーに育ったものたちが今の米国社会をどのようにみているのか、問題を解決するためには何が必要なのかという問題を論じています。
2016年6月28日に出版された本で、「多くの白人がドナルド・トランプ氏を支持する背景にはこういった事情がある」という文脈でたくさんのメディアで紹介されていました。インタビューに答えたバンスさんは、「私自身はトランプ氏を支持するわけではないが、支持している人たちの気持ちは理解できる」としています。
で、話はケンタッキー南東部の石炭の産地、ジャクソンから始まります。非常に緊密なコミュニティーで、見知らぬ人が雪道で車を動かせなくなっていると、住民たちがこぞって助けだそうとするような地域です。バンスさんの祖父母はこのジャクソンで育ちました。非常に心優しい人たちです。
ただし、こうしたアパラチア山脈のコミュニティーに住む人たちには、荒くれ者という一面もあります。祖母の兄の1人は建設業を営んでいたのですが、ビジネスの相手が"son of a bitch"と生意気な口をきいたときは、車のなかにいた相手を引きずり下ろしてチェーンソーで切りつけ、病院送りにしてしまうような人です。「家族に対する侮辱は絶対に許さない」という掟に従った行動だとのこと。別の兄は、自宅の裏庭でマリファナを育てています。祖母自身も、家族で育てている牛を盗もうとした男を見つけたときに、ライフルを持ち出して発砲し、脚をケガした相手の頭に向かってライフルをかまえ、とどめを刺そうとしたことがあるそうです。
祖母の家だけが荒くれ者だらけだったというわけではありません。ジャクソンがあるBrethitt Countyという地域は"Bloddy Breathitt"という異名があるほどで、とある強姦犯は裁判の数日前、背中に16発の銃弾を受けて殺されました。地元の警察はまともに捜査せず、新聞も「犯罪」があったようだと報じただけでした。真相は明らかではありませんが、被害者の家族が裁きを下したということのようです。祖母が少女時代にある男に侮辱された際にも、兄たちがその男を懲らしめたことがあったそうです。
で、子供のころにこうした話を親戚たちから聞いたバンスさんは、「家族のためなら法律でも犯す」といったカルチャーを誇りに感じていたそうです。親戚一同がこんなエピソードを面白おかしく話したりしていたら、「これが男というものだ」と思っていたということなのでしょう。
祖父母は1947年に17歳と14歳で結婚しました。そして第二次世界大戦での勝利に対する興奮がさめていくなかで、よりよい生活を求めて、オハイオ州ミドルタウンに引っ越します。ミドルタウンにはArmcoという鉄鋼会社が工場を構えていて、大量の労働者を雇うようになっていたからです。というと美しい話のようですが、実はできちゃった婚で、祖母の兄たちから懲らしめられることを恐れてミドルタウンに逃げていったという事情もあったようです。ちなみにこのときの子供は生後すぐに亡くなったとのこと。
ミドルタウンにはケンタッキー出身者が多く、"Middletucky"なんて呼ばれたりした。だから、ミドルタウンには、荒くれ者のカルチャーも持ち込まれて、元からオハイオにいた人たちとの間でトラブルも多かったそうです。祖母は、"You can take the boy out of Kentucky, but you can't take Kentucky out of the boy."なんて言っていた。アパラチアン魂百までってことでしょうか。
ただし生活が順調だったというわけではありません。祖父はジャクソンから離れたミドルタウンでの生活に馴染みきれないところがあったのか、バーから泥酔して帰宅したり、手にした給料を見栄をはるために浪費したりして、祖母を怒らせることも度々だった。祖母が泥水してソファーで眠っている祖父にガソリンをかけて、火をつけるということもあったらしい。バイオレントすぎるエピソードですが、家族の間ではそう伝えられているそうです。
で、そうした環境で育ったバンスさんの母親は、18歳で妊娠。19歳で離婚してシングルマザーになります。これが1980年ぐらいの話。母親の妹(バンスさんのおばさん)もその2年ほど前に16歳で高校を退学して、結婚しています。やはり結婚生活は厳しいものだったようです。こうした状況をなんとかせねばならないと決意したのか、祖父は1983年に禁酒し、別居状態だった祖母とも関係を修復するようになります。祖父は53歳、祖母は50歳ぐらいの計算ですね。祖父母は孫のケアや金銭的な援助を買って出るようになります。母親は1983年に再婚して、翌1984年にバンスさんが生まれます。
で、ここから先はバンスさん自身の話ですが、それはそれはなかなか過激なエピソードが満載です。
19歳でシングルマザーになってその4~5年後にバンスさんを生んだ母親は、その後も離婚と結婚を繰り返し、バンスさんが高校を卒業するまでに6人の男性と一緒に生活しています。バンスさんは、母親としては「子供たちに父親が必要だ」という思いで結婚相手を探していたのではないかと推測していますが、バンスさん自身の思いとしては「全く見知らぬ男が家の中に入ってきて、ようやく好きになったかなと思い始めたころに、離婚して家から出て行く」という状況が繰り返されることは子供時代の自分の心を深く傷つけていたとしています。また母親は看護師として働いてはいましたが、お酒におぼれ、バンスさんたちと大げんかをしては「ごめんなさい。もう二度とこんなことはしない」と謝罪するような生活を続けて来ました。バンスさんたちはそのたびに謝罪を受け入れるのですが、数日後には同じ状態に戻ってしまう。
バンスさんが12歳のときには、母親が反省の証としてバンスさんにフットボールカードを買ってくれると約束するのですが、車で高速道路を走っている最中にけんかになって、母親は「このまま車をクラッシュさせて、死んでやる」と言い出します。バンスさんは助手席から後部座席に移って、シートベルトを2つつければ生き延びられるんじゃないかと考えたりしましたが、母親はそうしたバンスさんの行為に怒りを増幅させて、車を止めてバンスさんに殴りかかります。止まった車から逃げ出したバンスさんは近くの民家にかけこんで、そこにいた女性に警察を呼ぶように依頼。母親は駆けつけた警察に逮捕されます。バンスさんはその後の裁判で、裁判官から日頃の母親の状況を聞かれ、「こうしたことは初めてのことです」と嘘をつききます。母親を刑務所には行かせたくないという思いからの嘘だったそうです。この後、バンスさんは、母親の家と祖父母の家の両方で暮らすようになります。自分の好きなときに、好きな方の家で暮らすことで、生活の安定と母親とのつながりを実現しようという狙いでした。
その後、バンスさんは実の父親と会うようになります。バンスさんは母親たちから父親が酒浸りになったから離婚したと聞かされて育ちましたが、実際にあった父親は敬虔なクリスチャンとして生活を立て直していました。ただ、既存の科学を否定するような極端なところもある信仰で、バンスさんも「2007年には世界が終わる」といった終末思想を信じるようになり、信仰と現実の狭間で悩んだりしたそうです。ただ、教会や父親のことも好きになったとのこと。信仰が人々の生活にあたえるポジティブな影響の大切さを感じるようになったといいます。
バンスさんが13歳のときには、心の支えの一人だった祖父が急死します。母親は動揺します。このころには看護師として働いていた病院にあった薬物に手を出したようで、奇行も目立つようになり、リハビリセンターの世話になるようになりました。バンスさんは実の父親と暮らそうとしたこともありましたが、母親に懇願されて家に戻ります。そこでは母親と当時の恋人とと一緒に暮らすのですが、「世界の終わりの最前線に座っている」ようなものだったそうです。2人の間のけっかは絶えません。しかも母親はこうした生活を続けるなかで、病院の上司の男性と結婚することを決めます。もうなんのこっちゃよく分かりません。
一方、いつもバンスさんを支えてくれた姉は祖父の急死の直後に結婚し、幸せな生活を送るようになります。しかしバンスさんは、荒れた母親と見知らぬ上司が暮らす家のなかに閉じ込められ、将来を見通すことができません。高校生になったころには、勤務先の病院から薬物検査のための尿の提出を求められた母親から、バンスさんの尿を提出することを頼まれます。自分の尿からは薬物が検出されるおそれがあるということのようでした。このときバンスさんは指示に従いましたが、「この朝、私のなかで何かが壊れた」と回想しています。高校2年生のとき、母親とバンスさんは上司の家を追い出されます。バンスさんは母親から離れて、祖母と一緒に暮らすことにします。
このころまでバンスさんの学校での成績は落第寸前でした。しかし祖母と暮らす生活を始めてからは、学校の宿題にも取り組むようになり、成績は上向くようになります。もともと祖父母は教育熱心なところがあったそうです。学校で良い先生とも出会い、SATで高得点をあげたりします。"I was happy --- I no longer feared the school bell at the end of the day, I knew where I'd be living the next month, and no one's romantic decisions affected my life. And out of that happiness came so many opportunities I've had for the past twelve years"という心境だったそうです。祖母の勧めでつきあう友達も変わり、大学進学も意識するようになり、オハイオ州立大学とマイアミ大学から合格通知を受け取ります。これまでの生活からの出口が見えたというわけですね。
でも、バンスさんは大学進学をとりやめます。「自分はまだ準備ができていない」と感じていたからです。成績は上向いていたけれど、十分だとはいえず、奨学金のための書類を理解するだけでも膨大な時間がかかるほどの世間知らずでもあります。結局、バンスさんが決断したのは海兵隊への入隊でした。1年前の米中枢同時テロも理由のひとつ。海兵隊のリクルーターはお金は稼げないだろうし、戦争に行かされるかもしれないと断りながらも、"They'll teach you about leadership, and they'll turn you into a disciplined young man."と説明したそうです。海兵隊で任務についた後で大学に入れば、学費の面でも大幅な援助が受けられることも魅力でした。
海兵隊でのエピソードもいろいろ紹介されていますが、ある海兵隊の教官はバンスさんに初めて3マイルを走らせた後、"If you're not puking, you're lazy! Stop being fucking lazy!"と怒鳴りつけて何度もダッシュをするように命じ、バンスさんが意識を失うんじゃないかと思ったころあいに、"That's how you should feel at the end of every run!"と怒鳴ったそうです。バンスさんは常に全力を尽くさなければならないことや、全力を尽くせば自分が思っている以上の成果を生み出せることを体で覚えるわけです。バンスさんは、白人の貧困層にもたらすべき変化について問われると、"The feeling that our choice don't matter"と答えるようにしているそうです。バンスさんはイラクにも派遣されました。海兵隊勤務中の2005年には最愛の祖母を喪っています。
この後は順風満帆な感じのエピソードです。2007年にオハイオ州立大学に入学したバンスさんは猛勉強して1年11カ月で2つの学位を優秀な成績で取得。その後、イエール大学のロースクールに進学します。そこで自分が育った環境と多くの同級生が育った環境の違いや認識のズレに驚いたりしながらも、楽しい生活を送ります。のちに結婚する彼女とも出会いました。一般の人たちが仕事を見つけようとしたら履歴書を埋めて会社に送るのに、彼らエリートたちは一流の企業や法律事務所で働いている家族や親戚、友人、先輩たちの紹介で面接を設定してもらい、高い給料の仕事についているといった社会の仕組みも学びます。就職の際には、イエール大教授のAmy Chuaからたくさんのアドバイスをもらったそうです。例の"The battle Hymn of the Tiger Mother"の著者ですね。もうこのころには、バンスさんは生まれ育ったミドルタウンを故郷だとは思えなくなります。
本の中でバンスさんはミドルタウンの経済状況や人々の感情についても描写しています。
バンスさんが大人になっていった時期はミドルタウンの経済を支えてきたArmcoの経営が悪化していった時期です。Armcoは1989年に川崎製鉄に吸収されて、Armco Kawasaki Steelと名称を変更。第二次世界大戦の敵国だった日本の企業に地元経済が救われたかたちで、米国の製造業の厳しい現実が明らかになっていきます。バンスさんの祖父は、かつては子供たちに「日本車を買ったら勘当する」と言っていたそうですが、川崎製鉄による救済後は「今となっては日本は友人だ。もしも戦う相手があるとすれば、それは中国の奴らだ」とバンスさんに話すようになったそうです。
最近、バンスさんがミドルタウンの高校の先生に話を聞いたところ、子供たちは自分たちがプロ野球選手になれないことに気づくと、「それならArmcoで働くよ。おじさんも働いているし」といったような返事をするそうです。実際には、Armcoはかつてのような安定的な職場ではないにも関わらず、子供たちはこうした厳しい現実に気づいていない。それでいて、勉強して生活をステップアップできるような仕事に就こうとも考えない。「成功できるのは幸運な人間か、生まれつき頭がいい人間だ」といったセンチメントが蔓延していて、まともに働こうという意識もないまま製造業が衰退していくミドルタウンに閉じ込められていく。
これは本の冒頭で紹介されているエピソードですが、バンスさんが数年前に学費を稼ぐためにミドルタウンの企業で重たいタイルを扱う仕事をしていたとき、経営者は人手不足で困っていたそうです。数年働けば時給は16ドルまで上がって、年収3万2000ドルにはなるような仕事で、景気が悪くなっていくミドルタウンでは悪い額じゃない。経営者が19歳の若者に仕事を与え、妊娠していた恋人にも事務職を割り当ててあげたことがあったそうですが、恋人の方は3日に1度は無断欠勤し、数カ月で辞めてしまった。若者の方も1週間に1度は欠勤し、遅刻も常習的で、1日に3度も4度も30分ほどのトイレ休憩をとるような態度だった。その結果、最終的には解雇を言い渡されるのですが、そのときこの若者は"How could you do this to me? Don't you know I've got a pregnant girlfriend?"と食ってかかったそうです。ダメな感じですよね。こういう、自分が怠け者であることにも気づかないようなムードが、米国の一部には存在するということです。
バンスさんは高校時代、祖父母から勧められてスーパーで働くようになり、そこで貧しい人から豊かな人までさまざまな人が暮らす社会の現実を目の当たりにします。貧しい人たちがフードスタンプで炭酸飲料を大量に買い込んで、ディスカウントストアで売って現金を手にする様子や、食品はフードスタンプで買って、現金で酒やタバコを買うといった様子も目撃します。バンスさんの給料からは税金が引かれていますが、フードスタンプでバンスさんには手が届かないようなステーキを買うような生活をしている「貧困層」もいます。一方で、こうした貧困層と自分たちの生活が似ていることにも気づきます。政府の補助を得て隣家に引っ越してきた家族は、バンスさんの一家と同じように、ケンタッキーからオハイオに移り住み、ケンタッキーなまりの英語を話し、夜中になれば家の中からケンカの声が聞こえてくるような家庭です。バンスさんの祖母は「あの女は怠け者の売女だ。強制的に仕事に就かせれば、あんな女にはならなかったろうに。政府があの女にカネを渡して、我が家の隣に引っ越させたと思うと腹がたって仕方がない」「私たちは懸命に働いても生活を切り詰めなければならないのに、ろくでなしどもが我々の税金で酒を買って、携帯電話を使っているのは許せない」と毒づいていたそうです。
一方で、バンスさんの内面にはこうした貧困層は自分の母親の姿であり、かつての自分でもあることを自覚しています。職が一切ないわけじゃないけれど、ひどい勤務態度で解雇される。子供がしっかりと勉強できるような家庭環境を与えず、「自分たちが働かないのは社会が不公平だからだ。オバマのせいで炭鉱は閉鎖され、工場の仕事は中国に行ってしまった」と言い訳する。朝ご飯にシナモンロールを食べ、昼ご飯にタコベルを食べ、晩ご飯にマクドナルドを食べるような生活を続け、ケンタッキーの一部での平均寿命は67歳でしかない地域もあるそうです。バンスさんには祖父母や姉という心の支えがあり、高校2年からは安定した生活が送れるようになった。でも、そうした環境が得られなかったら、どうなっていたか分かりません。
バンスさんはイエールに入った後も、自分が子供のころに負ったトラウマを背負っていることに気づきます。恋人との意見の違いに過剰に反応したり、運転中に割り込んできた車の運転手にケンカをふっかけようとしたり。自分の身を守るために、他人からの攻撃に身構えてしまうという生活習慣がついてしまっているわけです。こうした問題を克服していけているのも、恋人の存在があったからだとのことです。そして、バンスさんの母親も、子供のころは生活が乱れていた祖父母に育てられてきました。母親はバンスさんがイエール在学中、ヘロインに手を出し、今も薬物依存との戦いを続けているようです。
バンスさんは現在の政治状況について「ヒーローのいない時代だ」と指摘します。オバマ大統領は期待されたけど、多くの人からは懐疑的にみられている。ブッシュ前大統領の支持者は少なく、クリントン元大統領も倫理的な腐敗のシンボルだとみられている。レーガンは亡くなって久しい。米国は2つの戦争に多くの兵士を送り込んだけど、経済は安定した賃金を確保することもままならないとみられています。亡くなったとき72歳だったバンスさんの祖母が最も誇りにしていたのは、自分の家族が第二次世界大戦で戦ったことだったそうです。祖母にとっての神はイエス・キリストとアメリカ合衆国でした。しかしそのアメリカ合衆国は、多くの人からアメリカンドリームを体現する存在ではなくなってきているとみなされています。
多くの米国人はオバマ大統領に違和感を感じています。肌の色だけが原因ではなく、一流大学を優秀な成績で卒業し、聡明で、裕福で、憲法の教授のような完璧な英語を話す。親戚のなかに大卒者は一人もいない貧乏な家庭で、ケンタッキーなまりの英語を話し、酒や薬物におぼれる家族と暮らしているような生活を送っている人たちには何の共感もできない存在なのです。こうした人々は今の米国の社会は自分たちのための社会ではないと感じているし、自分たちの生活がうまくいっていないことも自覚しています。オバマ大統領はこうした人々の複雑な心情をかき乱します。
バンスさんはオバマ大統領について、こう書いています。
"He is a good father while many of us aren't. He wears suits to his job while we wear overalls, if we're lucky enough to have a job at all. His wife tells us that we shouldn't be feeding our children certain foods, and we hate her for it ---not because we think she's wrong but because we know she's right."
こうした人々は主要メディアも信用していません。保守系のFOXニュースでさえ、オバマ大統領はハワイ生まれだと言っているのに、世論調査では保守層の間では「オバマ大統領は外国生まれだ」との回答が32%に達し、19%は「定かではない」と答えています。一方で、インターネット上や保守系ラジオから流れる拠のない情報は信じ込みます。米中枢同時テロは米国政府の企み、オバマケアは米国民にマイクロチップを埋め込もうとしている、ニュータウンの乱射事件は銃規制に関心を向けるための政府の陰謀、オバマ大統領は戒厳令を発動して3期目を務めようとしている、といった情報です。どれだけの人がこうした情報を信じているかは定かでないですが、多くの人々がオバマ大統領が米国生まれでないと信じているなかでは、相当な数の人たちがこれらの情報を信じている可能性はあります。
一方で、保守系の政治家たちも、生活に苦しんでいる人々に一生懸命勉強して、真面目に働き、新しい生活を築くように訴えかけたりはしません。彼らの言説は"It's not your fault that you're a loser; it's the government fault."といったものです。
バンスさんは今の米国社会の仕組みや、貧しい人々が暮らす生活環境が厳しいものであることを否定するわけではありません。ただ、自身や姉のように生活を改善できる人もいることを踏まえて、"No person's childhood gives him or her a perpetual moral get-out-of-jail-free-card"だとしています。重要なのは身近にロールモデルがいることで、宗教上のコミュニティーがそうした役割を果たすことも指摘しています。またバンスさんのような家族にとっては、祖父母や親戚の役割が非常に大きともしています。そして、政府はコミュニテイーの問題を解決できるほど力があるわけではないとして、"Studies now show that working-class boys like me do much worse in school because they view schoolwork as a feminine endeavor. Can you change this with a new law or program? Probably not"とも疑問を投げかけます。
バンスさんは、自身の子供時代と同じような境遇にあるブライアンという15歳の少年について、このように考えたといいます。
"There are many cards left to deal: whether his community empowers him with a sense that he can control his own destiny or encourages him to take refuge in resentment at forces beyond his control; whether he can access a church that teaches him lessons of Christian love, family, and purpose; whether those people who do step uo to positively influence Brian find emotional and spiritual support from their neighbors"
まぁ、そうなんでしょうな。
このストーリーはあくまでバンスさん個人が経験した内容で、どこまで一般化できるかどうかは分かりません。バンスさんもこのことは冒頭で断っています。でも、実際にこうした生活を経験した本人が書いている話で、外部の人間はなかなか家庭内の事情までは踏み込んで知ることはできないだけに、傾聴に値する話なんだと思います。
家庭は大事だよね。
2016年8月28日日曜日
Bootlegeer's Daughter
"Bootlegger's Daughter"という本を読んだ。ミステリです。
この本を選んだきっかけは、英語で好きなジャンルである推理小説でも読んでみようかということだったのですが、英語圏の有名作家が誰なのかも知らないもので、どの本を選んでよいのか分からない。そこで「伝統的なミステリ」を対象とするアガサ賞受賞作から選んでみた次第です。
ウィキペディアによると、アガサ賞が対象とする伝統的なミステリとは、
あからさまな性描写や過激な流血、暴力シーンがないミステリ作品と緩やかに定義されていて、たいていは、警察官や私立探偵ではない一般の人が主人公となり、狭い地域を舞台として、お互い顔見知りの人々の中で起きる事件や謎を解決するミステリ
とのこと。映画化されるような「サスペンス+アクション」みたいなのではなく、プロット重視の「謎解き」みたいな感じなのではないでしょうか。
作者のMargaret Marronはアガサ賞の常連で、ほかにもいろんな賞をとっています。2013年には、Mystery Writers of Americaが授与する最高賞であるGrand Master Awardを取っています。そうそうたる面々が受賞している賞ですから、なかなか立派な作家なのでしょう。
で、読んでみた感想としては、面白かったです。派手なアクションもないうえ、不可能犯罪的なトリックもありませんが、きちんと意外な人物が犯人ですし、その動機も納得できるように思えました。オープニングもショッキングです。同性愛者が出てきます。あまりストーリーとは関係ないですが、双子も出てきます。
主人公はノースカロライナ州のDeborah Knottという女性弁護士で、民主党からDistrict Judgeに立候補しているという設定。その予備選で、Luther Parkerという黒人の弁護士と、候補者の座を争っています。その最中、18年前の未解決殺人事件の被害者の娘から、「18年前に母親が死んだときの真相を探ってほしい」と依頼されます。その調査の過程で、新たな殺人事件も発生します。つまり、選挙の話と、謎解きの話の2本立てでストーリーが進行するわけですね。だから、登場人物はやたらと多いです。ミステリなので、このやたらと多い登場人物の全員が怪しいように思えます。だから、最初のうちはやたらと読むのに時間がかかるのですが、だいたい「この人は悪い人じゃないな」とか「どう考えたって仲間だな」というのが分かってくると、スムーズに読めるようになりました。
正直、ミステリが読みたくで選んだ本ですから、選挙の話はややこしいばかりで面白くないようにも思えます。ただ、Deborahの父親のKezzie Knottという人が魅力的で、もともとは密造酒とかマリファナ栽培なんかに手を染めていた悪い人なうえ、脱税で起訴されて、8カ月ほど刑務所に入っていたこともあったけど、知事や上院議員の動きによって、この起訴と収監の記録は抹消されているという設定です。この本では、すべての謎が解決した後で、このお父さんがいろいろとなんやかんやして、選挙の話で、先に続くような展開が出てきます。この本は1992年に出版されたDeborah Knottシリーズの第1作で、2015年8月までに20作出ているみたいなので、今後は政治の方の話も大河ドラマ的な展開になっていくんじゃないでしょうか。間違っているかもしれませんけど。
次作も読んでみたいと思います。
この本を選んだきっかけは、英語で好きなジャンルである推理小説でも読んでみようかということだったのですが、英語圏の有名作家が誰なのかも知らないもので、どの本を選んでよいのか分からない。そこで「伝統的なミステリ」を対象とするアガサ賞受賞作から選んでみた次第です。
ウィキペディアによると、アガサ賞が対象とする伝統的なミステリとは、
あからさまな性描写や過激な流血、暴力シーンがないミステリ作品と緩やかに定義されていて、たいていは、警察官や私立探偵ではない一般の人が主人公となり、狭い地域を舞台として、お互い顔見知りの人々の中で起きる事件や謎を解決するミステリ
とのこと。映画化されるような「サスペンス+アクション」みたいなのではなく、プロット重視の「謎解き」みたいな感じなのではないでしょうか。
作者のMargaret Marronはアガサ賞の常連で、ほかにもいろんな賞をとっています。2013年には、Mystery Writers of Americaが授与する最高賞であるGrand Master Awardを取っています。そうそうたる面々が受賞している賞ですから、なかなか立派な作家なのでしょう。
で、読んでみた感想としては、面白かったです。派手なアクションもないうえ、不可能犯罪的なトリックもありませんが、きちんと意外な人物が犯人ですし、その動機も納得できるように思えました。オープニングもショッキングです。同性愛者が出てきます。あまりストーリーとは関係ないですが、双子も出てきます。
主人公はノースカロライナ州のDeborah Knottという女性弁護士で、民主党からDistrict Judgeに立候補しているという設定。その予備選で、Luther Parkerという黒人の弁護士と、候補者の座を争っています。その最中、18年前の未解決殺人事件の被害者の娘から、「18年前に母親が死んだときの真相を探ってほしい」と依頼されます。その調査の過程で、新たな殺人事件も発生します。つまり、選挙の話と、謎解きの話の2本立てでストーリーが進行するわけですね。だから、登場人物はやたらと多いです。ミステリなので、このやたらと多い登場人物の全員が怪しいように思えます。だから、最初のうちはやたらと読むのに時間がかかるのですが、だいたい「この人は悪い人じゃないな」とか「どう考えたって仲間だな」というのが分かってくると、スムーズに読めるようになりました。
正直、ミステリが読みたくで選んだ本ですから、選挙の話はややこしいばかりで面白くないようにも思えます。ただ、Deborahの父親のKezzie Knottという人が魅力的で、もともとは密造酒とかマリファナ栽培なんかに手を染めていた悪い人なうえ、脱税で起訴されて、8カ月ほど刑務所に入っていたこともあったけど、知事や上院議員の動きによって、この起訴と収監の記録は抹消されているという設定です。この本では、すべての謎が解決した後で、このお父さんがいろいろとなんやかんやして、選挙の話で、先に続くような展開が出てきます。この本は1992年に出版されたDeborah Knottシリーズの第1作で、2015年8月までに20作出ているみたいなので、今後は政治の方の話も大河ドラマ的な展開になっていくんじゃないでしょうか。間違っているかもしれませんけど。
次作も読んでみたいと思います。
2016年7月14日木曜日
"The Long Game"
共和党のミッチ・マコネル上院院内総務の自伝”The Long Game”を読んだ。5月31日発売。以前、民主党のハリー・リード上院院内総務の自伝"The Good Fight: Hard Lessons from Searchlight to Washington"を読んだときから、マコネルさんの本も読んでみたいと思っていたので、待望の新刊だったわけです。マニアックな話ですが。
リードさんの本は、自分の子供時代の友人や学校の先生たちについて事細かな描写や分析があったり、弁護士時代のエピソードなんかはミステリ風にも読めたりして、なかなか楽しめました。上院院内幹事になってからの議会工作についても、「あの議員はこんなポストを要求した」なんていう話を盛り込んだり、法案に賛成した議員と反対した議員の名前を羅列したりしてあった。なんか冒険譚っていう感じです。ただ、その分、「このリードさんはどうして政治家になりたかったのだろう」とか「なんで民主党なんだろう」なんていう感じがしたのも事実で、全体的に「リードさんは根っからのケンカ屋で、政策云々よりは勝ちたいっていうだけの政治家なんじゃないか」という印象を持ちました。
これに対してマコネルさんの本は、比較的あっさりしています。他人に対する評価はそれほど多くなくて、基本的には自分の行動や政治の流れを時系列で追いながら、そのときの思いとか分析とか自分の理念とかを書き綴っていくという内容です。だから、面白くないっちゃぁ面白くないんですが、「共和党の本流の人たちっていうのはこういう者の考え方なのか」とか「リードさんとは随分違うな」と思うと、それはそれで面白いです。
ただ、このマコネルさんが口を極めて批判している対象が3つあります。一人目はオバマ大統領。次がオバマ大統領在任中にオバマケア撤廃を強硬に訴えるような共和党内の勢力。最後がリードさんです。
オバマさんについては、ほとんど生理的に嫌いといった印象を受けます。もう、何から何まで気に入らない。誰かからオバマ評を尋ねられた際には、いつでもこのように答えるそうです。
“He’s no different in private than in public. He’s like the kid in your class who exerts a hell of a lot of effort making sure everyone thinks he’s the smartest one in the room. He talks down to people, whether in a meeting room among colleagues in the White House or addressing the nation.”
政治上の立場的にも全く違います。
“He has a bold progressive agenda, and if he can’t get what he wants through the legislative branch, he’ll work to do so through the bureaucracy.”
“Knowing I could do little to change this perspective on things, my goal has been to stop him when I think he’s pushing ideas that are bad for the country.”
それだけに2010年にオバマケア関連法が上院共和党の40議員から1人の賛成も得ずに成立したことへの怒りは大きかったそうです。無念さに涙を流したとうい描写も出てくる。ただ、共和党議員が団結できたことには達成感もあったとのこと。
2011年の債務上限引き上げをめぐるオバマ大統領との噛み合わない感じも面白いです。2010年の中間選挙で下院を奪還した共和党としては債務上限引き上げをするなら、歳出削減とセットでなければならないという立場。マコネルさんは下院は共和党がとったんだから、それぐらいの歩み寄りは当然だろうと思うわけです。でも、オバマ大統領との協議は上手くいかない。オバマ大統領は協議の場でいかに自分の立場が正しくて、共和党の立場が間違っているかを長々と語り始めて、相手に自分の主張を受け入れさせようとするわけです。マコネルさんは「私だったら、民主党との交渉の場で、いかにリベラリズムに瑕疵があるかを語るようなことは生産的だとは思わない。そんなことは相手の立場を尊重していないだけでなく、ただの時間の無駄だ」としています。
ベイナー下院議長はオバマ氏からの電話を受けても、受話器を机に置いて、別の誰かと会話をしていたそうです。マコネルさんは「自分はそこまではしていないが、テレビで野球の試合をみていたことはあった」なんて書いています。
で、結局、オバマ大統領は交渉をバイデン副大統領に丸投げすることが多かった。バイデンさんといえば長話というエピソードはこの本でも面白おかしく書かれていて、「時間を尋ねたら、時計の作り方から話し出すような男」だとのこと。でもそのうえで「彼は話すだけの男ではなく、相手の話に耳を傾けることもできる男だ」とも評価しています。
“Joe, on the other hand, made no effort to convince me that I was wrong, or that I held an incorrect view of the world. He took my politics as a given, and I did the same, which was what allowed us to successfully negotiate when it came to our discussion on taxes in 2010.”
で、このマコネルさんとバイデンさんのディールがBudget Control Act of 2011につながる。裁量的歳出を10年間で900ビリオンドル削減し、共和党6人、民主党6人の”super committee”を作って、追加的な1.2トリリオンドルの昨年についても協議するという内容です。で、債務上限は引き上げる。これこそが「ディール」だというマコネルさんのドヤ顔が浮かびます。
一方、共和党強硬派に対する批判も、オバマ氏への怒りと表裏一体な気がします。「現実を無視したような主張をして、アメリカを混乱に陥れるなよ」っていう感じですね。2013年の財政の崖や政府機関閉鎖をめぐる協議に臨む際の心境については、
“Speaker Boehner and I were prepared to fight for the Bush-era tax cuts to extend to all Americans on a permanent basis, but we also had to be realistic. A cornerstone of Obama’s reelection campaign was the promise to increase taxes on the wealthy. It was not possible that the Democratic-controlled Senate would pass the bill we wanted --- a bill that was in direct opposition to Obama’s promise --- or that Obama would sign it.”
と振り返ります。
こういうとき共和党の強硬派は「指導部は生ぬるい」なんて批判して、予備選で現職候補に対抗馬を立てたりする。でも、その対抗馬は例え予備選に勝ったとしても、本選では民主党候補に勝てる見込みがないことも多く、そんなことしたって共和党の不利に働くだけだったりするわけです。そもそもオバマ大統領が拒否権をもっているのに、「オバマケアを撤廃する」なんていう公約を掲げたって、それは有権者をミスリードするだけじゃないかというわけですね。
“These groups convinced people that the only acceptable outcome was getting exactly what they wanted, when those things were, at a time when Democrats held the White House and at least one house of Congress, impossible to get.”
“So telling Republican primary voters they should settle for nothing less than ensuring that Obamacare is repealed was selling an impossible idea.”
なかでもサウスカロライナ州選出のJim DeMint議員への批判は厳しいです。一方で、テッド・クルーズ上院議員の名前は一度も出てきません。つまんないの。
あと、リードさんについては「好きだし、個人的に憎しみを抱いているわけじゃない」としています。ただ、
“But Harry is rhetorically challenged. If a scalpel will work, he picks up a meat-ax. He also has a Dr. Jekyll and Mr. Hyde personality. In person, Harry is thoughtfull, friendly and funny. But as soon as the cameras turn on or he’s offered a microphone, he becomes bombastic and unreasonable, spouting things that are both nasty and often untrue, forcing him to then later apologize.”
と評しています。わはは。分かるような気がしますね。やっぱりケンカ屋のイメージです。
でも、リードさんが上院院内幹事時代の大勝利として生々しく描写した2000年の選挙で民主党と共和党の議席が50対50になったけど、共和党の上院議員が無所属に寝返った結果、民主党が多数派になった件については、
“Democrat Tom Daschle, who had become majority leader the previous June as a result of Jim Jeffords’s switch from Republican to Independent, announced that the Senate would convene the next day.”
とほんの一言触れているだけです。
2013年にリードさんが行使した核オプションについても、事実関係を述べているだけ。舞台裏の描写とかはないです。つまんないの。まぁ、マコネルさんにすれば大敗ですから、無理もないですけど。
“The Long Game”というタイトルは、従軍経験があるお父さんがアイゼンハワー支持者だったことをきっかけに、14歳だった1956年の共和党党大会の様子をみて共和党の理念に共感するようになって、高校時代、大学、ロースクールと学生代表を務め、インターンとして仕えたことがあるJohn Sherman Cooper上院議員に憧れて上院議員を志し、準備に準備を重ねて上院議員になった1985年に多数派の上院院内総務になると決意し、辛抱に辛抱を重ねて2014年になってようやくその夢を実現させたというマコネルさんの生き様を表しているものです。
院内幹事や院内総務に立候補したときは、ポケットに全議員の名前を書いたカードをしのばせて、「あなたに投票する」と確約した議員にチェックを入れていって票を固めていったそうです。「あなたは良い院内総務になるでしょうね」なんていう返事をする議員には、「じゃぁ、私に投票してくれますか」と詰める。そこで「イエス」と答えなければ、固めた票としてはカウントしないとのこと。渋い。マコネルさんは政治マンガでは「カメ」として描かれることが多いですが、まさにそういう粘りが信条の政治家なんでしょう。
その他のエピソードもいろいろとあります。
ゴールドウォーターについては大学時代の1962年に一緒に撮った写真を今でも執務室に飾っているほどで「政治的なヒーロー」の一人だそうです。ただ、ゴールドウォーターが1964年の公民権法案に反対票を投じたことに失望して、その年の大統領選ではリンドン・ジョンソンに投票したとのこと。
現職を僅差で破って上院議員に初当選した1984年の選挙ではロジャー・アイルズの世話になったそうです。効果的なテレビ広告を作ってくれた。
政治資金規制については、有権者の表現の自由を奪うものだとして徹底的に反対してきたそうです。
“Despite the argument offered by the Left, limiting a candidate’s speech does not level the playing field, it does the opposite. Like trying to place a rock on Jell-O, pushing down on one type of speech just raises that speech elsewhere, allowing someone else to control the discourse --- the press, the billionaire, the special interests, the incumbent. On more personal level, my first run for the Senate brought these issues to light in a concrete way. I never would have been able to win my race if there had been a limit on the amount of money I could raise and spend. ”
わはは。なるほど。
あと、第二次世界大戦当時、子供だったマコネルさんの日本に対する原爆投下時の感慨が面白い。マコネルさんのお父さんは欧州戦線から戻ってきて、次は太平洋戦線に向かう予定だったタイミングでの原爆投下だったそうで、
“But to the substantial relief of our family, President Truman dropped the A-bomb on Japan. Knowing the potential suffering this saved my dad, and the great number of lives spared by bringing an end to the war, there’s never been any second thoughts in our family about the wisdom of that decision.”
と振り返っています。そりゃ、そうだわな。戦争なんてやるもんじゃないですね。
それとどうでもいい話ですが、マコネルさんが子供時代、何度も近所の大柄な子供にいじめられているのを目撃したお父さんから「殴り返せ」と言われて、勇気を振り絞ってケンカしたら、勝ったというエピソードが出てきます。
この手のエピソードは、これまでに読んだ米国人のほとんどの自伝に出てくるような気がします。だから真偽のほどは眉唾な気もするのですが、米国人としては大好きな類いの逸話なんでしょうね。
ということで、結構面白かったですね。マコネルさんはいい人だと思います。
リードさんの本は、自分の子供時代の友人や学校の先生たちについて事細かな描写や分析があったり、弁護士時代のエピソードなんかはミステリ風にも読めたりして、なかなか楽しめました。上院院内幹事になってからの議会工作についても、「あの議員はこんなポストを要求した」なんていう話を盛り込んだり、法案に賛成した議員と反対した議員の名前を羅列したりしてあった。なんか冒険譚っていう感じです。ただ、その分、「このリードさんはどうして政治家になりたかったのだろう」とか「なんで民主党なんだろう」なんていう感じがしたのも事実で、全体的に「リードさんは根っからのケンカ屋で、政策云々よりは勝ちたいっていうだけの政治家なんじゃないか」という印象を持ちました。
これに対してマコネルさんの本は、比較的あっさりしています。他人に対する評価はそれほど多くなくて、基本的には自分の行動や政治の流れを時系列で追いながら、そのときの思いとか分析とか自分の理念とかを書き綴っていくという内容です。だから、面白くないっちゃぁ面白くないんですが、「共和党の本流の人たちっていうのはこういう者の考え方なのか」とか「リードさんとは随分違うな」と思うと、それはそれで面白いです。
ただ、このマコネルさんが口を極めて批判している対象が3つあります。一人目はオバマ大統領。次がオバマ大統領在任中にオバマケア撤廃を強硬に訴えるような共和党内の勢力。最後がリードさんです。
オバマさんについては、ほとんど生理的に嫌いといった印象を受けます。もう、何から何まで気に入らない。誰かからオバマ評を尋ねられた際には、いつでもこのように答えるそうです。
“He’s no different in private than in public. He’s like the kid in your class who exerts a hell of a lot of effort making sure everyone thinks he’s the smartest one in the room. He talks down to people, whether in a meeting room among colleagues in the White House or addressing the nation.”
政治上の立場的にも全く違います。
“He has a bold progressive agenda, and if he can’t get what he wants through the legislative branch, he’ll work to do so through the bureaucracy.”
“Knowing I could do little to change this perspective on things, my goal has been to stop him when I think he’s pushing ideas that are bad for the country.”
それだけに2010年にオバマケア関連法が上院共和党の40議員から1人の賛成も得ずに成立したことへの怒りは大きかったそうです。無念さに涙を流したとうい描写も出てくる。ただ、共和党議員が団結できたことには達成感もあったとのこと。
2011年の債務上限引き上げをめぐるオバマ大統領との噛み合わない感じも面白いです。2010年の中間選挙で下院を奪還した共和党としては債務上限引き上げをするなら、歳出削減とセットでなければならないという立場。マコネルさんは下院は共和党がとったんだから、それぐらいの歩み寄りは当然だろうと思うわけです。でも、オバマ大統領との協議は上手くいかない。オバマ大統領は協議の場でいかに自分の立場が正しくて、共和党の立場が間違っているかを長々と語り始めて、相手に自分の主張を受け入れさせようとするわけです。マコネルさんは「私だったら、民主党との交渉の場で、いかにリベラリズムに瑕疵があるかを語るようなことは生産的だとは思わない。そんなことは相手の立場を尊重していないだけでなく、ただの時間の無駄だ」としています。
ベイナー下院議長はオバマ氏からの電話を受けても、受話器を机に置いて、別の誰かと会話をしていたそうです。マコネルさんは「自分はそこまではしていないが、テレビで野球の試合をみていたことはあった」なんて書いています。
で、結局、オバマ大統領は交渉をバイデン副大統領に丸投げすることが多かった。バイデンさんといえば長話というエピソードはこの本でも面白おかしく書かれていて、「時間を尋ねたら、時計の作り方から話し出すような男」だとのこと。でもそのうえで「彼は話すだけの男ではなく、相手の話に耳を傾けることもできる男だ」とも評価しています。
“Joe, on the other hand, made no effort to convince me that I was wrong, or that I held an incorrect view of the world. He took my politics as a given, and I did the same, which was what allowed us to successfully negotiate when it came to our discussion on taxes in 2010.”
で、このマコネルさんとバイデンさんのディールがBudget Control Act of 2011につながる。裁量的歳出を10年間で900ビリオンドル削減し、共和党6人、民主党6人の”super committee”を作って、追加的な1.2トリリオンドルの昨年についても協議するという内容です。で、債務上限は引き上げる。これこそが「ディール」だというマコネルさんのドヤ顔が浮かびます。
一方、共和党強硬派に対する批判も、オバマ氏への怒りと表裏一体な気がします。「現実を無視したような主張をして、アメリカを混乱に陥れるなよ」っていう感じですね。2013年の財政の崖や政府機関閉鎖をめぐる協議に臨む際の心境については、
“Speaker Boehner and I were prepared to fight for the Bush-era tax cuts to extend to all Americans on a permanent basis, but we also had to be realistic. A cornerstone of Obama’s reelection campaign was the promise to increase taxes on the wealthy. It was not possible that the Democratic-controlled Senate would pass the bill we wanted --- a bill that was in direct opposition to Obama’s promise --- or that Obama would sign it.”
と振り返ります。
こういうとき共和党の強硬派は「指導部は生ぬるい」なんて批判して、予備選で現職候補に対抗馬を立てたりする。でも、その対抗馬は例え予備選に勝ったとしても、本選では民主党候補に勝てる見込みがないことも多く、そんなことしたって共和党の不利に働くだけだったりするわけです。そもそもオバマ大統領が拒否権をもっているのに、「オバマケアを撤廃する」なんていう公約を掲げたって、それは有権者をミスリードするだけじゃないかというわけですね。
“These groups convinced people that the only acceptable outcome was getting exactly what they wanted, when those things were, at a time when Democrats held the White House and at least one house of Congress, impossible to get.”
“So telling Republican primary voters they should settle for nothing less than ensuring that Obamacare is repealed was selling an impossible idea.”
なかでもサウスカロライナ州選出のJim DeMint議員への批判は厳しいです。一方で、テッド・クルーズ上院議員の名前は一度も出てきません。つまんないの。
あと、リードさんについては「好きだし、個人的に憎しみを抱いているわけじゃない」としています。ただ、
“But Harry is rhetorically challenged. If a scalpel will work, he picks up a meat-ax. He also has a Dr. Jekyll and Mr. Hyde personality. In person, Harry is thoughtfull, friendly and funny. But as soon as the cameras turn on or he’s offered a microphone, he becomes bombastic and unreasonable, spouting things that are both nasty and often untrue, forcing him to then later apologize.”
と評しています。わはは。分かるような気がしますね。やっぱりケンカ屋のイメージです。
でも、リードさんが上院院内幹事時代の大勝利として生々しく描写した2000年の選挙で民主党と共和党の議席が50対50になったけど、共和党の上院議員が無所属に寝返った結果、民主党が多数派になった件については、
“Democrat Tom Daschle, who had become majority leader the previous June as a result of Jim Jeffords’s switch from Republican to Independent, announced that the Senate would convene the next day.”
とほんの一言触れているだけです。
2013年にリードさんが行使した核オプションについても、事実関係を述べているだけ。舞台裏の描写とかはないです。つまんないの。まぁ、マコネルさんにすれば大敗ですから、無理もないですけど。
“The Long Game”というタイトルは、従軍経験があるお父さんがアイゼンハワー支持者だったことをきっかけに、14歳だった1956年の共和党党大会の様子をみて共和党の理念に共感するようになって、高校時代、大学、ロースクールと学生代表を務め、インターンとして仕えたことがあるJohn Sherman Cooper上院議員に憧れて上院議員を志し、準備に準備を重ねて上院議員になった1985年に多数派の上院院内総務になると決意し、辛抱に辛抱を重ねて2014年になってようやくその夢を実現させたというマコネルさんの生き様を表しているものです。
院内幹事や院内総務に立候補したときは、ポケットに全議員の名前を書いたカードをしのばせて、「あなたに投票する」と確約した議員にチェックを入れていって票を固めていったそうです。「あなたは良い院内総務になるでしょうね」なんていう返事をする議員には、「じゃぁ、私に投票してくれますか」と詰める。そこで「イエス」と答えなければ、固めた票としてはカウントしないとのこと。渋い。マコネルさんは政治マンガでは「カメ」として描かれることが多いですが、まさにそういう粘りが信条の政治家なんでしょう。
その他のエピソードもいろいろとあります。
ゴールドウォーターについては大学時代の1962年に一緒に撮った写真を今でも執務室に飾っているほどで「政治的なヒーロー」の一人だそうです。ただ、ゴールドウォーターが1964年の公民権法案に反対票を投じたことに失望して、その年の大統領選ではリンドン・ジョンソンに投票したとのこと。
現職を僅差で破って上院議員に初当選した1984年の選挙ではロジャー・アイルズの世話になったそうです。効果的なテレビ広告を作ってくれた。
政治資金規制については、有権者の表現の自由を奪うものだとして徹底的に反対してきたそうです。
“Despite the argument offered by the Left, limiting a candidate’s speech does not level the playing field, it does the opposite. Like trying to place a rock on Jell-O, pushing down on one type of speech just raises that speech elsewhere, allowing someone else to control the discourse --- the press, the billionaire, the special interests, the incumbent. On more personal level, my first run for the Senate brought these issues to light in a concrete way. I never would have been able to win my race if there had been a limit on the amount of money I could raise and spend. ”
わはは。なるほど。
あと、第二次世界大戦当時、子供だったマコネルさんの日本に対する原爆投下時の感慨が面白い。マコネルさんのお父さんは欧州戦線から戻ってきて、次は太平洋戦線に向かう予定だったタイミングでの原爆投下だったそうで、
“But to the substantial relief of our family, President Truman dropped the A-bomb on Japan. Knowing the potential suffering this saved my dad, and the great number of lives spared by bringing an end to the war, there’s never been any second thoughts in our family about the wisdom of that decision.”
と振り返っています。そりゃ、そうだわな。戦争なんてやるもんじゃないですね。
それとどうでもいい話ですが、マコネルさんが子供時代、何度も近所の大柄な子供にいじめられているのを目撃したお父さんから「殴り返せ」と言われて、勇気を振り絞ってケンカしたら、勝ったというエピソードが出てきます。
この手のエピソードは、これまでに読んだ米国人のほとんどの自伝に出てくるような気がします。だから真偽のほどは眉唾な気もするのですが、米国人としては大好きな類いの逸話なんでしょうね。
ということで、結構面白かったですね。マコネルさんはいい人だと思います。
2016年5月13日金曜日
"The Paper Menagerie and other stories"
"The Paper Menagerie and other stories"を読んだ。中国出身のSF・ファンタジー作家、Ken Liu(ケン・リュウ)の短編集です。米国版は2016年3月出版。日本版の短編集「紙の動物園」は2015年4月に出ています。短編集ですから、それぞれの作品はそれより先に発表されていて、日本の方で先に短編集が出たってことなんでしょうね。
表題作の"The Paper Menagerie"は2011年発表。この年のヒューゴー賞ショート・ストーリー部門、ネビュラ賞ショート・ストーリー部門、世界幻想文学大賞短編部門賞の三冠を獲得しました。これが日本のSFマガジン2013年3月号に掲載されています。
いつもチェックしている前川淳という折り紙作家のブログで2014年6月と2015年5月に「紙の動物園」が紹介されていて、読んでみたいなと思っていました。そしたら英語の短編集も最近になって出たということで、早速購入してみた次第です。
日本語版、英語版とも15編の収録ですが、作品は異なっています。同じなのは7作品。
The Paper Menagerie(紙の動物園)
Good Hunting(良い狩りを)
Mono No Aware(もののあわれ)
A Brief History of The Trans-Pacific Tunnel(太平洋横断海底トンネル小史)
The Waves(波)
The Bookmaking Habits of Select Species(選抜宇宙種族の本づくり習性)
The Literomancer(文字占い師)
英語版だけに載っている8作品は以下の通り。
State Change
The Perfect Match
Simulacrum
The Regular
An Advanced Readers' Picture Book of Comparative Cognition
All the Flavors
The Litigation Master and the Monkey King
The Man Who Ended History: A Documentary
どの作品も面白いです。
日本語版と共通作品のなかでは、「紙の動物園」「もののあわれ」「波」「文字占い師」、
英語版のみの作品のなかでは、
インターネットの検索を牛耳る企業による情報統制が常態化した社会を描く"The Perfect Match"
サイボーグ化した中国系米国人の女性のアクション活劇"The Regular"、
19世紀のゴールドラッシュで西海岸にやってきた中国人労働者の集団と三国志の関羽雲長のストーリーをごちゃませにした"All the Flavors"、
不都合な歴史を押し隠そうとする清王朝とそれに抵抗する詭弁家の男の話を西遊記で味付けした"The Litigation Master and the Monkey King"、
意識だけをタイムトリップさせて過去を観察する技術を開発した日系女性物理学者と、その夫で第二次世界大戦中の日本の731部隊の実体を世に知らしめようとする歴史家の男性の行動をとりあげながら、歴史と現在の関係性について考察した"The Man Who Ended History: A Documentary"
なんかが印象的です。
ケン・リュウさんは中国の甘粛省蘭州市生まれで11歳で渡米したということです。中国、台湾、日本の文化や歴史にも詳しいのでしょう。「もののあわれ」では典型的な日本人観に基づいた日本人を描いています。一方、"The Man Who Ended History: A Documentary"では、第二次世界大戦中の日本人による残虐な行為を中国視点で描きつつ、日本としての「歴史的な過ちは認めるんだけれど、過去の行為を否定しきってしまうこともできない」という悩ましい内面も描いています。
また別の本も読んでみたい。
表題作の"The Paper Menagerie"は2011年発表。この年のヒューゴー賞ショート・ストーリー部門、ネビュラ賞ショート・ストーリー部門、世界幻想文学大賞短編部門賞の三冠を獲得しました。これが日本のSFマガジン2013年3月号に掲載されています。
いつもチェックしている前川淳という折り紙作家のブログで2014年6月と2015年5月に「紙の動物園」が紹介されていて、読んでみたいなと思っていました。そしたら英語の短編集も最近になって出たということで、早速購入してみた次第です。
日本語版、英語版とも15編の収録ですが、作品は異なっています。同じなのは7作品。
The Paper Menagerie(紙の動物園)
Good Hunting(良い狩りを)
Mono No Aware(もののあわれ)
A Brief History of The Trans-Pacific Tunnel(太平洋横断海底トンネル小史)
The Waves(波)
The Bookmaking Habits of Select Species(選抜宇宙種族の本づくり習性)
The Literomancer(文字占い師)
英語版だけに載っている8作品は以下の通り。
State Change
The Perfect Match
Simulacrum
The Regular
An Advanced Readers' Picture Book of Comparative Cognition
All the Flavors
The Litigation Master and the Monkey King
The Man Who Ended History: A Documentary
どの作品も面白いです。
日本語版と共通作品のなかでは、「紙の動物園」「もののあわれ」「波」「文字占い師」、
英語版のみの作品のなかでは、
インターネットの検索を牛耳る企業による情報統制が常態化した社会を描く"The Perfect Match"
サイボーグ化した中国系米国人の女性のアクション活劇"The Regular"、
19世紀のゴールドラッシュで西海岸にやってきた中国人労働者の集団と三国志の関羽雲長のストーリーをごちゃませにした"All the Flavors"、
不都合な歴史を押し隠そうとする清王朝とそれに抵抗する詭弁家の男の話を西遊記で味付けした"The Litigation Master and the Monkey King"、
意識だけをタイムトリップさせて過去を観察する技術を開発した日系女性物理学者と、その夫で第二次世界大戦中の日本の731部隊の実体を世に知らしめようとする歴史家の男性の行動をとりあげながら、歴史と現在の関係性について考察した"The Man Who Ended History: A Documentary"
なんかが印象的です。
ケン・リュウさんは中国の甘粛省蘭州市生まれで11歳で渡米したということです。中国、台湾、日本の文化や歴史にも詳しいのでしょう。「もののあわれ」では典型的な日本人観に基づいた日本人を描いています。一方、"The Man Who Ended History: A Documentary"では、第二次世界大戦中の日本人による残虐な行為を中国視点で描きつつ、日本としての「歴史的な過ちは認めるんだけれど、過去の行為を否定しきってしまうこともできない」という悩ましい内面も描いています。
また別の本も読んでみたい。
2016年4月20日水曜日
How I Met Your Mother
10日ほど前に"How I Met Your Mother"を見終わった。ネットフリックスで1~9シーズンまで。非常に面白かったです。すべての日本人が見るべき。
「ママと恋に落ちるまで」の邦題で日本でもケーブルテレビで放送されていたらしいです。今でも放送されているのかもしれません。
CBSが2005年から2014年、足かけ10年かけて放送したシットコムです。CM抜きで1話20分ぐらいで、全208エピソード。つまり4160分=約69時間半。基本的にはドラマを観ることはほとんどないのですが、日本での放送を見たことがあった嫁さんが「面白い」と言っていたので、英語の勉強になると思って見始めてハマった。
物語は主人公のテッド・モズビーが2030年時点で、ティーンネージャーの子供2人対して「自分がどうやって君たちの母親(ママ)と出会ったか」と語るという設定です。実際の物語自体は2005年から2013年5月25日の2人の出会いの場面まで。ただし登場人物たちの学生時代のエピソードや、ママと出会った後のエピソードもところどころに挟まれます。
各ストーリーの内容は、いってしまえばテッドたち仲良し男女5人組がマンハッタンを舞台に繰り広げる恋愛模様と面白エピソードということになります。ウィキペデイアで、"Known for its unique structure and eccentric humor, How I Met Your Mother has gained a cult following over the years"とされているように、各エピソードのシナリオはよく練られていて、洒落たセリフや思いがけない展開が満載です。で、ジョークは8割が下ネタ。だからと言ってはなんですが、日本人でもよく分かります。子供に説明を求められたら、返答に窮するようなものばかりですが。このほかのジョークは、男女交際あるある、学生生活あるある、酔っ払いあるある、親子あるある、社会人あるある、子育てあるある、夫婦あるある、カナダあるある、懐かしのテレビ番組あるある、スターウォーズあるあるって感じですかね。懐かしのテレビあるあるは、正直よく分からないですが、ある意味勉強になります。
最初の設定では5人のうち幼稚園の先生のリリー・オールドリンと弁護士志望のマーシャル・エリクソンが鉄板のカップル。バーニー・スティンソンはバーでナンパを繰り返す遊び人。テッドはカナダからニューヨークに来たばかりのロビン・シュバツキーに一目惚れします。ここにサブキャラクターたちが加わって、くっついたり、はなれたり、くっついたり、はなれたり、くっついたり、はなれたりして、テッドとママとの出会いまで物語が続きます。
観る側の関心は「結局、テッドと結婚するママって誰なの?」っていうところなんですが、2030年の時点のテッドは子供たちに対してロビンのことを「ロビンおばさん(Aunt Robin)」と呼んでいるので、どうも「ロビン=ママ」ではないようです。じゃぁ、誰なんだってことですよね。物語が進展していくと、やっぱり「テッドとロビンが結婚するしかしかありえなんじゃないか」と思える展開もあるし、「テッドとロビンが結ばれることはありえないな」と思えるような展開も出てきます。
こうしたシリーズ全体の構成上、私なんかは「ママと出会った瞬間に物語は終わってしまうから、テッドとママの間のドラマが十分に描かれないんじゃないか」なんて心配していたんですが、そんなことは心配しなくて良かったです。ママとの出会いのシーンへの複線はシーズン3ぐらいから少しずつ引かれ始め、シーズン6ぐらいからはあからさまに引かれ出して、シーズン9では複線を見事に回収していきます。出会いのシーンなんてね、悶絶ものですよ。この構成は最初から決められていたんでしょうか。それとも適当に引いた複線を強引に改修したんでしょうか。いずれにしても悶絶ものであることに変わりはないですが。
エンディングには賛否両論あったようですが、あれは観る側が好きなように納得すればいいんじゃないでしょうか。作品の評価を落とすものではないと思います。
私のような40代のおっさんがマンハッタンを舞台にした男女5人の恋愛ドラマをみるなんていうのは気持ちが悪いかもしれませんが、テッドたちとほぼ同世代であるだけに楽しめる部分が多かったと思います。
「ママと恋に落ちるまで」の邦題で日本でもケーブルテレビで放送されていたらしいです。今でも放送されているのかもしれません。
CBSが2005年から2014年、足かけ10年かけて放送したシットコムです。CM抜きで1話20分ぐらいで、全208エピソード。つまり4160分=約69時間半。基本的にはドラマを観ることはほとんどないのですが、日本での放送を見たことがあった嫁さんが「面白い」と言っていたので、英語の勉強になると思って見始めてハマった。
物語は主人公のテッド・モズビーが2030年時点で、ティーンネージャーの子供2人対して「自分がどうやって君たちの母親(ママ)と出会ったか」と語るという設定です。実際の物語自体は2005年から2013年5月25日の2人の出会いの場面まで。ただし登場人物たちの学生時代のエピソードや、ママと出会った後のエピソードもところどころに挟まれます。
各ストーリーの内容は、いってしまえばテッドたち仲良し男女5人組がマンハッタンを舞台に繰り広げる恋愛模様と面白エピソードということになります。ウィキペデイアで、"Known for its unique structure and eccentric humor, How I Met Your Mother has gained a cult following over the years"とされているように、各エピソードのシナリオはよく練られていて、洒落たセリフや思いがけない展開が満載です。で、ジョークは8割が下ネタ。だからと言ってはなんですが、日本人でもよく分かります。子供に説明を求められたら、返答に窮するようなものばかりですが。このほかのジョークは、男女交際あるある、学生生活あるある、酔っ払いあるある、親子あるある、社会人あるある、子育てあるある、夫婦あるある、カナダあるある、懐かしのテレビ番組あるある、スターウォーズあるあるって感じですかね。懐かしのテレビあるあるは、正直よく分からないですが、ある意味勉強になります。
最初の設定では5人のうち幼稚園の先生のリリー・オールドリンと弁護士志望のマーシャル・エリクソンが鉄板のカップル。バーニー・スティンソンはバーでナンパを繰り返す遊び人。テッドはカナダからニューヨークに来たばかりのロビン・シュバツキーに一目惚れします。ここにサブキャラクターたちが加わって、くっついたり、はなれたり、くっついたり、はなれたり、くっついたり、はなれたりして、テッドとママとの出会いまで物語が続きます。
観る側の関心は「結局、テッドと結婚するママって誰なの?」っていうところなんですが、2030年の時点のテッドは子供たちに対してロビンのことを「ロビンおばさん(Aunt Robin)」と呼んでいるので、どうも「ロビン=ママ」ではないようです。じゃぁ、誰なんだってことですよね。物語が進展していくと、やっぱり「テッドとロビンが結婚するしかしかありえなんじゃないか」と思える展開もあるし、「テッドとロビンが結ばれることはありえないな」と思えるような展開も出てきます。
こうしたシリーズ全体の構成上、私なんかは「ママと出会った瞬間に物語は終わってしまうから、テッドとママの間のドラマが十分に描かれないんじゃないか」なんて心配していたんですが、そんなことは心配しなくて良かったです。ママとの出会いのシーンへの複線はシーズン3ぐらいから少しずつ引かれ始め、シーズン6ぐらいからはあからさまに引かれ出して、シーズン9では複線を見事に回収していきます。出会いのシーンなんてね、悶絶ものですよ。この構成は最初から決められていたんでしょうか。それとも適当に引いた複線を強引に改修したんでしょうか。いずれにしても悶絶ものであることに変わりはないですが。
エンディングには賛否両論あったようですが、あれは観る側が好きなように納得すればいいんじゃないでしょうか。作品の評価を落とすものではないと思います。
私のような40代のおっさんがマンハッタンを舞台にした男女5人の恋愛ドラマをみるなんていうのは気持ちが悪いかもしれませんが、テッドたちとほぼ同世代であるだけに楽しめる部分が多かったと思います。
2016年4月7日木曜日
Crippled America: How to Make America Great Again
“Crippled America: How to Make America Great Again”という本を読んだ。共和党の大統領候補選びでトップを走っている不動産王のドナルド・トランプさんの本です。昨年11月に出た本で、一応読んでおいた方がいいのかと思って読んだ。200ページほどのボリュームで、すぐに読めます。まぁ、演説や討論会で話している内容と同じなわけですが、本なので一応のまとまりがあります。思いのほか面白かった。
本は全体で17章構成。最初のうちは1章ごとにひとつの政策課題について書いています。不法移民、外交、教育、医療保険といった感じですね。そのうち自己紹介的な内容になってきて、「俺は実はいいヤツなんだ」とか「俺こそ愛国者なんだ」みたいな話になります。
いわんとすることは、「俺は成功したビジネスマンだから、交渉の仕方を知っているし、妥協の仕方も知っている。政治家は政治献金をしてくれる企業の顔色ばかりをうかがっているけど、俺はそうじゃない。自分の考えで動くし、いつも米国全体のことを考えている。大統領にふさわしいのは俺だし、俺を批判するメディアの連中は偏向している」ということですね。
トランプさんの問題意識は一般国民と違うわけじゃないです。「貧乏人は勝手に苦労してろ!」みたいなことは言わない。共和党のエスタブリッシュメントみたいな人は「大企業寄り」みたいなイメージがありますが、そうした立場とは一線を画しているんだと思います。ただ、解決の方法は具体的じゃない。ひたすら「俺はビジネスマンだから、同じことをやらしても、政治家よりはうまくやれる」という論法を繰り返すだけです。既存の政策は全否定。どんな政策だって、「俺がやったら、もっとうまくいっていたはずだ」と言ってしまう。
こんな論法のトランプさんが支持されるのは、今のワシントンの政治が「オバマ対議会」「共和党対民主党」「共和党穏健派対ティーパーティー」なんていう対立がこじれちゃって、どこにも妥協が成立しない状況が続いてきたからだと思います。2008年にオバマが大統領に初当選したとき、オバマは「ひとつの米国」を訴えたし、国民もそれを期待した。でも実際はそうはならなかった。下院議長になったばかりのポール・ライアンが仕切った昨年12月の予算協議はようやく出てきた前向きな動きだったわけですが、米国民はちょっと待たされすぎたわけです。だから、「政治家じゃないトランプさんだったら、なんとか上手くやってくれるかも」というムードがあるのだと思います。
自分が大金持ちで成功者であることをアピールするのも、そういった期待を高めるためなんでしょう。あと、自分の子供たちが立派な大人になっていることをアピールするのも、自分が父親としても成功していることを強調しているのだと思います。実際、トランプの子供たちの悪い評判は聞きません。
ただ、こうした論法はオーナー企業のトップとしては成立するかもしれませんが、政治の世界ではどうなんでしょうという疑問もあります。トランプさんが自分の会社で決断したことは、例え妥協の産物で不満を抱く人がいたとしても、異議を挟む人はいません。株主は自分ですしね。でも大統領が現実的な妥協をすれば、あらゆる方向から異議が出てくる。そもそも大統領は独裁者じゃないから、なんでも自分の思い通りの決断ができるわけじゃないし。このあたりのことをトランプさんはどう考えているのか。自分の資金と弁舌とメディア操縦術をもってすれば、政治家たちを黙らせることが出来ると思っているんでしょうか。それともオーナー企業のトップと大統領は同じようなものだと思っているのか。
ちなみにトランプさんは高い手腕をもった大統領として、レーガンとジョンソンの名前を挙げています。ジョンソンについては、公民権法を成立させたときの交渉手腕を評価しているみたいですね。”he took on the far left and the far right and threatened them in order to get his way”なんて書いています。あと、自分は1990年代の失敗から学んでいるとしているのも印象的です。こんなトランプさんでも、辛かったんでしょうね。
そのほかの語録としては、
“I’m a practical businessman who has learned that when you believe I something, you never stop, you never quit, and if you get knocked down, you climb right back up and keep fighting until you win”
“I learned a long time ago that if you’re not afraid to be outspoken, the media will write about you or beg you to come on their show”
(移民排斥主義者だとの批判について)“The next thing you heard was that Trump said all immigrants were criminals. That wasn’t what I said at all, but it made a better story for the media
“It’s not fair to everyone else, including people who have been waiting on line for years to come into our country legally”
“Most important is ending or curtailing so-called birthright citizenship, or anchor babies”
“If fact, I would like to reform and increase immigration in some important ways…..This country is a magnet for many of the smartest, hardest-working people born in other countries, yet we make it difficult for these bright people who follow the laws to settle here ”
(現在の外交政策を批判して)“When you’re digging yourself deeper and deeper into a hole, stop digging”
“The best way not to have to use your military power is to make sure that power is visible. When people know that we will use force if necessary and that we really mean it, we’ll be treated differently. With respect”
(イラクが1991年にクウェートを侵攻した際、クウェートの富裕層は避難先のパリで贅沢な暮らしを続けていたとして)”They were watching TV in the best hotel rooms in Paris while our kids were fighting for them”
“We can’t be afraid to use our military, but sending our sons and daughters should be the very last resort”
“Unfortunately, it may require boots on the ground to fight the Islamic State. I don’t think it’s necessary to broadcast our strategy”
“The side that needs the deal the most is the one that should walk away with the least”
“I know the best negotiators in this country, and a lot of them would be ready to go to work creating a fair balance of trade”
“I don’t want people to know exactly what I’m doing ---or thinking. I like being unpredictable”
(教育問題について)“You know what makes a kid feel good? Winning. Succeeding”
“We need to get a lot tougher on trouble makers. We need to stop feeling sorry for them. They are robbing other kids of time to learn. I’m not saying we should go back to the days when teachers would get physical with students, but we need to restore rules about behavior in the classroom and hire trained security officers who can help enforce those rules”
(気候変動問題について)”We have even had ice ages. I just don’t happen to believe they are man-made”
(オバマケアについて)”And it was only approved because President Obama lied 28 times saying you could keep your doctor and your plan --- a fraud and the Republicans should have sued --- and meant it”
“To succeed in business, you have to be flexible and you have to change with the realities of the world”
“There is no question we need real health care reform. We can’t let Americans go without health care because they don’t have the right resources”
“We should hire the most knowledgeable people in the world on this subject and lock them in a room --- and not unlock the door until they’ve agreed on the steps we need to take”
“During the Recession of 1990 many of my friends went bankrupt, and never recovered. I never went bankrupt. I survived, and learned so much about how to deal with bad times”
“In the 1990s, the government changed the real estate tax laws and made those changes retroactive. It was very unfair, but I fought through it and thrived. It absolutely killed the construction industry. It put a lot of people out of business”
“We should not touch Social Security”
“I’m a nice guy. I really am”
“A great leader has to be flexible, holding his ground on the major principles but finding room for compromises that can bring people together”
“By nature, I’m a conservative person. I believe in a strong work ethic, traditional values, being frugal in many ways and aggressive in military and foreign policy. I support a tight interpretation of the Constitution, which means judges should stick to precedent and not write policy”
(火星に人類を送るミッションについて)”I think it’s wonderful. But I want to rebuild our infrastructure first on Earth…I don’t understand how we can put a man on the moon but we can’t fix the potholes on the way to O’Hare International Airport”
“There is nothing, absolutely nothing, that stimulates the economy better than construction”
“I’m not going to pretend that being rich doesn’t offer a lot of wonderful opportunities, but it doesn’t necessarily make you happy. I’ve learned that wealth and happiness are two completely different things. I know the riches people in the world. Many of them are great negotiators and great businesspeople. But they’re not necessarily nice people, nor are they the happiest people”
“It’s not fun being a landlord. You have to be tough”
“My two oldest sons claim they’re the only sons of a billionaire who know how to run a Caterpillar D10”
“Honestly, I was a bit of a troublemaker. My parents finally took me out of school and sent me upstate to the New York Military Academy”
“Stand behind your word, and make sure your word stands up”
“The way you dress and the way you act is an important way of showing respect for the people you are representing and the people you are leading with. Impressions matter”
(税制改革案について)“It also eliminate the death tax, because you earned that money and already paid taxes on it. You saved it for you family. The government already took its bite; it isn’t entitled to more of it”
“The Democrats want to make inversions illegal, but that isn’t going to work. Whatever laws they pass, with literally billions of dollars at stake, corporations will find methods to get around them. It makes a lot more sense to create an environment that welcomes business”
(1970年代に手がけたグランドハイアットの改装事業について)”During the years it took me to put this deal together, I learned a lot about working with the city and the banks, the construction industry and the unions”
(トランプタワーの建設事業について)”One of the things I’m most proud of about that building is that the person I put in charge of overseeing construction was a 33-year-old woman. I made that decision in 1983, when the fight for gender equality in business was really beginning”
政治や外交、経済の専門家からすれば笑止千万な内容なのかもしれませんが、一般庶民の目線に立てばうなずける部分も多いと思います。問題はここに書かれていることが、どれだけ本当か分からないところでしょうか。
本は全体で17章構成。最初のうちは1章ごとにひとつの政策課題について書いています。不法移民、外交、教育、医療保険といった感じですね。そのうち自己紹介的な内容になってきて、「俺は実はいいヤツなんだ」とか「俺こそ愛国者なんだ」みたいな話になります。
いわんとすることは、「俺は成功したビジネスマンだから、交渉の仕方を知っているし、妥協の仕方も知っている。政治家は政治献金をしてくれる企業の顔色ばかりをうかがっているけど、俺はそうじゃない。自分の考えで動くし、いつも米国全体のことを考えている。大統領にふさわしいのは俺だし、俺を批判するメディアの連中は偏向している」ということですね。
トランプさんの問題意識は一般国民と違うわけじゃないです。「貧乏人は勝手に苦労してろ!」みたいなことは言わない。共和党のエスタブリッシュメントみたいな人は「大企業寄り」みたいなイメージがありますが、そうした立場とは一線を画しているんだと思います。ただ、解決の方法は具体的じゃない。ひたすら「俺はビジネスマンだから、同じことをやらしても、政治家よりはうまくやれる」という論法を繰り返すだけです。既存の政策は全否定。どんな政策だって、「俺がやったら、もっとうまくいっていたはずだ」と言ってしまう。
こんな論法のトランプさんが支持されるのは、今のワシントンの政治が「オバマ対議会」「共和党対民主党」「共和党穏健派対ティーパーティー」なんていう対立がこじれちゃって、どこにも妥協が成立しない状況が続いてきたからだと思います。2008年にオバマが大統領に初当選したとき、オバマは「ひとつの米国」を訴えたし、国民もそれを期待した。でも実際はそうはならなかった。下院議長になったばかりのポール・ライアンが仕切った昨年12月の予算協議はようやく出てきた前向きな動きだったわけですが、米国民はちょっと待たされすぎたわけです。だから、「政治家じゃないトランプさんだったら、なんとか上手くやってくれるかも」というムードがあるのだと思います。
自分が大金持ちで成功者であることをアピールするのも、そういった期待を高めるためなんでしょう。あと、自分の子供たちが立派な大人になっていることをアピールするのも、自分が父親としても成功していることを強調しているのだと思います。実際、トランプの子供たちの悪い評判は聞きません。
ただ、こうした論法はオーナー企業のトップとしては成立するかもしれませんが、政治の世界ではどうなんでしょうという疑問もあります。トランプさんが自分の会社で決断したことは、例え妥協の産物で不満を抱く人がいたとしても、異議を挟む人はいません。株主は自分ですしね。でも大統領が現実的な妥協をすれば、あらゆる方向から異議が出てくる。そもそも大統領は独裁者じゃないから、なんでも自分の思い通りの決断ができるわけじゃないし。このあたりのことをトランプさんはどう考えているのか。自分の資金と弁舌とメディア操縦術をもってすれば、政治家たちを黙らせることが出来ると思っているんでしょうか。それともオーナー企業のトップと大統領は同じようなものだと思っているのか。
ちなみにトランプさんは高い手腕をもった大統領として、レーガンとジョンソンの名前を挙げています。ジョンソンについては、公民権法を成立させたときの交渉手腕を評価しているみたいですね。”he took on the far left and the far right and threatened them in order to get his way”なんて書いています。あと、自分は1990年代の失敗から学んでいるとしているのも印象的です。こんなトランプさんでも、辛かったんでしょうね。
そのほかの語録としては、
“I’m a practical businessman who has learned that when you believe I something, you never stop, you never quit, and if you get knocked down, you climb right back up and keep fighting until you win”
“I learned a long time ago that if you’re not afraid to be outspoken, the media will write about you or beg you to come on their show”
(移民排斥主義者だとの批判について)“The next thing you heard was that Trump said all immigrants were criminals. That wasn’t what I said at all, but it made a better story for the media
“It’s not fair to everyone else, including people who have been waiting on line for years to come into our country legally”
“Most important is ending or curtailing so-called birthright citizenship, or anchor babies”
“If fact, I would like to reform and increase immigration in some important ways…..This country is a magnet for many of the smartest, hardest-working people born in other countries, yet we make it difficult for these bright people who follow the laws to settle here ”
(現在の外交政策を批判して)“When you’re digging yourself deeper and deeper into a hole, stop digging”
“The best way not to have to use your military power is to make sure that power is visible. When people know that we will use force if necessary and that we really mean it, we’ll be treated differently. With respect”
(イラクが1991年にクウェートを侵攻した際、クウェートの富裕層は避難先のパリで贅沢な暮らしを続けていたとして)”They were watching TV in the best hotel rooms in Paris while our kids were fighting for them”
“We can’t be afraid to use our military, but sending our sons and daughters should be the very last resort”
“Unfortunately, it may require boots on the ground to fight the Islamic State. I don’t think it’s necessary to broadcast our strategy”
“The side that needs the deal the most is the one that should walk away with the least”
“I know the best negotiators in this country, and a lot of them would be ready to go to work creating a fair balance of trade”
“I don’t want people to know exactly what I’m doing ---or thinking. I like being unpredictable”
(教育問題について)“You know what makes a kid feel good? Winning. Succeeding”
“We need to get a lot tougher on trouble makers. We need to stop feeling sorry for them. They are robbing other kids of time to learn. I’m not saying we should go back to the days when teachers would get physical with students, but we need to restore rules about behavior in the classroom and hire trained security officers who can help enforce those rules”
(気候変動問題について)”We have even had ice ages. I just don’t happen to believe they are man-made”
(オバマケアについて)”And it was only approved because President Obama lied 28 times saying you could keep your doctor and your plan --- a fraud and the Republicans should have sued --- and meant it”
“To succeed in business, you have to be flexible and you have to change with the realities of the world”
“There is no question we need real health care reform. We can’t let Americans go without health care because they don’t have the right resources”
“We should hire the most knowledgeable people in the world on this subject and lock them in a room --- and not unlock the door until they’ve agreed on the steps we need to take”
“During the Recession of 1990 many of my friends went bankrupt, and never recovered. I never went bankrupt. I survived, and learned so much about how to deal with bad times”
“In the 1990s, the government changed the real estate tax laws and made those changes retroactive. It was very unfair, but I fought through it and thrived. It absolutely killed the construction industry. It put a lot of people out of business”
“We should not touch Social Security”
“I’m a nice guy. I really am”
“A great leader has to be flexible, holding his ground on the major principles but finding room for compromises that can bring people together”
“By nature, I’m a conservative person. I believe in a strong work ethic, traditional values, being frugal in many ways and aggressive in military and foreign policy. I support a tight interpretation of the Constitution, which means judges should stick to precedent and not write policy”
(火星に人類を送るミッションについて)”I think it’s wonderful. But I want to rebuild our infrastructure first on Earth…I don’t understand how we can put a man on the moon but we can’t fix the potholes on the way to O’Hare International Airport”
“There is nothing, absolutely nothing, that stimulates the economy better than construction”
“I’m not going to pretend that being rich doesn’t offer a lot of wonderful opportunities, but it doesn’t necessarily make you happy. I’ve learned that wealth and happiness are two completely different things. I know the riches people in the world. Many of them are great negotiators and great businesspeople. But they’re not necessarily nice people, nor are they the happiest people”
“It’s not fun being a landlord. You have to be tough”
“My two oldest sons claim they’re the only sons of a billionaire who know how to run a Caterpillar D10”
“Honestly, I was a bit of a troublemaker. My parents finally took me out of school and sent me upstate to the New York Military Academy”
“Stand behind your word, and make sure your word stands up”
“The way you dress and the way you act is an important way of showing respect for the people you are representing and the people you are leading with. Impressions matter”
(税制改革案について)“It also eliminate the death tax, because you earned that money and already paid taxes on it. You saved it for you family. The government already took its bite; it isn’t entitled to more of it”
“The Democrats want to make inversions illegal, but that isn’t going to work. Whatever laws they pass, with literally billions of dollars at stake, corporations will find methods to get around them. It makes a lot more sense to create an environment that welcomes business”
(1970年代に手がけたグランドハイアットの改装事業について)”During the years it took me to put this deal together, I learned a lot about working with the city and the banks, the construction industry and the unions”
(トランプタワーの建設事業について)”One of the things I’m most proud of about that building is that the person I put in charge of overseeing construction was a 33-year-old woman. I made that decision in 1983, when the fight for gender equality in business was really beginning”
政治や外交、経済の専門家からすれば笑止千万な内容なのかもしれませんが、一般庶民の目線に立てばうなずける部分も多いと思います。問題はここに書かれていることが、どれだけ本当か分からないところでしょうか。
登録:
投稿 (Atom)